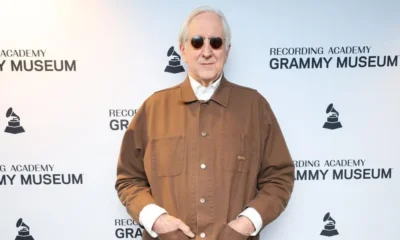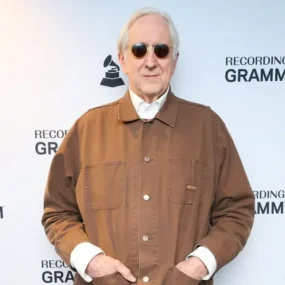Stories
ボビー・ジェントリー:貧しい生い立ち、「ビリー・ジョーの唄」の秘密と音楽業界の女性の権利を勝ち得た先駆者
ボビー・ジェントリーは先駆者だ。自身の音楽、イメージ、そしてビジネスというものをしっかりと捉え、わずか5年間で7枚のアルバムをリリースし、カントリー、ポップ、ソウル、フォーク、どんな音楽でもこなした。社会格差、ジェンダー、家族、セクシュアリティの複雑に絡み合った関係性をアメリカ南部を舞台にして物語を紡いでみせた彼女は、アメリカの偉大な語り部の一人である。そんなボビーの画期的な業績を記念してCD8枚から成る豪華なボックス・セット『The Girl From Chickasaw County』が2018年9月21日にリリースされた。
彼女は本名をロバータ・リー・ストリーターといい、1944年7月27日に生まれた。ジェントリーという名は、1952年の映画『ルビイ』のタイトル・キャラクターに影響されて彼女が自ら選んだものだ。このメロドラマ的作品に、南部出身のルビー・ジェントリーという上品な顔立ちとは裏腹にふしだらで貧しい少女が登場するのだが、ボビーの初期のソング・ライティングは明らかにこの少女から影響を受けている。ボビー本人もまた、電気もおもちゃもない寂しい農村の貧困の中で育っている。彼女は自分の作品が自伝的であることを否定していたが、彼女の歌の中に登場する場所や、食べるのがやっとという生活ならでは問題は、どれも彼女の実生活の中で身近にあるものだった。
ボビーは哲学とショービズの両方を愛していた。前者はUCLAで、後者はロサンゼルスのナイトクラブでのモデルやパフォーマーの仕事を転々とする中で学んだ。しかし、そうした生活をする中でボビーは常に自分のビジョン、日常と非日常とを併せ持つ表現を追求した。
■貧しい生い立ちが生んだ悲しき大ヒット曲
女性シンガー・ソングライターという存在が珍しかった当時、彼女は独特の語り口で異彩を放っていた。彼女は1967年にキャピトル・レコードにデモを渡している。それは彼女が初めてレコーディングしたデモ・テープで、そこには「Ode To Billie Joe(ビリー・ジョーの唄)」という曲が含まれていた。そのタイトルだけを聞けば好きな男の子にときめく少女の恋心を連想するところだが、なんとボビー・ジェントリーは聞き手にまるで自分が経験しているかのような悲しみを味わせたのだ。当時の流行りのテーマだった「若死にする若者の悲劇」とは異なり、橋から飛び降りて自殺したビリー・ジョー・マカリスターの悲劇が、「Ode To Billie Joe」では話のついでに触れられる程度の他人事として扱われている。ボビーが代わりに焦点を当てるのは、衝撃的な事件に対するコミュニティの沈黙だ。ビリー・ジョーの死によって、家族の中にすら存在する人の繋がりの孤独さが容赦なく露わになるのだ。

Manchester Square, London, 1969
この曲は、非常に優れたミステリー作品でもある。 若い二人がタラハシー橋から投げ捨てたのは一体何だったのか。インタビューでそのことをしつこく尋ねられてうんざりしたボビーは断固として答えず、そしてこう言った。
「二人が橋から何を捨てたかなんていうのはたいしたことじゃないのよ。重要なことは、他人に起きていることを人はそれほど気にかけないということなの」
1967年にリリースされた「Ode To Billie Joe」に世間は騒然となり、即座に多くのカヴァー・ヴァージョンが生まれた。ザ・スプリームス、ナンシー・ウィルソン、タミー・ワイネット、ルー・ドナルドソンといったアーティストたちがおよそ1年のあいだに同曲のカヴァー・ヴァージョンをレコーディングしている。
噂話と田舎町の偽善をテーマに採り上げたジニー・C・ライリーの「Harper Valley PTA」(1968年)は、その南部仕立ての筋立てといいボビー直系の子孫に思えてくる。そしてドリー・パートンの感動的なソングライティングは、ボビーの貧しさと希望を語るボビーの物語のいとこといっていいだろう。シェールの「Gypsies, Tramps And Thieves」の陽気な心理劇もまた同様だろう。ボビーのレンジとスキルによって、成功を手にする女性シンガー・ソングライターの挑戦の場は一気に広がったのだ。
1970年の「Fancy」で、ボビーは貧しい母親が自分の娘を売春婦に仕立て上げる物語をテーマに採り上げ、再び自身の子供時代を振り返った。彼女はこう言っている。「きちんと聞いてくれれば、”Fancy”がウーマンリブについての私の強い思いが込められている曲だとわかるはず。女性の地位や賃金の格差やデイケアセンターや堕胎の権利という深刻な問題に挑むこの運動に、私は全面的に賛成の立場よ」。
この曲には、化粧を施されてダンス用ドレスを着せられた少女が、自分の履いているハイヒールにゴキブリが這っているを見て怯えるという、ボビーの書く素晴らしい歌詞の中でも一二を争う一節があるが、かのアメリカ南部の観察者にして作家、ウィリアム・フォークナーを彷彿とさせる描写だ。
■女性アーティスト、女性プロデューサーとして権利を勝ち取った先駆者
ボビー・ジェントリーの音楽をカントリーと呼ぶのもいいだろう。フォーキーと評しても構わない。「Mississippi Delta」のようにサイケなスワンプ・ロックをシャウトするかと思えば、彼女がイギリスで1位を獲得した唯一楽曲「I’ll Never Fall In Love Again」のようにテンポよく軽やかに歌ってみせもする。彼女にはソウルがあった。コンセプチュアルな想像力もあった。アバンギャルドなポップがあった。未発表だがスタンダード・ジャズのアルバムをレコーディングしてもいる。 ダスティ・スプリングフィールドやジョニ・ミッチェルといったアーティストも、こうした要素の二つ三つにまたがっていたかもしれないが、彼女のように易々とやってのけられる者はそういない。女性アーティストの制約が多かった当時にあれほど勇敢に挑んだボビー・ジェントリーのスピリットは希有なものだった。
ボビーはまた、スタジオ作業の慣習にも挑戦した。 彼女は言っていた。「レコードは自分でプロデュースしているわ。初めから私は”Ode To Billie Joe”や他の殆どの曲をプロデュースしていたけれど、レコーディングスタジオには女性のチャンスはあまりなかった。スタッフ・プロデューサーの名前は必ずと言っていいほどレコードにクレジットされるのにね」
「Ode To Billie Joe」での鬱々とした不幸せな感情を表している不安げなストリングスのアレンジがこの言葉の例証だ。実際、女性プロデューサーが機会を得るための環境の改善は信じられないほどに遅れている(女性がプロダクション部門でグラミー賞を受賞したことは一度もなく、ノミネートされたのがほんの数例あるだけだ)。しかし、少なくとも当時ボビーは自身の貢献をきちんと認識してもらうために戦ったのだ。そして1971年にリリースされた彼女のラスト・アルバム『Patchwork』で、ようやく彼女はプロデューサーとしてクレジットされるに至った。

Recording at FAME Studios, Muscle Shoals, 1969
『Patchwork』をリリースした後、ボビー・ジェントリーのレコーディング活動はほぼ休止状態になったものの、活動そのものを止めたわけではなかった。自身の音楽を生で観衆に聞かせることに関心が向かった彼女は、10年前のタフでグラマーなナイトクラブ時代からの着想で、継続的なラスベガスでのステージ活動を始めた。その70年代のショーについて、彼女はこう言っている。「音楽も、衣装のデザインも、振り付けも、全部私が責任を持ってやっていたの。着想からステージまでの全てが私のものだった」。
■現在に至るまで消えないその影響力
ステージ中に行われる様々な衣装替え、キャラクター主体の作品演出、計算された振り付けで踊るダンサー、それらは現代の音楽業界のスタンダードになっているものだが、ボビーはそれらに真っ先に手を付けた一人だ。彼女は芝居じみた演劇向きであったし、モノマネ芸で対象への敬意を表しつつ笑いをとることもしておりエルヴィスのモノマネはお忍びでショーを観に来ていたキング本人をも感心させるほどだった。ビジネスの一から全てを自らが取り仕切り、彼女はこれらのショーによって大金を稼ぎ出した。
そしてその後、遂に完全に意欲をなくした時に彼女はきっぱりと引退した。彼女が公の場に再び姿を現したのは1981年だったがそれ以降はインタビュー、出演依頼、活動再開の要請……どんなオファーであれ、彼女は一切受け付けなかった。
ボビー・ジェントリーは、作曲活動、作品発表、そしてステージ活動などで素晴らしい業績を勝ち取ったが、もう一つ、より抽象的な、そしておそらく最も重要なものを手に入れている。それは彼女のペルソナだ。結局のところ、彼女は不可知な存在なのだ。彼女の音楽は聞けば聞くほど謎が生まれ、そしてその謎に対する答えはほぼ帰ってこない。女性らしさとアメリカらしさを身にまとっていた彼女。その影響力は依然としてミシシッピ・デルタの平原を覆っている。
By Jeanette Leech

ボビー・ジェントリー
『The Girl From Chickasaw County – The Complete Capitol Masters』