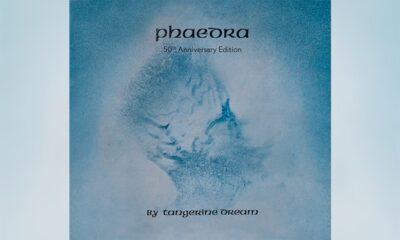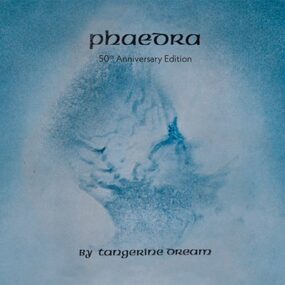Stories
80年代のヴァージン・レコード:英米の80年代のエレクトリックを独占したレーベル


ヴァージン・レコードからリリースされたそのニュー・シングルが初めてラジオで流れたのは、1982年9月初めのことだった。穏やかなオープニングからホワイト・レゲエへと変化していくこの曲は、英国の音楽ファンを魅了してチャート1位に登りつめ、アメリカでも1983年初めに2位をマークした。
その曲、カルチャー・クラブの「Do You Really Want To Hurt Me(君は完璧さ)」はサウンドが変わっているだけでなく、バンドのルックスも変わっていた。彼らは異質だった。すぐに世界最大のポップ・バンドになったが、同時に物議もかもした。
カルチャー・クラブはデビュー・ソングに続き、大西洋の両側でトップ10ヒットを連発した。「Karma Chameleon」は全米1位に輝いた。しかし、当時まだヴァージンはアメリカに進出しておらず、同レーベルから正式にリリースされたものではなかった。ヴァージン・レコードがアメリカでその頭角を現したのは、USオフィスを開き、カッティング・クルーのアンセム「(I Just) Died In Your Arms(愛に抱かれた夜)」が全米1位を獲得した1987年だった。
<関連記事>
・ヴァージン・レコード創業期:リチャード・ブランソンとアーティストたち
・カルチャー・クラブは真の意味で“多民族クラブ”だった
80年代のエレクトリックを独占
1984年夏、リチャード・ブランソンのビジネス帝国がアメリカへ進出した。ヴァージン・アトランティック航空がニューヨーク~ロンドン間を飛び始めたのだ。ヴァージンは世界征服を目論んでいたが、レコード会社はそれにはなくてはならない存在だった。
70年代の創立当時から、ヴァージン・レコードは、タンジェリン・ドリームらとエレクトロニック・ミュージックを開拓し、ヒューマン・リーグ、ヘヴン17、OMD(オーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダーク)といったエレクトロニカ&シンセ・ポップ・バンドを通じ、影響を与え続けた。また、ジャパンやデヴィッド・シルヴィアンは、このレーベルが先鋭で他とは違うことを証明していた。
ヴァージンはさらに、シンプル・マインズやカッティング・クルーなどロック系のバンドとも契約した。ダニー・ウィルソンとUB40という、ポップの常識とはかけ離れているが、スタイリッシュなアルバムを作り人気を博したバンドも見出した。ロキシー・ミュージック、ブライアン・フェリー、ブライアン・イーノ、キリング・ジョークらが所属したEGレコードを買収したころには、ヴァージンはその多岐にわたるマーケット、特に80年代のエレクトリックを独占することに成功していた。
シンセサイザーの移り変わり
1967年、ジミ・ヘンドリックスが「Third Stone From The Sun」の中で、「I shall put an end, you’ll never hear surf music again(俺が終わらせる。もうサーフ・ミュージックを聴くことはないだろう)」と約束する声がスピーカーから流れてきたとき、我々は彼が意味することを理解した。1967年は、ロック・ミュージックにとって転機の年だったが、波は押し寄せては消えた。サイケデリカはサーフ・ミュージックを打ちのめすことはなかったし、パンクがプログレッシヴ・ロックに終止符を打つわけでもなかった。しかし、わずかな変化は訪れていたのだ。
通信販売から始まり、ロンドン(靴屋の上)で最もクールなレコード・ショップになったヴァージン・レコードは、エクスペリメンタルなサウンドに触れる格好の場だった。80年代のエレクトロニック時代が近づきつつあるころ、トラディショナルな楽器が使われているのはごくわずかというアルバムを聴いたり、コンサートへ行くのは珍しくなかった。
その20年ほど前は、カールハインツ・シュトックハウゼンのようなアヴァンギャルド・ネオ・クラシック主義者の占有物だったシンセサイザーが、ニューウェイヴ・ロック・グループの間で必要不可欠なものとなった。テクノロジーの進化に対する抵抗はあったものの――機械に取って代わられるのではないかと恐れる人は多かった――、エレクトロニック・ミュージックは、探求的な若者の間では、前時代からのギターやベース、ドラムから成るグループと同じように自然に受け入れられた。
ヴァージン初の作品がリリースされたのは、1972年、グラム・ロック時代の前夜だった。マイク・オールドフィールドの『Tubular Bells』、ゴングの『Flying Teapot』、ファウストの『The Faust Tapes』、全てが一部で原始的なエレクトロニカを使用しているが、新興のクラウトロックに最も大きなインパクトをもたらしたのは、タンジェリン・ドリームとの契約、彼らのヴァージン時代だった。
彼らが早くから採り入れていたシーケンサー、信頼性にかけるモーグのシンセサイザー、当時ほとんど知られていなかったデジタル・テクノロジーは非常に未来的で、ボブ・ディランがフォーク・エレクトリックに転換しブーイングが巻き起こったときと同じように、オーディエンスを困惑させた。もちろん、タンジェリン・ドリームがやっていたことは、最終的には普通になったのだが。
Ricochet (Part One)
Live at Conventry Cathedral 1975
ロキシー・ミュージックによるシンセサイザー
ロバート・モーグの発明品が初めて公の場で実演されたのは、1967年モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティバルでのことだ。そして、ザ・ビートルズの「Here Comes The Sun」など60年代では画期的だった曲の中でも使われたが、VCS3シンセサイザーを初めてステージや『トップ・オブ・ザ・ポップス』に持ち込んだのは、ロキシー・ミュージックのブライアン・イーノだった。
「Ladytron」のセッション中、ブライアン・フェリーから「狂気を表現してみよう、月にいるような音にしよう」と言われたブライアン・イーノは、VCS3の低周波発振器、フィルター、薄気味悪いノイズ・ジェネレーターを駆使し、絶賛された。サックス奏者のアンディ・マッケイはこう話している。
「折衷主義を考案したのは間違いなく僕らではないが、ロックン・ロールはなんでも受け入れることができると言い、それを証明したのは僕らだ」
これが、ブライアン・イーノの目指したところだった。ロキシー・ミュージックのセカンド・アルバム『For Your Pleasure』をレコーディングしているとき、ブライアン・イーノはクラウトロックに夢中になり始め、ケルンの教師たち、とくにカンを手本に「The Bogus Man」を作りあげた。
ブライアン・イーノはまた、タイトル・トラックのテープ・エフェクト、ゾッとするようなテープ・ループ、「In Every Dream Home A Heartache」や「Editions Of You」でのVCS3による壮大なソロも生み出した。ここで、彼は実際に、アンディ・マッケイのサックスやフィル・マンザネラのギターと“リックス”を交換したのだ。
ロキシー・ミュージックは、クラフトワークと同じようにエレクトロニック80’sで大きな影響力を持っていた。しかし、人々がインスピレーションの源について話すとき、彼らはブライアン・イーノのきらびやかなイメージと風変りなサウンドを挙げることが多い。ブライアン・イーノは音楽に限って言うと、じっとしていなかった。
『Here Come The Warm Jets』からアンビエントな『Music For…』シリーズ、『Before And After Science』のアンビエント・スタイルまで、彼のアルバムは、ヒューマン・リーグからオーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダークまで全ての人々が持つ聖書のような存在となった。ブライアン・イーノは可能性という新しい世界を開く人だった。
ヒューマン・リーグとOMD:シンセによる革新
エルヴィス・プレスリー以降ずっと、ポピュラー・ミュージックには革新の力があると考えられてきたが、それを証明したのがヒューマン・リーグとOMDだった。ヒューマン・リーグの前宣伝には、「Electronically Yours」というステッカー、「beware of sugar-coated bullets(砂糖でコーティングされた弾丸に注意)」というキャッチ・フレーズ、バンドの世界観をコンピューターでプリントアウトしたもの、音楽を重ね継ぎしたデモテープ、自虐的なバイオグラフィなどが用意された。
そして彼らは従来のロック・ラインナップを用いなかった。ドラム、ベース、ギターは、イアン・マーシュとマーティン・ウェアがコントロールする2台のシンセサイザーにすげ替えられた。彼らは、同じくシェフィールド出身のバンド、キャバレー・ヴォルテールとは異なり、扇動的なシンセ・バンド、スロッビング・グリッスルがスタンダードなアコースティックの楽器を引き立てるためにエレクトロニクスを使っていたのとは違い、「シンセサイザーはシンセサイザーとして使うのがベストだ」と考えていた。マーティン・ウェアはこう話している。
「誰もがじっとしたままでおかしくなれる。そういった僕らが初期に作った曲を、いまみんなに聴かせたいとは思っていないが、僕らと比べられていた他のバンドが発表したものと比べても引けを取らないだろう。はるかに実験的だから」
「規律の問題だ。僕らはプロフェッショナルであろうと自らに課している。ステージでよろよろ歩き回り、自意識過剰で、自分ではアートだと思い込んでいて、オーディエンスには受け入れるかさもなければ出て行けなんて言う連中よりも、たくさんの労力が込められた作品だと知ったときのほうが、人々はより感銘を受けるだろう。僕らは前者のようなタイプには興味がない」
イアン・マーシュとマーティン・ウェアは、フィル・オーキーの恋愛ソングへの傾倒にも興味がなく、ヒューマン・リーグを去ることに決め、ニュー・シンガーのグレン・グレゴリーと、よりアンダーグラウンドでクラブ系のバンド、ヘヴン17を結成した。
フィル・オーキーがある種、冷たく、ウィットに富んだ偏屈さを極めた一方、ヘヴン17は、ジョルジオ・モロダー風のNYのフルなシンセ・ディスコをやりたいと考えていた。彼らは、壮大な『Penthouse And Pavement』で、余裕でそれを成し遂げた。
ペナイン山脈の向こう側にいたOMDのアンディ・マクラスキーとポール・ハンフリーズ、エレクトロニカ界のレノン&マッカートニーは、もう少しトラディショナルなアングルを持っていた。と、ポール・ハンフリーズは当時こう話している。
「1975、76年ごろ、僕らはその辺に出回っていたものの代わりにクラフトワークのようなドイツの音楽に興味を持つようになった。だから、パンク・エクスプロージョンが起きる前に、僕らの基礎は出来上がっていた」
だから、彼らはラウドで速いギターの道を進む代わりに、シンセサイザーを選んだ。
系図的には興味深いがマイナーな時期を通過した後、2人はテープ・デッキ、ウィンストンと共に、オーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダークという壮大な名でクラブ・サーキットを周るようになった。アンディ・マクラスキーはこう話している。
「1978年の終わり、僕らはOMDとしてライヴでプレイするようになった。僕らのようなバンドがたくさん出てきた。僕らはパンク・バンドにはなりたくなかったけど、パンクの素晴らしいところは、国中にたくさんのクラブをオープンさせたことだ。(ベース、キーボード、バッキング・テープという異例のラインナップではあったが)拒絶はされなかった。多分、僕ら2人がポップなダンス・ソング、強力なメロディ、強力なリズムをプレイしていたからだろう。僕らは格好つけてステージに立っていたわけじゃない」
ヒューマン・リーグとOMDはそれぞれ、エレクトリック80’sを完璧に体現する三部作を制作した。マーティン・ウェアとイアン・マーシュは去ったものの、新たにリーダーとなったフィル・オーキーはこれまで通りのやり方で、猛然とシンセを使い続けた。『Dare』『Hysteria』『Crash』の大ヒットは、彼らのキャリアの頂点となった。
彼らはカシオ、コルグ、ローランド(Jupiter-4とMC-8がお気に入りだった)を駆使し、あらゆる限りの時間をプロデューサーのマーティン・ラシェントと共にプログラミングに費やし、曲の基礎を組み立てようとしていた。
OMDの方は、ポップ・フォーマットと実験的なデジタル・テクノロジーの理想的なコンビネーションが『Dazzle Ships』『Junk Culture』『Crush』で聴くことができる。彼らもまた、イミュレーターからProphet 5まで全てを要したが、主要なエフェクトはローランドJP8とFairlight CM1から作られた。音楽から人間性が奪われるのを拒否し、曲に温かみを与えた。(ヒューマン・リーグとは)まるっきり正反対だった。
進んで新しいテクノロジーを取り入れるのか否か
オーガニック・ロックと呼ばれるものにこだわる人達とサンプリングを歓迎した人達の間で論争が巻き起こった。それは、トラディショナルだと思われていたバンドが、進んで新しいテクノロジーを取り入れたせいでもあった。
シンブル・マインズはアルバム『New Gold Dream』でエフェクトを用いただけでなく、誰もが認めるコンピューター・キーボードの巨匠ハービー・ハンコックとコラボまでした。彼の「Hunter And The Hunted」でのソロ・パフォーマンスはこのアルバムのハイライトだ。
シンガーのジム・カーは、続いて大ヒットした『Sparkle In The Rain』を「芸術的な作品だが、涙や頑強な肉体は持たない」と表し、エレクトリック・サウンドとスタジアム・ロックへの野望は共存するとの信念を、簡潔に要約した。シンプル・マインズのマイケル・マクニールは当然、ハービー・ハンコックに大きな感銘を受け、彼のシンセの腕前は飛躍した。それは、リマスターされた『Once Upon A Time』で聴くことができる。
ジャパンとデヴィッド・シルヴィアン
ヴァージンに所属していたエレクトロニック分野のアーティストの中で、ジャパンは多分、最もぶれなかった――間違いなくデヴィッド・シルヴィアンは。ジャズ、アンビエント、アヴァンギャルド、プログレッシヴ・ロックの影響は、彼のカノンのどこにでも聴くことができる。彼をニュー・ロマンティック・グラム・ロックのアイコンと呼ぶのは、しばらくは正しかったかもしれないが、彼がその後発表していく作品により、その呼び名は消滅した。
エレクトリック80’sはデヴィッド・シルヴィアンにとって黄金時代だった。彼は、イエロー・マジック・オーケストラの坂本龍一や実験的なトランペット奏者ジョン・ハッセル、カンのホルガー・シューカイ、ミヒャエル・カローリ、ヤキ・リーベツァイトと共作した。
デヴィッド・シルヴィアンのマルチメディア・インスタレーションへの傾倒や「Steel Cathedrals」のようなアンビエントな曲に、ブライアン・イーノとの繋がりを見出す人もいるかもしれない。『Gone To Earth』『Secrets Of The Beehive』『Plight & Premonition』の中のテープ、プレペアド・ピアノ、幅広い種類のシンセを見れば、ザ・ビートルズとジョージ・マーティンがEMIのアビイ・ロードとソーホーにあったトライデント・スタジオに対してそうであったように、デヴィッド・シルヴィアンもスタジオを重要な楽器として扱うアーティストだったことを証拠している。
キリング・ジョークのエレクトロニカ
キリング・ジョークもエレクトロニカに興味を抱いていたと言われてもピンとこない人は多いかもしれないが、リーダーのジャズ・コールマンはもちろん、名キーボード・プレイヤーであり、ヘヴィにミックス、プログラミングされた『Brighter Than A Thousand Suns』をベルリンのハンザ・スタジオでレコーディングしようと主張したのは彼だった。
また、そのほかのキリング・ジョークのアルバムも、クラフトワークやノイ!、クラスター、アシュ・ラ・テンペル、カンのホルガー・シューカイなど――キャリア初期にヴァージンの支援により成功したアーティスト達――のコンソールのブレインだったコンラッド・“コニー”・プランクが監修している。これで一回りした。コンラッド・プランクはブライアン・イーノに影響を与え、ブライアン・イーノはディーヴォやユーリズミックスのインスピレーションとなった。風変り、メインストリーム、どちらも手にできる。
カルチャー・クラブの影響力
80年代、カルチャー・クラブは一時期、ヴァージンの収益の40%に貢献した。ソニック・チェンジのるつぼと評される彼らの音楽は、外側は急進的だが、中は純粋なポップスだった。ドラム・プログラミングとコラボレーター、フィル・ピケットのキーボード・シンセが強調された彼らのデビュー作『Kissing To Be Clever』は、「Do You Really Want To Hurt Me」「I’ll Tumble 4 Ya」「Time (Clock Of The Heart)」を収録し、プラチナ・ヒットとなった。
カルチャー・クラブは、流行の曲が好きな人達やダンス・ミュージック・ファンを魅了した。このアルバムの中から、アメリカでは3枚のトップ10ヒットが誕生。このような快挙を成し遂げたバンドは数少ない。続くアルバム『Colour By Numbers』は、マイケル・ジャクソンの『Thriller』に1位の座を阻まれたが、UKアルバム・チャートの1位獲得を邪魔するものはなかった。カルチャー・クラブの最初のシングル7枚は、UKで全てがトップ5をマークした。シンプル・マインズ同様、彼らは12インチ・ミックスにも力を入れた。新しいノイズで蜂起したのだ。
ヴァージン初の全米1位
ヴァージンの歴史においては、カルチャー・クラブの影さえ薄くしてしまうのが、1987年「(I Just) Died in Your Arms」がアメリカで1位を獲得したニック・ヴァン・イード率いるカッティング・クルーだった。
同曲が収録されたアルバム『Broadcast』は、ヴァージンのアメリカでの新会社ヴァージン・レコード・アメリカがリリースした初の作品だった。時代はまた変わった。このイミュレーターを強調したシングルは時代を超え、エミネムからブリトニー・スピアーズ、ジェイ・Zまでこれをサンプリングしている。
バーミンガム出身のUB40は、80年代最もビッグなバンドの1つで、彼らは“出口”と書かれたドアを通過するのとは無縁だった。UB40は、魔法のポップとレゲエのテンプレートに固執し、アルバムとシングル(そのどれもがカラフルな名盤だ)を制作したという通念を受け入れるのは正しい。
だが、1980年、デビュー・アルバム『Signing Off』で成功したとき、彼らはダブ・ビートにアナログのシンセを激しく打ちつけていたし、それを辞める理由もなかった。カッティング・クルーと同様に、彼らは1988年、「Red Red Wine」で全米チャートの1位に輝いた。
1987年、ゲイリー&キット・クラーク兄弟により結成されたスコットランドの洗練されたポップ・バンド、ダニー・ウィルソンは、得体の知れない“ファンド”パーカッションなどエレクトロニックのワイルドカード的な要素を用い、「Mary’s Prayer」をヒットさせた。彼らは、ポップは使い捨てである必要はないことを証明し、ゲイリー・クラークはその後、ソロ・アーティストとして豊富な鉱脈を掘り続けていった。
様々な意味で、ダニー・ウィルソンは、ヴァージンのレコード会社としての在り方を要約している。創立以来、常に最先端だったヴァージン・レコードはリスクを負い、移り変わりの激しい80年代において、その時代のムードを反映するだけでなく、音楽はどの方向へも突き進むことができると証明するバンドと契約してきた。
CDが長くプレイし続けられてきたヴィニール盤に取って代わり、アーティストは新しい音楽の規定を模索していた。ヴァージンは彼らにクリエイティヴ空間を提供し、あの時代の素晴らしい音楽の数々が誕生した。
Written By Richard Havers

2022年12月21日発売
CD
 カルチャー・クラブ&ボーイ・ジョージ
カルチャー・クラブ&ボーイ・ジョージ
紙ジャケット/ハイレゾCD 6タイトル発売
2022年12月21日発売
CD
- ヴァージン・レコード創業期:リチャード・ブランソンとアーティストたち
- カルチャー・クラブは真の意味で“多民族クラブ”だった
- プログレッシヴ・ロック界のベスト・ドラマー25
- プログレッシヴ・ロックのベスト・ギタリスト25
- マイク・オールドフィールド『Tubular Bells』50周年記念盤発売