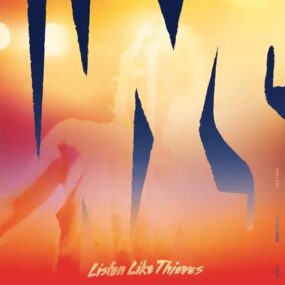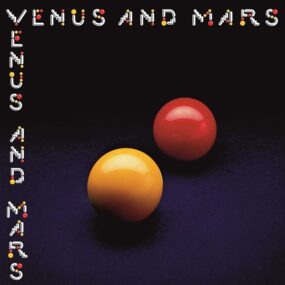Stories
ザ・バンドが1972年から1977年のあいだに残した過小評価されがちな作品たち


もしも1968年の『Music from Big Pink』、1969年の『The Band』、そして1970年の『Stage Fright』が、音楽のロックではなく物理的なロック (つまり岩) で形作られていたとしたら、この3つはラシュモア山に刻まれたアメリカの歴代大統領の顔のように、威厳に満ちたまなざしで我々を見つめていただろう。
「The Weight」「Chest Fever」「Up on Cripple Creek」「The Shape I’m In」といった曲を通じて、ザ・バンドはロックンロールの地図の中に“アメリカーナ”という新たなジャンルを刻み込み、ある種のお手本を作り出したのだ。
ルーツ・ロックのミュージシャンたちは、今もそのお手本に習って活動を続けている。しかし、熱心なザ・バンドのファンでない人は、その後の作品を飛ばして、いきなり伝説的な“サヨナラ”・イヴ・アルバム ―― 1978年の『The Last Waltz』に手を伸ばしてしまう。そんな風にして、ザ・バンドの作品カタログで重要な位置を占めている数多くの曲を聴き逃してしまっている。
1970年の『Stage Fright』から『The Last Waltz』までのあいだにザ・バンドは4枚のスタジオ・アルバムを発表したが、この4枚はさほど高く評価されることもない日陰の存在となっている。その時期は、メンバー間の感情的な軋轢が次第に大きくなり、アルバムの制作がどんどん困難になっていった。それでもなお、これら4枚のアルバムにはザ・バンドの5人が作り出した最高の作品と肩を並べるほどの優れた楽曲が収められていた。
<関連記事>
・ザ・バンドのメンバー、ロビー・ロバートソンが逝去
・ザ・バンド『Music From Big Pink』核心にある神秘的な美しさ
・ロビー・ロバートソン、スコセッシによるザ・バンドのドキュメンタリーを語る
・ロビー・ロバートソンが語るスコセッシや曲作り、そして裏社会との関係
メンバー間の不仲
『Stage Fright』がリリースされるころには、ザ・バンドのメンバー間の結びつきは既にかなりの速度で希薄になりつつあった。薬物の乱用はメンバーに悪影響を及ぼし、商業的な成功も事態を悪化させるだけだった。
レヴォン・ヘルム、ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、リック・ダンコ、そしてガース・ハドソンの5人は、ほぼ同じ年代で一緒に成長してきた精神的な兄弟だった。1950年代後半から60年代半ばにかけては、シンガーのロニー・ホーキンスのバック・バンドとして、さらには独立したバンドとしてさまざまなクラブでライヴ活動を繰り広げてきた。
しかし、この5人はだんだんと互いのあいだに距離を置くようになり、バンドでの共同作業も楽しみが減り、むしろやらなければいけない“仕事”という性格が強くなっていった。特にマニュエルは依存症に飲み込まれてしまい、自ら曲を作って提供することもなくなった。
『Cahoots』の制作
そんなザ・バンドは後戻りできないところまで来ていた。彼らはマネージャーのアルバート・グロスマンがウッドストックに新しく作り上げたベアズヴィル・サウンド・スタジオに集まり、1971年の『Cahoots』を制作した。ロバートソンはこのアルバムの再発盤でライナーノートを執筆し、その中で次のように回想している。
「それまで僕たちには、実験をしたり遊んだりできるスタジオがなかった。 (……) でも、“アルバム作り”をやろうとしていたわけじゃない。ただゴチャゴチャ試して、何か曲を作ろうとしていただけ。蓋を開けてみれば、あそこにはどこかしら魔法が潜んでいた」
当時のベアズヴィル・スタジオは、まだ設備が十分に整っておらず、またザ・バンドの内部でも軋轢が生じていた。そうした事情もあって、レコーディングは以前と違った場当たり的なものとなった。録音前にあらかじめ作られた曲はたったの2~3曲しかなかった。ロバートソンはこう振り返っている。
「メンバーが姿を現すと、僕は土壇場になってようやく曲を聞かせて、それからどうするかをみんなで考えていった」
そうした状況だったにもかかわらず、彼らは『Stage Fright』に続いて価値ある作品を作り上げた。前の3枚よりもひねくれて複雑な『Cahoots』には一風変わった構成の曲が含まれていたが、これは哀愁と情熱にあふれたアルバムだった。
このアルバムで底流となっているのは、悲痛なまでの喪失感である。このアルバムで最も印象的な曲のひとつである「Last of the Blacksmiths」は、アメリカで名声を得ようとしてカナダを離れたものの、その後の成り行きに不安を感じたことを歌っている。マニュエルが「鍵盤の上で凍りつく指/なかなかのご褒美だよな」と歌うとき、それは不気味な味わいを醸し出していた。
ザ・バンドのメンバーがウッドストックに住んでいた時期に親しく付き合っていた友人ヴァン・モリソンは、ゲスト・ヴォーカリストとして「4% Pantomime」を共作することになった。最初のヴァースは、音楽業界の策略に対する堕落した反応を描いているが、マニュエルとモリソンがヴォーカルの掛け合いを繰り広げるこの曲には断固たるスウィング感が含まれていた。レヴォン・ヘルムは、2000年にMOJO誌のアンディ・ギルに次のように語っている。
「まあ、あれはリチャードとヴァンの曲だよ。ああいった友情と創造性を潰すことなんかできない。あのふたりが一緒になれば、間違いなくいい曲ができるさ!」
一方「Life Is a Carnival」は『Cahoots』の中で最も希望に満ちた曲であり、ザ・バンドのカタログの中で最もファンキーな曲と言えるだろう。ここで歌い手は、世の中の予期せぬ変化に対して困惑気味の態度をとっている。そんな状況下でも、陽気なアラン・トゥーサンのホーン・アレンジの助けを借りれば、気楽に笑みを浮かべることができるだろう。
ニューオーリンズR&Bの王様であるトゥーサンの参加は、見事な成功を収めた。それゆえザ・バンドは、1971年12月のコンサートでも再び彼にホーン・アレンジを依頼している (このコンサートの模様は、1972年の傑作ライヴ盤『Rock of Ages』に収録された) 。
1973年の『Moondog Matinee』
『Cahoots』はかなり魅力的な作品だったが、これ以降ザ・バンドのレコードの売上は落ち込んでいく。グループ内部の問題は深まるばかりだった。1973年の『Moondog Matinee』では、ザ・バンドは新曲の代わりに旧き佳きロックンロールやR&Bナンバーのカヴァーをレコーディングすることにした。
これは“アイゼンハワー時代の文化に敬意を表するカウンターカルチャーのヒーロー”というコンセプトだったが、世間の人々にはこうした手法を受け入れる準備がまだ整っていなかった。『Moondog Matinee』が発売されたのは、デヴィッド・ボウイが似たようなスタイルで作り上げた『Pin Ups』と同じ月だった。
また同じく、ジョン・レノンが50年代の音楽をカバーした作品『Rock ‘n’ Roll』が出るのは、さらに2~3年後のことだった。『Zoo World』のライター、アーサー・レヴィは、このレコードについて次のように断言していた。
「1973年にリリースされた作品の中で、最も誤解され、無視されたアルバムになるように運命づけられている」
ロバートソンは後にMelody Maker誌のハーヴェイ・クバーニックに次のように語っている。
「ザ・バンドのアルバムをもう1枚作る方がずっと簡単だっただろう。こういうカヴァー・アルバムを作ると、自分自身だけでなく、昔の曲や過去のアーティストたちと競争する羽目になる……。残念なことに、世間の人は作品をありのままに受け止めるのではなく、いつも過去に出たた他の何かと比較するんだ。『Moondog Matinee』を『Music From Big Pink』や『Rock of Ages』と比べるのは馬鹿げていると思う」
それ以前からずっと、マニュエルは内に秘めた悲しみの井戸に入り込むことで、ずば抜けたパフォーマンスを披露してきた。プラターズの大ヒット曲「The Great Pretender」をザ・バンドがカヴァーしたとき、彼のヴォーカルはほとんど悲劇的と言っていいくらいの重々しさをもたらした。
一方ファッツ・ドミノの「I’m Ready」やクラレンス・“フロッグマン”・ヘンリーの「Ain’t Got No Home」のような猛烈なR&Bでは、レヴォン・ヘルムがリード・ヴォーカルを担当している。彼はこうした曲で、ザ・バンドが初期に影響を受けた曲の核心にある艶やかで柔軟な奔放さを存分に表現していた。
2002年、ヘルムは”GRITZ”のミッチ・ロペートに次のように語っている。
「誰も僕らを評価してくれなかった。評論家はほぼ間違いなくそうだったし、レコード会社も似たようなものだった。とにかく、評論家もレコード会社の人間も何が起きているのかわかっていなかったんだ。当時僕らがやれることといえばあれくらいが精一杯だった。僕らはうまくやっていくことができなかったんだ」
『Northern Lights, Southern Cross』オリジナルのザ・バンドによる最後
1976年の『Northern Lights, Southern Cross (南十字星)』では、ロバートソンは4年ぶりとなるザ・バンドの新曲を作り上げた。そしてこのアルバムは、オリジナルのザ・バンドが出した最後の作品となった。このころになるとザ・バンドはアメリカの東海岸からはるか離れた西海岸に移住していたが、メンバーの感情面での距離はそれ以上に開いていた。
それでもなお、彼らはこのアルバムを見事な内容に仕上げることができた。ファンキーな「Ophelia」、18世紀のアカディア人の追放を描いた痛切な物語「Acadian Driftwood」、そして胸を刺すようなバラード「It Makes No Difference」は、ロバートソンがこれまでに作り上げた作品の中でもとりわけ印象的な楽曲として数えられている。ザ・バンドの状態がどうであろうと、これらの曲は高く評価されただろう。とはいえ、彼らの演奏のおかげで楽曲が1段階上の仕上がりになったことは間違いない。
このアルバムでは、ガース・ハドソンが実に個性的で自然体のシンセサイザーを奏でている。レヴォンの著書『This Wheel’s on Fire』では、その演奏ぶりが称賛されている。
「[ザ・バンドのスタジオだった]シャングリラには、24トラック・テープ・レコーダーがあった。ガースはそれを思う存分使って、たったひとつの曲でキーボードを6トラックも録音していた」
またロバートソンは、回顧録『Testimony』の中でガースの「Ophelia」での演奏を次のように振り返っている。
「ガースがこの曲でオーバーダビングしたホーンとキーボードのコンビネーションは、僕がこれまで聴いた彼の演奏の中でも最高のものだった」
そして「Forbidden Fruit (禁断の木の実) 」や「It Makes No Difference」では、ロバートソンのリード・ギター (ザ・バンドの秘密兵器のひとつ) が冴え渡っている。この2曲は、彼のギターが最高に輝いた名録音として挙げることができるだろう。それでもなお、ザ・バンドが終わりに向かうのを止めることはできなかった。レヴォンは次のように書いている。
「『Northern Lights, Southern Cross』は、1969年の『The Band』以来、最高のアルバムだった。けれどキャピトルは、ファースト・シングルの”Ophelia”をラジオでヒットさせることができなかった」
アウトテイク集『Islands』
ザ・バンドはその1976年の感謝祭に華々しいコンサートを行い、それを最後に活動を停止した。そのコンサートの模様は、『The Last Waltz』と題した歴史的なドキュメンタリー映画とサウンドトラック・アルバムに記録され、1978年に発表された。この映画とレコードのリリースに先立つ1977年、ザ・バンドは過去数年間のアウトテイクを集めた『Islands』を発表している。
こうしたアウトテイク集は、もっと低レベルなグループの手にかかれば投げやりな内容になっていたかもしれない。しかしこのザ・バンドのアルバムには、他のアーティストなら是が非でも作りたいと思うような素晴らしい録音が含まれていた。
ドラッグに酔いしれたような浮かれた気分とアーシーな雰囲気を併せ持つ「The Saga of Pepot Rouge (伝説の女)」や、大恐慌時代の情景をニューオーリンズ風味で描いた「Knockin’ Lost John (ドジなジョン)」があれば、どんなアーティストのアルバムであろうと輝きを増すだろう。そしてマニュエルが歌い上げた「Georgia on My Mind」のカヴァーもある。この曲の最高の歌い手として考えられているのはレイ・チャールズだが、このカヴァーを聞けばマニュエルがレイを脅かす存在だったことが十分に納得できる。
1978年、ロバートソンはザ・バンドでのツアー生活について、”NME”のミック・ファーレンに次のように語っている。
「精神的な面で、とても辛いんだ。たくさん酒を飲むことになるし、ドラッグに手を出す人間も増える。ツアーの辛さを和らげることができるなら、何にだって手を出してしまう。基本的に、不自然で我慢できないような生活なんだ」
それでも、ザ・バンドが1972年~77年のあいだに発表したスタジオ・アルバムは、ひとつのことを決定的に証明している。レヴォン、ロビー、リチャード、ガース、そしてリックの個人的な苦しみは多くのものを奪ったのかもしれないが、たとえ本調子ではなくても、彼らは期待に見事に応えていたのである。
Written By Jim Allen
- ザ・バンドのメンバー、ロビー・ロバートソンが逝去
- ロビー・ロバートソン、スコセッシによるザ・バンドのドキュメンタリーを語る
- ロビー・ロバートソンが語るスコセッシや曲作り、そして裏社会との関係
- ザ・バンド『Music From Big Pink』核心にある神秘的な美しさ
- ザ・バンドの”時間を超越した作品”『The Band』
- ザ・バンド『Stage Fright』解説:「ダークなアルバムだ」