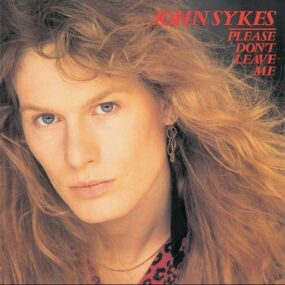Stories
忘れられた70年代ロックの英雄たち


音楽史における70年代という時代は人々の記憶に確かな形で残っている。ザ・ビートルズが解散し、T.レックスやデヴィッド・ボウイ、スレイド等のグラム・ロック系アーティストが登場した他、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ブラック・サバスといったバンドは飛ぶようにレコードを売り上げていた。更にイエス、ELP(エマーソン、レイク&パーマー)、マイク・オールドフィールド、ジェネシスといったプログレッシヴ・ロック勢も登場した。対抗するかのようにディスコ系ではELO(エレクトリック・ライト・オーケストラ)、アバらがシーンに姿を現した。その後はパンク、そしてジョイ・ディヴィジョン等のポスト・パンク系、更には2トーンというジャンルも登場。そして、ボブ・マーリーやイーグルスもいた。そして誰もがロンドン・ブーツとホット・パンツを履いていた。それが格好よかったのだろう・・・きっと。
現代の若者にとってアデルやエド・シーランが全てなのだろうか? いいや、大衆に受け入られるアーティストの陰には素晴らしい音楽を作り続ける多くのアーティストたちが存在しているのも事実だ。それは70年代の頃も同じだったと言える。才能のあるバンドは何千もの観客の前で演奏し、素晴らしいアルバムを世に出し、そしてやがては消えていった。今や減り続けるマニアックな愛好家たちにとっては懐かしいアーティストも、同時期に一世を風靡した人気者たちと同等の扱いを受けるに値しながら、ロックの歴史家たちにとってはその存在すら無視されていることがある。今からご紹介するアーティストたちは、70年代の忘れられた英雄たちだ。彼らを思い出し、そして改めて彼らの魅力に迫ってみよう。
天才ギタリストのヤン・アッカーマンを擁していたフォーカスは、巧妙な音楽スタイルで当時としては珍しいインストゥルメンタル系で成功し、70年代においてオランダを代表するバンドとなっていた。1969年に結成したフォーカスはシングル「House Of The King」で注目を集め、イギリスでは4つものテレビ・シリーズのテーマ曲を担当した。メンバーのテイス・ヴァン・レールがフルートを使うことから、うっかりジェスロ・タルと勘違いしてしまう人もいたかもしれないが、このバンドには大きな違いがあった。1971年に発表されたセカンド・アルバム『II』からの鮮烈な楽曲「Hocus Pocus(邦題:悪魔の呪文)」は世界的なヒットとなり、フォーカスは見事にブレイクした。更にサード・アルバムではエレガントなメロディが印象的な「Sylvia」によって世界中で更なるファン層を獲得すると同時に、ヤン・アッカーマンも称賛の的となった。1976年にヤン・アッカーマンはバンドを脱退したものの、その後は何度かバンドに復帰も果たしている。フォーカスは現在も活動を続けている。
ヤン・アッカーマンだけではなく、70年代はみんなギター・ヒーローに憧れていた。亡きジミ・ヘンドリックスの後継者としても認められていた元プロコル・ハルムのロビン・トロワーもその一人だった。1973年にトリオ・バンドを結成したロビン・トロワーは、ストラトキャスターから奏でられる泣きのギターで素晴らしい作品をいくつも世に発表した。中でも1974年発表のソロ作『Bridge Of Sighs(邦題:魂のギター)』や1975年発表の『For Earth Below(邦題:はるかなる大地)』はヒット・チャートの上位にも登場。母国イギリスよりもアメリカでの人気が高かったプレイヤーの一人でもあった。優れたギター・バンドといえば、ウィッシュボーン・アッシュも忘れてはいけない。ウィッシュボーン・アッシュはツイン・リードのギター編成に加え、アンディ・パウエルとテッド・ターナーの二人のヴォーカリストでファンを魅了した。メロディックかつブルージーなサウンドに神話的な要素を取り入れた1971年発表の『Pilgrimage(邦題:巡礼の旅)』と1972年発表の『Argus(邦題:百眼の巨人アーガス)』はその時代の名盤として評された。あまりにも多くのファンが彼らの名曲「Blowin’ Free」のイントロを楽器店で引くことから、店によってはこの曲の演奏を禁止するところも出たという社会現象まで起こっている。アイアン・メイデンの中心人物として知られるスティーヴ・ハリスもウィッシュボーン・アッシュから大きな影響を受けた一人だった。

次に紹介するのは所謂B級系とも言えるバンドだが、主流のアーティストに比べて個性的なバンドが多かった。かの有名なデザイナー、ロジャー・ディーンによるユニークなアルバム・ジャケットを使っていたことでも知られるオシビサはアフリカ・ガーナ系のサウンドにロックとカリブ系のグルーヴをブレンドさせたアフロ・ロック系の音楽をプレイしていた。彼らの最大のヒット曲でもあった「Sunshine Day」はさておき、注目すべきは当時のリスナーを熱狂させたデビューLPと1974年に発表されたセカンド・アルバムの『Woyaya』。初期メンバーとしてサンディ・デニーやリック・ウェイクマンも参加していたストローブスはフォーク、ロック、グラムをブレンドしたスタイルに社会的な歌詞を取り入れ、「Part Of The Union」や「Lay Down」といった楽曲でヒットした。バンドのスタイルが多彩過ぎたという点もあるが、『Just A Collection Of Antiques And Curios』(1970年発表)と『Grave New World』(1972年発表)は高く評価された。その他にアメリカ・イリノイ州出身のシンガーソングライター、エミット・ローズも忘れてはいけない存在だ。’新たなポール・マッカートニー’とも言われたエミットの楽曲は自分自身で全ての楽器を演奏してレコーディングするという手法をとっていたので驚きだ。セカンド・アルバムとなったセルフ・タイトルの作品は美しくメロディックで、バロック風なエッセンスも兼ね備えた楽曲を揃えながら1970年のヒットチャートでは29位までしか上がらなかったというのも不思議だ。紛れもなく素晴らしい才能の持ち主と言えるだろう。
70年代後半、シーンを彩ったのは美しいハーモニーを取り入れたアメリカ・カリフォルニア出身の4人組プログレッシヴ・ロック・バンド、アンブロージア。イマジネーションに満ちたセルフ・タイトルのデビュー・アルバム(1975年発表)ではカート・ヴォネガットの詩を取り入れたシングル曲「Nice, Nice, Very Nice」や「Holdin’ On To Yesterday」が話題になった。美しいオーケストレーションや現代音楽ではダウンテンポ・グルーヴと呼ばれるようになった独特のビートがアメリカでの人気のきっかけとなっていた。デビュー翌年にリリースされた『Somewhere I’ve Never Travelled』はFM局のDJたちの間で密かなブームにもなり、更にはザ・ビートルズのドキュメンタリー映画として公開された『ザ・ビートルズと第二次世界大戦(原題:All This And World War II)』のサウンドトラックではザ・ビートルズの「Magical Mystery Tour」をカヴァーしたことによりその名を更に広めた。80年代にはソフトかつソウル風なヒットを何曲か飛ばし、バンド自体は今でも活動を続けている。
素晴らしいバンドとして定評のあったアトランタ・リズム・セクション。ひとつ欠点だったのはバンド名がARSと簡略化されてしまったことだが、それでも彼らは成功を収めた。バンドの出身地は説明する必要もないだろう。彼らは1972年から1976年の間に5枚のアルバムを発表したものの、特に注目もされずレコードの売り上げも低迷した。しかし、1977年にソウルフルなサザンロック系の楽曲「So Into You」がアメリカのヒット・チャートでトップ10入りを果たしたことで全てが一変した。シングル曲のトップ10入りと同時にアルバム『A Rock And Roll Alternative』も大ヒットした。翌年には「Imaginary Lover」と「I’m Not Going To Let It Bother Me Tonight」も続けてヒットし、アルバム『Champagne Jam』もプラチナディスクを獲得 。その後も「Do It Or Die」等をヒットさせた他、ARS以前に二人のメンバーが所属していたクラシックス・フォーの1967年ヒット曲「Spooky」をリバイバルさせたことも話題となった。紛れもなく一流アーティストと呼べるバンドだった。
アトランタ・リズム・セクションと共通したスタイルを持つバンドといえば「Jackie Blue」(1974年)が最大のヒット曲となったAORとカントリー系のサウンドをブレンドしたスタイルを特徴としたオザーク・マウンテン・デアデヴィルズ。彼らのブギーな「If You Want To Get To Heaven」も是非聴いて頂きたい。また、サード・アルバムのタイトルを『The Car Over The Lake Album』(訳:湖の上の車のアルバム)というような少し馬鹿げたセンスを持ち合わせていたところも話題となった。1973年から1980年までアナログ時代を支えたバンドのひとつだった。
同じ南部系のバンドで、子供の悪戯からバンド名を取ったウェット・ウィリーというバンドもいた。名前の由来はともかくとして、その音楽は一級品だった。アメリカ・アラバマ州出身のウェット・ウィリーは5〜6人の中心メンバーに加えてザ・ウィリエッツと呼ばれたコーラス隊で構成されていた。このザ・ウィリエッツにはイギリスのスター歌手エルキー・ブルックスが短期間参加していたこともある。4枚目のアルバム・タイトルにもなった簡潔でノリの良い「Keep On Smilin’」がバンドの最も有名なヒット曲となったが、バンドの真骨頂でもある荒くてファンキーなロックを堪能するなら、その前作となったライヴ・アルバム『Drippin’ Wet』を是非とも聴いて頂きたい。その他にも1972年から1973年にかけて素晴らしいアルバムを2枚発表したマナサスも忘れてはいけない。真のスーパースター、スティーヴン・スティルスを擁し、ザ・バーズやフライング・ブリトー・ブラザーズのクリス・ヒルマンをはじめ、多くの優れたミュージシャンが参加した素晴らしいバンドのひとつだった。セルフ・タイトルのデビュー・アルバムはカントリー・ロックのルーツ的な魅力を全て封じ込めた名盤となった。関係者の間では誰もが最高のバンドと高く評価していたものの、これ以上の成功を収めなかったのが不思議である。きっとファンはクロスビー、スティルス&ナッシュを望んでいたからに違いない。
一方、アメリカから海を渡りイギリスではギタリストの名前をそのままバンド名にしたブリンズリー・シュウォーツというバンドがいた。アメリカ進出でニューヨークのフィルモア・イーストでライヴを行った際に過剰に宣伝され、厳しい評論家たちの批評の対象となってしまったことも有名な話ではあるが、その後バンドは地味な活動を続けながらもロンドンのパブ・ロック系音楽の土台ともなるカントリー・ロック&ルーツのスタイルを貫き通した。決して大きいとは言えないファン層を確立しながらブリンズリー・シュウォーツはウィングスやデイヴ・エドモンズの前座として常にツアーを行っていたが、大きな成功もなく1975年に解散。カントリー色の強い『Nervous On The Road』等、6枚のアルバムを世に残した。その後、ブレンズレー・シュウォーツのメンバーはそれぞれの道を歩み、成功を収めた者も多い。ベーシストでソングライターだったニック・ロウはダムドやエルヴィス・コステロをプロデュースした他、デイヴ・エドモンズ率いるロックパイルのメンバーとしても活躍した。また、ニック・ロウはドクター・フィールグッドの代表曲となった「Milk And Alcohol」のソングライターとしてもクレジットされている。ダウンビート系の英雄といえばスコットランドのギタリスト、ミラー・アンダーソンがいる。彼はキーフ・ハートリー・バンドやサヴォイ・ブラウン、イアン・ハンター、ジョン・ロード等、多くのアーティストの作品でブルース色の強い情熱的なギターを披露している。70年代に英国デラム・レコードの傘下にあったデッカ・レーベルからリリースされたミラー・アンダーソンのソロ・アルバム『Bright City』は意欲的であり、見事なオーケストラ・アレンジと70年代アーバンライフをテーマにした素晴らしい作品でありながら・・・全く売れなかった。それまではあまり注目されることのなかったミラー・アンダーソンのヴォーカリストとしての才能も十分にあっただけに、とても残念な結果である。
ギタリスト兼フルート奏者のアンドリュー・ラティマー率いるプログレ界のスター・バンド、キャメル。キーボード奏者のピーター・バーデンズも参加していたキャメルは1972年にMCAより名曲「Never Let Go」を収録した『Camel』でデビュー。その後はデラム・レコードに移籍し『Mirage(邦題:蜃気楼)』をリリースしてアメリカでも着実にファン層を広げた。1975年に発表されたインストゥルメンタル・アルバム『The Snow Goose(邦題:白雁)』は同名の子供向け短編小説の著者ポール・ギャリコとの闘争に発展。バンドがタバコ・ブランド“キャメル”と関係しているのではないか、というポール・ギャリコ側の誤解から生じた事件だったが、結果的にアルバム自体は予想以上の成功を収めた。その翌年にリリースされた『Moonmadness(邦題:月夜のファンタジア)』もヒットとなり、何度かメンバーチェンジを行いながらもバンドは1984年までヒット・チャートに名を連ねていた。
次にご紹介したいのは実力派の4人組プログレッシヴ・ロック・バンド、バークレイ・ジェイムス・ハーヴェスト。チャートのトップ40に全く入ることなく5枚ものアルバムを発表した後、遂に2枚組のライヴ・アルバム『Live』でブレイクした。長年の苦労と努力が生んだファン層によって支えられた結果と言える。彼らがリリースした数々のLPの中でも『Everyone Is Everyone Else』、『Octoberon』、『Time Honoured Ghosts』はバンドの名盤として評価されている。また、これらのアルバムに収録されている「Mocking Bird」や「Poor Man’s Moody Blues」は現代音楽ではもはや聴くことのできないような名曲と言っても過言ではない。次にサイケデリック時代に活動していたサイモン・デュプリー&ザ・ビッグ・サウンド(60年代後期にはザ・モールズとも名乗っている)が母体となって生まれ、後に70年代プログレッシヴ・ロック・バンドの代表格へと成長したのがジェントル・ジャイアント。母国イギリスではあまりヒットしなかったものの、ヴァーティゴやクリサリスといったレーベルに10年所属してアルバムを発表していたことからアメリカではファン・ベースが確立されていた。アルバム『Free Hand』はチャートでトップ50入りを果たした他、『Octopus』や『The Power And The Glory』は真の音楽リスナーたちを魅了した。
今回のリストに辛うじて入ったのは残念な話ではあるが、最後にイギリスからもう2バンド紹介したい。スプリングは1971年にセルフ・タイトルのアルバムを発表したメロディックな5人組。ザ・ムーディー・ブルースに似せることなく、独自のメロトロンを使ったサウンドが特徴的なバンドだが、最も評価されるべき点は後にイギー・ポップをプロデュースすることとなる、温かみのある独特の歌声を披露するヴォーカリストのパット・モーランの存在だ。そしてもう一組はT2だ。T2といえば映画を想像する方が多いだろうが、伝説的なプログレ・アルバム『It’ll All Work Out In Boomland』をリリースしたのがイギリスのバンドだ。この名盤を世に出しながらメンバーがスターになれなかったのは不思議な話としか言いようがない。ニール・ヤングとデヴィッド・ボウイを足して2で割ったようなヴォーカリスト兼ドラマーのピーター・ダントン、パワフルなギター・プレイを披露してくれるキース・クロス等、聴きどころも満載だ。BBCセッションや80年代には再結成も行われながら、バンドは大きな成功を収めることはなかった。いかに70年代が幸せな時代だったかが分かるだろう。
Written By Ian McCann
♪本記事で登場したグループの楽曲等をまとめたプレイリストをSpotifyで聞く