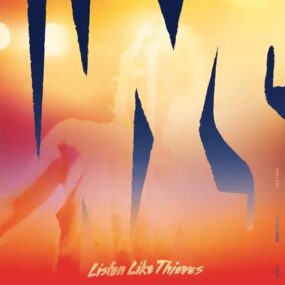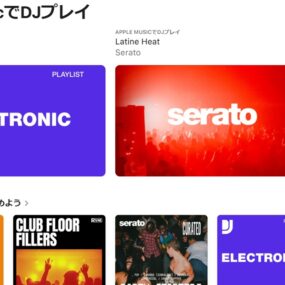Stories
スティーヴ・ミラーの力強い活躍


ロックの殿堂入りを果たしたスティーヴ・ミラーは、現在その舵取りを始めてすでに彼の半世紀の後半へと差し掛かっている。についての最近の話題といえばついついそのことになりがちだ。だがミルウォーキー出身の彼は、依然としてその力を増し、2017年6月には、彼の全てのバック・カタログに関して、彼がキャリアの大半をすごしたキャピトルと新しい契約を結んだばかりだ。
現在のラインナップでもフロントマンを務めているスティーヴ・ミラー率いるスティーヴ・ミラー・バンドの活動歴は、実に50年以上になる。全ての始まりは、1966年にサン・フランシスコでスティーヴ・ミラーがスティーヴ・ミラー・ブルース・バンド名義で活動を開始し、を結成したことにある。以降、数え切れないほどの回数のギグをこなし、2011年の『Let Your Hair Down』に至るまで合計17枚のアルバムをリリースしている。
1974年1月12日にアメリカで1位を獲得したのみならず、1990年のリイシューによって今度はイギリスでも1位を記録した長寿ヒット「The Joker」をはじめ、ミラーと彼のバンドは70年代及び80年代に繰り出した一連のポップなヒット作品によって多くのファン達に愛されている。1976年の「Rock’n Me」、1982年の「Abracadabra」など、6曲をトップ40圏内に送り込んだグループだ。
スティーヴ・ミラーは、T・ボーン・ウォーカーやレス・ポールと親交のあった父親からの影響を強く受け、ブルースとギターの魅力に夢中になって故郷のダラスで育った。そして、当時最新の音楽の発信地として盛り上がりを見せていたサン・フランシスコに移り住んだことも彼に大きな影響を与えた。これらの基盤の上に当時のブリティシュ・ロック・シーンの要素を取り込んで制作された彼らの初期3枚のアルバムは、21世紀の現在大いに再評価されるべき作品だ。
1968年にリリースされた彼らのデビュー・アルバムにして重要作『Children Of The Future(邦題:子供たちの未来)』は、あのグリン・ジョンズを迎えてロンドンでレコーディングされたもので、ジョンズは以降3枚の彼らのアルバムのレコーディングに引き続き関わっている。ちなみに『Children Of The Future』と同年リリースの2枚目『Sailor』のレコーディングには、ソロ活動を始める前のボズ・スキャッグスも加わっている。これ以上ない強力な布陣だった。
ザ・ローリング・ストーンズをはじめ多くのアーティストのレコーディングに関わったエンジニアとして尊敬を集めるグリン・ジョンズだが、その著作「Sound Man」の中で、スティーヴ・ミラーらの最初のアルバムは、自分のプロデューサーとしてのキャリアの第一歩になったと振り返っている。3枚目のアルバムとなる1969年リリースの『Brave New World(邦題:素晴らしき新世界)』の時期、グリン・ジョンズはザ・ビートルズと仕事をしている最中で、彼にセッションに招待されたスティーヴ・ミラーは、アルバムの収録曲「My Dark Hour」の着想を得ている。ポール・ラモーン名義によるポール・マッカートニーが、ドラムやパワフルなヴォーカルで参加している曲だ。
1973年の『The Joker 』は、大ヒットを記録したタイトル曲の貢献もあってスティーヴ・ミラー・バンドをメジャー級バンドに昇格させたアルバムだ。彼らにとっての初となるプラチナム・アルバムで、以降『Fly Like An Eagle(邦題:鷲の爪)』、『Book Of Dreams(邦題:ペガサスの祈り)』と続くアルバムのヒットの起爆剤になっただけでなく、過去の作品の掘り起こしをも促すことに貢献した。編集アルバム『Greatest Hits 1974-1978』は、Billboard誌のカタログ・アルバム・チャートに10年以上も居座り続け、驚異の13回プラチナム認定という離れ業をアメリカ国内だけで成し遂げている。
その後にカタログエントリーしたアルバムにも注目作品は多い。1988年の『Born 2B Blue』は、スティーヴ・ミラーが自身の音楽的バックグラウンドであるブルースへの敬意を表して1988年にソロ名義でリリースした名盤だ。グリン・ジョンズの弟であるアンディ・ジョンズを迎え、B.B.キング (「Rock Me Baby」) やハウリン・ウルフ (「Who’s Been Talkin’?」)、そしてオーティス・ラッシュ (「All Your Love」) などのブルース・マン達への愛を込めてバンド名義で2010年にリリースしたカヴァー集『Bingo!』もある。
そうした実績を持ち相変わらず精力的にツアーを行うミラーがロックの殿堂入りを果たしたことは、きわめて妥当なことだと言っていいだろう。
Written by Paul Sexton