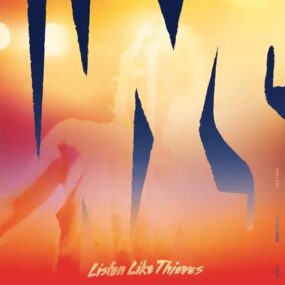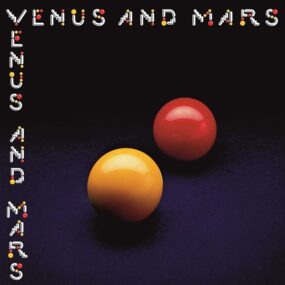Stories
スティーリー・ダンの快進撃を支えた名セッション・ミュージシャンたち


サウンドの完成度という点で、スティーリー・ダン(Steely Dan)のアルバムは常に最高水準を保ち続けてきた。そして、その多くはプラチナ・ディスクに認定されている。そんなグループを創作面で引っ張っていたのは、ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの二人だった。
だが、彼らの名曲の数々は一流のセッション・ミュージシャンたちの才能によって、いっそう質の高いものになっていた。フェイゲンとベッカーは、彼らの作風が難解さを増していくにつれて、名だたるセッションマンたちから成る“殺人打線”の力を頼るようになったのである。
また、それらの楽曲に輝きをもたらした名手たちにとっても、スティーリー・ダンの作品に参加した実績は是非とも履歴書に書き加えたいステータスだった。宇宙空間から降ってきたようなギター・ソロや、最高にファンキーなドラムのグルーヴなど、スティーリー・ダンのキャリアを彩った名手たちによる驚愕の演奏を振り返っていこう。
<関連記事>
・スティーリー・ダンとドナルド・フェイゲンのライブ盤が同時発売
・スティーリー・ダンの最高傑作『Aja(邦題:彩(エイジャ))』
・スティーリー・ダン『Gaucho』解説:いかにして悲劇を勝利に変えたのか
エリオット・ランドール:「Reelin’ In The Years」(『Can’t Buy A Thrill』収録/1972年)
スティーリー・ダンのデビュー・アルバムに収録された1曲。中盤のセクションにおける怒涛のギター・リフはあまりに印象的であり、4年後に発表されたシン・リジィの名曲「The Boys Are Back In Town」に影響を与えたのではないかとも思われる。だが、この曲をさらに上の次元へと押し上げているのは、“6弦の魔術師”と呼ぶに相応しいエリオット・ランドールによるそのあとのソロである。
ランドールは60年代に制作されたグループ最初期のデモにも参加していたため、彼らの狙いをよく理解していた。たった一度のテイクで録音されたという彼のソロでは、丁度いい具合に歪んだギターの音色が印象的だ。
またその演奏においては、指が壊れそうなほどの速弾きと、ザ・ビートルズ時代のジョージ・ハリスンの名演を思わせる会話のようなフレーズが見事に組み合わせられている。もちろん、ランドールの弾く同曲のイントロも、その後の素晴らしい展開を予感させる壮大なネタバレとして機能している。
ジェローム・リチャードソン:「Dirty Work」 (『Can’t Buy A Thrill』収録/1972年)
グループの結成時から、ジャズはフェイゲンとベッカーにとって一つの価値基準になっていた。二人はお互いに出会う前から、ビバップに魅了されていたのだ。「Dirty Work」は、スティーリー・ダンの楽曲の中でも特に素朴なソウル風の楽曲だ。しかし彼らはそんな同曲にも、ビバップ・サックス界の大物であるジェローム・リチャードソンをちゃっかりと起用している。
当のリチャードソンには、錚々たるジャズ界の巨匠たちと共演した実績があった。サラ・ヴォーンやキャノンボール・アダレイ、チャールズ・ミンガスなどはそのごく一部だ。このように実に数多くの作品に参加している彼だが、ロックのアルバムで演奏するのはこれが初めてだったという。
この曲では2回目のコーラス・パートのあと、彼のテナー・サックスが前面に躍り出る。しかし、彼は熱烈なビバップ流の演奏を繰り出す訳ではない。ここでの彼はまず、官能的にも思えるブルージーなスラーを立て続けに披露。そのあと、低音域から高音域へと移行する歯切れの良いフレーズを吹いて、楽曲を最終部へと導くのである。
フィル・ウッズ:「Doctor Wu」(『Katy Lied』収録/1975年)
4thアルバム『Katy Lied』の制作に着手したころ、スティーリー・ダンの面々はジャズらしいニュアンスの出し方を何段階も進化させていた。同作の収録曲である「Doctor Wu」は、厭世的な内容のバラードだ。彼らはその核心にある”必死さ”を表現するため、何かを探し求めるようで、同時に情熱的なソロを加えようと考えた。
そこで彼らがコンタクトを取ったのは、ビバップ界のレジェンドであるフィル・ウッズだった。リチャードソン同様にジャズの世界を代表する大物であるウッズは、バンドリーダーとして著名な人物だ。
他方で彼は、ビル・エヴァンスやディジー・ガレスピーなど、ダンの面々にとっての憧れのミュージシャンとも共演していた。そして、ロックのアルバムに参加するのはウッズにとっても初めての経験だった。この曲でウッズは、感情豊かなロング・トーンを多用したアルト・サックスのソロを披露。そのほろ苦い響きは、主人公の手から溺れ落ちていく喜びの感情を表現しているように思える。同曲の主人公にとっての喜びは、手が届きそうなのに、夢のように遠くも感じるものなのである。
ラリー・カールトン:「Kid Charlemagne (滅びゆく英雄)」(『The Royal Scam』収録/1976年)
「Kid Charlemagne」に多大な貢献をする以前から、ラリー・カールトンはソロとしてのキャリアを積みんでいた。さらにバーブラ・ストライサンドからジョニ・ミッチェルまで幅広いアーティストの作品に参加し、セッションマンとしても高い評判を得ていた。
そんな彼は、1976年作『The Royal Scam』に収録された激しくもファンキーな1曲「Kid Charlemagne」で、才気溢れるプレイを披露。彼のギターを含む同曲のインストゥルメンタル・パートは、ダンのキャリアの中でも際立った演奏として称賛を集めている ―― 彼らの作品の質の高さを考えれば、それは並の偉業ではない ――。カールトンは、楽曲の中盤でいよいよ本領を発揮する。
そこで彼は、優雅さと激しさを兼ね備えたソロを弾き、同曲におけるアウトローの物語にさらなる奥行きを加えてみせる。そして、彼は曲の最後にも再びソロを取る。ジャズ・ロック調の刺激的な演奏で聴く者の度肝を抜き、楽曲を締めくくるのである。
バーナード・パーディ:「Home At Last」 (『Aja』収録/1977年)
“ドラムの神様”と呼ぶに相応しいバーナード・パーディは、ジェームス・ブラウンが60年代に発表した楽曲の数々で好演していた。また、アレサ・フランクリンのバンドを取り仕切り、彼女の楽曲で素晴らしいグルーヴを生み出していたのも彼だった。
スティーリー・ダンが1977年に放った傑作『Aja』には、そうした輝かしい実績を持つパーディが参加した。フェイゲンとベッカーは、容易に予測できる展開に陥ることなく「Home At Last」の演奏をリードできるグルーヴを見つけるのに苦労していた。そんなときに登場したのが、“プリティ”・パーディの愛称で知られる彼であった。
そして彼は、代名詞である“パーディ・シャッフル”を応用したグルーヴですべてを纏め上げてみせたのである。ベッカーはのちに、同曲のことを振り返ってこう話している。
「彼はいつでも、独特のスタイルで演奏していた。実際に聴くまでは予測もつかないし、彼以外の誰にもできないような演奏だ。この曲はその好例だね」
ジェイ・グレイドン:「Peg」 (『Aja) 』収録/1977年)
アレサ・フランクリン、マーヴィン・ゲイ、ジョー・コッカー、ドリー・パートンなど数え切れないほどのアーティストの作品に参加してきたジェイ・グレイドン。セッション・ミュージシャンとしての長いキャリアにおいては、漫画の登場人物になった経験も持つ。ギャリー・トゥルードーの漫画『Doonesbury』の中で、架空の70年代ロック・ミュージシャンであるジミー・サドパッカーと共演したのだ。
「Peg」のギター・ソロには数人のギタリストが挑戦したが、それでも満足のいくものは生まれなかった ―― そんなとき、誰を頼ればいいというのだろう? ラリー・カールトン、ロベン・フォード、そしてベッカー自身もソロを弾いたがうまくいかなかったとくれば、スティーリー・ダンの面々がこの曲を諦めようとしたとしても無理はない。だが、そんなときにグレイドンが“打席”に立ち、“場外ホームラン”を打ってみせたのだ。
このソロだけを個別に聴いてみると、まるで別の惑星から突然降ってきたかのように聴こえる。だがその演奏は、入り組んだジャズ調のハーモニーと圧倒的にポップなメロディーが共存したトラックと見事に溶け合っている。同曲がダンのキャリアでも指折りのヒット曲になったことも頷ける仕上がりである。
Written By Jim Allen
スティーリー・ダン『Gaucho』
1980年11月21日発売
LP / iTunes Store / Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music
最新ライヴ・アルバム

スティーリー・ダン『Northeast Corridor: Steely Dan Live!』
2021年9月24日発売
CD / iTunes Store / Apple Music / Spotify / Amazon Music
- スティーリー・ダン アーティスト・ページ
- スティーリー・ダンのオリジナルメンバー、ウォルター・ベッカーが67歳で死去
- スティーリー・ダンの最高傑作『Aja(邦題:彩(エイジャ))』
- スティーリー・ダン関連記事一覧