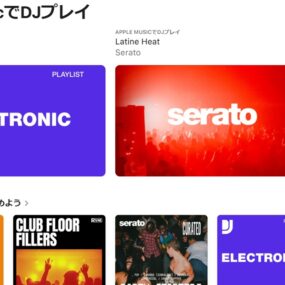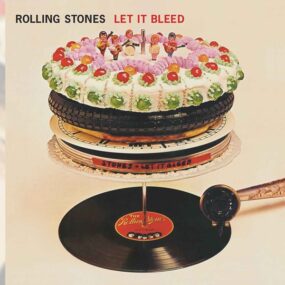Stories
テクノロジーと音楽の発展史:ハモンド・オルガンからモーグ、MIDIや808まで
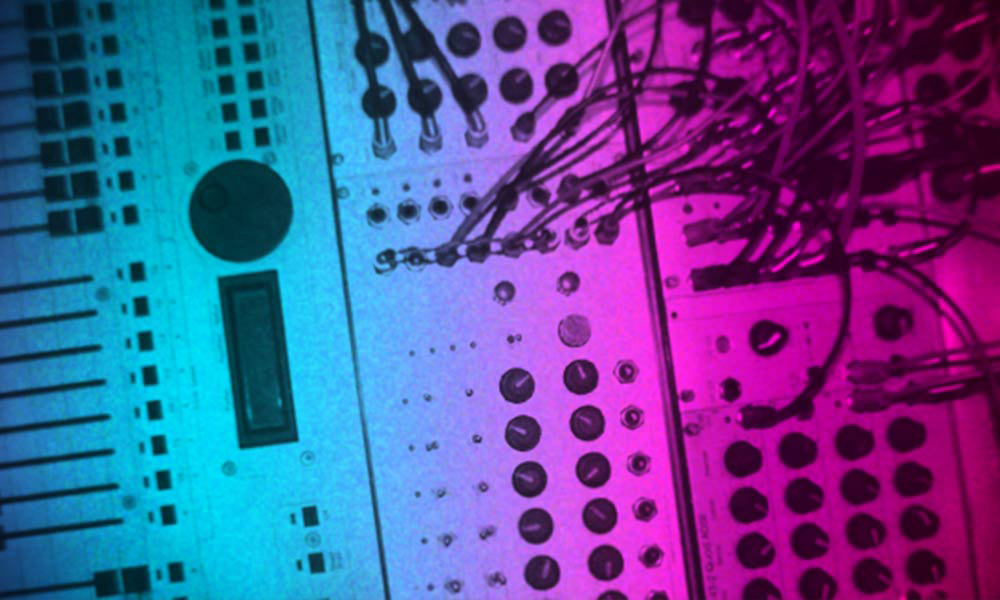
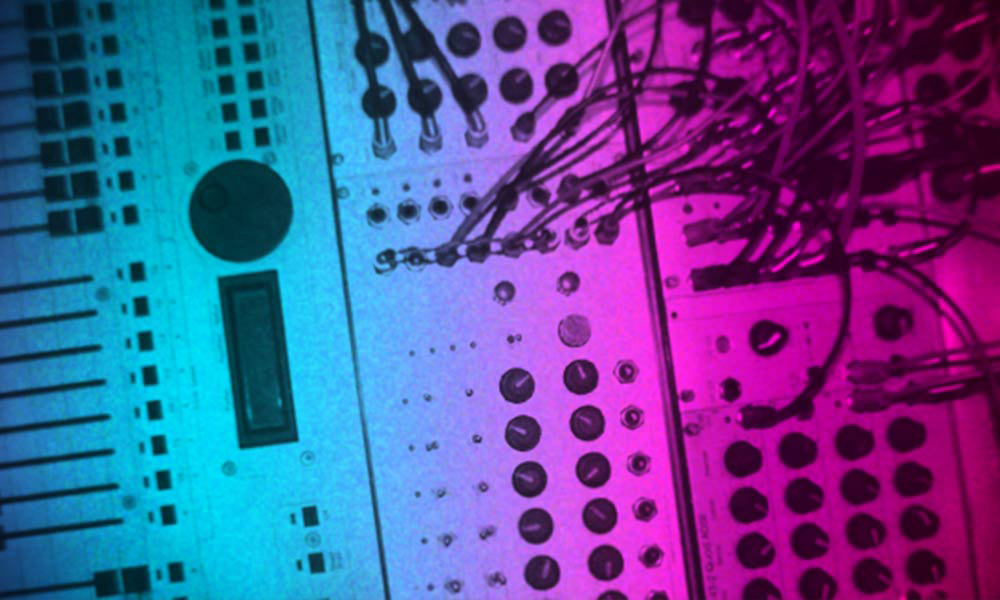
オルガンの革新者:ジミー・スミス
今の時代に聴いてみると、「単に男がオルガンを弾いているだけ」と思うかもしれない。
ブルーノート・レコードが、そのアーティストのデビュー・アルバムのタイトルを『A New Sound, A New Star』(新たなサウンド、新たなスター)としたのも、いささか気の早い話だと思うだろう。ライナーノートには、「激しく噴出する火」「音楽の天才」といった言葉が躍り、サード・アルバムの頃には、ジミー・スミスの名前には「The Incredible(ジ・インクレディブル/超人)」が付くようになった。そしてこれは本当だった。ジミー・スミスは才気に溢れていたのだ。
1年の間に、ジミー・スミスは腕の良いクラブ・ピアニストから、ジャズの世界で電子オルガンの存在を示すことになった。ジミー・スミスは、アルト・サックスにおけるチャーリー・パーカーのように、オルガンの革新者となったのだ。
ジミー・スミスは、教会の楽器だと一般には認識されていたオルガンを使って、ハリケーン襲来中に揺れるハンモックのようにスウィングしてみせた。ジャズ・オルガン奏者の第一号ではないが、彼が電子オルガンの可能性を切り開いた最初の人物であることは確かだ。
一人オーケストラとも言える彼は、まるでオルガンのヴォリューム・スライドをすべて引くかのように、全力を尽くしてサウンドを変化させ、エンファシス(音質を確保するの手段の1つ)を加え曲の雰囲気を自在に変えると、電子オルガンの中にグルーヴ、ソウル、ファンクを見出した。彼は、冷たい電子機器を熱く演奏した。しかし、ジミー・スミスの変革は、鍵盤楽器だけの話ではない。あれは、音楽的な変革であったと同時に、経済的な変革でもあったのだ。リスナーだけでなく、クラブのオーナーたちもこのサウンドを愛した。ジミー・スミスの例に倣い、多くのオルガン奏者がデュオ、またはトリオでツアーに出た。
ハモンド・オルガンの広がり
オルガン奏者たちは、ペダルでベース、右手でメロディ、左手でオーケストラ的なテクスチャーのコードを弾いた。ホーンのような効果も容易く、フルートやパーカッションはプリセット・サウンドとしてついてきた。オルガン奏者が本当に必要としていたのはドラマーだけで、リズムや彩りを加えるために、ギタリストを招くこともあった。つまり、オルガン・バンドは低予算で雇えたのだ。ステージが193キロのハモンドB-3の重みに耐えられるクラブは、喜んでオルガン・バンドをブッキングした。
ジミー・スミスの後に続き、大勢の演奏家がピアノからオルガンに転向し、人気を博した。ブラザー・ジャック・マクダフ、リチャード・‘グルーヴ’・ホームズ、ジョニー・‘ハモンド’・スミス、ラリー・ヤング……彼らは力強く誇り高く、大音量でオルガンを弾いた。そして、グルーヴするのが大好きな黒人オーディエンスをターゲットとしていた。観客はオルガンのサウンドに慣れていた、というのも、土曜日にクラブで盛り上がった翌日、日曜日には教会で祈りを捧げていたからだ。
ハモンドは当初、パイプ・オルガンの割安な代替品として売り出され、60年代半ばには、アメリカにある50,000の教会に設置された。そのため、グルーヴは違えど、ナイトクラブで流れるサウンドは、彼らにとって聴きなれたものだったのだ。
ロータリースピーカーとフルにきかせたヴィブラートを従えたオルガンのサウンドは、クラブでも教会でも、人々の魂を動かした。パイプ・オルガンやフル・バンドに比べれば扱いやすく比較的安価だったハモンドが音楽を変貌させたのも当然だろう。オルガン音楽は60年代には大衆のジャズとなった。ジャズはハード・バップから‘ニュー・シング’、そしてフリー・ジャズからフュージョンへと進展したが、オルガン・ジャズは、大学の学位を持たない観客にも理解できる音楽であり続けたのだ。
当時、ロックン・ロール・バンドの大半はまだピアノを使っていた。ピアノは、17世紀終盤の発明時、革命的なテクノロジーだった。というのも、ひとつのヴォリュームのみでしか弦を弾くことができなかったピアノの前身であるハープシコードとは異なり、ピアノは強くも弱くも弾けたためである(ピアノ本来の名称は、弱い音と強い音を意味する‘ピアノフォルテ’だ)。しかし、ピアノは持ち運ぶには不便な楽器だった。そのため、60年代にトランジスタを備えたキーボードがミュージック・ショップに並ぶと、ビート・グループやガレージ・バンドはこれを喜んで取り入れた。英国では、白鍵と黒鍵を入れ替えた個性的な外観を持つオルガン、ヴォックス・コンチネンタルがよく使用された。
ヴォックス・コンチネンタルの発売から2年後、アニマルズは同オルガンを世界的スマッシュ・ヒットとなった「The House Of The Rising Sun」で使用し、そのダークで物悲しい音色は、多くのアーティストに影響を与えた。例えば、ザ・ドアーズのレイ・マンザレクは同バンドのデビュー・アルバムと「Light My Fire」で、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドは「Sister Ray」でヴォックス・コンチネンタルを使った。
その後、60年代的なサウンドを求めたバンドは、ヴォックスのオルガンに注目した。例えば、エルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズのスティーヴ・ナイーヴは「Watching The Detectives」で、ザ・スペシャルズのジェリー・ダマーズは「Ghost Town」で同オルガンを演奏している。今日では、ザ・ホラーズのトム・ファースや、マット・ベリーが使用している。
アメリカにおいては、コンチネンタルはイタリア製のファルフィッサとの競争にさらされた。ファルフィッサはコンチネンタルよりも甲高く、時に不気味なサウンドで、60年代のガレージ・バンドの個性を際立たせた。サム・ザ・シャムの「Wooly Bully」をはじめ、多くの名曲で使用されている。また、ファルフィッサはマッスル・ショールズでソウル・ミュージシャンにも愛用され、パーシー・スレッジの「When A Man Loves A Woman」で厳粛かつ神聖なサウンドを提供している。
さらに、サンフランシスコでは、スライ・ストーンによるヒッピー革命にグルーヴをもたらした。スライ・ストーンがファルフィッサを弾いている姿は、ウッドストックの映像で見ることができる。プログレ・バンドやサイケ・バンドも、ファルフィッサの異世界的な可能性に心惹かれた。
ピンク・フロイドは『The Piper At The Gates Of Dawn(夜明けの口笛吹き)』で、ヴァン・ダー・グラーフ・ジェネレーターのヒュー・バントンは『The Aerosol Grey Machine』でファルフィッサを使用している。しかしそれでも、鍵盤の王者はハモンドだった。偉大なる故キース・エマーソンは、その高度な技術とショーマンシップを融合し、ハモンドL100にナイフを突き立てると、ザ・ナイスと共にクラシック音楽的ロックの先駆となった後、エマーソン・レイク&パーマーでその音楽性をさらに極限まで進めた。
無接触の楽器テルミン
60年代でも特にモダンなサウンドは、古来のテクノロジーによって作られていることもある。ザ・ビーチ・ボーイズは、ロシア人発明家のレフ・テルミンにちなんで名づけられた楽器(テルミンは1928年に特許を取得)を使った。テルミンは‘無接触’の楽器で、2つのアンテナの間で手を振ることによって、音が調整される。
「Good Vibrations」で聞かれる甲高く薄気味悪いハウリング・サウンドは、テレミンで作られたものだ。ザ・ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズも、テルミンの奇妙で物悲しい電子音に魅せられ、ザ・ローリング・ストーンズの「2,000 Light Years From Home」で使用している。
電子楽器が音楽を形成するというと、しっぽが犬を振るのように主語と述語が逆転しているかのように思えるかもしれないが、電子楽器で作られたサウンドは、アコースティックな楽器で作られたサウンドよりも手を加えやすい。ヒュー・バントンは自身のファルフィッサ・オルガンをカスタマイズすると、エフェクト・ペダルに通した。鈴のように響く時に妖精のようなサウンドを持つフェンダーローズの電子ピアノは、時にファズボックスでラフな雰囲気を加えられた。
ヴァリトーンという電子サックスは、ラスティ・ブライアントやルー・ドナルドソンに、新たな電子的トーンを与えた。有名なところではエディ・ハリスもヴァリトーンを愛用したが、ヴァリトーンに対する彼らの関心は長続きしなかった。
サウンドの電子化
マイクロフォン、いわゆるマイクも、アコースティックな楽器に一味違った趣を加えることができた。エディ・ハリスはサックスにマイクを通してちょっとしたエフェクトをつけることを好み、ナポレオン・マーフィー・ブロック(フランク・ザッパと70年代半ばに共演していたバンドのフロントマンで過小評価されている)は「Cosmik Debris」でサックスにワウワウのエフェクトをかけている。
ジャズ・ミュージシャンの中でも特に生の音を大切にしていたマイルス・デイヴィスも、『Live-Evil』でワウペダルを使いながらトランペットを吹き、純粋主義者たちに衝撃を与えた。最も熱心な信奉者はニック・ターナーで、ホークウィンドと共に、ソリッドステートのサックスで、銀河を漂っているかのようだった。70年代初頭には、マイクさえ使えば、電子的なサウンドを作ることができたのだ。
ロバート・モーグ博士による新しいサウンドを出す楽器
それでも、サウンドを電子的にすることと、電子楽器を弾くことは似て非なるものだった。ギタリストはエフェクト・ペダルを揃えたが(これでギターの技術不足をごまかそうとする向きもあったが)、その目的は常に、楽器の音質を変えることにあった。10ccのケヴィン・ゴドレイとロル・クレームが開発したギズモトロンの場合、その目的は、ギターのサウンドを他の楽器の音色にする、というものだった。「Gizmo My Way」で聞かれるストリング・サウンドがその例である。
一方、ニューヨークはマンハッタンにあるコロンビア大学の研究室では、技術者たちが全く他とは違う新しいサウンドを出す楽器を作ろうと、研究に励んでいた。実際、地上に存在しない音だと言った人々もいた。
ロバート・モーグ博士が手掛けた原子爆弾開発計画マンハッタン・プロジェクトの音楽版は、トランジスタ技術を使い鍵盤楽器を作るというもので、その鍵盤楽器で作ったサウンドを無限に形成することができるという理論だった。高音を増やしたい、低音域を避けたい、サウンドを振動させたい、滑らかでクリーンな正弦波から不鮮明な音の矩形波へと波形を変化させたい、といったことがすべて可能で、その他にもたくさんのことができた。
モーグは1964年にはこの技術を作り出しており、60年代半ばには、彼のモジュラー・シンセサイザー(旧式の電話交換機のように、ケーブルで様々なセクションを繋いでいた)は、冒険好きなミュージシャンに向けて発売されていた。実験主義なコンポーザーたちがまずは試したが、1967年にはモンキーズのミッキー・ドレンツが『Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd』でモーグを使った。ミッキー・ドレンツはごく初期の使用者で、彼が持っていたのはモーグが最初に製造したシンセサイザー20台のうちのひとつだった。そして、いくつかの証言によれば、3台目に売れたものだという。
シンセサイザーの可能性
それでも、シンセサイザーの実際の役割をきちんと分かっている者はいないようだった。音楽の核を作るというよりも、当時はシューッというノイズや雰囲気を作り出すために使わることが多かった。60年代半ば、フランス人コンポーザーのジャン=ジャック・ペリーはガーション・キングスレイと組んで、モーグとオンディオリンで制作したアルバムをリリースしはじめた。オンディオリンは、初期の電子鍵盤で、音楽というよりは「斬新な電子エンターテインメント」と考えられていた。
ジャン=ジャック・ペリーはテープ・サンプリングのパイオニアで、「Gossipo Perpetuo」(1972年)では人間の声のクリップを使っている。13年後、世界的メガヒットとなったポール・ハードキャッスルの「19」でもこのエフェクトが使われているが、ペリーはその功績をほとんど認められていない。
同様の運命を辿ったのが、BBCレディオフォニック・ワークショップ(BBCの音響ユニット)だ。一般に認知された最初の電子音楽チューンともいえるドラマシリーズ『ドクター・フー』のテーマ曲を作ったことで知られる同ユニットだが、ここに属していたエレクトロ・ミュージックのパイオニアたちは、テレビの冒険番組に奇妙な音を提供することばかりを求められた。
ロッカーたちは、シンセサイザーの大きな可能性に飛びついた。キース・エマーソンはモーグを使った。ジョージ・ハリスンは2作目のソロ・プロジェクト、『Electronic Sound(電子音楽の世界)』(1969年)で、楽しみながらファンの先入観に挑んだ。ポール・ブレイ、ディック・ハイマン、そしてもちろん、宇宙の旅人、サン・ラーなど、ジャズ・ミュージシャンもシンセサイザーを取り入れた。
しかし、シンセサイザーには音楽的な信頼性があることを広く一般に示したのは、ロバート・モーグ博士とモーグ・シンセサイザーの開発に携わったコンポーザー/レコーディング・エンジニアのウェンディ(元ウォルター)・カルロスだ。
当時作られていた電子音楽の大半を「無意味でインチキで日和見主義のもの」と呼んでいたロバート・モーグだが、カルロスの商業デビュー・アルバムについては、「非の打ちどころない出来」だと力説し、「明らかな音楽的意義を持ち……非常に革新的」だと評している。そのアルバムとは、1968年にリリースされて大ヒットした『Switched-On Bach』で、アメリカのクラシック音楽チャートで数年にわたって首位の座を守った。
カルロスによるバッハの解釈はセンセーションとなり、ウェンディ・カルロスがスタンリー・キューブリック監督の問題作『時計じかけのオレンジ』(1971年)で音楽を担当したことも、その成功を後押しした。
モーグを使ったアルバムは、レコード店にも数多く登場した。ジャズ・フルート奏者のジョー・トーマスは、エボニー・ゴッドファーザーという別名で『Moog Fluting』を制作し、「エキゾチカ」の代表的アーティスト、マーティン・デニーは『Exotic Moog』をリリース。トントズ・エクスパンディング・ヘッド・バンド(マルコム・セシルとロバート・マグーレフのデュオ)は、批評家からの高い評価を受けている。
プログラマーというクレジット
シンセは至るところにあったが、それを使いこなすには専門知識を必要とした。スティーヴィー・ワンダーが70年代にシンセサイザーを取り入れ、名盤『Music Of My Mind』と『Talking Book』(どちらも1972年リリース)を制作した時、スティーヴィー・ワンダーはマルコム・セシルとロバート・マーゴレフの助けを必要とし、コンピューターの世界でか使われなかった‘プログラマー’という言葉は、いまや正当な音楽業界の仕事としても認められるようになった。
プログレシンセ・バンド、タンジェリン・ドリームは、シンセサイザーを多数使用して70年代半ばに『Phaedra』や『Rubycon』といったアルバムを制作したが、シンセは次第に小型化していった。1971年、プログレ・ロック・バンド、イエスのキーボーディスト、リック・ウェイクマンは、便利で持ち運びのできるミニモーグをごく初期に使い始めた人物だ。
シンセサイザーを製造していた企業は、モーグだけではない。EMSのVCS3はポータブルなシンセとして人気が高く、ブライアン・イーノがロキシー・ミュージックで使用していたほか、ザ・フーの「Won’t Get Fooled Again」のイントロでは、ロウリーのオルガンに接続されて使われている。EMSはブリーフケースに入ったEMS Synthiでさらに一歩先へと進んだ。
オーケストラの代わりに
これとは対照的に、ARPはいくつかの楽器を並行して使えるシーケンサーを内蔵した巨大なシンセを作った。初期のシンセサイザーはモノフォニックで、これは1度にひとつの音しか出ないことを意味する。なお、ポリモーグ(1975年)やコルグPE 2000(1976年)といったポリフォニックなシンセサイザーでは、キーボード奏者は和音を出すことができる。

60年代と70年代、奇妙な合成音だけがシンセサイザー唯一の選択肢ではなかった。ミュージシャンはオーケストラやストリング・アンサンブルのサウンドを使いたいと思うことも多かったが、オーケストラやアンサンブルを雇ってオーケストラのアレンジを書くのは、法外に金がかかった。
70年代、ストリング・シンセサイザーが実用化され、例えばARPストリング・アンサンブル(1974年)は、エルトン・ジョンの「Someone Saved My Life Tonight」やリック・ジェームスの「Mary Jane」で使われている。それ以前は、メロトロンが使われていた。
メロトロンという機材
メロトロンは、鍵盤が押されると、テープ・ループを用いてストリングス、ホーン、フルート、リコーダー、オルガン、声といったサウンドを出す機材だ。1963年に発売され、それから2年後、グラハム・ボンドがロック・ミュージシャンで初めてメロトロンを使ったと言われている。
ザ・ビートルズは「Strawberry Fields Forever」でメロトロンを使用し、今日に至るまで続いているサイケデリックで斬新な音楽の基準を定めている。こうした音楽の中で、メロトロンのリコーダーとわずかに不気味な雰囲気のあるオーケストラが、LSDによる幻覚状態を表現している。
しかし、メロトロンと最も密接に結びついていたグループは、ムーディー・ブルースだ。彼らは、キーボード奏者のマイク・ピンダーの先見の明により、息の長いキャリアを築いた。ピンダーは、労働者クラブから中古楽器を買うと、1967年に「オーケストラをやろう」とバンドを説得。そこからシングル・ヒット「Nights In White Satin」と、メロトロンを多用したアルバム『Days Of Future Passed』が生まれた。
とはいえ、ハモンド・オルガンもロック界でいまだ愛用されており、1972年リリースの『Machine Head』に収録されているディープ・パープルの名曲「Highway Star」や「Lazy」で聴かれるジョン・ロードの演奏は、ロック・キーボードの進化同様に刺激的だった。
ジョルジオ・モロダーとディスコ
完全な電子音楽という概念は、70年代初頭の時点ではまだまだ珍しく、1972年にガーション・キングスレイの「Popcorn」をヒットさせたホット・バターのようなアーティストぐらいしか実践していなかった。しかし、ある1人の男が、マシンの意のままに人間を前進させる(「踊らせる」と言った方がいいだろう)未来を思いついた。その男とは、ジョルジオ・モロダーだ。
イタリア出身で、ミュンヘンを本拠にユーロポップ・ヴォーカリストとしてまずまずの成功を収めていたジョルジオ・モロダーは、60年代にバブルガム・チューンを書き、70年代には自身のレコードをプロデュースしていた。例えば、シンセサイザーを大きくフィーチャーした「Son Of My Father」(1972年)もそのうちの1曲である。
ジョルジオ・モロダーのヴァージョンは、すぐに英国出身の無名バンド、チコリー・ティップにカヴァーされ、カヴァー・ヴァージョンの方が大きなヒットとなったが、数年のうちにモロダーは、セクシーなディスコ・ヴォーカリスト、ドナ・サマーのプロデューサーとして名声を確立する。
ジョルジオ・モロダーは、ディスコ・ミュージックに反復的なリズム・セクションが必要であることを知っていた。スパンデックス、サテン、スパンコールのチューブトップを身にまとった人々が、ダンスフロアをSFのファッション・ショウに変えていた当時、シンセサイザーのサウンドが時代にマッチしていることは明らかだった。
ジョルジオ・モロダーは、電子楽器だけを使って音楽を作っていたデュッセルドルフのクラフトワーク(1974年の魅惑的な「Autobahn」がチャート入りするヒット)をインスピレーションにすることもできたが、ジョルジオ・モロダー本人によれば、タンジェリン・ドリームの多層的で陰影のあるサウンドを好んでいたという。ジョルジオ・モロダーは、電子音楽に対する10年来の関心をまとめ上げ、1977年にドナ・サマーの「I Feel Love」を制作。同曲は、全てを凌駕するディスコ・クラシックとなった。
とてつもなく大きく高価なモーグ・モジュラーで主に作られた同曲の中で、人力によるものは、マイクをつけたバスドラムとドナ・サマーのヴォーカルだけである。そしてそのうち、モロダーは全くドラマーを使う必要もなくなった。
ドラムマシンの発展
原始的な形のドラムマシンは30年代から存在した。50年代には塊のように大きなキットとなり、メロトロンのようにテープを基盤とし、マンボやタンゴなどプリセットされているリズムしか演奏できなかった。オルガン奏者が使用することが多く、時にオルガンの一部として使われることもあったドラムマシンだが、ドラムのサウンドには程遠く、大抵はプログラムもできなかった。とはいえ、少なくともドラマーよりも静かなビートを提供した。
60年代、ドラムマシンはさまざまなラテンのリズムを刻んでいたが、そのうちのひとつはバンディート・ザ・ボンゴ・アーティストと呼ばれていた。60年代後半になると、ロック・アーティストは、生のドラムに代わるものとしてではなく、生のドラムの補助として、原始的なリズム・ボックスを使いはじめた。
ロビン・ギブの「Saved By The Bell」(1969年)や、「Family Affair」をはじめとするスライ・ストーンのプロダクションの数曲にもリズム・ボックスが使われている。なお、「Family Affair」で使われていたのはマエストロ・リズム・キングMRK-2で、スライはこれを「俺のファンク・ボックス」と呼んでいた。
![Maestro Rhythm King MRK-2 [2] - 300](https://www.udiscovermusic.jp/wp-content/uploads/2016/05/Maestro-Rhythm-King-MRK-2-2-300-300x200.jpg)
1974年には、レゲエ・アーティストがドラムマシンで実験を始め、リー・ペリーはマックス・ロメオの「Tan And See」でドラムマシンを使い、アストン・バレットは1974年、「So Jah Seh」でボブ・マーリーにドラムマシンを紹介した。
ローランドTR-808
80年代初頭になると、ドラムマシンはポータブルになり、既存のパターンに依存することなく、プログラムもできるようになっただけでなく、ドラムさながらのサウンドも出せるようになった。また、値段も手ごろになったため、ニューヨークのエレクトロ・アーティストはスタジオに入る前にベッドルームで練習することができた。
ローランドTR-808は、特に好んで使用された。当時出回っていたリンLM-1ほどの柔軟性はなかったが、腹に響くバスドラムのサウンドが魅力で、リンの20%の価格で購入できた。808を開発したのは、日本のエンジニア、梯郁太郎だ(彼は2017年4月3日、87歳で死去)。

梯が作ったアイコニックなキック・ドラム・サウンドは、アフリカ・バンバータの「Planet Rock」(1982年)で鳴り響いている。マーヴィン・ゲイも「Sexual Healing」で使用しているほか、‘ブーンバップ’というビートが印象的なヒップホップ楽曲の数々に‘ブーン!’の音を提供している。
808を受け継いだのはTR-909で、同機はハウス・ミュージックとダンスポップ・ヒットにビートを提供した。例えば、スナップの「I’ve Got The Power」は、909のデモンストレーション楽曲と言えるだろう。レゲエもようやくドラムマシンの喜びに目覚めると、1985年、小さなカシオ・キーボードで作られたウェイン・スミスの「Under Me Sleng Teng」で「ディジ(デジタル)」時代に突入する。
ルーツ・レゲエもこれに続き、ディジダブとステッパーズ・スタイルは安価なテクノロジーを使い、ディープ・ダブを作った。オーバーハイムDMXもビートボックスで、ラッパーのDMXの名前は同機に由来している。幅広い人気を獲得したオーバーハイムDMXは、ロック界にも受け入れられ、ユーリズミックスの「Sweet Dreams (Are Made OF This)」や、ニュー・オーダーの「Blue Monday」、ZZトップの「Eliminator」に使用された。
高級だったフェアライトCMI
80年代前半に入ると、至る所で目につくようになったテクノロジーがある(ただし、所有するには大金を必要とした)、それがフェアライトCMI(コンピューター・ミュージカル・インストゥルメント)だ。これは、ワークステーションとして使用されることを意図したサンプリング・シンセサイザーだった。大きめの家庭用コンピューターといった外観だったが、その質の高いサウンドと使いやすさで、進取の気性に富んだ幅広い層のミュージシャンから人気を博した。
ピーター・ガブリエルは英国で一台目を購入し、友人のケイト・ブッシュもピーター・ガブリエル同様にフェアライトCMIに魅了された。ヤン・ハマー、エイジア、アート・オブ・ノイズほか、多くのアーティストが同機を取り入れた。フィル・コリンズは、誰もが同機を使っていることを皮肉り、「このレコードにフェアライトは入っていません」と『No Jacket Required』のスリーヴに記している。
ワンマン・ファンク&ロックの天才、プリンスも当然のことながら、アルバムを独力で制作することを可能にするテクノロジーを最大限に活用した。サウンドはプリンスの頭の中にあり、テクノロジーによって、彼の頭の中にあったサウンドがリスナーの耳に届けられた。プリンスはリンLM-1を使用したが、80年代はこれが革命的とされた。マシンから素晴らしいサウンドを作ることができたため、彼はドラマーを雇う必要はなかった。彼はLM-1をコンプレッサー(音量が均等になるよう、楽器音のダイナミック・レヴェルを調整する機器)に通し、ドラムによりパンチを効かせた。
また、フランジャーも使用することで、短くうねりのあるエフェクトを作り出した。これこそが、「When Doves Cry」や、ジャム&ルイスによる80年代半ばのプロダクションで知られる「ミネアポリス・サウンド」だ。サウンドを聞いて、当時にタイムスリップしてみよう。テクノロジーは、時代の象徴である。時代の音楽と結びつき、流行りの楽曲をサポートしているのだ。
音楽と楽器の民主化
電子的なサウンドの質が向上し、機材の携帯性も高まったうえ、値段も手ごろになると、かつてパンクのモチベーションとなっていた「音楽の民主化」が起こった。楽器やミキシング・ボードの習得に何年もかけることなく、誰もがまともなサウンドが出せるようになったのだ。
パンクはエレクトロポップ・ムーヴメントを引き起こし、ここでミュージシャン志望の小さなグループは、ガレージを出ることなくレコードを作れるようになった。華やかなニュー・ポップで80年代前半を明るくしたグループの例としては、ヒューマン・リーグ、デペッシュ・モード、ソフト・セルなどが挙げられる。なお、ソフト・セルは、大ヒットした「Tainted Love」で、マシンにも(ノーザン・)ソウルがあることを証明してみせた。
1983年、MIDIの発達により、自宅の寝室で機材をいじっていたエンジニアたちは電子的なグルーヴをより容易く作れるようになった。MIDIは、複数のテクノロジー企業が、顧客の利益のためにひとつのプロトコルに同意したという珍しい例だ。MIDIは、電子楽器の間での通信を可能にし、ひとつのソースから電子楽器をコントロールすることを可能にする。こうして、DIY(自分でやる)精神がレイヴ・ブームまで続き、ア・ガイ・コールド・ジェラルド、ジ・オーブ、エイフェックス・ツインといった実験的ミュージシャンによる素晴らしい音楽が生まれた。
ジェラルドはローランドTB-303を見事に使いこなしていたが、この機種は短命に終わったポケットサイズのベースシンセで、2年間という製造期間を遥かに超える影響力をアシッド・ハウスに及ぼしていた
アタリやアミーガに始まりPC、マックに至る家庭用コンピューターは、より洗練されたレコーディング・ソフトを寝室で音楽づくりに興じるプロデューサーに提供した。ここに、S900(ザ・45・キングの「The 900 Number」はS900にちなんだタイトルだ)やS950(政治的な風刺が好きなKLFが使用)といったアカイのサンプラーや、業界標準のツールでようやく手ごろな価格で販売されるようになったレキシコンのリヴァーブ・ユニットなどのラックマウント式のアウトボード機材、E-muのヴィンテージ・キーズ(サンプリングの技術を使い、レトロなアナログ・サウンドを提供)が加わった。
理論上は、いまや誰でも音楽を作ることができる。また、世界中で同じテクノロジーが使われているため、例えばベルリンで作られたダンス・ミュージックは、デトロイトで作られたダンス・ミュージックに劣る、ということもなくなった(60年代から70年代の間はそうだったが)。マシンが語り、人々は踊った。ジョルジオ・モロダーのヴィジョンが現実になったのだ。
新人アーティストでも特に才能のある者たちは、技術的な先達の功績を認めた。ヴァンゲリスによる1982年のサウンドトラック『ブレードランナー』は絶賛された。スティーヴ・ヒレッジとミケット・ジローディが在籍し、70年代にサイケデリックな音楽を演っていたゴングは、ジ・オーブのアレックス・パターソンとテクノ・アーティストのカール・クレイグ、デリック・メイの助けを得て、エレクトロニック・ダンス・バンド、システム7を結成。新旧のアーティストが、テクノロジーを通じてひとつになった。
音楽活動の絶対的平等と反発
1990年代から2010年頃にかけて、音楽活動の場に絶対的な平等がもたらされた。誰もが家庭用コンピューターを持ち、誰もがプロの使ったサウンドにアクセスできるようになったのだ。マウスをクリックすれば、あらゆるものが手に入った。モロダーやクラフトワークが数週間かけて行っていたシーケンシングも、短時間でできるようになった。特別な才能など存在せず、どの才能も特別だった。問題は、その才能をいかに使うか、にあるのだ。ロック・バンドはこの状況に反発した。
ザ・ヴァーヴやプライマル・スクリーム、オアシスといったバンドは、音楽の均一化に反抗し、レトロ・クラシックな音楽を作った。大半のバンドは、60年代のヒーローたちが使った機材やアンプを欲しがっていただけだった。「ブライアン・ジョーンズはヴォックスAC30を使っていたって? 俺もそれが欲しい」といった調子だ。
また、彼らはレコードを集め、自分たちのアルバムもヴァイナル(レコード)として欲しがった。CDやダウンロードの代わりというわけではなく、CDやダウンロードに加えて、ヴァイナルというフォーマットも加えたのだ。皮肉なことに、こうしたバンドの中には、DJやサンプラーに頼って自己最大のヒットを作った者たちもいた。「Bittersweet Symphony」、「Loaded」……これらは、テクノロジー主導の楽曲だ。
古いテクノロジーが最高の存在だという思いから、ヴァイナル・リヴァイヴァルはたちまち広まり、カセットのみのインディ・レーベルが発足し、人々は旧式のアナログ・ハイファイや音楽系機材に大金を払っている。プロディジーは、ジュノ・リアクターや808ステイト同様、生産中止となったモーグのシンセサイザーにちなんでバンド名をつけた。つまり彼らは、レトロモダン時代の先を歩んでいたのだ。
機材がメッセージとなる傾向は、ますます強まっている。ジミー・スミスが当初弾いていたハモンドは、遥か昔に捨て去られているが、興味のある人々は、そのオルガンがどのモデル(型)だったかを知っている。ジミー・スミスがハモンドを弾いていた当時は、誰もそんなこと気にしていなかった。彼らが知っていたのは、音楽が素晴らしい、ということだけだ。
Written By Ian McCann