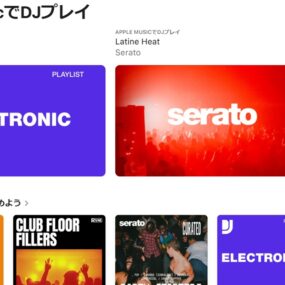Stories
プロテスト・ソング特集:人種差別や抑圧、偏見に立ち向かい、不正の告発や反戦のために歌われた歌の歴史とは?


“I thought that if you had an acoustic guitar,
Then it meant that you were a protest singer”
“アコースティック・ギターを手にしてる者は、
プロテスト・ソング歌手なのだと思ってた”
とモリッシーが歌っていたのは、ザ・スミスの曲「Shakespeare’s Sister」だ。この曲が発表された1985年当時、それはさほど珍しい観点ではなかったかもしれない。プロテスト・シンガーといえばアコギを爪弾くフォーク歌手のことを指すというのは、長い年月をかけ、ポピュラー・カルチャーの中で強固な概念となっていた。その起源は、ボブ・ディランが「The Times They Are A-Changin’(邦題:時代は変わる)」を始めとする数々の曲を大衆に届け、その後、彼の真似をした歌い手が数え切れないほど誕生し、道義的正しさについて自らの曲を通じて声を上げるようになった、1960年代に遡る。
だがそれは、何も新しいことではなかった。自分達の置かれた状況に対し不満を表現する手段として、人は有史以来、音楽を用いてきた。抗議の歌に関する記録は、古くは中世イングランドから残っている。印刷機の登場に伴い、楽譜の普及が進むと、“ブロードサイド”(片面刷りの紙に民謡を印刷して売っていた、新聞の原型)は多くの場合、バラッドを取り上げていた。そこで歌われていたのは、愛や喪失などの身近なテーマであったが、その時代の人々が懸念を抱いている様々な問題にも取り組んでいた。例えばイングランド内戦から生まれたのが、ピューリタン革命の指導者オリバー・クロムウェルを批判する歌である。このようないわゆる“ブロードサイド・バラッド”は、やがて社会主義を宣伝したり、あるいは節制や奴隷制といった様々な道徳的問題について説く歌へと移行していった。
そういった中で特に傑出していたものが、様々な国歌や伝統的な民謡として、現代にも生き続けている。共同体における歌の共有は、米国の奴隷の間でも行われていた。奴隷は踊ることを禁じられていた一方、歌うことは許されていたからだ。とはいえ、もちろん彼らの主人に批判的でない限りにおいてではあったが。
奴隷達は「Swing Low, Sweet Chariot」や「Steal Away」といった歌を、奴隷逃亡支援組織を通じて脱走する際の隠れたメッセージとして使用。私達が今考えるプロテスト・ソングとは異なるかもしれないが、こういった集団的な歌には力があるということが、やがてジョーン・バエズの「We Shall Overcome(邦題:勝利を我らに)」や、ジョン・レノンの「Give Peace A Chance(邦題:平和を我等に)」といった曲が抗議デモ行進の際に歌われるようになった時、世界中に知れ渡ることとなる。
だが20世紀初頭、新興ビジネスとして誕生したばかりのレコード業界は、第一に、人々を楽しませられる音楽を求めていた。そのためこういった立派なテーマは、ポピュラー音楽として徐々に人気を集めつつあった当時の音楽ビジネスの中では、次第に距離を置かれるようになっていった。実際、私達が今日プロテスト・ソングと見なしているものが誕生したのは、1930年代、北米で連続して起きた恐ろしい事件が、ニューヨーク在住のロシア系ユダヤ人移民の子の心を突き動かした時のことである。
20世紀初頭、米国の一部では、アフリカ系アメリカ人に対するリンチが非常に一般的に行われていた。それはボブ・ディランが1965年に発表した壮大な「Desolation Row(邦題:廃墟の街)」で詳述している通りだ。「そこで売られているのは、絞首刑の絵はがきだ」というその歌詞の一節は、彼の生まれ故郷の町で1920年に3人の黒人青年の遺体が木に吊るされた写真が出回っていたことを指していた。ニューヨークのソングライター兼詩人のエイベル・ミーアポルも同じように、1930年にインディアナ州マリオンで木に吊るされた、トーマス・シップとエイブラム・スミスの遺体の写真を目にしたことに刺激を受け、ある作品を書き上げた。それはタイム誌により、“20世紀最高の1曲”と呼ばれることになる。
その曲「Strange Fruit(邦題:奇妙な果実)」は、ビリー・ホリデイが歌った1939年のヴァージョンが特に有名だ。曲のメッセージがあまりに強過ぎたため、彼女が契約していたコロンビアがレコーディングを拒否したほどだ。しかしながらコロンビアは、別のレーベル<コモドア>から彼女が同曲をリリースすることを許可。そのシングルは、やがて百万枚以上のセールスを記録することになった。この曲は、冒頭から聴き手の心を強く捉える。
南部の木々は奇妙な果実を付ける
葉は血に染まり、根元には血が滴る
南の風に揺れる黒い体
ポプラの木にぶら下がっている奇妙な果実
ビリー・ホリデイがニューヨークのクラブに出演し始めた当初、セットリストの最後は常にこの歌で締めくくられていた(この後に歌える曲などなかったのだ)。照明を落とした会場は闇に沈み、一本のスポットライトだけが彼女の顔を照らす。そして彼女がこの曲を歌っている間、ウェイター達は給仕を中断するのだった。
その歌唱力とメッセージの力は、聴衆を捉えて離さなかった。そしてビリー・ホリデイとエイベル・ミーアポルの死後もずっと、この曲は生き続けることになる。アトランティック・レコードの創設者で有名プロデューサーのアーメット・アーティガンは、同曲を「宣戦布告……公民権運動の始まりだ」と表現していた。
公民権運動が絶頂期を迎えていた1965年、ニーナ・シモンは「Strange Fruit」をレコーディングし、そこに新たな怒りを吹き込んだ。また、英国の歌手レベッカ・ファーガソンは、ドナルド・トランプ米大統領の就任式での歌唱を打診された際、「もし“Strange Fruit”を、この歴史的に非常に重要な1曲を、あまりに大きな論争を引き起こしたためアメリカ合衆国でブラックリストに載っていたこの歌を、歌わせていただけるなら。米国で軽視されている全ての人々、そして虐げられている全ての黒人の人々について取り上げているこの歌を、この世界の全ての憎しみは愛のみによって克服できるのだということを思い出させてくれるこの歌を、歌わせていただけるなら、私は喜んで御招待に応じ、ワシントンであなたにお会いしましょう」と返答している。
「Strange Fruit」により、プロテスト・ソングは単なる一つの楽曲以上の存在となり、プロテスト・ソングの概念は芸術のレヴェルへと押し上げられた。初期のプロテスト・ソングおよびプロテスト・シンガーの全てが、必ずしもそういった力を発揮するようになったわけではないが、「Strange Fruit」の持つメッセージの直接性は、ちょっとした青写真のようなものとなったのである。
1912年にオクラホマ州で生まれたウディ・ガスリーの名前は、民主党員(で後の第28代米大統領)ウッドロウ・ウィルソンにちなんで名付けられた。ウディ・ガスリーの父チャーリーは、ウディ・ガスリーが誕生する前年、ローラ・ネルソンとその息子のリンチ事件に恐らく関わっていたようで、自身の息子にも反社会主義的な思想に従うよう促していた。
しかし大恐慌の間、多くの“オウキー”(※オクラホマ州出身の移動農業労働者)と同様、ウディ・ガスリーはカリフォルニアへと移住。人々は降り注ぐ太陽と経済的な成功、そして良い暮らしを見込んで、その約束の地へと向かったのだが、大部分の人にとって、それは絵に描いた餅に過ぎなかったことがやがて判明する。黄塵地帯を砂嵐が襲った大災害(=ダストボウル)により、多くの住民が農場や家、生活の基盤を失ったのを目の当たりにしたウディ・ガスリーは、人々が直面した苦難を題材にした曲を書き始めた。
これらの曲がまとめて収録されているのが、彼にとって初めてでそして最も成功した1940年のアルバム『Dust Bowl Ballads』だ。同アルバムには、砂嵐に土地を奪われ新天地に移住するオクラホマ農民一家の姿を描いた、ジョン・スタインベックの砂嵐によってオクラホマから移住せざるを得なかった家族をテーマにした小説『怒りの葡萄』に基づいた「Tom Joad」も含まれている。伝えられるところによると、ジョン・スタインベックは同曲について「私が2年の歳月を費やして書いた物語全体を、彼は17節で表現してしまった!」とコメントしていたそうだ。
ウディ・ガスリーが1940年に書いたある曲は、レコーディングされないまま4年間寝かされていたが、その後、彼の作品中で最も有名な、そして最も長く歌い継がれる曲となった。その「This Land Is Your Land(邦題:我が祖国)」は、アーヴィング・バーリンの「God Bless America」などの歌に代表されるような、戦時中の自国優位主義とウディ・ガスリーが認識していたものに対し、批判を込めたアンサー・ソングとして書かれたものだ。
「ここは皆の世界なんだと証明する歌を、私は歌いたくてたまらない」と彼は記している。「向こう側、つまり大金が動く側で仕事を得ようと思えば、私には出来る。そして自分の本音を込めた歌を歌うのを辞め、人々を更に鞭打つような歌を、人々をもっとからかうような歌を、自分にはまるで判断力がないと人々に思わせるような歌を、そんな歌って毎週いくばくかの金を稼ぐことだって出来る。だが私はもうずっと前に、心に決めたのだ。そんな曲を歌うくらいなら、飢えて死んだ方がましだと」。
ウディ・ガスリーが政治的なソングライターであったのか、それともカントリー・シンガー・ソングライターのスティーヴ・アールが言及していたように「非常に政治的な時代に生きていたソングライターであった」だったのかは、解釈の問題である。だがひとつ明らかなのは、ピート・シーガーから、ビリー・ブラッグ、ボブ・ディラン、そしてブルース・スプリングスティーンに至るまで、後に「This Land Is Your Land」を歌うことになる次世代のソングライター達が皆、それを自分のもののようにして歌っていたくらい、彼の曲から大きな影響を受けていたということ。それこそ正に、ウディ・ガスリーが望んでいたことだろう。
微妙な問題に関わる生き方を支持する歌を歌うことによって、冷戦期の被害妄想的とも言えるマッカーシズム(赤狩り)時代には、多くのアメリカ人が窮地に陥った。労働組合歌は共産主義賛歌と受け止められ、またその歌い手達は、ジョセフ・マッカーシー上院議員とその支持者から反逆者と見なされ、狩り立てられていたのである。
ウディ・ガスリーの友人で共産党員のピート・シーガーは、1949年にニューヨーク州北部でコンサートを開催しようとした際、自分達が立ち向かっているものを直に目の当たりにした。退役軍人とKKK団員達が、そのコンサートを共産主義者の集会と見なして中止に追い込もうと乗り込んで来ただけでなく、黒人歌手ポール・ロブソンに対して直接的な行動をとったのである。
ドリアン・リンスキーは、プロテスト・ソングの歴史を解説した著書『33 Revolutions Per Minute』の中でこう説明している。「ピート・シーガーが現場に辿り着く前に、既に退役軍人達はコンサートの参加者達を取り囲み、『ポール・ロブソンを出せ!俺達がそのxxxxをリンチして血祭りに上げてやる!』と叫んでいた。群衆は互いに腕を組み合いながら、ゴスペルの改作であり、公民権運動で広く歌い継がれていた「We Shall Not Be Moved」(※直訳すると“我らはてこでも動かない”という意味)を合唱し、それに対抗した。だが、彼らは動かざるを得なかった。暴徒化した退役軍人達が、燃え盛る十字架を打ち立てて、勝利宣言を行ったからである」。
当時のマスコミは、この事件について「ロブソン:彼が自ら蒔いた種」という見出しで報道。延期となったそのコンサートが翌週に開催された際には、コンサート参加者達は帰り際に待ち伏せされ、“憂慮する市民達”による襲撃には州警察官までもが加担していた。
その頃ピート・シーガーは、絶え間なく進化を続けるチャールズ・ティンドリー作のゴスペル「I’ll Overcome Someday」を原曲にした、ある改作曲を歌っていた。それについてドリアン・リンスキーは「真髄にまで煎じ詰められたプロテスト音楽。我々は、つまりコミュニティの力は、輝かしい未来を目指し、果敢な抵抗と忍耐とで、必ずや打ち勝つ」と解説。その「We Shall Overcome(邦題:勝利を我等に)」は、どんな場面にもふさわしい、最初の代表的プロテスト賛歌となった。
スターリンの冷酷な政治体制の現実が明らかになると、ピート・シーガーは共産党を離党。だがその頃既にアメリカの左翼達の間には、新たな団結の大義が生じていた。すなわち公民権である。公民権運動に拍車がかかったのは、アラバマ州モンゴメリーでバスに乗っていた黒人女性ローザ・パークスが、白人乗客に座席を譲ることを拒否し、人種分離法違反容疑で逮捕されたのがきっかけだ。
そして世界中の聴衆にメッセージを伝え、多種多様な抗議者達をひとつの旗の下に団結させる上で、歌が大きな役割を果たしたのであった。それは丁度、数世代前の奴隷達が、共に声を合わせて歌っていたのと同様だ。実際、モンゴメリー・バス・ボイコット事件(1955年)でローザ・パークスを支持した人々は、その抗議の一環として「Steal Away」を始めとする黒人霊歌を再流行させていた。
60年代を通じて、黒人と白人の両方のアーティスト達が、人種的偏見と不平等を強く非難する曲を書き、歌っている。ニーナ・シモンの痛烈な「Mississippi Goddam」は、アラバマ州バーミンガムにあるバプテスト教会で行われていた子供たちの聖書集会が爆弾で襲われ、4人のティーンエイジャーが殺された事件に対し、激しい怒りを込めて書かれた曲だ。
そしてサム・クックの力強い「A Change Is Gonna Come」は、公民権運動の賛歌となった。彼はボブ・ディランの「Blowin’ In The Wind」を聴いて、それを書いたのが白人のボブであって自分ではなかったことを恥じ、この曲を書いたという。同曲は後に、アレサ・フランクリンやオーティス・レディングらにカヴァーされたが、それが最も強い説得力を持って読み上げられたのは、その40年後、当選直後のバラク・オバマ前大統領が、シカゴで支持者達にこう語った時のことだろう。「大変長い道のりでした。ですが今夜、アメリカにようやく変化が訪れたのです(Change has come to America)」と。
モータウンのレコードは、“若きアメリカの音”として知られ、陽気な踊れる音楽として愛されていた。その楽曲は、少年少女を題材に精巧に作り上げられたポップ・ソングであったが、アーティスト達が抗議表明をポップに取り入れる際には、それが公民権運動の強みともなった。例えばテンプテーションズの「Message From A Black Man」や、マーヴィン・ゲイの1971年の傑作「What’s Going On」がそうだ。ジェームス・ブラウンが「Say It Loud – I’m Black And I’m Proud」(※直訳すると“大声で言おう。私は黒人であり、それを誇りに思う”)と歌い、カーティス・メイフィールドは「People Get Ready」(※直訳すると“民衆よ、準備せよ”)と説いた。
この当時、ソングライター達が怒りを集中的に向けていたもうひとつの対象が、拡大中のベトナム戦争だ。ボブ・ディランの「Masters Of War(邦題:戦争の親玉)」には、ミネソタ州ダルース出身のこの若者が、憧れのウディ・ガスリーからどれほどのことを学んでいたかが示されていた。ボブ・ディランのメッセージ・ソングの多くは、例えばマンフレッド・マンの「With God On Our Side」や、ニーナ・シモンが力強く朗読した「Ballad Of Hollis Brown」等、他の数多くのアーティスト達にカヴァーされている。
ウディ・ガスリー同様、ボブ・ディランについては、彼がプロテスト・ソングおよびメッセージ・ソングのライターであったのか、それとも単に自らが生きていた変わりゆく時代について書いていただけなのか、今日でも議論が交わされている。しかし、ひとつ疑いの余地がないのは、不正を告発する彼の歌が成功を収めたことにより、歯止めが一挙に解かれたということだ。
バリー・マクガイアは1965年、「Eve Of Destruction(邦題:明日なき世界)」で全米No.1のヒットを記録。この曲は、俳優マーロン・ブランドが映画『乱暴者』で見せていた反抗(「お前は何に反抗しているんだ?」「何もかもにさ」 )と同様の姿勢で、目の前のあらゆる問題に対し抗議を行っているように思われた。一方、モンタレーやウッドストックのような大勢の人々が集まるフェスティバルの場でも、プロテスト・ソングが溢れかえっていた。カントリー・ジョー&フィッシュの「I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag」で大合唱が湧き上がったことは、ウッドストックにおける最も象徴的な瞬間の一つだったが、そこには次のような一節がある。
そして、1、2、3
俺逹は何のために戦ってるのか?
俺に聞かないでくれ、どうでもいいのさ
次の目的地はベトナム
そして、5、6、7
天国の門を開けてくれ
理由を問うている暇はない
ワーイ、俺逹は皆、死ぬだろう
プロテスト・ソングの活用を先導したのは、非常に大規模かつ理解しやすい公民権運動や反戦運動であったが、プロテスト・ソングの全てが必ずしもそういったキャンペーンでのみ使用されていたわけではない。その頃になると政治家達もまた、ポップ・ソングの持つ力を熟知するようになっていたからだ。
ジョン・F・ケネディは1960年、史上最も接戦となった大統領選挙の最中に、フランク・シナトラから支援を受けたことに感謝した。リチャード・ニクソンを相手に選挙戦を闘っていたこの若き民主党員を支援するため、フランク・シナトラは人脈を駆使して有力な知人達を勢揃いさせたのである。
フランク・シナトラは、自身の大ヒット曲でオスカーを受賞した「High Hopes」の歌詞を替え、ジョン・F・ケネディへの支持を表明する形で再録音し「誰もがジャックを支持したがってる/ジャックのやってることは間違ってない/彼は大いなる希望を抱いてるから」と歌った。(しかしながら、全ての大統領が自分にふさわしい応援歌を選ぶことに成功したわけではない。例えばロナルド・レーガンは、ブルース・スプリングスティーンの「Born In The USA」を希望のメッセージとして引用したが、それは誤解であった。一方、ザ・ローリング・ストーンズは、ドナルド・トランプが選挙キャンペーンのイベントで「Start Me Up」を使おうとした際、きっぱりとそれを拒否している)。
ポップ・スターが皆、そのように自身の政治的立場について率直に語っていたわけではない。実際、ミュージシャンが政治的な問題について意見を表明することは、一般的には不適切だと考えられていた。ジョン・レノンは1980年、プレイボーイ誌のインタビューでこう語っている。
「何年もの間ずっと、ビートルズのツアー中は、ベトナムのことや戦争について尋ねられても何も言わないようにと、(マネージャーのブライアン・)エプスタインに止められていたんだ。だけどあるツアーで、僕はこう言ったんだ。“これからは、戦争に関する質問には答えるつもりだよ。それを無視することは、僕らには出来ない”ってね。僕はどうしても、ビートルズとして何かを発言させたかったんだ」
そのザ・ビートルズの発言とは、彼らがベトナム戦争には賛同していないということであった。彼らの曲は時を経るにつれ、より公然と自分達の意見を反映したものになっていくが、その最初となったのが、若い世代にとってスローガン的な役割を果たした「All You Need Is Love」であった。
そして、1968年のシングル「Revolution」では、時事問題に対する彼らの立場を直接訴えている。ジョン・レノンはその1年後、プラスティック・オノ・バンドのシングル「Give Peace A Chance(邦題:平和を我等に)」をリリース。これはベトナム反戦運動のデモ行進で歌われるよう意図してジョン・レノンが書いた、あからさまなプロテスト・ソングであった。
「僕は心の奥底で、密かに“We Shall Overcome”の後を引き継ぐような曲を書きたいと思っていたんだ」と、ジョン・レノンは後に振り返っている。「なぜかは分からないんだけどね。みんながいつもあの曲を歌っていて、それで思ったんだよ、『今の人々を代弁する曲を、どうして誰か書かないんだろう? それこそ僕のやるべきことだ、僕らのやるべき仕事だ』とね」。
70年代が進むにつれ、60年代に差していた希望の光は再び怒りへと変わっていった。それが反映されていたのが、例えば、ギル・スコット=ヘロンの「The Revolution Will Not Televised」(※直訳すると“革命はテレビ中継されない”)で彼はこう歌っていた「コンセントを差し、スイッチを入れ、高みの見物をしようったって無理だ」。そして当初テンプテーションズが発表し、後にエドウィン・スターが歌った「War」を始めとする曲だ。また、ボブ・マーリーの「Exodus」は、変化の最中にあったジャマイカの政治情勢を反映しており、西インド諸島から大型船ウインドラッシュ号に乗って渡ってきた移民の二世達が成人に達するようになっていた英国に、非常に大きな衝撃を与えた。
レゲエとパンクは、70年代から80年代にかけ、不満のはけ口を求めていた多くの英国の若者達にとって、ひとつの表現手段となった。当時、英国各地のスラム地区では、抑圧や偏見、公然とした人種差別などに端を発した暴動が頻発していた。ザ・クラッシュのジョー・ストラマーは、ウディ・ガスリーの曲を聴いて育っており(彼はしばらくの間、ウディというニックネームを名乗っていたほど)、レゲエやパンクを政治と融合させた彼のバンドの音楽性は、強力であると同時に高い影響力を備えていた。
サッチャー政権時代、世論を二分する政治的対立をテーマにした曲を全英チャートに送り込むようになっていたのが、英国におけるもう一人のウディ・ガスリー信望者、ビリー・ブラッグである。彼の「To Have And To Have Not」は、ダストボウルに襲われたオーキー達の苦境についてウディ・ガスリーが歌っていたのと同じように、英国の何百万人もの失業者達が感じていた絶望感を取り上げていた。
ビリー・ブラッグが愛用のギターに「この機械はファシストを殺す」というスローガンを書きなぐっていたのは、彼の憧れのヒーローの例に倣ったものだ。ビリー・ブラッグは、ミュージシャンとしての力を使い、若者の政治に対する関心を高めて、1987年の英国総選挙で労働党に投票するよう呼びかけるため、選挙運動『レッド・ウェッジ』を立ち上げた。この運動に参加していたのが、ポール・ウェラーや、ジミー・ソマーヴィル、ザ・スミス、マッドネスらのアーティスト達だ。
1984年、スペシャルズは、獄中にいた南アフリカの反アパルトヘイト活動家ネルソン・マンデラへの支援を訴えるシングル「Free Nelson Mandela」(※直訳すると“ネルソン・マンデラを解放せよ”)をリリース。全英チャートでトップ10入りするヒットとなり、反アパルトヘイト運動のスローガンと化した。そしてその後も様々なアーティストが、自身の手掛けた抗議の歌を歌うことにより、政治との協調を継続していく。
U2の「Sunday Bloody Sunday」が、北アイルランド紛争の悲惨さを反映していた一方、同じくU2の「Pride (In the Name Of Love)」は、マーティン・ルーサー・キング牧師の暗殺を(部分的に事実誤認はあるものの)回想した歌となっている。 強い影響力を持つR.E.M.のアルバム『Document』には、「Exhuming McCarthy」を始め、レーガン政権に異議を唱えた複数の曲を収録。またヒップホップのアーティスト勢も、パブリック・エネミーによる「Fight The Power」の革命的なレトリックを筆頭に、社会に対する不満を訴えていた。
今日では、新旧問わず、様々な歌手やソングライター達から、夥しい数のプロテスト・ソングが世に送り出され続けている。ニール・ヤングは近年の曲「Child Of Destiny」で、「信じるもののために立ち上がれ/権力者に抗え」と力説。レディー・ガガは、2017年のスーパー・ボウルのハーフタイム・ショーで、ウディ・ガスリーの「This Land Is Your Land」を披露し、また同じ舞台ではその1年前、ビヨンセが『ブラック・ライヴズ・マター(“黒人の命だって重要だ”)』運動のキャンペーンに対する支持を表明、ブラック・パンサー党を称えていた。
人々が政治について、再び盛んに語るようになったこの時代、プロテスト・ソングの力がもう一度、新たに活用され始めている。ピート・シーガーやジョン・レノンから渡されたバトンを受け取り、路上で合唱されるような新しい賛歌を生み出すアーティストが今後出てくるかどうか、現時点では不明だ。しかし、これまでずっと常にそうであったように、人々の関心を高め、共通の目標を分かち合う手段として、音楽が用いられることは確実視されている。
「プロテスト音楽の核心は、世界の軸を動かすのではなく、人々の意見や観点を変えるところにある」と、著書『33 Revolutions Per Minute』の中でリンスキーは説明する。「そして、自分達が生きている時代について何かを語り、時には自らの発言が、別の時代のある瞬間、別の誰かに訴えかけることもあるということを知るところにあるのだ」と。その時にこそ、サム・クックが歌う「A Change Is Gonna Come」の予言が現実となり、変化が訪れるのである。
Written By Paul McGuinness
- エドウィン・スターの反戦アンセム「War」
- すべての宗教や人種の観衆の心を動かしたジェームス・ブラウンの曲
- U2が『War』で宣戦布告
- 丸屋九兵衛 連載第3回「憎悪と対立の時代を見つめて」
- カーティス・メイフィールドが好きなら、ケンドリック・ラマーも好きになるはず
♪プレイリスト『We Shall Overcome』 をフォロー