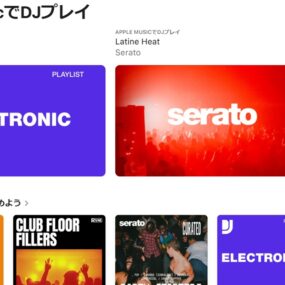Stories
モータウンと社会問題:政治やプロテスト・ソングと人々が自由になるための手助け


モータウンと政治とのあいだには深いつながりがある。そこには、素晴らしい音楽と世界を変えていこうとする前向きな姿勢があった。
あらゆる時代は変化の最中にある。しかしある時期の変化は、他の時期よりも激しく進んだ。それはモータウンが絶頂期を迎えたのは1960年代のことだった。モータウンは経営のことをしっかりと考える会社だったが、そんな会社でもこの時代の若者に起こっていた変化を見過ごすことはできなかった。1960年代の若者たちの革命は非常に重要な出来事だった。そういう若者たちにレコードを買ってもらおうと考えるなら、そうした変化をしっかり意識しなければならない。さもなければ、堅物のまま時代から取り残されるだろう。モータウンと政治・社会はゆっくりとではあったが互いに距離を縮めていった。やがて両者の距離が近くなると、そこから作品が生まれ、それらは爆発的な結果となった。
成功するためにあらゆる手立てを尽くすのはどのレコード会社も同じだが、中でもモータウンはずば抜けた存在だった。それでもレーベルのボスのベリー・ゴーディは、自社のレコードが最高のグルーヴを伝えるだけでなく、若者の考えを (少なくとも部分的に) 反映しなければならないと考えていた。なにしろモータウンのモットーは、 (ある一時期ではあったかもしれないが) 「若いアメリカのサウンド」だったのだから。しかしメッセージ性を盛り込んだ曲作りは慎重に進められた。1960年代のほとんどの時期では、モータウンは売れ線の楽曲の中に急進的な思想をひっそりと忍ばせる程度に抑えていた。
その例として、マーサ&ザ・ヴァンデラスの「Dancing In The Street」を見てみよう。これは、今や反乱や街頭での抗議活動を呼びかける楽曲として定着して久しい。しかし1964年当時、街の中で踊る若者たちに向けてそのメッセージをマーサ&ザ・ヴァンデラスが訴えた形跡はほとんどない。それでも時が経てば、そうしたつながりはくっきりと浮かび上がってくる。それに歌というものは、時として作者の狙い以上の意味を持つ場合があるのだ。こうした初期のモータウンのプロテスト・ソングは、必ずしもあからさまにメッセージを訴えるものではなかった。とはいえ、のちにメッセージがあからさまになる場合もあった。
社会問題を正面から採り上げる
1960年代のアメリカでは、たくさんの社会問題が渦巻いていた。人種隔離政策、ベトナム戦争、警察の横暴、機会の不平等といったものだ。ベトナム戦争がきっかけで生まれたモータウンの作品と言えば、まず徴兵されて遠くに行った恋人を思う歌を挙げなければいけない。この種の作品は無数に作られた。まずはシュープリームスの「You’re Gone (But Always In My Heart) 」 (1967年) やマーサ&ザ・ヴァンデラスの「Jimmy Mack」 (1967年) を見てみよう。前者では、恋人が戦死したとは明言されていない。しかしながら、楽曲の弔うような雰囲気は、そうした悲劇を暗示的に示唆している。また後者は、恋人が遠く離れているあいだに別の男から誘惑されているという作品だ。「遠く」というのがどこかなのか、歌の中でははっきり示されていない。しかし行軍マーチのようなビートを聴けば、それがどこなのか察しは付くに違いない。
一方で、モータウンの楽曲の中にはベトナム戦争を正面から扱ったものもある。その例としては、ヴァラディアズの「Greetings (This Is Uncle Sam) 」 (1961年) 、あるいはエドウィン・スターの「War」や「Stop The War Now」 (どちらも1970年) が挙げられる。ただしこの2曲のあいだには、10年という年月が流れており、そのあいだにアプローチはずいぶん変わっている。ヴァラディアズのレコードは悲しげな雰囲気で、そこに笑いを誘うような命令口調の語りが被さってくる。一方のエドウィン・スターの楽曲はトゲトゲしく、ファンキーで怒りに満ちている。この類の曲で、もっと穏やかに仕立てられた例としては、シュープリームスが1970年にリリースしたヒット曲「Stoned Love」がある。そこでは、相互理解と愛情があれば国同士の戦争は終わると歌われている。もっと暗い (そして恐ろしいほどリアルな) 例としては、トム・クレイの「The Victors」 (1971年) がある。この曲では、陰鬱な消灯ラッパのメロディをバックに、戦死した兵士たちの名前と (あまりにも若い) 享年が読み上げられていく。
このクレイのレコードはチャート入りを果たせなかった。そのB面に収録されていた「Tom Clay’s What The World Needs Now Is Love」では、曲名に含まれているバート・バカラックとハル・デヴィッドの楽曲がバックに流れる中、クレイが子供に社会の害悪について尋ね、子供が純真無垢な答えを返していく。やがてケネディ大統領暗殺などさまざまな事件のニュースが流れ始め、楽曲は「Abraham, Martin And John」へと移り変わっていく。この「Abraham, Martin And John」という曲はフォーク時代のディオンのヒット曲だったが、1969年にマーヴィン・ゲイがカヴァーしていた。そのカヴァーをきっかけに、マーヴィンは新たな方向性に進み始める。それまでの彼はミュージカルの楽曲やシャウト系のR&Bなどありとあらゆるジャンルに挑戦していたが、1960年代後期はタミー・テレルとのデュエットでラヴ・ソングの名手として知られるようになった。しかしこのころのマーヴィンは、世界情勢に対する不安を反映した作風を追求し始めていた。
あまりにもたくさんの人が死んでいる
やがてマーヴィンはアルバム『What’s Going On』を発表。これは究極のプロテスト・ソウル・アルバムとして多くの人から認められている。しかしマーヴィンのファンが受け入れることができるプロテスト・ソングは、これが限界のようだった。1972年に彼がリリースしたあからさまに政治的なシングル「You’re The Man」は、『What’s Going On』ほど反響を呼ぶことがなかった (*この時に制作されたアルバムはお蔵入りに。そして2019年に初めて発売された)。マーヴィンは1974年の『Let’s Get It On』で再びラヴ・ソングに回帰する。これは当初『What’s Going On』をしのぐ売れ行きとなった。マーヴィンは政治性の強いモータウン歌手の先駆けだったかもしれない。しかしその後の作品は、よりプライベートな面での政治的駆け引きが中心テーマとなっていく (『Here, My Dear』や『In Our Lifetime』など) 。
その後のモータウンのアーティスト/グループも、これに似た展開を見せた。まずテンプテーションズの例を見てみよう。彼らの楽曲ではさまざまな社会問題が扱われていた。たとえばドラッグに溺れた逃避主義(「Psychedelic Shack」1970年) 、世界の混乱 (「Ball Of Confusion」1970年) 、家族の崩壊 (「Papa Was A Rollin’ Stone」1973年) といった具合である。「Message From A Black Man」(1969年) はさらに直接的な内容だったが、モータウンはこれをシングルとしてリリースしなかった。テンプテーションズの代わりにこれをシングル化したのは、モータウンの一番手とはいえないグループ、スピナーズだった。
別のプロテスト・ソング「Law Of the Land」も似たような経過をたどった。テンプテーションズのヴァージョンはアメリカではシングル化されていない。代わりに、アンディスピューティッド・トゥルースがこの曲のカヴァー・ヴァージョンを発表し、ヒット・チャートに送り込んでいる。有名な話だが、テンプテーションズはこの種の楽曲にはあまり熱心になれないと不平を述べ、むしろ自分たちはラヴ・ソングの歌い手であると自認していた。彼らは1971年に「Just My Imagination」をリリースし、嬉々として得意分野に戻ってきた。特にメンバーの肝をつぶしたのは「Papa Was A Rollin’ Stone」だった。一部のメンバーは自分たちの家族がこの曲を聞いて気分を害するのではないかと恐れていた。
家族の問題は、1968年以降のモータウンの楽曲で度々採り上げられている。ボビー・テイラー&ザ・ヴァンクーヴァーズの「Does Your Mama Know About Me」は実に優れたラヴ・ソングだったが、歌詞には異なる人種間の恋愛が家族に受け入れられるだろうかという問いかけが含まれていた。ヴァンクーヴァーズはさまざまな人種のメンバーから成るグループだったので、こうした楽曲を作ってレコーディングするのは意外でも何でもないことだった。またダイアナ・ロス&ザ・シュープリームスでさえ、家族間のきわどい問題を扱っていた。その好例が「Love Child」で、この曲は「シングル・マザー」をテーマにした作品だった。これは、モータウンのスターを1968年という時代に合わせてイメージ・チェンジするために意図的に作られた楽曲だったのである。
『Songs In The Key Of Life』
1960年代も終わろうとするころには、モータウンの中でも特に好感度が高いアーティストでさえも、時代の変化に合わせて厄介そうなテーマに挑戦することがほぼ義務となっていた。グラディス・ナイト&ザ・ピップスですら、ゴスペル風の「Friendship Train」 (1969年) で人々に団結を呼びかけている。またジュニア・ウォーカー&ジ・オール・スターズは、1971年にクルセイダーズの「Way Back Home」の2通りのヴァージョンをレコーディングしている。それらのうちのひとつ、ヴォーカル・ヴァージョンのほうでは、南部では黒人が抑圧されているため、ポジティブな生活が送れないと訴えていた。
言うまでもないことだが、モータウンの中で政治性を強めた大物スターのひとりはスティーヴィー・ワンダーだった。彼は1960年代の終わりにモータウン・レーベルから離れることを考えていた。レーベル側は、この元少年歌手が大人のスターに成長するかどうか判断できずにいたのだ。また、スティーヴィーとしても自らの求める創作上の自由を、モータウンが許すかどうか見きわめられずにいた。幸い、その後の成り行きは良い方向に進む。スティーヴィーはモータウン社内のスタジオやプロデューサーから離れてレコーディングを始めたが、レコードはやはり従来通りモータウンからリリースすることになったのである。
彼はすぐに世界に対するメッセージを楽曲に盛りこみ始める。モータウンの通常の体制でレコーディングされた1970年の『Where I’m Coming From』ですら、世界情勢についての楽曲を含んでいた (「Do Yourself A Favor」、「Sunshine In Their Eyes」) 。さらに1972年の『Talking Book』では「Big Brother」、『Innervisions』 (1973年) では「He’s Misstra Know-It-All」や「Living For The City」、『Fulfillingness’ First Finale』 (1974年) では「You Haven’t Done Nothin’」、『Songs In The Key Of Life』 (1976年) では「Village Ghetto Land」や「Pastime Paradise」といった楽曲が生まれている。これらはどれもあからさまに政治的な内容を含んでいた。また他の曲も、よりスピリチュアルな志向は強かったけれど、現在の世界の仕組み (あるいは混乱ぶり) に対する批判を含んでいた。
こうしたスティーヴィーの政治的な志向の作風は、1980年のシングル「Happy Birthday」でピークに達した。この楽曲は、マーティン・ルーサー・キング師の誕生日をアメリカ合衆国の正式な祝日にするように呼びかける運動を後押ししていた。これはモータウンと政治の関係が最も有効に機能した例として挙げられるだろう。アメリカ史上最大の誓願が為された結果、マーティン・ルーサー・キング牧師の誕生日は1986年から祝日となった。集まった署名の数は600万筆。その中には、スティーヴィーの署名も含まれていた。
『People… Hold On』
1960年代、モータウンはアフリカ系アメリカ人のあいだで「ルーツ探求」がひとつのブームになっていることに気づいた。そうしたブームを反映した楽曲もいくつか作られている。たとえば「Ungena Za Ulimwengu (Unite The World) 」は、テンプテーションズとアンディスピューティッド・トゥルースがレコーディングしている。またノーマン・ホイットフィールドが作った別のプロテスト・ソングの中にはスワヒリ語の題名のものもある。その一方でモータウンはブラック・フォーラムという子レーベルを設立し、そちらでも政治性の強いレコードをリリースすようになった。ここからレコードをリリースした人としては、詩人のイマム・アミリ・バラカ (『It’s Nation Time』) やブラック・パンサー党の女性指導者だったエレイン・ブラウンが挙げられる。さらには、マーティン・ルーサー・キング師の演説テープもこのレーベルからレコード化された。ブラック・フォーラムは1970~73年の4年間しか続かなかった。しかしこうした動きを見れば、アーティストだけからではなくモータウンという会社そのものが政治的な活動に積極的に乗り出していたことがわかるだろう。
一方チャートでは、元テンプテーションズのエディ・ケンドリックスがマーヴィン・ゲイのあとに続いていた。彼の「My People… Hold On」は、アフリカン・ドラム・サウンドをバックに黒人の団結を呼びかける強力なメッセージ・ソングだった。それが収められたアルバム『People… Hold On』 (1972年) のジャケットでは、ケンドリックスが蝶ネクタイとスーツを着込むと同時に、アフリカの部族の仮面でできた椅子に座り、槍を手にしている。これはリチャード・プライヤーのデビュー・アルバムの物議を醸したジャケット・デザイン (プライヤーがアフリカの原住民の扮装をしていた) にも似ていた。一見すると矛盾したような取り合わせにも見えるジャケット写真だが、そこに込められたメッセージは明らかだ。つまり、どんな人種の人間であろうと、アフリカ起源の血筋をひいているに違いないというわけである。民族考古学の研究によれば、それは正しい主張である。
こうした楽曲は今も人の心に響き続けている。やらなければいけないことはただひとつ。まわりをジッと見つめること。すると、かつてマーヴィン・ゲイが「What’s going on」と歌ったように、「なんなんだ、この世の中は」と自問自答している自分に気づくだろう。モータウンと政治のつながりは実に根深いものがある。採り上げられたテーマは多種多様だった。人類のルーツ、戦争反対、自由を求めて戦う人々、高名な政治指導者……。モータウンは気づいていた。自分たちの役割は、人々が自由になるための手助けを行うことだと。そしてそれは、単にダンスフロアの上だけの話ではなかったのである。
Written By Ian McCann
- MOTOWN 60 レーベルサイト
- モータウン関連記事一覧
- 肌の色・宗教の違いを超えてファン層を広げたモータウン
- ヴァレリー・シンプソンが語るモータウン
- モータウンの重役までになりレーベルを支えたマルチプレイヤー
- 人種差別や抑圧解放のために歌われた歌の歴史とは?
- エドウィン・スターの反戦アンセム「War」
- マーヴィン・ゲイ1972年の未発表アルバム『You’re The Man』が発売
- モータウンのグループ達:デトロイト発、一大レーベル創世記