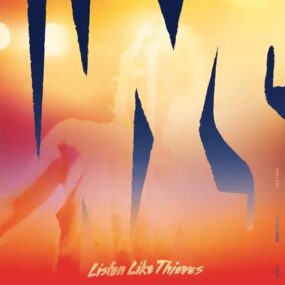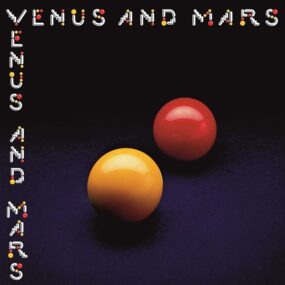Stories
ザ・フーのキース・ムーンの生涯と彼が遺したもの「彼は限界ってものを知らなかった (by ピート)」


ザ・フー(The Who)のドラマーとして、キース・ムーン(Keith Moon)はロック史上屈指の激しさをもつバンドの原動力となった。「彼の思考回路はちょっと普通じゃないんだよ」とロジャー・ダルトリーは話す。そんな彼の生涯をご紹介しよう。
伝説は真実より大袈裟に語られることが多い。だが真実通りの伝説が、別の側面を隠してしまうこともある。キース・ムーンの場合は後者だ。ほとんど、とは言わないにしてもザ・フーのドラマーである彼の奇行(という言い方が的確かはわからないが)の噂の多くはおそらく真実だ。一方で、その噂は音楽に関する彼の真実をかき消してしまうこともある。彼は唯一無二のドラマーだったことは忘れられがちだし、まして彼がもともとラッパ吹きだったことは知られていない。
<関連記事>
・ザ・フー、13年ぶりの新作『WHO』:ピート・タウンゼントによる全曲解説
・ザ・フーと再始動後の全米成功を支えた『CSI:科学捜査班』の関係
「彼の思考回路はちょっと変わっている」
1964年、パブでのオーディションに合格してキースが駆け出しのザ・フーにスカウトされると、ロック界で最も結束力の強い4人はみるみるうちに危険で強力な化学反応を起こしていった。彼は長生きをしそうにはなかったが、ロック・スターの寿命が犬と同じだとすれば、キース・ムーンの14年は一般人の生涯にあたるといえる。
真面目な話をすると、キースはザ・フーのほとんどすべてのレコードで重要な役割を果たしている。彼は8枚のアルバムと約35枚のシングルに参加したが、どれも記憶に残る仕事ぶりだ。ピート・タウンゼントとロジャー・ダルトリーはバンド名義で2019年に13年ぶり、12作目となる傑作『Who』を発表するなど現在も精力的に活動しているが、そんな二人もザ・フーの魂は1978年9月7日の悲しい夜に大きく傷ついたと認めるだろう。その日ムーンが32歳の若さでこの世を去ったことは今でも信じられない。
「ザ・フーにとってはそれがぴったりだった」
2016年、ロジャー・ダルトリーは筆者の取材に対し、ザ・フーにとってのキース・ムーンの重要性について愛情をもってこう話していた。
「ドラマーとしてのムーンは雑でいいかげんと思われているが、実際はその真逆なんだ。ちょっと変わっているのは彼の思考回路 (と言いながらダルトリーは笑った) で、それだけさ」
「彼はステージにある色んな楽器を試してみては、なんとか形にしていた。4つ打ちのロックンロールらしいドラミングではないけど、ザ・フーにとってはそれがぴったりだったんだ。彼のユーモアには楽しませてもらった。観客を向くのはシンガーの仕事だけど、彼はバンドのことを見なかった。恐ろしいことをして俺をからかっていたんだろうね。彼には度肝を抜かれたよ」
キース・ムーンが亡くなる直前の映像のひとつが、彼の参加した最後のアルバム『Who Are You』のタイトル・トラックのプロモーション・フィルムだ。ドキュメンタリー映画『キッズ・アー・オールライト』のためにロンドンのバタシーにあるラムポート・スタジオで撮影された同映像は、亡くなる直前の彼を捉えたすばらしいものだ。彼のいたずら心や、ピートやロジャー、ジョン・エントウィッスルとふざけ合う心温まる様子が垣間見える。そしてドラム・パートでのムーンはガムテープでヘッドホンを頭にくくりつけ、激しく見事なドラムを披露している。
「常に予測不能な演奏」
彼以外にドラム・セットをリード楽器として扱うロック・ドラマーはいなかったし、1965年からはメディアがザ・フーについて「アンプを殺戮している」と書き立てるようになった。だがそれは、キース・ムーンがステージやレコードで無理やり目立とうとしていたということではない。特にグループが成熟し、ピート・タウンゼントが繊細で物語的な作曲 (『トミー』の頃から顕著だ) をするようになってからは、そのことが日の目を浴びるようになった。キースはバンドの強大な原動力になるとともに、いとも簡単に明暗を表現してみせたのだ。
ジョン・エントウィッスルはキース・ムーンが左右にではなく前に向けて演奏する、と話したころがある。「キース・ムーン、後ろに座っているというポリシーに従わないドラマーがついに現れた!」というのは、後にキースの後釜となるケニー・ジョーンズが1966年のスモール・フェイセズ全盛期に放った言葉だ。
彼のコメントは言い得て妙だが、一方でキースは控え目で細やかなドラミングもできる。それは芝居がかった「I’m Free」や「Won’t Get Fooled Again (無法の世界) 」などザ・フーの多くの曲で聴くことができる。また、「5:15」のような曲では激しさと繊細さがひとつの曲に同居している。
ブロンディのクレム・バークは2016年出版の『A TRIBUTE TO KEITH MOON : THERE IS NO SUBSTITUTE』の序文にこう寄稿した。
「キースは革新的で、演奏はいつも予測不能だった。影響を受けたすばらしいリフやフィルはたくさんある。例えば『Live at Leeds』の“Young Man Blues”を聴いてみてほしい」
「映画『キッズ・アー・オールライト』のあるシーンが忘れられない。シンセサイザーに合わせて演奏するキースの頭にヘッドホンがテープで固定されているんだ。時代を先駆けていたという意味では、あれこそ最近のドラマーがコンサートでやっていることさ!」
キース・ムーンの大ファンとして知られるドラマーにはレッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムもいる。彼は機会さえあれば必ずムーンの演奏を出来るだけ近くで見ていた。ジョン・ボーナムは「Won’t Get Fooled Again」のレコーディングの一部始終に立ち会っていた。ピート・タウンゼントによれば、バディ・リッチやトニー・ウィリアムスら一流のジャズ・ドラマーも彼のファンだったという。
「ハムレットを演じたいけど、彼はドラマーじゃないだろう?」
キース・ムーンは地元のロンドン北部で、エスコーツやマーク・トウェイン&ストレンジャーズ、ビーチコーマーズといったグループに在籍し修行を積んでいた。新しいバンドに入れば即戦力になる実力が備わっていたのだ。彼はサーフ・ミュージックと下らないユーモアを愛するモッズだった。
キースはザ・フーとしての最初のシングル「I Can’t Explain」や同じく1965年発表のデビュー・アルバム『My Generation』から自分のサウンドを確立していた。彼ほどに当初から自らのスタイルを持っていたミュージシャンがほかにいただろうか?
1966年のレイヴ誌にはこう綴られた。
「キース・ムーンの風変りな人間性にはさまざまな側面がある。人を侮辱したり騒いだり冗談を言ったりしていたかと思えば、次の瞬間には素朴で純粋なドラム少年に変わっている」
その3年後、同じ雑誌で記者のキース・オールサムはムーンへのインタビューを試みた。結果は予想通り滅茶苦茶だった。「ハムレットを演じたいけど、彼はドラマーじゃないよね?」とキースは言った。
「彼が空き時間にはドラマーだったと書かれていてもいいと思うよ。スティックさばきの名人だったとね。だって、彼には良いリズム感があるじゃないか。俺が上手いドラマーかどうかも紙一重だ。俺はドラムの名人じゃない。ドラムの憧れの人 (idol) はいないのさ。怠け者 (idle) のドラマーは何人か知っているけどさ」
「彼は限界ってものを知らなかった」
キース・ムーンはソロ・アルバムをひとつ残している。1975年の『Two Sides Of The Moon』だ。だがもうひとつの野望は叶わないままだった。1972年にムーンはクリス・チャールズワースの取材にこう答えている。
「名ドラマーになりたいという野心はない。ドラムに全精力を注ぎたくないし、バディ・リッチになりたいわけでもない。ザ・フーでドラムを叩きたいだけなんだ。俺の奇行の多くは映画に出たいから。ピートには作曲があるし、ジョンにも作曲やプロデュースがあるし、ロジャーには農場がある。俺の興味は映画やビデオに出ることなんだ」
テレビを窓から投げ捨てても、スマザーズ・ブラザーズのテレビでセットを爆破しても、芝生でホバークラフトに乗っても、キース・ムーンは何よりザ・フーでドラムを叩きたかっただけだと知れば心強く思える。短い人生ではあったが、彼はほかの誰にも出来ないその役割を全うした。
『A TRIBUTE TO KEITH MOON : THERE IS NO SUBSTITUTE』の導入でピート・タウンゼントはこう記した。
「キースのドラミングは”無秩序”ではなく”自由”という言葉で表現したい。彼は限界というものを知らなかった」
Written By
- ザ・フー アーティスト・ページ
- ザ・フー “ 四重人格 以来最高作”と語る13年ぶりの新作『WHO』発売
- ザ・フー、新作スタジオ・セッションの全7日分の動画ブログを公開
- 『Tommy』ある男の想像の産物であり、ある男が見る素晴らしい光景
- ザ・フーにとっての『White Album』、1971年の傑作アルバム『Who’s Next』
- ザ・フーと再始動後の全米成功を支えた『CSI:科学捜査班』の関係
- ザ・フー関連記事