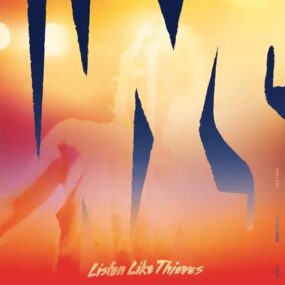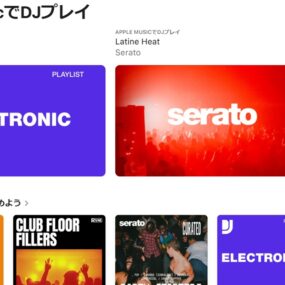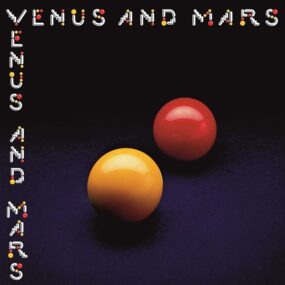Stories
60年代の終焉:ビートルズの解散、オルタモントの悲劇、ヒッピーの夢は終われど音楽は生き続ける


1969年の夏、世界が希望でひとつになった。だがその年の終わりには、60年代の終焉と共に、明るい未来を思い描いていたヒッピーたちの夢に終止符が打たれた。しかし、1969年を通じて大規模なイベントで何千何百万という人々を繋いだ音楽は、現在でも生き続けている。では、1969年がそれほどまでに美しく、また同時にショッキングな60年代のクライマックスとなったのは、何があったからなのか?
その答えは1962年9月の連続した2日間に起きたその後の全てを一変させてしまうことになる2つの出来事に端を発している。少なくともそのうちのひとつは特に害のないものに思えたが、どちらも結果としては広く甚大な影響を及ぼし、60年代の終わりに、カルチャーと社会そのものに新たな定義を与え、それ以前には想像もしなかったような可能性の扉を開くことになったのだ。
<関連記事>
・ザ・ビートルズのジャケット写真大解説
・ロックの歴史に残る60年代の最大の失敗「ボスタウン・サウンド」
・ウッドストック・フェスティバルのパフォーマンス・ベスト15
60年代を定義づけた二つの出来事
1962年9月に起きた2つの出来事の最初の一つとは、1962年9月11日、EMIのプロデューサー、ロン・リチャーズがパーロフォーン・レーベルが新たに契約を交わしたグループ、ザ・ビートルズによる「Love Me Do」と「P.S. I Love You」のレコーディングだ。カップリングされたこの2曲は、やがてこのリヴァプール出身のバンドの初めてのリリース作として世に出ると、以後7年間にわたって音楽とアートの世界を根底から作り変えてしまう一大革命の始まりの狼煙となったのである。
1962年9月に起きたもう一つの出来事とはビートルズがレコーディングを行った翌日の9月12日、まだ残暑厳しい米テキサス州ヒューストンで、若きアメリカ大統領ジョン・F・ケネディがライス大学のフットボール・スタジアムで大観衆を前に演説を行なったことだ。彼のスピーチの目的は、この10年代の終わりまでに人間を月へと送り込み、かつ無事帰還させることをこの国の目標として掲げるところにあった。
「我々は新たな海原へと出帆する、何故ならそこには得るべき新たな知識があり、勝ち得るべき権利があるからだ。我々はそれを勝ち取り、全ての人類の進歩のために利用しなければならない」
第二次大戦後、西側世界は再構築の過程にあり、20世紀の前半を台無しにしたような戦争を乗り越え懸命に新たな世界を作り上げようとしていた。60年代が進むにつれ、どんなことでも可能なのだという、それまでとは違う希望的な感覚が世の中に徐々に満ちてきた。人類を地上の苦役に縛り付けてきた手かせ足かせは、間もなく消えてなくなるという希望だ。
人類史上最も偉大な冒険
ケネディ大統領はスピーチをこう締めくくった。
「我々はこの60年代の間に月へ行くことを選び、他にも様々なことをやろうと決意しています。それは決してそうすることが容易いからではありません、寧ろ困難な挑戦です。その目標とは、我々の最大級のエナジーと技術とを結集させ競わせることに役立つからです。その挑戦とは我々が率先して受け容れるものであり、先延ばしにすることを潔しとしないものであり、そして我々が勝利することを期しているからで、その他のことについても同様なのです」
これら幾つかの短いスピーチをもって、ケネディ大統領は自らの国家を人類史上最も偉大な冒険である宇宙へと乗り出す軌道へと導いたのである。
その後に続く歳月に目撃されたのは、ザ・ビートルズと彼らと同輩であるポップ・ミュージックの開拓者たちによる連戦連勝だった。時代を超えて支持されるシングル曲が出れば、またそれを上回る画期的なアルバムがリリースされ、ポップ・ミュージック界における卓抜した才能の持ち主たちの勃興はとどまるところを知らなかった。
だが、遥かな星に向かって手を伸ばしている最中に暗殺されたケネディ大統領の悲願だったアポロ計画は、ポップ・ミュージックと同じようにはうまくは運ばなかった。月へと向かう道程をことごとくソヴィエト連邦に先回りされ、アポロ計画はひたすら挫折と焦燥に見舞われているかのようだった。ザ・ビートルズがアビー・ロードにあるEMIのスタジオに篭って『Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band』をレコーディングしていた時、フロリダではアポロ1号の乗組員となる予定だった3人のクルー全員が、テスト中の火災で命を落とすという悲惨な事故も起こっていた。
60年代も終わりに差しかかろうという段階になって、約束されていた何もかもがいちどに現実になるのではないかという空気が漂い出したが、1967年のサマー・オブ・ラヴは1968年には台無しになってしまった。パリ、シカゴ、ロンドン、プラハでも(その他多くの都市でも)暴動が立て続けに起こってばかりの一年であり、ロバート・ケネディとマーティン・ルーサー・キングJr.の暗殺は全米を震撼させ、そしてエスカレートするベトナムでの戦闘は日に日に国民の支持を失っていた。
しかし、それでも1968年のクリスマス・イヴには希望の光が差し込んだ。恐らくこれまで撮られた写真の中で最もパワフルな一枚、アポロ8号の宇宙飛行士たちが、月から地球を振り返った最初の人類として記録した写真である。希望は止めどなく湧き起こり、宇宙という果てしない空間から、やはり60年代は特別な10年なのだと信じる気持ちが再び息を吹き返した。

Photo : NASA
1969年の夏
1969年に入るとヒッピーの夢である“ラブ&ピース”がにわかに活気を取り戻した。それまでの年にも数々の大規模な野外音楽イベントが開催されており、音楽フェス自体が決して目新しいものではなかった。1954年にニューポート・ジャズ・フェスティヴァルが年に一度の大がかりな集まりとして定着し、マイルス・デイヴィスからニーナ・シモン、マディ・ウォーターズ、ジョニー・キャッシュにボブ・ディランまで、いずれ劣らぬケタ外れの才能を披露する場を提供しており、中でもディランは1965年の出演時、エレクトリック・ギターとバンドを率いてプレイしたことで観衆に衝撃を与えたことで話題になった。
恐らく世界最初となる大規模ロック・フェスティヴァルは、ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス、オーティス・レディング、サイモン・アンド・ガーファンクル、ザ・フーらをフィーチュアして開催された1967年のモンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティヴァルということになるだろう。
翌年にはロンドンのハイド・パークで数多くの無料コンサートが行なわれるようになったが、その第一回が1968年6月、ピンク・フロイド、ティラノサウルス・レックス、 ジェスロ・タル、ロイ・ハーパーというラインナップで開催された(「俺がそれまで行った中で一番良いコンサートだった」とジョン・ピールは回想している)。
1969年の夏が近づくにつれ、アポロ計画がようやくケネディの約束の成就へと向かっているという確信を抱かせるようになるのと並行して、大西洋の両岸で、志を同じくする者たちによる大規模なフェスが立て続けに開かれるための礎が築かれていった。
ロンドンでは夏のはじまりと共に、エリック・クラプトン、スティーヴ・ウィンウッド、ジンジャー・ベイカーにリック・グレッチを加えたスーパーグループ、長く待望されていたブラインド・フェイスのデビュー・コンサートが行なわれた。1969年6月7日に行なわれた彼らのフリー・コンサートには、ドノヴァン、リッチー・ヘイヴンズ、エドガー・ブロートン・バンドらも出演者に名を連ね、前代未聞の推計12万人と言われる観衆の前でプレイした。
クリームのショウと同じようなものだろうと予想していたファンは、皆サイケデリックな体験を期待してその場に立って待っていた。だがいざセットが始まり、彼らのギグがもっとブルージーでレイドバックした内容であることが判明すると、観客はじりじりするような夏の暑さの中で、可能な限りチルアウトするよう精いっぱい努めた。
「英国の社会史に残る素晴らしくエポックメイキングな一大イベント」
次にハイド・パークで行なわれたのは、ロック史の年間記録に刻まれることになったザ・ローリング・ストーンズによるイベントである。ストーンズはそれまで丸2年の間、公の場に姿を見せていなかった。しかしながら、ミック・ジャガーとキース・リチャーズが麻薬取締法違反容疑で懲役刑の判決を受けた後、調停期間中の彼らの動向はずっと新聞の一面を飾っていた。
この判決は一般市民からの抗議殺到で取り消されたのだが、意外なことにその抗議の急先鋒となったのはウィリアム・リース・モグ[訳注:1967年から81年までザ・タイムズ紙の編集長を務めた]で、タイムズ紙に掲載された彼の論説には、ストーンズに対する判決は彼らが実際にやったことではなく、彼らの存在に対して当局が与えたものだと断罪した。メインストリームのポップ・アクトとカウンターカルチャー(若者文化)が衆目の中で初めてぶつかり合ったこの一件自体が、60年代という時代を定義づけたひとつの瞬間だった。
1969年にはストーンズはカウンターカルチャーの代表格となっており、彼らがロンドンの王立公園のひとつでプレイするということは、ひとつの禁忌を意味していたこともあり、会場の警備業務は英国警察の警察官ではなく荒くれもののヘルズ・エンジェルズに託された。それでもストーンズのハイド・パークでのショウが成功する保証はきわめて乏しかった。そんな中、バンド内で日に日に孤立を深めていた結成メンバーのブライアン・ジョーンズは、1969年初頭にジョン・メイオールのブルース・ブレイカーズで話題を振りまいていた若き凄腕ギタリスト、ミック・テイラーに取って代わられていた。
新編成となったローリング・ストーンズが、ライヴのリハーサルのためにザ・ビートルズのアップル・スタジオに篭る一方、事態は暗転してしまう。それは来るコンサートに余計な不穏さを煽る出来事だった。7月3日未明、ブライアン・ジョーンズが自宅のスイミング・プールの水底で発見されたのである。
検死官の見立ては、彼がドラッグとアルコールを摂取した状態でプールに入り、不慮の死を遂げたというものだった。その2日後、ミック・ジャガーは亡くなったブライアンに捧げられたハイド・パークのライヴの幕開けに、英国のロマン派詩人シェリーが友人の詩人ジョン・キーツの死に際して作ったという詩「Adonais」を朗読し、この世を去ったバンドの元ギタリストを悼んで何百匹という白い蝶を空に放った。
ブライアン・ジョーンズの死はコンサートに暗い影を落としたが、バンドのライヴへの復帰は凱旋と言って良いものだった。ザ・ガーディアン紙は約50万人のヒッピーとビートニクス、ヘルズ・エンジェルス、そしてポップ・ファンが参加したと言われるこのコンサートを、「英国社会史に残る素晴らしくエポックメイキングなイベント」と絶賛した。
これはイベントであると同時にハプニング[訳注:現代芸術において、あらかじめ予期された効果と偶然的効果を結合しようとする聴覚的・視覚的な表現行為]であり、ある意味音楽は二の次だったのだ。それはキース・リチャーズがローリング・ストーン誌に語った通りだろう。
「俺たちの演奏は最後の方はもうグダグダになってたよ、何しろ何年も一緒にプレイしてなかったからな……けど気にしてる奴なんか誰もいなかった。みんな、ただ俺たちが一緒に演ってるのが聴けりゃそれで良かったんだよ」
「3日間の平和と音楽の祭典」
一方、ニューヨーク州北部では、マイケル・ラング、アーティー・コーンフィールド、ジョエル・ローゼンマンにジョン・P.ロバーツという面々が、自分たちの同族を集結させるための場所を確保するのにほとほと苦労していた。彼らはボブ・ディランやザ・バンドといった多くのミュージシャンたち、芸術家たち、詩人たちが活動拠点としていたニューヨーク州ウッドストック周辺でフェスティヴァルを催したいと考えていたのである。
最終的に彼らが「3日間の平和と音楽の祭典」と銘打った一大イベントを開催したのは、1時間ほど車で走ったところにあるベセルにあるマックス・ヤスガーの酪農農場だった。ポスターには「みずがめ座の博覧会(An Aquarian Exposition)」などというタイトルが使われていたものの、この1969年8月15日から18日にかけて行われたイベントは、後にごくシンプルにウッドストックという呼び名で世界中に知られることとなるのである。
出演者は規格外の豪華さだった。 かいつまんで紹介するだけでも、ラヴィ・シャンカール、ティム・ハーディン、ジョーン・バエズ、サンタナ、ジャニス・ジョプリン、スライ&ザ・ファミリー・ストーン、ザ・フー、ジェファーソン・エアプレイン、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル、ジョー・コッカー、ザ・バンド、クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング、そしてジミ・ヘンドリックスと錚々たる顔ぶれで、スケジュールはどんどん押せ押せで後倒しになり、ヘンドリックスがステージに上がってアメリカ国歌「星条旗よ永遠なれ」を彼にしか出来ない解釈でプレイしたのは、実に月曜日の午前9時という有様だった。
前売り段階でハケたチケットが18万6000枚余りにのぼったため、主催者側はウッドストックが相当大がかりなイベントとなることを予測し、20万人前後のオーディエンスの来場を想定して準備をしていた。だが開演時間が近づくにつれ、明らかに少なくともその倍に当たる人々が会場を目指していることが発覚する。
防護柵を完成させるか、ステージを切りあげるか、二つに一つの選択を迫られた主催者側の出した答えは、この時点をもって入場無料のフェスティヴァルとするという決定だった。物資の供給もままならない中、膨れ上がった観衆が互いに仲良く助け合う様子は、空の栓が抜けたような土砂降りの雨で地面がドロドロのぬかるみと化しても、その気になればみんなで楽しい時間を過ごせることを雄弁に請け合っていた。
そんな当日の観客のスピリットに、イべント終了後壊滅的に荒らされた自分の農場の敷地を見回っていたヤスガーはこう語っている。
「もし私たちが彼らに加われば、今のアメリカが直面してる色んな苦難を逆手にとって、もっと明るく平和な未来へと向かう希望に昇華できるのかも知れない」
この時は確かに、より良い世界を築こうという60年代の夢が、ようやく実現に向かおうとしているかに見えたのである。
華々しいインパクトと共に終わる
翻って英国では、8月の終わりに行なわれたワイト島フェスティヴァルでボブ・ディランがライヴ・ステージに復帰し、ポール以外のザ・ビートルズの3人(ポールの妻リンダがフェス前日に娘のメアリーを出産したため)も観客として参加し、豪華なアーティストたちが大観衆の前でパフォーマンスを披露した。ショウの後、ディランはアスコットにあったジョン・レノンの大邸宅で彼らと合流し、音楽界の牽引役の頂点を極める面々と夏を締めくくった。
折しもザ・ビートルズの最新アルバムにして歴史的傑作『Abbey Road』はミックスを終え、リリースを待つばかりというタイミングであり、更にディランとストーンズがステージに戻り、西洋文化史上最大規模の人々が集まった素晴らしい夏のおかげで、60年代は華々しいインパクトと共に終わりを迎えようとしていた。そして、楽観主義を盛り上がらせた10年を定義づけたのは、既存のヒーローたちばかりではなかった。
「人類にとっての大きな第一歩」と新たなスター
ひと夏の間にこの世界は新しいヒーローたちの台頭を目撃した、中でも特筆すべきは人間を月に降り立たせた上で無事に地球に戻すという、ケネディの定めた目標を実現させた3人の宇宙飛行士たちである。ニール・アームストロング、エドウィン・“バズ”・オルドリン(映画『トイ・ストーリー』に登場するバズ・ライトイヤーの元ネタ)、そしてマイケル・コリンズの3人の名は、1969年7月20日、彼らの乗った月着陸船イーグル号が月面に着陸した瞬間から、人々の記憶に刻まれることとなった。
「人類にとっての大きな第一歩」というのはアームストロングが口にした言葉だったが、それはまるで60年代がその先の未来へと向かうための発射台に過ぎないような印象を与えた。だが、果たしてこれから来ようとしているのは、本当に必要なのは愛だけなのだと人々がようやく悟ることになる時代なのだろうか?
地上に話を戻してみても、未来はいかにも明るいように感じられた。新しいスターも登場していたのだ。デヴィッド・ボウイのヒット・シングル「Space Oddity」は、アポロの着陸成功を受けてよりいっそう広まることになった。
クリームやジミ・ヘンドリックスらが切り拓いたヘヴィなブルーズ・ロックのシーンが数年間隆盛を誇ると、1968年には新たなグループが出現する。凄腕セッション・ギタリストのジミー・ペイジが結成したそのバンドは、あらゆる楽器がラウドでヘヴィかつハードにプレイされた。彼らのバンド名であるレッド・ツェッペリンをそのまま冠したデビュー・アルバムは、たちまちのうちに年間最優秀アルバムの一枚に数えられるようになり、ここに新たな価値基準が定められることとなったのである。
そして、レッド・ツェッペリンがシーンに高い演奏技術を持ち込もうと画策するのと並行して、また新たなロック・ミュージックの流れも姿を現す。10月にリリースされたキング・クリムゾンのデビュー作『In The Court Of The Crimson King』は、ジャズと交響楽の要素をロックとブルーズに持ち込むことで、芽を出したばかりのプログレッシヴ・ロックというジャンルにおけるひとつの礎となった。
未だかつてないほどの多様化
1969年、ロック・ミュージックは未だかつてないほどの多様化を遂げていった。デトロイトでは、英国で出現したプログレとは対極の存在として、MC5と共にイギー・ポップのストゥージスがロックン・ロールにアナーキー的アプローチを採り入れ、彼らの煽動的なクラブ・ショウはビートルズの活動開始当時のハンブルク時代を彷彿とさせた。この2組のバンドが各々1969年に出したアルバムは、どちらも大いに人気を博し、後世に大きな影響を与えた。
スライ&ザ・ファミリー・ストーンはウッドストックで、ロックとソウルの見事な融合を見せつけ、(ほぼ)白人だらけのオーディエンスにファンクの洗礼を施した。また、スティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイらモータウンのアーティストたちが実験的なアルバムで新たな可能性を探る中、ポップ・シーンではジャクソン5というイキのいい新人グループが爆発的人気を集め、 シングル「I Want You Back」は全米シングルチャートをぐんぐん上昇して行った。
60年代の夢の終焉:ビートルズの解散とチャールズ・マンソン
しかしながら、ロックの楽園は外から見るほどバラ色の幸福感に満ちてはいなかった。最も大きい喪失は、1969年8月20日、アビー・ロードのEMIスタジオで行なわれたザ・ビートルズの新作セッションが、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴの4人にとって、全員揃って一緒に作業をした最後の機会となってしまったことだ。
ロサンゼルスでは、ビーチ・ボーイズのドラマーのデニス・ウィルソンが、自分の住んでいた自宅から逃げ出す羽目になった。というのも彼の友人であったチャールズ・マンソンの日に日に常軌を逸してゆく“ファミリー”の実質的な根城として乗っ取ってしまったのだ。ウィルソンの出奔から間もなく、デニス呼ぶところのザ・ウィザード(魔法使い)は、ザ・ビートルズから受け取った暗号による指示だと信じ込んだことに基づき、自らの思い描く革命を実行に移し、8月初旬にシャロン・テイトと友人たちを残虐に殺害したのである。
1969年の夏は、すべての人々が人類史上最も偉大な冒険の成功を祝うことで連帯感を深め、世界中の若者たちがハイド・パークやウッドストック、ワイト島、シアトルなどに集結した。デヴィッド・ボウイからジャクソン5、レッド・ツェッペリンの登場と、レゲエにプログレ、ファンクという新しい音楽の台頭も、夏の祝祭というポジティヴな空気と結びついたと言える。
だが、宇宙飛行士たちが地球に帰還する頃、この最も華々しい10年間が終わりを告げようとする時期に合わせるように、ヒッピーたちの夢もまた瓦解に向かっていた。
オルタモントの悲劇
チャールズ・マンソンの非道さと彼の殺人衝動への耽溺により暗転した時代の空気は、60年代の最後を飾る大集会、1969年12月6日にカリフォルニア北部のオルタモント・スピードウェイで開催されたザ・ローリング・ストーンズの無料コンサートにおいて、くっきりと明確な焦点を結ぶこととなる。ローリング・ストーン誌が後にロックン・ロール史上最悪の一日と呼び、「何もかもが完璧に悪い方に転んだ」と書いた日だ。
キース・リチャーズに言わせれば、そもそもヘルズ・エンジェルズを会場の警備担当として雇ったことが、良いアイディアではなかった。彼はイヴニング・スタンダード紙にこうコメントしている。
「俺たちはグレイトフル・デッドのお墨付きでその案を受け入れたわけだよ、問題は俺たちにとっちゃどっちにしろ面倒にしかなりようがなかったってことだ。もし連中を雇ってなかったとしても、あいつらはどっちにしろやって来て揉め事起こすところだったんだ」
丸一日がかりのショウには、他にもサンタナ、ジェファーソン・エアプレイン、ザ・フライング・ブリトー・ブラザーズ、クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングらのパフォーマンスがフィーチュアされていた。時間が進むにつれ、30万人強と言われた観衆がひしめき合う現場はどんどん荒っぽさを増して行った。
酔っぱらって平常心を失い出したヘルズ・エンジェルズの一部のメンバーたちによる小競り合いが暴力的な色合いを濃くしていることを見て取ったグレイトフル・デッドは、土壇場になって出演を取り止めた。ストーンズがステージに上がる頃には、事態は既に収拾がつかなくなっていた。彼らは観衆の異様な興奮状態を鎮めるために、 「Sympathy For The Devil」の演奏を中断することを余儀なくされた。
メイズレス兄弟によるこのコンサートのドキュメンタリー映画『ギミー・シェルター』で恐ろしいほど明確に記録されている通り、「Under My Thumb」の演奏中、ステージのすぐ前に近い位置で、18歳のメレディス・ハンターとエンジェルズのメンバー数人との間で喧嘩が勃発した。
伝えられるところでは喧嘩のさなかに、ハンターは相手に刺され、反撃するために拳銃を取り出した。だがそのお返しに、ヘルズ・エンジェルズのアラン・パッサーロがハンターを刺し、ハンターは地面にれ、そこへ更に他のエンジェルズのメンバーたちが襲い掛かり、ローリング・ストーンズがプレイしているまさにその真っ只中のステージから僅か数ヤードという場所で、地面に横たわったまま息絶えたのである。
ストーンズは何かトラブルが起こったことは認識していたものの、この襲撃の一部始終については分からずにいた。ステージ前に医者を呼ぶ場内放送が何度となく繰り返されたが、彼らはセットを続行し、まさか自分たちの目の前で殺人が行なわれているとまでは思っていなかったのだ。もしかするとショウをキャンセルした方がいいのではないかという考えも頭をもたげたかも知れないが、自分たちが職場放棄して逃げようとすれば、恐らくは暴動が引き起こされるであろうことを、彼らは敏感に感じ取っていた。
“西のウッドストック”になると目されていたはずのイベントは最悪の結果を迎えた。メレディス・ハンターの殺害に加え、伝えられるところでは2人の男性がひき逃げ事故で命を落とし、更にもうひとり、どうやらLSDをやっていたらしい若者が、流れの速い灌漑用水路で溺れて4人目の犠牲者となった。
コメンテイターたちの多くは、オルタモントを単に4人もの人間が悲劇的な死を遂げた現場としてのみならず、60年代の夢そのものが終わりを迎えた場所であると言及した。この一件から何十年もの時を経て、ザ・ニューヨーカー誌に寄稿した評論家のリチャード・ブロディは、「自発性という概念であり、物事は自然発生的に起こるものという感覚、その善意のスピリットは放っておいても広まるものだという認識、それらが全てオルタモントで死んだのだ」と書いている。
オルタモントで起こった出来事を『蠅の王』[訳注:ウィリアム・ゴールディングの1954年の小説。飛行機事故で無人島に生きることになった少年たちが、秩序ある社会を作ろうとするが、次第に原始的野蛮に支配されていくという物語]になぞらえた上で、彼はこう締めくくっている。
「ここで表面化した何が呪わしいかと言えば、ありのままという考え方それ自体だ。身にまとったより広義における社会秩序の虚飾や縛りから自由になって、各々の持つ性癖や傾向に素直に従えば、新世代の若者たちはきっとどうにかして自主的かつ率先して、もっと崇高で思いやりのある、愛に溢れた草の根の秩序を生み出してくれるだろうという期待だ。オルタモントで死んだのはルソー主義(自然主義)的な夢そのものだった」
しかし音楽は生き続ける
オルタモントにおける大惨事が、60年代が死ぬ瞬間の予兆であったにせよ、その時代の音楽はそこで死に絶えたわけではない。シーン最大の売れっ子たちがいまだに60年代の大スターたちと共演したがっている。リアーナとカニエ・ウェストはポール・マッカートニーと組んで仕事をし、2018年夏にはロンドンで行なわれたザ・ローリング・ストーンズのコンサートで、フローレンス・ウェルチが彼ら屈指の名曲「Wild Horses」のパフォーマンスに飛び入りしたことからも、それは言わずもがなだろう。
60年代が生んだ音楽の解放は、その後にやって来た全てを受容した。それは決してデヴィッド・ボウイやジャクソン5といった当時の新たなスターたちに限ったことではない。ザ・ビートルズはもはや存在しなくても、4人のソロ・アーティストのキャリアは更に時代を超越した名作を生み出した。70年代に入ると、ザ・ローリング・ストーンズは『Sticky Fingers 』や『Exile On Main St(メインストリートのならず者 )』といういずれ劣らぬ傑作アルバムを連発し、確実にペースを掴んで行った。
そして、それも所詮は氷山の一角に過ぎないのだ。これまでもそしてこれからもきっと、どれだけ世代が移り変わろうと、ポップ・ミュージックを生み出す若者たちは、過去どの10年代とも比較にならないほど絶大なる影響力を持った60年代に、永遠に返すことの出来ない借りを作り続けるのである。
60年代の終わりには、ポップ・ミュージックの歴史の中にこの10年代の重要度を刻み付けるに十分なクリエイティヴィティの爆発がみられた。ザ・ローリング・ストーンズやザ・フー、ジ・オールマン・ブラザーズ・バンドらによるこの時代が生んだ最高のアルバムたちをご堪能あれ。
Written By Paul McGuinness
- ウッドストック・フェスティバルのパフォーマンス・ベスト15
- ウッドストック以降:現代の音楽フェスティバルはいかに変貌を遂げたか
- ニューポートからウッドストックへ:音楽フェスティバルの真の歴史
- アメリカ初の大規模ロック・フェス “モントレー・ポップ・フェスティバル”
- 名曲「On The Road Again」収録、キャンド・ヒートの『Boogie With Canned Heat』
- “ブラインド・オウル”ウィルソンのブルースとキャンド・ヒートの物語
- ザ・フーの金字塔『Live At Leeds』を明らかにする
- ザ・フー 最高傑作『Tommy』:ある男の想像の産物であり、ある男が見る素晴らしい光景
- 偉大なるラヴィ・シャンカールの想い出