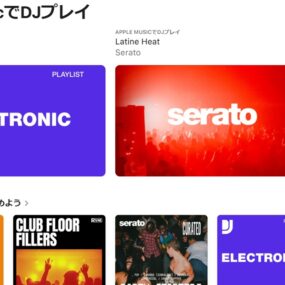Stories
デヴィッド・シルヴィアンとジャパンのベスト・ソング20曲:類稀なる音楽的知性とその名曲たち


デヴィッド・シルヴィアン(David Sylvian)の最高の楽曲をリストアップするというのはたやすいことではない。というのも、シルヴィアンの作品は、グラム・ロックに始まりアバンギャルド・ポップスに路線転換したジャパン(Japan)のリード・ヴォーカル時代から、最新の実験的な作品まで、さまざまなジャンルに及んでいるからである。
そう、シルヴィアンのディスコグラフィーは、単純な1本の道として描くことができない。しかし、そうした簡単にまとめられない複雑さのおかげで、彼の作品は実に魅力的なものになっている。そしてその魅力が実に長いあいだ保たれているのである。
その音楽活動の中で、シルヴィアンは純粋なポップス、アジア的な要素、中東の楽器、フリー・ジャズ、実験的なエレクトロニック・サウンド、フォーク、ファンクなど、多彩な要素を自身の作品に取り入れてきた。これらの影響を深い歌声と詩的な歌詞に合わせてすべて取り入れてきたという事実は、それ自体、彼が比類のない才能の持ち主であることを証明している。
このような幅広い作品群から最高のものを抽出するというのは不可能な作業のように思える。とはいえ今回は、敢えてデヴィッド・シルヴィアンのベスト・ソングをリストアップしていきたい。これをきっかけに、まだシルヴィアンのことよく知らない方が、彼の広大で多様なディスコグラフィーを探求していくことを願っている。
<関連記事>
・ジャパン『Tin Drum』(邦題:錻力の太鼓)の想い出
・『孤独な影』と『錻力の太鼓』がハーフ・スピード・マスタリングLPで発売
ジャパンの活動初期
1. Adolescent Sex (果てしなき反抗)
2. Don’t Rain on My Parade (パレードに雨を降らせないで)
3. Deviation (若き反抗)
4. The Tenant (愛の住人)
ジャパンは1970年代初頭にデヴィッド・シルヴィアン、弟のスティーブ・ジャンセン、そして3人の友人たちによって結成された。当時の彼らはポップスやグラム・ロックに夢中になっていた。そして大好きだったT.レックス、ルー・リード、モータウンの曲をコピーしながら、曲作りのコツを学んでいった。
このバンドが発展させたサウンドは、そもそもの出発点と比較すると驚くべきものになっていた。1978年に発売となったジャパンの最初のアルバム2枚『Adolescent Sex (果てしなき反抗) 』と『Obscure Alternatives (苦悩の旋律) 』は、このグループのディスコグラフィーの中でも異彩を放っている。
当時の彼らが目指していたのは、ビバップ・デラックスやロキシー・ミュージックのようなクリエイティブな、そして売れ線の音作りだった。アルバム『Adolescent Sex』のタイトル曲は、キーボーディストのリチャード・バルビエリが奏でるガラスのように透明なシンセサイザーの音色が特徴のディスコ・ロックだった。またミュージカル「Funny Girl」のために書かれた曲「Don’t Rain On My Parade」のカヴァーは、研ぎ澄まされた爪で切り裂くような強烈なサウンドになっている。
『Obscure Alternatives』でジャパンは1980年代の全盛期のクールなサウンドに近づいたが、そもそもの出発点であるアート志向のグラム・ロックを完全に振り切るところまでは至らなかった。「Deviation」は、ソウルフルなホーン・アレンジ、ゴムのように弾むベース・ライン、そして最後のシンセの炸裂が特徴的だ。
アルバムを締めくくる「The Tenant」は、1976年のロマン・ポランスキー監督の同名映画にインスパイアされたインストゥルメンタルで、繊細なピアノとロバート・フリップのようなギター、そしてシンセサイザーの轟音が融合している。
ジャパンの活動全盛期
5. Life In Tokyo
6. In Vogue
7. All Tomorrow’s Parties
8. Swing
9. Visions of China
10. Ghosts
1970年代最後の年を迎えたジャパンは、グループの音楽性が完全に変化することを予感させるシングルでスタートを切った。ディスコのアイコンであるジョルジオ・モロダーとのコラボレーションで作られた「Life in Tokyo」では、ドナ・サマーやブロンディとのヒット曲でお馴染みのいかにもモロダーらしいシンセサイザーのアルペジオが響きわたっている。この曲の一部の要素はジャパンのサード・アルバムである1979年の『Quiet Life』にも取り入れられているが、それ以外の部分はポップな文脈の中にぼんやりとした音量を取り入れたものとなっている。
「In Vogue」では、シンセ・ソウル・サウンドの下で低音のドローンが鳴り続けている。さらにジャパンは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「All Tomorrow’s Parties」をノイ!の機械的なリズムとロキシー・ミュージックの小生意気な態度でアレンジし直し、お気に入りの曲を解体し続けた。
そしてデヴィッド・シルヴィアンは、ジャパンの最後のアルバム2枚をレコーディングしているあいだに、よりクリエイティブな主導権を握るようになった。その結果グループ内の人間関係はピリピリと張り詰めたものになったが、それでもこのグループは非常にパワフルな作品を完成させることができた。
1980年にリリースされたアルバム『Gentlemen Take Polaroids (孤独な影) 』は、ほぼすべてがスタジオで録音され、ベーシストのミック・カーンの流れるようなフレットレス・ベースがすばらしく前面に出た「Swing」といったきわめてスリリングな楽曲を収録している。しかし、これらのレコーディング・セッションでメンバー間の緊張があまりに高まったため、ギタリストのロブ・ディーンがグループから離脱してしまった。
彼の脱退は悲しい出来事だったが、四人組となったジャパンは1981年に『Tin Drum (ブリキの太鼓) 』という傑作を作り上げた。このアルバムでは国際的な文化の音楽への関心が高まっており、哨吶 (スオナ:中国の木管楽器) やアフリカのハンド・ドラムなどが「Visions In China」のようなトラックに彩りを添えている。
また、このアルバムからはジャパンの最大のヒット・シングル「Ghosts」が生み出された。ほとんど電子楽器のみで構成されたこのバラードには、シルヴィアンがジャパンに別れを告げているように思える瞬間がところどころにあった。彼は2009年に雑誌『MOJO』の取材に応え、次のように語っている。
「個人的な性質のようなものが表に出てきたのはあのときだけだった。あれは、自分のソロ活動の目標を定める上で道筋をつけてくれた曲でもある」
ジャパンが解散したのは、それからわずか数ヶ月あとのことだった。
デヴィッド・シルヴィアンの初期作品
11. Forbidden Colours (禁じられた色彩)
12. Red Guitar
13. River Man
14. Orpheus
15. Brightness Falls
デヴィッド・シルヴィアンのソロ活動は、元イエロー・マジック・オーケストラの坂本龍一の協力を得て、幸先の良いスタートを切った。坂本は、第二次世界大戦を描いた映画『戦場のメリークリスマス』でデヴィッド・ボウイと共演し、さらにはテーマ曲を作曲していたが、ヴォーカルと歌詞を必要としていた。そうして坂本とシルヴィアンが共作した曲「Forbidden Colours」は、瞬く間に名曲となった。サティにインスパイアされた坂本のメロディに、シルヴィアンはスピリチュアルでロマンティックな歌詞を乗せ、見事な歌声を響かせている。
この曲は、ブリティッシュ・ポップ・ミュージックの世界でシルヴィアンの地位を確固たるものにした。前述の『MOJO』のインタビューでシルヴィアンは以下のように語っている。
「あの曲はドアを開いてくれた。それで『OK、準備は完了』と思って、『Brilliant Trees』を作り始めたんだ」
このソロ・アルバムの曲作りを始めた彼は、ポップな方向性に進路を取った。そうしてできた「Red Guitar」は、坂本のピアノをフィーチャーした軽やかな作品に仕上がっている。
しかしそれに続くソロ・アルバムで、彼はより親しみやすい作品に加えて実験的な作品を盛り込み、両者のバランスを取るようになった。2枚組LP『Gone To Earth』には、「River Man」のようなスローなポップ・ソングと、アンビエントなインストゥルメンタルの両方が収録されている。
さらに次の『Secrets of the Beehive』ではこの2つの要素を融合させ、船乗り歌のような「Orpheus」でさえも、ドローン調のストリングスと優美なシンセに包まれている。
1980年代を通して、シルヴィアンはほかの先進的なアーティストたちと創造的な関係を築いていった。共演相手の中には、元カンのベーシストであるホルガー・チューカイ、ビー・バップ・デラックスのリーダーであるビル・ネルソン、ジャズ・ミュージシャンのケニー・ウィーラー、デヴィッド・トーンなどが含まれていた。
またギタリストのロバート・フリップは、シルヴィアンに自らのバンド、キング・クリムゾンに参加しないかと誘いをかけた。その申し出は断られたが、代わりに彼らはコラボレーション作品『The First Day』を制作した。これは、ジミ・ヘンドリックスにインスピレーションを得て作られた「Brightness Falls」を含むラウドでファンキーなロック・アルバムだった。
デヴィッド・シルヴィアンのその後のソロ作品
16. Every Colour You Are
17. Krishna Blue
18. The Good Son
19. The Banality of Evil
20. Snow White In Appalachia
ジャパン解散から10年後の1991年、デヴィッド・シルヴィアンはグループのかつての同僚3人と再び組んで、レイン・トゥリー・クロウという新しいグループ名でスタジオに入った。このグループの唯一のアルバムには、アーシーなインストゥルメンタル・ナンバーや「Every Colour You Are」のようなゴージャスなバラードなどが収録されている。もしジャパンが解散せずに活動を続けていたらどのような方向に進んでいたのだろう? そんな問いかけに、このアルバムはひとつの答えを提示していた。
シルヴィアンと弟のジャンセンは、ドイツ人プロデューサーのバーン・フリードマンとのトリオ、ナイン・ホーセスでも共演していた。フリードマンは、「The Banality of Evil」や2005年にリリースされたナイン・ホーセスの唯一のフル・アルバム『Snow Borne Sorrow』にネオ・ソウルのエネルギーを注入している。
シルヴィアンは過去20年間に多くの作品をリリースしてきたが、そのペースは散発的で、曲作りも伝統的な手法から離れようとしているように見える。こうした志向性は、彼のスピリチュアルな欲望と現世的な欲望のあいだの葛藤を反映したアルバム『Dead Bees on a Cake』から見え始めた。
たとえば「Krishna Blue」では、そうした葛藤を音楽的に表現するために、インドのパーカッションとアコースティック・ギターが使われている。また、この曲のあいだ奏では当時の妻でシンガーのイングリッド・シャヴェイズがハスキーなダイアローグを担当しており、さらに複雑な様相を呈している。
2003年に自分のレーベル、サマディサウンドからリリースした最初のアルバム『Blemish』で、シルヴィアンは自分自身を完全に解き放っている。このアルバムは、結婚生活にピリオドを打った後の彼の精神状態を音楽で赤裸々に描いた作品だった。ここには、デレク・ベイリーの即興ギターに彼自身のダークな歌声を乗せた「The Good Son」などの曲が収録されている。
それから6年後にリリースされた『Manafon』では、シルヴィアンの歌詞と音楽がさらに抽象的になっていた。イギリスのジャズ界の巨匠エヴァン・パーカーやジョン・ティルベリー、ターンテーブル奏者の大友良英と言ったコラボレーターたちの即興演奏の録音をもとに、シルヴィアンは手早く歌詞を書き、ヴォーカルを吹き込んだ。そうしてできたのは抽象的で不思議な曲だった。たとえば「Snow White In Appalachia」では、きしむようなドローンに合わせて、ひどい家庭環境からの脱出を試みる女性の物語が歌われる。
『Manafon』を最後に、シルヴィアンが自分の声を音楽作品に吹き込む機会はほとんどなくなっている。その後の彼の作品は、アンビエント調のうなるようなサウンド、短波ラジオのサンプルや電子ノイズを利用したミニマル作品、不協和音と残響音のさまざまなバリエーションを探求してきた。
たとえ彼の作品がさらに独特で神秘的なトーンになったとしても、彼の創造的な精神はいつまでも俊敏で好奇心旺盛、そして輝かしいものであり続けるだろう。
Written By Robert Ham