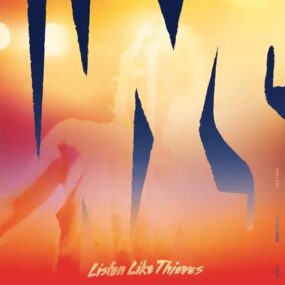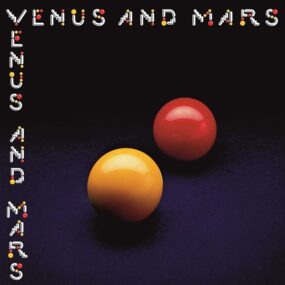Stories
80年代にシンセサイザーを活用した有名ロック・ミュージシャン8組
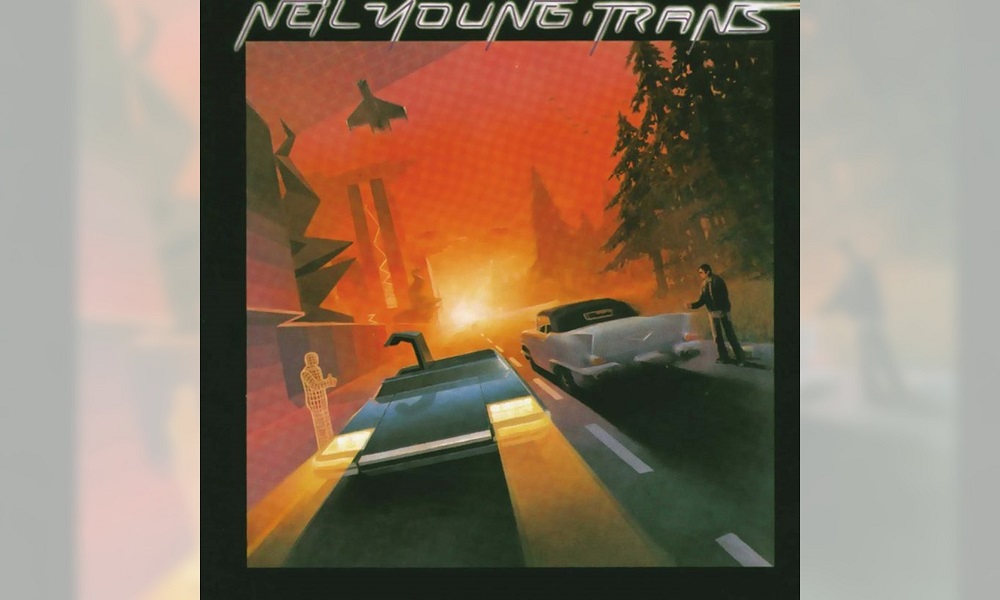
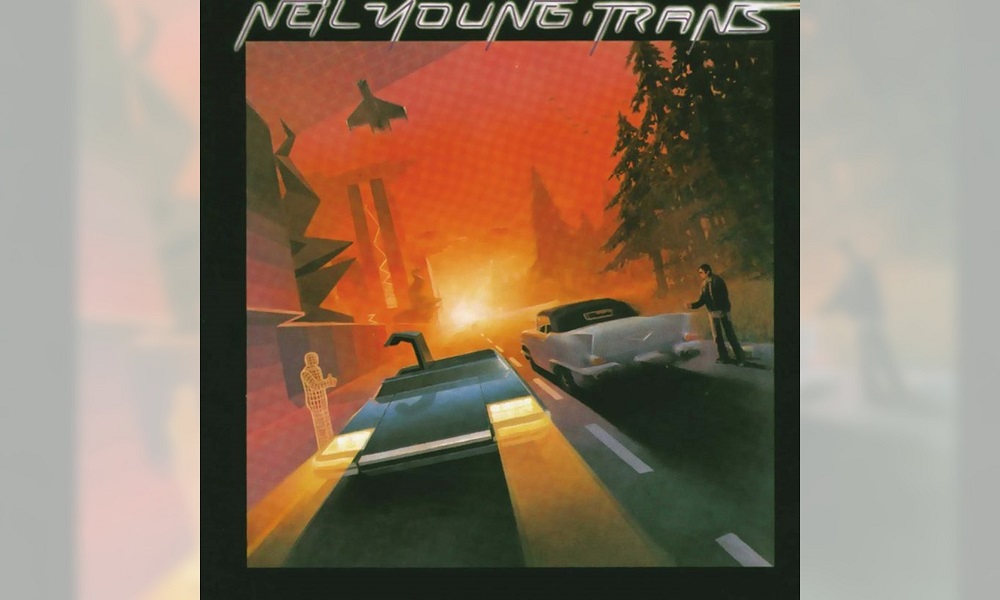
1970年代、シンセサイザー奏者たちはギターを中心としたロック界からは“下らないことに時間を費やすオタク”とみなされることが多かった。しかし1980年代に入ると“オタクの逆襲”が始まった。気づけば、劣勢に立たされていたのはギタリストたちの方だったのである。
もちろん、中には例外もあった。たとえば、プログレは1970年代のロック界でも主要なサブジャンルの一つで、そこには恐るべきシンセ奏者も多く存在していた。また、ブライアン・イーノなどの奇抜なアート・ロック・ミュージシャンたちも、狭い仲間内で電子楽器をクールなものとして扱っていた。
だが、1970年代ロック界、特にハード・ロック界隈のアーティストの多くは、弦楽器や打楽器以外のものを見下したままだった。オジー・オズボーンやデヴィッド・リー・ロスなどに至っては、それから時が経っても、ツアーに帯同するキーボーディストをステージに上げないことが多かった。そうすることで、オマケのような“ダサい”シンセ奏者にバンドが毒されないようにしていたのだ。
だが1980年代に入ってその力関係が変わると、シンセは突如として当たり前のものになった。すると、昔ながらのロック・アーティストたちも時代に遅れまいと、電子楽器を導入するようになった。そのころには、シンセを取り入れたとしてもグループの評判が下がるような心配はなくなっていたのである。
この記事では、その中でも特筆すべきミュージシャンたちを紹介しよう。
<関連記事>
・早弾きやソロだけじゃない80年代のギター・ヒーローたち
・プログレッシヴ・ロックのベスト・ギタリスト25
・意外に多いパンクとプログレの共通点
1. ラッシュ / RUSH
ラッシュはロック・バンドの中でも、1980年代になってシンセに熱を上げても不思議のないグループだった。彼らは既に1970年代から、必要とあらば、特にプログレッシヴ・ロック色の強い壮大な楽曲でシンセサイザーを使用することを厭わなかった。たとえば1981年の大ヒット作『Moving Pictures』に収録された「Tom Sawyer」では、シンセが主役に躍り出るパートまであるほどだ。
そして『Moving Pictures』に続くアルバムとなった1982年の『Signals』で、ラッシュの面々はその方向性をさらに推し進めた。ヴォーカル、ベース、キーボードの三役を一人でこなしていたゲディ・リーは、1982年にシーン誌のインタビューに応え、以下のように語っている。
「これまでの俺たちの作品は、基本的にギターを中心としたサウンドだった。その中でリズム・セクションが前に出ることがあったり、ときにはシンセサイザーが華を添えたりすることもあった。だけど今回は、もっとシンセサイザーを活用することにしたんだ……。最初のころ、俺はバンドの音数の少なさを補うためにペダル式のシンセ・ベースを使っていた。そのあとミニモーグを手に入れて、それからもっと大掛かりな機材も導入した。時間が経つにつれて、シンセの音の使い方がだんだんと分かってきたんだ」
ゲディはそんな風にして身につけたノウハウを惜しげもなく作品に取り入れた。たとえば、「New World Man」はボコボコと湧き上がるようなシンセの音で幕を開け、そのサウンドが同曲全体を纏め上げている。同曲は『Signals』からの1stシングルとしてリリースされると、ラッシュの作品として唯一の全米トップ40入りを果たすヒットを記録した。
また、『Signals』からの2枚目のシングルで10代の若者の疎外感を歌ったアンセム「Subdivisions」は、電子音を主役に据えた1曲だった。この曲では、終盤でこそアレックス・ライフソンのリード・ギターが唸りを上げるものの、それまでギターはゲディの奏でる荘厳なシンセの影に隠れている。
2. スティクス / STYX
スティクスも、当時ラッシュと同じような状態にあったグループの一つである。スティクスのシンガー兼キーボーディストだったデニス・デ・ヤングもゲディ・リーと同様、グループの作品の中でもアート色の強い楽曲で、何の抵抗もなくシンセを使用していた。
だが同グループのフロントには、スポットライト映えする派手なスタイルのリード・ギタリストが二人もいた。そのため、1983年作『Kilroy Was Here』が発表される以前の数年間、スティクスのヒット曲にシンセが使用されることは「Too Much Time On My Hands (時は流れて)」の低音部分を除いてまずなかったのである。
1980年の暮れにギャラップ社が行った世論調査で、スティクスは“アメリカ最大のロック・バンド”に選出された。世界のトップに立った彼らにとって、あらためて実力を証明する必要はなく、彼らは自分たちのやりたい音楽を追求すればよかった。それでもデ・ヤングはゲディと同じく、新技術を駆使して新たな路線へと歩みだした。そうして『Kilroy Was Here』の収録曲である「Mr. Robot」は、グループを代表するヒット曲の一つとなった。
2010年、デ・ヤングはBackstage Axxessのインタビューで、同曲についてこう語っている。
「 (“Mr. Robotは”)ピアノ中心じゃないという点で、俺には珍しい1曲だ。ローランド製のシンセサイザーを活用しながら書いたんだ。どのモデルだったかは忘れてしまったけど、アルペジエーターを搭載した最初のシンセサイザーだったはずだよ。初期型のシーケンサーのような感じさ。一つの音を弾いたままにしておけば、それだけでいくつものリズム・パターンを作れるっていう仕組みだった。この曲ではそのプログラムを使って”ジャン、ジャン、ジャン”という音を作り、そこにリズムのパートを足していった。そうやって“Mr. Robot”が出来上がったんだ」
3. ジェスロ・タル / Jethro Tull
ジェスロ・タルはもともと、ラッシュとスティクスを足したよりもさらにプログレ色の強いグループだった。しかし、二人のキーボーディストを擁していた時期さえあったにもかかわらず、彼らは1970年代のほかのプログレ・バンドよりシンセの導入に後ろ向きだった。
ジェスロ・タルのサウンドは、マーティン・バーの強力なギター・リフを前面に押し出したもので、彼らには中世ヨーロッパをモチーフにしたお祭り「ルネサンス・フェア」がもっともよく似合いそうなロック・バンドというイメージがあった。そしてその通りの音楽を展開するのが常だったのである。
そんな状況に変化が起き始めたのは、新メンバーにキーボーディストのピーター=ジョン・ヴェテッシを迎えた1982年のアルバム『The Broadsword And The Beast』からだった。若きシンセサイザー奏者であった彼が、「Clasp」や「Watching Me Watching You」といった楽曲に現代的な電子音を持ち込んだのである。しかしジェスロ・タルの作風がもっとも劇的に変わったのは1984年のアルバム『Under Wraps』であった。
同2作の制作の合間に、ヴェテッシはグループのシンガーであるアンダーソンの最初のソロ・アルバム『Walk Into Light』に参加。シンセサイザーを多用した同作で、彼はアンダーソンと密な協力関係を築いた。
そして、アンダーソンがジェスロ・タルの活動に復帰すると、今度はグループとしてもシンセ中心の路線に転換。ジェスロ・タルは結成以来初めてドラマーすらいないまま、電子音のビートでその役割を代替してアルバムを制作したのである。そんな『Under Wraps』では、ポップ・センスのあるヴェテッシのシンセ・ワークが非常に大きくフィーチャーされている。そのため、アンダーソンの存在を除けば、『Aqualung』などギター中心の作品をリリースしていた10年以上前のバンドの面影はほとんどなくなっていたのだった。
4. ニール・ヤング / Neil Young
ニール・ヤングは1970年代のロック・ミュージシャンの中で、もっとも電子音と縁遠い存在だったかもしれない。カナダ出身の吟遊詩人、ヤングは、ほかの誰よりも、素朴で気骨のあるルーツ・ロックの音楽と強く結びついていたのだ。
しかしながらその一方で、“常に自分のやりたいことだけをやる”という姿勢がヤングの揺るぎない特徴でもある。実際、ゲフィン・レコードと契約して初めてリリースした1982年作『Trans』以降、彼はこの点を何よりも裏付ける型破りなアルバムを次々に発表していった。
ヤングは新技術を駆使した未来的な衝撃作『Trans』に続いて、王道のカントリー・サウンドとなった『Old Ways』や、賑やかなロカビリー調のアルバム『Everybody’s Rockin’』をリリース。
その中でも『Trans』はテクノ・ロックを先駆けた作風のアルバムだった。中でも「Computer Age」や「Sample And Hold」といったトラックでは、タイトルにも電子的なものへの偏愛ぶりが表れており、内容の面でも、シンセサイザーを使用したリフとヴォーコーダーによる機械的なヴォーカルが組み合わされている。
ヤングはまた、この新路線でバッファロー・スプリングフィールド時代の楽曲「Mr. Soul」をセルフ・リメイク。おそらく彼の保守的なファンはこれを聴いて怒りに我を忘れ、スピーカーに感情をぶつけたことだろう。
この突然の路線転換の理由は、ヤングの家庭環境にあったという。1995年、彼はモジョ誌のインタビューでニック・ケントに以下のように語っている。
「18ヶ月のあいだ、毎日15時間から18時間かけて、幼い息子のベンとのプログラムに励んでいた。プログラムにはとにかくあらゆることが含まれていて、その経験が『Re-ac-tor』や『Trans』の音楽に直接影響を与えているんだ。知っているだろうけど、俺の息子は重度の障がいを抱えている(編註:脳性麻痺と言語障害)。あのころは、言葉を話して、他人とコミュニケーションを取る方法を模索していたんだ。『Trans』では、そのことがテーマになっている。だからあのアルバムでは、俺の声が聴き取れないだろう?あれは、俺が息子と関わる中で感じていたのと同じ感覚を表現しているんだ」
5. ZZトップ / ZZ Top
そんなニール・ヤングよりもさらに泥臭く無骨な音楽を特徴とする1970年代のアーティストといえば、ZZトップくらいのものだろう。1980年代を迎えたころ、彼らはスランプに陥っており、作品のヒントになるものを探し求めていた。そして、ギタリストのビリー・ギボンズは意外なところにそれを見つけたのだった。2015年、彼はローリング・ストーン誌のデヴィッド・フリッケに以下のように語っている。
「あるとき、よりによってカントリーが流れるヒューストンのクラブで、ディーヴォのサウンドチェックを見たんだ。俺はそれより前に彼らのファースト・アルバムを聴いたことがあって、結構気に入っていた。それでそのとき、メンバーの一人がミニモーグでこんなフレーズを弾いたんだ(そう言ってギボンズは、機械的かつ軽快なリフを鼻歌で再現する)。 彼はその場の思いつきで弾いているだけだったが、俺にはそれで十分だった」
その経験から生まれたのが、シンセを取り入れたユニークなリズムの1曲で1981年のアルバム『El Loco』に収録された「Groovy Little Hippie Pad」だった。
以降、気がつくとギボンズはデペッシュ・モード、OMDらのシンセ・ポップ・サウンドや、ミニストリーらによるインダストリアル・ミュージック調のビートに傾倒。そうして誕生したのが、シンセを多用したZZトップの1983年作『Eliminator』だった。特に「Legs」や「Gimme All Your Lovin」などの収録曲では、機械的に生成されたドラムや、小気味よいシーケンサーのフレーズ、電子的なベース・ラインなどが強い印象を残す。そんな『Eliminator』は、ヒューストン出身のトリオである彼らにとってキャリア最大のヒット作となったのだった。
6. ヴァン・ヘイレン / Van Halen
ヴァン・ヘイレンもまた、1970年代はギター、ベース、ドラムという昔ながらの編成に全力を傾けながら、のちにシンセを多用するようになったバンドの一つだ。グループは結成からの数年でマルチ・プラチナ級のアルバムをいくつも生み出し、その中でエディ・ヴァン・ヘイレンはギターの新たな表現方法を作り上げた。
その後、彼は次に挑戦するべき新たな方向性を模索。そして、ヴァン・ヘイレンとしての6thアルバム『1984』の準備を進める中で自宅スタジオの製作に着手し、その完成までのあいだ、彼は最新のシンセサイザーで実験をして過ごしたのだという。結果として生まれたのは、「Jump」や「I’ll Wait」などの大ヒット・シングルだった。
エディはそれらの楽曲を通じて、オーバーハイムのシンセも彼の手にかかればギターと同じくらい堂々と弾きこなせることを見せつけた。そのうち「I’ll Wait」では、マイケル・アンソニーも一時的に通常のベースから低音域を強みとするシンセサイザーに担当楽器を持ち替えている。
7. ウイングス、ポール・マッカートニー / Wings、Paul McCartney
1970年代を代表するバンドのフロントマンたちの中にも、1980年代前半に発達したシンセサイザーの技術に触発され、電子楽器を導入する者が存在した。ウイングスではリンダ・マッカートニーがアープ・オデッセイを奏でることもあったが、このグループの持ち味はなんといっても、ポールのヴォーカルを完璧に引き立てるツイン・ギターの演奏だった。
ポールがウイングスとしての活動を実質的に終えて最初に発表したのは、彼がほぼ一人だけで作り上げた1980年のアルバム『McCartney II』だったが、同作はその後の音楽シーンのトレンドを見事に予告するような作品だった。「Temporary Secretary」や「Front Parlour」などにおける滴る水のような電子音は、当時発展途上にあったシンセ・ポップによる革命、ひいては将来的なエレクトロニカの流行をも先取りしていたのである。
8. スティーヴ・ウィンウッド / Steve Winwood
トラフィックの作品にシンセサイザーが使用されることはほとんどなかった。だが、スティーヴ・ウィンウッドがルーツ・ミュージックの影響を感じさせるトラフィック時代のアート・ロックから脱却し、1980年代に入ってソロ・アルバムを制作したとき、状況は大きく変わっていた。
ウィンウッドが1980年に発表したセカンド・アルバム『Arc Of A Diver』は、ソウルフルな彼の魅力を、電子楽器をフィーチャーした1980年代らしいポップ・サウンドに落とし込んだ1作。このアルバムで、彼は大物ソロ・アーティストの仲間入りを果たした。中でも、心に響くヒット曲「While You See A Chance」や、官能的なナンバー「Spanish Dancer」では、和音を奏でられる最新式のシンセやドラム・マシンが手の込んだ音作りを可能にしている。
1980年代が終わるまでに、シンセやシーケンサー、電子音によるビートなどは、空気と同じくらいありふれたものになっていた。そうしたものが“使用されていること”より、“使用されていないこと”の方が注目されるようになっていたのである。しかし1980年代前半、そういった要素はベテランたちにとって、作品を新鮮で目新しいサウンドに仕上げるためのチャンスとなっていたのである。
Written By Jim Allen

2023年4月28日発売
2023年5月31日日本盤CD発売
 マイク・オールドフィールド『Tubular Bells – 50th Anniversary Edition』
マイク・オールドフィールド『Tubular Bells – 50th Anniversary Edition』
2023年5月26日発売
CD
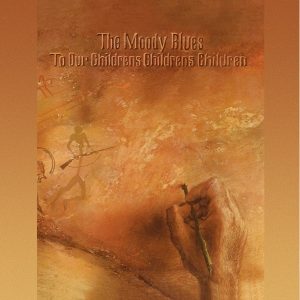 ムーディー・ブルース『To Our Children’s Children’s Children / The Royal Albert Hall Concert December 1969』
ムーディー・ブルース『To Our Children’s Children’s Children / The Royal Albert Hall Concert December 1969』
2023年5月12日発売
4CD+ブルーレイ
- ブライアン・メイのギター・ソロBEST10
- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達
- ミュージシャンらによるカスタムメイド楽器ベスト10
- ロック界最高のパワー・トリオ10選(ビデオ付き)
- 史上最高のプロテスト・ソング10曲:不朽の政治的アンセム
- 平和を歌った名曲ベスト25:最も重要なことを思い出させてくれる楽曲たち
- 最高の女性ドラマー・ベスト25:様々なジャンルのミュージシャンたち
- 最高の男性ロック・シンガー・ベスト100:伝説のヴォーカリストたち
- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達