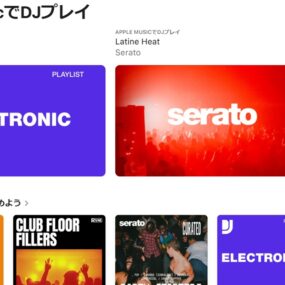Stories
ビーチ・ボーイズのベスト・ソング25:サーフ・ポップだけではない、後進に影響を与えた名曲たち


アメリカが誇る名グループであるビーチ・ボーイズ(The Beach Boys)が世界にもたらしたものは、初期のブレイクのきっかけになったサーフ・ポップだけでは決してない。ビーチ・ボーイズのベスト・ソングからそれを紐解いていこう。
当時19歳だったブライアン・ウィルソンが、ふたりの弟であるカールとデニス、いとこのマイク・ラヴ、そして学友のアル・ジャーディンを誘ってオリジナル曲の「Surfin’」をレコーディングしたのは1961年10月のこと。その先に何が待ち受けているのか、そのときは想像もつかなかっただろう。
そのデビュー・シングルこそ全米チャート75位に終わり、少々幸先の悪いスタートとなったが、それは彼らにとってほんの第一歩に過ぎなかった。そのあとビーチ・ボーイズはヒット曲の数々で世間を賑わせ、正真正銘のスーパースターへと変貌を遂げる。そしてビーチ・ボーイズの代表曲は、アメリカ音楽の礎を築き上げていった。
そのシングルやアルバムは枚数を重ねるごとに洗練されていき、彼らは1960年代にポップ・ミュージックの常識を塗り替えた。70年代にはそのサウンドをより成熟させ、当初のサーフ・ミュージックとは一味違う作品群をリリース。それらも後進の音楽に大きな影響を与えることとなった。ここではビーチ・ボーイズのベスト25曲を振り返ることで、彼らの功績を称えよう。
<関連記事>
・ブライアン・ウィルソン80歳の誕生日を祝う豪華ミュージシャンたち
・ビーチ・ボーイズ、1969~1971年を振り返る5CDボックス発売決定
・なぜ、ビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』が芸術品であり続けるのか?
25位:Surfer Girl (『Surfer Girl』収録、1963年)
ビーチ・ボーイズの初期のヒット曲には、賑やかで無鉄砲なサーファーたちの生活を歌ったものが多かった。だがほどなくして、ブライアン・ウィルソンはそこに潜む哀愁を深掘りしていくようになる。そのひとつである「Surfer Girl」は、若者の空想を描いた1曲だ。
まだ言葉を交わしたことすらないのに、恋をした相手との未来を思い描いてうっとりとする男の心情が歌われている。ブライアンは1961年に、自分へのある種の試練として、頭の中だけでこの曲のメロディを始めから終わりまで考えたのだという。それは驚くべき偉業であり、彼のソングライターとしての直感が初めて花開いた瞬間であった。
24位:You’re So Good To Me (素敵な君) (『Summer Days (and Summer Nights!!)』収録、1965年)
鼓動のようなビートから、キャッチーなリフ、そしてコーラス部分で”ラララ…”というフレーズが繰り返されるバック・ヴォーカルに至るまで、ビーチ・ボーイズ屈指のキャッチーさを誇るポップ・ソング。
巧みなアレンジこそ翌年の『Pet Sounds』の中で比較的陽気なナンバー (「Here Today」や「I’m Waiting For The Day」) への繋がりを感じさせるが、歌詞にはまだ同作のようなほろ苦さはない。そんな「You’re So Good To Me」は、恋人の懐の深さや優しさに強く感銘を受ける気持ちを歌った内容だ。
23位:Time To Get Alone (『20 / 20』収録、1969年)
もともとは1967年作『Wild Honey』のレコーディングで取り上げられていたという、ワルツ調のバロック・ポップ・ナンバー。演奏面ではヴァースで交互に現れるベースとハープシコードや、渦を巻くようなアウトロのストリングスなど、ヴォーカルに関しては複数のメロディ・ラインが絶妙に絡み合うコーラス部分など、ビーチ・ボーイズらしい革新的なアレンジが施されている。ミドル・エイトでの”deep and wide”のハーモニーは、楽曲に強烈なインパクトを加えている。
22位:Feel Flows (『Surf’s Up』収録、1971年)
「Feel Flows」はウィルソン兄弟の末っ子であるカールの才能と冒険的な発想が花開いた1曲。メトロノームのように規則的なリズムを刻む未来的なモーグ・シンセに乗せて、カールは喜びに満ちた歌声を聴かせている。彼のヴォーカルのおかげで、当時のマネージャーであるジャック・ライリーが”悟りの探求”を題材に書き上げた観念的な言葉遊びは、非常に神々しい響きを帯びている。
中盤の間奏では、カールの歪んだギターがチャールズ・ロイドによるフルートとサックスの即興演奏と激しく重なり合う。キャメロン・クロウ監督はこの曲を、ほろ苦い青春映画『あの頃ペニー・レインと』のエンド・クレジットに使用。世界中のビーチ・ボーイズ愛好家は、劇場でポップ・コーンを床にこぼしたことだろう。
21位:Add Some Music To Your Day (『Sunflower』収録、1970年)
ブライアンとマイク・ラヴは、ブライアンの友人であるジョー・ノットと協力し、心から元気が湧いてくるような楽曲を書いた。それはまさに、リスナーを心から元気付ける”音楽の力”を讃える1曲だった。
歌詞の中では、音楽が苦しみを和らげ喜びをもたらしてくれる日常の場面がたくさん挙げられているが、メンバー全員が代わる代わるリード・ヴォーカルを取るこの曲はそれを体現している。音楽的には、同曲を収録する名盤『Sunflower』の多くの楽曲同様、のどかな喜びを感じさせるサウンドに仕上がっている。
20位:Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) (『Pet Sounds』収録、1966年)
『Pet Sounds』が完成したとき、23歳のブライアン・ウィルソンはアセテート盤を持って自宅へと急ぎ、妻のマリリンにその全編を聴かせたという。彼女はのちにこう話している。
「これ以上ないほど感動的な時間でした。1曲ずつ順番に聴いていくと、そのたびに息を呑んだんです。それはとても美しくて、生きている中で特に心揺さぶられる瞬間だった。ふたりとも泣いてしまいました」
「Don’t Talk」を聴けば、その様子は容易に想像できる。実質的にブライアンのソロ曲である同曲には、言葉を必要としない親密な関係性が表現されている。サウンド面から見ると、同曲はキャロル・ケイの上品なベースラインがリードする、ジャズ風のスロー・バラードと言い表せる。「聴いて、聴いて、聴いて」と彼は懇願するが、リスナーにも同じことを伝えたい。
19位:All This Is That (『Carl & The Passions – “So Tough”』収録、1973年)
アル・ジャーディンとマイク・ラヴの共作曲の中で最高傑作といえる「All This Is That」は、精神世界を探求する内容の魅惑的な1曲だ。筆者が2018年にマイク・ラヴ自身から聞いたところによると、作曲者のひとりとしてカール・ウィルソンがクレジットされているのは、長いアウトロの始まりを告げる「Jai guru dev」というマントラを震えるような繊細な声で歌って楽曲に貢献したからだという。あらためて聴くと納得がいく。
18位:Friends (『Friends』収録、1968年)
急速に円熟味を増していた彼らだからこそ作れた、甘く、優しく、肩の力の抜けた共作曲。『SMiLE』のレコーディング以降、ほとんどの楽曲が最新鋭のスタジオ設備から離れた環境で制作されたが、それでも『Friends』をはじめとする一連のアルバムには細部における進化がみられる。
そんな中でブライアン、カール、デニス、アルが共作した「Friends」は、牧歌的なワルツ調のナンバー。楽曲に彩りを添える見事なハーモニーは、友情のすばらしさを物語っている。
17位:California Girls (『Summer Days (and Summer Nights!!)』収録、1964年)
牧歌的な交響曲を短く纏めたような20秒間の導入部を持つ世界的な大ヒット・シングル「California Girls」は、そうそう見当たらない類の名曲である。だがこの当時、ビーチ・ボーイズの楽曲制作への衝動や野心は、すでにほかのアーティストの先を行っていた。
楽曲としての「California Girls」は聴くだけで陽の光に照らされた気分になれる陽気な1曲で、いい意味で耳につくホーン隊のアレンジや、思わず口ずさみたくなる歌詞もその大きな魅力だ。だが、なんといってもこの曲はイントロに尽きる。
16位:I Get Around (『All Summer Long』収録、1964年)
1964年ごろの彼らを振り返ると、「I Get Around」の歌詞に出てくるような流行りの不良グループに入れそうなのは、ドラマーのデニスくらいであった。だが曲作りの面では、ブライアンとマイクの力量が発揮されている。ふたりは「Surfin’ Safari」や「Surfin’ USA」など初期のヒット曲のサウンドを踏襲しつつ、舞台をビーチから街へと移してみせた。結果として生まれたのは、目がくらむような傑作である。
ギターの音色が印象的なブレイクや、はつらつとした手拍子、そしてブライアンの突き抜けるようなファルセットなどすべてが相まって、同曲はビーチ・ボーイズにとって初めての全米ナンバー・ワン・シングルとなった。当時のチャートはザ・ビートルズが席巻していたことを考えると、これは快挙であった。
15位:Please Let Me Wonder (『Today!』収録、1965年)
ビーチ・ボーイズにとって初期の哀愁溢れるバラードと、豪華なアレンジに乗せて人生の意味を問う『Pet Sounds』の架け橋となった名曲がこの「Please Let Me Wonder」である。ブライアンとマイクはこの曲で、”夢見ていた恋愛になるかどうか”という若い恋人たちの不安感を描いた。
同曲の主人公は、自分の気持ちが報われることを確信してはおらず、むしろ「不安に思って (wonder)」いる。また彼は、目の前にいる恋人本人ではなく、心に描いてきた彼女の「美しい虚像 (beautiful image)」を見つめている。だが、そのサウンドから不安感のようなものは感じられず、繊細なアレンジの中には巧みなアイデアが散りばめられている。
ヴァースの華やかなメロディや、エコーのかかった力強いギター、そしてファルフィッサのオルガンが見せ場を作るミドル・エイトなどはその好例である。
14位:I Just Wasn’t Made For These Times (駄目な僕) (『Pet Sounds』収録、1965年)
ビーチ・ボーイズは神がかり的な能力で、心の苦しみから優れた芸術を生み出してきた。そして、その代表例を挙げるとすれば「I Just Wasn’t Made For These Times」以上のものはなかなか見当たらない。『Pet Sounds』のほかの収録曲同様、同曲の作詞にはトニー・アッシャーを起用した。
当時26歳だったアッシャーは、コマーシャル・ソングのコピーライターとして働いていた際にブライアンと出会ったという。彼の助けを得たブライアンは、アーティストとして感じるフラストレーションや疎外感、幻滅などを赤裸々に表現している。「時々すごく悲しくなるんだ (Sometimes I feel very sad)」とはっきり口にするコーラス部分では、それが特に顕著である。
同曲は、サウンド面から見てもまさに力作といえる仕上がり。限界を超えようとする彼らの自信とやる気が、ほかのグループなら詰め込みすぎと感じてしまうであろうアレンジを可能にした(パーカッションだけをとっても野心的だが、レコード史上初のテルミン・ソロはその上を行く)。それでも巧みに纏め上げられた同曲は、ダイナミックで繊細な、とてつもない1曲になった。
13位:Darlin’ (『Wild Honey』収録、1967年)
『SMiLE』のレコーディングの後、ブライアン・ウィルソンはレッドウッドという新グループ(のちのスリー・ドッグ・ナイト)との仕事に着手した。その音源を聴いたマイクらビーチ・ボーイズの面々は、同グループのためにブライアンが書いた楽曲、特に「Thinking ‘Bout You Baby」を明け渡すよう説得。その曲を再構成し、モータウン風のリズムで仕上げたのがこの1曲である。
カール・ウィルソンはリード・ヴォーカルとしてその実力を遺憾無く発揮し、ソウルフルな歌声という知られざる武器を披露した。この曲はライヴの定番としても愛されており、「感じたことのないほどの情熱 (More soul than I ever had)」という一節のカールの歌声だけでも、後年のライヴ映像には一見の価値がある。年齢を重ねた彼が声の限り歌う姿は実に魅力的である。
12位:In My Room (『Surfer Girl』収録、1963年)
ブライアンと彼の初期の共作者であるゲイリー・アッシャーが、少年時代の厳しい現実から逃れる”聖域”としての子供部屋を回想した1曲。思春期のブライアンが父であるマレーに植えつけられた心理的トラウマで苦しんでいたことを考えると、「In My Room」は一層痛切な楽曲として響いてくる。
最初のヴァースでは、そのテーマに相応しくウィルソン三兄弟が美しいハーモニーを聴かせる。3人で部屋を共有していた子ども時代、ふたりの弟に歌を教えていたブライアンの姿が目に浮かぶようである。
11位:When I Grow Up (To Be A Man) (『Today!』収録、1965年)
「When I Grow Up (To Be A Man)」は、子ども時代に感じた不安を振り返る10代後半の若者の視点で描かれている、一風変わった楽曲だ。アウトロではバック・ヴォーカルが早口で年齢を数え上げる中、「永遠に続かないって、なんだか悲しいね (Won’t last forever, it’s kinda sad)」と歌うブライアンのリード・ヴォーカルが重なる。だがビーチ・ボーイズのそのほかの名曲同様、そのサウンドは不安げな歌詞に逆行している。
ハープシコードやグラス・ハーモニカの演奏も独創的だし、ハル・ブレインによるパーカッションの独特なリズムもこの曲と見事に調和している。楽曲全体として、複雑なアレンジをごく自然に聴かせるブライアンの才能が見事に発揮されており、シングルとしても全米チャートでトップ10入りを果たした。
10位:Heroes And Villains (英雄と悪漢) (『Smiley Smile』収録、1967年)
『Pet Sounds』、そして「Good Vibrations」に続く作品の制作は難航した。歌詞を壮大なサウンドの構想に見合うものにするため、ブライアンは、ロサンゼルスのミュージシャン/作曲家として業界に顔が広いヴァン・ダイク・パークスの協力を仰いだ。そうしてブライアンとパークスは、アメリカの歴史 (特に西部開拓と”マニフェスト・デスティニー”の思想) をテーマにした楽曲群の制作に着手。そこに自然界やユーモア、生命のサイクルといったアイデアを盛り込んでいった。
一方でブライアンは、”モジュール方式”を用いて「Good Vibrations」を別次元の楽曲に仕立てていた。それは、楽曲を小さな断片ごとにレコーディングしていき、最後にジグソー・パズルのように組み上げることで、壮大なアート・ポップ作品を作り上げる手法だった。
荒々しい西部劇が展開される「Heroes And Villains」は、アルバム『SMiLE』の中核を担う楽曲になる予定だった。ヴァン・ダイク・パークスは、言葉遊びやシャレを大胆に取り入れた遊び心溢れる歌詞を提供。他方の演奏面では、ノコギリのようなコントラバスの低音を軸に、複数のセクションにまたがって変化に富んだサウンドが展開される。その中では様々な装飾音やドゥ・ワップ調のサイケデリックなバック・ヴォーカル、そして何やら不穏なアカペラまでが飛び出す。だがそれは、アルバム『Smiley Smile』からのシングルとして発表されたひとつのヴァージョンに過ぎない。
2011年にリリースされたボックス・セット『The Smile Sessions』には、一枚丸々「Heroes And Villains」のアウトテイクを集めたディスクも収められている。リスナーは、それらの音源を繋ぎ合わせて自分なりのヴァージョンを組み上げることができるのだ。そこにはきっと「Barnyard」も入っているはずだ。
9位:Sail On, Sailor (『Holland』収録、1973年)
『Holland』は一度完成に至ったものの、その後で、アルバムを成功に導くようなインパクトのあるリード・シングルを加えることになった。そこで選び出されたのは1972年にも制作されていた1曲で、『Holland』に収録するため一部の歌詞を書き換えて再録された同曲は、それなりのヒットを記録した。その完成度を考えれば当然のことである。
そんな「Sail On, Sailor」は、陽気なサウンドが魅力の力強く無骨なロック・ナンバー。これをソウルフルに歌い上げているのは、この前年にギタリストとしてビーチ・ボーイズに加入したブロンディ・チャップリンである。
8位:Forever (『Sunflower』収録、1971年)
ウィルソン家の次男であるデニスはデビューしてから数年の間、兄弟でもっとも音楽的才能に乏しいと思われていた。だが1960年代後半になると、独学でドラムを習得した彼はその天賦の才を開花させた。『SMiLE』の制作中には、スタジオでの試行錯誤の末にインストゥルメンタル・ナンバーの「I Don’t Know」を作曲。
その後、初めて日の目を見た彼の自作曲 (「Little Bird」「Be Still」) は1968年作『Friends』に見事な哀愁をもたらした。デニスの曲作りはみるみるうちに洗練されていき、『Sunflower』では聴きどころのひとつとなるバラードを書くまでに成長した。それが、永遠の愛を率直かつピュアに表現した「Forever」である。
7位:‘Til I Die (『Surf’s Up』収録、1972年)
下降気味だったセールスが再び上向いたアルバム『Surf’s Up』におけるブライアンの最大の功績といえる非常に感動的な1曲。彼はこの曲で、人生に対して感じていた無力感を表現している。
I’m a cork on the ocean
Floating over the raging sea
How deep is the ocean?
僕は海に浮かぶコルク
荒れ狂う海を漂っている
この海はどれほど深いんだろう?
という一節の美しいハーモニーから同曲は始まる。多くの人々に喜びを与えてきた天才が、これほどまでに打ちのめされているのを聴くのは心が痛む。だが最後に「死ぬまではこんな風に生きていよう (These things I’ll be until I die)」と歌っているところからは、ブライアンは自分の置かれた状況と折り合いをつけたようにみえる。それと呼応するように、サウンドも後半には明るく変化していくのだ。
6位:The Warmth Of The Sun (太陽あびて) (『Shut Down Volume 2』収録、1964年)
マイク・ラヴとブライアン・ウィルソンが「The Warmth Of The Sun」を書き上げたタイミングについては、1963年11月22日のケネディ大統領暗殺の前だったのか、後だったのか、現在も意見が分かれるところである。
いずれにせよ、それから1ヶ月以上経ってレコーディングされた同曲は、アメリカ全土に広がっていた喪失感を象徴する1曲になった。歌詞のついてないブライアンの上品なファルセットで、この荘厳なバラードの幕は上がる。そこに歌われているのは、終わってしまった恋の思い出に安らぎを見出す男の心情だ。だがそれと同時に、この曲はどんな苦しみを抱えた心も優しく癒してくれるのである。
5位:Don’t Worry Baby (『Shut Down Volume 2』収録、1964年)
ビーチ・ボーイズの面々は、プロデューサーのフィル・スペクターから多大な影響を受けていた。特にスペクターが共作およびプロデュースを担当したロネッツの「Be My Baby」を強く意識していたブライアン・ウィルソンは、作詞家のロジャー・クリスチャンと手を組み、同曲へのオマージュとして「Don’t Worry Baby」を書き上げた。
この曲は表面上、自動車レースを前に恋人の支えを必要とする不安げな男の心情を歌ったものだ。だが、衝撃的なほど美しい冒頭のメロディ
Well it’s been building up inside of me for,
oh, I don’t know how long
僕の心の中で大きく膨らんでいるんだ
覚えていないほど前から
という一節を取っても、コーラス部分のバック・ヴォーカルのインパクトを取っても、そのテーマ自体はあまり重要ではない。この曲は励ましを必要とするすべての人が共感できる普遍的な1曲なのだ。
サウンド面から見ても実に見事で、ブライアンのヴォーカルも魅力的だし、バック・コーラスは息を呑むような完成度だし、優雅な演奏はスロー・ダンスに最適である。スペクターからの影響を取り込むことで、ビーチ・ボーイズはすばらしいサウンドを自ら作り出してみせたのだ。
4位:Wouldn’t It Be Nice (素敵じゃないか) (『Pet Sounds』収録、1966年)
こちらもイントロがあまりに有名な1曲。オルゴールのような繊細な音色は突然、ハル・ブレインによるドラムの力強い一打に遮られ、今度はアコーディオン(当時に限らず、2台のアコーディオンがリードするヒット曲はあまりに珍しい)、3本のサックス、トランペット、鉄琴、そして息を呑むようなハーモニーによる怒涛の演奏が始まる。このヴォーカルのハーモニーは1997年のボックス・セット『Pet Sounds Sessions』のアカペラ・ディスクで深く堪能できる。
『Pet Sounds』の冒頭を飾る1曲は、手の届かないものへの憧れを表現した幸福感溢れるナンバーだ。そこでは、大人だけに許された結婚こそが幸せと捉え、辛抱できなくなった若い恋人たちの気持ちが描かれている。どこまでも魅力的なメロディはもちろん、華やかなアレンジとサウンドによって「Wouldn’t It Be Nice」はビーチ・ボーイズ屈指の名曲になった。
3位:Good Vibrations (シングルA面としてリリース、1967年)
ザ・ビートルズがアーティストとしての健全な競争心に火をつけたことで、ビーチ・ボーイズはヒット曲を生み出さなければいけないという重圧を抱えることになった。この曲のレコーディングは何ヶ月にも亘り断続的に行われ(「制作は『Pet Sounds』のレコーディング中だった1966年2月に始まり、同年10月まで続いた)、制作費は総額で5万ドルから7.5万ドルにも上ったといわれる。
これは当時としてはあまりに高額だった。だが、熱意溢れる3分半の風変わりなポップ・ソングである「Good Vibrations」には、その価値があった。確かにそのサウンドは浮世離れしているし、あらぬ方向に展開していくが、取っつきやすい楽曲であることには変わりない。各パートの寄せ集めという以上の魅力を持つ「Good Vibrations」は全米チャート1位を獲得。100万枚以上を売り上げ、世界中で大ヒットを記録した。
2位:Surf’s Up (『Surf’s Up』収録、1972年)
1967年、ブライアンはレナード・バーンスタインが司会を務めたアメリカのテレビ特番『Inside Pop: The Rock Revolution』に出演。年々洗練されていくポップ・ミュージックの秘密を探る同番組で彼が演奏したのは、名の知れたビーチ・ボーイズの名曲ではなく、『SMiLE』に収録すべくヴァン・ダイク・パークスと共作した「Surf’s Up」だった。
薄明かりの中でブライアンは、ひとりピアノの前に座ってこの曲を披露。間違いなく傑作になるであろう同曲を完全な形で聴けないことに、視聴者はじれったさを覚えたのである。
その後は未発表となっていた同曲だが、あるときテープ倉庫から発掘され、再度取り上げられることになる。そしてシリアスな曲調の名曲として、1971年リリースのアルバムの表題曲に選ばれた。日の目を見るまでの間、同曲の評判はずっと『SMiLE』に纏わる”神話”の盛り上がりに拍車をかけていた。その見事なメロディは不穏だったり、穏やかだったり、キャッチーだったりと次々に表情を変えるが、それ以上に美しくすばらしい。
歌詞には遠回しな表現が使われているものの、富裕層の絢爛な生活が描かれたあと、既成の秩序の崩壊が暗示されている。これはまさに、文化が著しく変容した1960年代のメタファーにほかならない。改めてレコーディングされ、アレンジを施され、リリースされた「Surf’s Up」の完成度はあまりに高く、膨れ上がった期待に応えるものだった。ブライアン・ウィルソンの才能を体感したければ、これ以上のものはない。
1位:God Only Knows (神のみぞ知る) (『Pet Sounds』収録、1966年)
「God Only Knows (神のみぞ知る)」という表現はもしかすると、単にブライアンとトニー・アッシャーのいずれかの耳にとまった陳腐な言い回しで、いつか曲にしようと温めておいたものなのかもしれない。だが、それが心を揺さぶるすばらしいサウンドに乗せて歌われると、実に神聖な響きを帯びてくる。
ブライアンが『SMiLE』について「少年による神様への祈り」と表現していたのは有名だが、実際のところ、ビーチ・ボーイズはこの曲ですでにそれを完成させていたのである。
そんな「God Only Knows」は、ある人物の視点から歌われる。その人は、愛とこの世界の前に圧倒され、神様以外に自分の気持ちは理解できないと悟っているのだ。この曲は、”愛が強ければ強いほど、失恋を恐れてしまう”という非情な真実を描き出そうとしている。この主人公は誰かを強く愛していて、いつかこの愛は終わるという現実に囚われている。そして、その意味を本当に理解できるのは神様 (“God”という単語は当時、気軽にポップ・ソングの歌詞にできるものではなかった) だけだと感じているのだ。
そう聞くと重たいテーマに思えるが、楽曲の中では非常に美しく表現されている。また、そのサウンドも優れた歌詞に少しも引けを取っていない。マーチング・バンドのようなハープシコードや、荘厳なフレンチ・ホルン、そして明快なハーモニーは、曲の冒頭からリスナーの胸に迫ってくる。
同曲は、ビーチ・ボーイズという王冠の中で燦然と輝く一粒の宝石のような1曲だ。人が他人への愛を持ち続ける限り、この曲も愛され続けることだろう。
Written By Jamie Atkins
60周年記念でベスト盤がリマスターで登場
今回初登場となる新ミックスは全13曲

2022年6月17日発売
日本盤3CD / 日本盤1CD / 6LP / 2LP
- ビーチ・ボーイズ アーティスト・ページ
- ビーチ・ボーイズ、1969~1971年を振り返る5CDボックス発売決定
- なぜ、ビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』が芸術品であり続けるのか?
- ビーチ・ボーイズの陰の立役者、アル・ジャーディン栄光の時とプレイリスト
- 「『Abbey Road』さえも羨ましがる」と評されたビーチ・ボーイズの復活作『Surf’s Up』
- ビーチ・ボーイズの10年ぶりの全米TOP10ヒットアルバム『15 Big Ones』
- ビーチ・ボーイズ関連記事