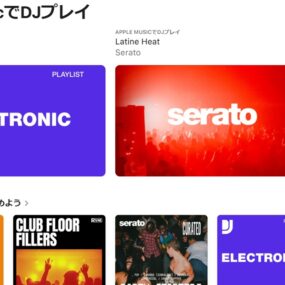Stories
ビーチ・ボーイズ:史上最高のヴォーカル・グループ


ロックン・ロール黎明期、ラジオというティーンエイジャーの夢の世界を席巻していたのは、アメリカ中の街角で歌っていたリズム&ブルースのヴォーカル・グループだった。その中でも数組抜きん出た存在がいた、例えば「I’ll Only Have Eyes For You」で、メンバーたちの声をまるで宇宙空間のような不思議な響きへと変貌させたザ・フラミンゴスやザ・デル・ヴァイキングス、それに長年にわたって様々なアーティストがカヴァーしてヒットさせた「Why Do Fools Fall In Love」を最初にレコーディングし、他にも数々のヒット曲を生んだフランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズ。そしてロカビリー界においては、ヴォーカルのブレンドという点において、エヴァリー・ブラザーズが他の追随を許さない圧倒的な人気を誇っていた。
そんな中、1961年の終わりにシーンに登場したビーチ・ボーイズは、誰ひとりとして楽器を持たず、バルボアのランデヴー・ボールルームで1本のマイクの周りに集まり、ディック・デイル&デル・トーンズの唸るギター・サウンドに合わせてダンスするために来ていた本物のサーファーたちの前で 「Surfin’」を披露していた。もっともオーディエンスは楽器なしのスタイルには懐疑的で、ほどなくしてビーチ・ボーイズはチャック・ベリーとディック・デイルを足して2で割ったようなサウンドを採り入れ、初期のヒット曲だらけのアルバム数作を作り上げた。とは言え、彼らの成功の鍵は一貫して、彼らが結成当時にもっぱらターゲットにしていた、ロサンゼルスエリアの身体を動かすのが大好きなダンス・ファンのために作られた「Surfin’ USA」に代表されるポップな曲調の上に緻密に組み上げられたヴォーカル・ハーモニーだった。
実のところ、ビーチ・ボーイズは彼らがよく耳にしていたニューヨークあたりの街角に立つグループの仲間入りをしようと、何度か地元のボウリング・アレイの外に立ったこともあった。ブライアン・ウィルソンがアレンジした分厚いコーラスの塊は、1959年のドク・ポーマスとモート・シューマンがザ・ミスティックスのために書いた「Hushabye」のオリジナル・ヴァージョンと、ビーチ・ボーイズが1964年にアルバム『All Summer Long』の3曲目に収録したヴァージョンを比べてみると一番よく分かるだろう。ザ・スチューデンツが1958年にリリースした 「I’m So Young」も、1965年のビーチ・ボーイズのアルバム『Beach Boys Today!』ではペット・サウンズ的な加工を施されてカヴァーされている。
しかしながら、ビーチ・ボーイズの作曲の特性にはもうひとつ重要な柱があった。ブライアン・ウィルソンは幼少時代、ジョージ・ガーシュウィンの「Rhapsody In Blue」に魅せられたことがきっかけで、ヴォーカル・アレンジの中にジャズ風の進行を組み込む方法を体得していたのだ。彼はとりわけザ・フォー・フレッシュメンとザ・ハイ・ローズという2組のジャズ・ヴォーカル・グループにいれあげていた。この2組はどちらも50年代、ランバート、ヘンドリックス&ロスが切り拓いたジャズ・ヴォーカルにおける実験的試みに賛同していた。やがてブライアン・ウィルソンは、『Pet Sounds』や『Smile』のセッションで、楽器でもヴォーカルと同じように多彩かつ重厚なフレイヴァーを加えたアレンジを施すようになった。その中でも、彼のジャズ・センスが最大限有効活用されたアルバムが『Beach Boys Today!』だろう。「Kiss Me Baby」でのヴォーカル表現を聴いてみれば、抱きしめられる時の唯一のキーワード“tigggghhhhhtttt”(ギューッと)で、ブライアン・ウィルソンが弟のデニス・ウィルソンから、これ以上はないほどセクシーな声を引き出しているのが分かるはずだ。
この心揺さぶる一言は、順々にヴォーカルが重なって分厚くビルドアップされた後にやって来る。マイク・ラヴが極上の低音のテナー・ヴォイスを提供し、アル・ジャーディンがマイク・ラヴ(あるいはカール・ウィルソン)と息を合わせてメトロノームの如く全体をしっかりと力強く支えている。カール・ウィルソンの声はブライアン・ウィルソンのファルセットの下、一番下で低音を唸らせるデニス・ウィルソンの上で、ひらひらと自在に動き回るのだ。1965年に入って間もなく、ブライアン・ウィルソンがツアーから退いたことを受け、新たなハイ・テナーとしてブルース・ジョンストンが加わり、ビーチ・ボーイズはスタジオでのリーダー抜きでツアーに出ることになった。「California Girls」での対旋律パートでも聴ける通り、ブルース・ジョンストンの声は大いにグループに貢献を果たしている。

ビーチ・ボーイズの代名詞とも言える塊のようなヴォーカルが最初にブレイクを果たしたのは 「Surfer Girl」で、1963年の夏の音楽シーンはこの大ヒット曲でもちきりだった。この大ヒットは彼らにとって初めてとなるナンバー1ヒット「I Get Around」のシングルB面曲だった「Don’t Worry, Baby」までもが、翌年全米シングル・チャートの24位にまで上昇するという結果まで引き起こしている。ビーチ・ボーイズ本体が各地でコンサート活動をしていた1965年半ば、長期間一種の鬱状態を患っていたブライアン・ウィルソンはツアーには参加せず、『Pet Sounds』収録曲のバックヴォーカルの録音作業に独り没頭していた。
ブライアン・ウィルソンがこのヴォーカル・ワークに深く取り組んでいたのは、ずっと他のメンバーたちに各パートを教え込んでいたのが彼だったからでもある。『Pet Sounds』ではメンバーのそれぞれにリード・パートが任され、バンド・メンバーたちが参加することによって、そこに新たな色が生まれたのだ。アルバムに収録されたナンバーの大半は、ブライアン・ウィルソンが「Malibu Sunset」や、アルバム『Surfin’ USA』の「The Lonely Sea」の初期のデモで表現していた焦燥感と孤独感と同じところから生まれていたものだ。これらのナンバーに盛り込まれた素直さが、ビーチ・ボーイズの他のメンバーたちに対して臨機応変にそれぞれの役割を発揮するスペースを与え、例えばブルース・ジョンストンとブライアン・ウィルソンがカール・ウィルソンの意味深長なリード・ヴォーカルのバックを務めている「God Only Knows(邦題:神のみぞ知る)」や、 「Caroline, No」でのブライアン・ウィルソンのソロ・ヴォーカルのようにこの上なく情熱的な楽曲のレベルを押し上げたのだ。様々な意味で、60年代のブライアン・ウィルソンのリード・ファルセットは、一グループ全体のミックスの中において一貫して圧倒的な存在だった。
『Smile』のセッションでは、フル・コンビネーションのヴォーカル・グループたるビーチ・ボーイズが完全復活を遂げ、グランド・キャニオンのように起伏に富んだ絵画的な効果を狙った「Cabinessence」の中盤パートのように、驚くようなコード進行の展開の中でも、再び個々のメンバーの声がバック・ヴォーカルでも明確に聴き分けられるようになった。この曲はリリースから50年以上を経た現在でも人々を驚嘆させて止まない「Good Vibrations」の声の壁や、暗示的な「Surf’s Up」と並び、彼らがこれまでで一番惜しみなくふんだんに和声をちりばめている作品だろう。
グループのルーツであるR&Bへの温故知新を図った1967年の『Wild Honey』を経て、ビーチ・ボーイズはヒットを連発した時代と同じレベルの卓越したハーモニー技術を携えて1968年への足を踏み入れた。瞑想を誘うLP『Friends』では、ウィルソン兄弟の父親であるマリー・ウィルソンまでが「Be Here In The Morning」で誰より低いパートを受け持って参加している。作品全体として重きが置かれていると思われるのは安らぎ、家族、そして歌の魂のために歌うこと――決して目先の糧のためではないのだ。バックを固めるジャジーな楽器の助けにより、聴き心地においても抜群の仕上がりである。ビーチ・ボーイズの『Friends』は感覚的にはヴァン・モリスンの『Astral Weeks』に近く、一時期ブライアン・ウィルソンは『Friends』を一番好きなアルバムに挙げ、その理由を「僕のより良い生き方にピッタリだから」としていた。このアルバムにフィーチュアされたハーモニーこそ、ビーチ・ボーイズの最も自然な姿なのである。
その温かみがもう一段進化したのが、1970年にリリースされた『Sunflower』だった。ビーチ・ボーイズはモンタレー・ポップ・フェスティヴァルのエンジニア、スティーヴン・J.デスパーにステレオ・ミックスを依頼、兄ブライアンの方法論に則ってアレンジメントを作り上げることを習得したカール・ウィルソンとデニス・ウィルソンがそのサポートについた。
ブライアン・ウィルソンもこの『Sunflower』には完全に参加していた。ここには彼のきらりと光る小品「This Whole World」が収められ、『Smile』の時にレコーディングされておりその時はお蔵入りになっていた「Cool, Cool Water」にも美しく仕上げられている。どちらの曲も非常に先進的なミックスの中で、ビーチ・ボーイズらしい最高にクリアなヴォーカル・サウンドとその表現が特に前面に押し出されているナンバーだ。このアルバムでは他にもデニス・ウィルソンの 「Forever」、カール・ウィルソンの 「Our Sweet Love」、そしてマイク・ラヴとブライアン・ウィルソンによる 「All I Wanna Do」と、ビーチ・ボーイズの作品の中でも屈指の瑞々しい楽曲群が堪能できる。
70年代が進むにつれ、ブライアン・ウィルソンの表立った活動は目に見えて減少していく。彼が少しだけ戦列復帰した『Holland』では、新メンバーのブロンディ・チャプリンが「Sail On, Sailor」のリード・パートに魂を吹き込んでいた。そしてこのアルバム以降、ビーチ・ボーイズはチャートの常連アーティストたちの数々の作品でも歌うようになり、中でもシカゴの 「Wishing You Were Here」とエルトン・ジョンの 「Don’t Let The Sun Go Down On Me」の2曲には、一聴しただけで間違いなくビーチ・ボーイズのヴォーカルだと即座に分かる、あの独特のサウンドが刻まれているのだ。
Written By Domenic Priore
- ビーチ・ボーイズ アーティストページ
- チェックすべきビーチ・ボーイズの名曲10曲
- なぜ、ビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』が芸術品であり続けるのか?
- ザ・ビーチ・ボーイズが『1967 –Sunshine Tomorrow』を発表
- ザ・ビーチ・ボーイズがキャピトルと契約した日
- ビーチ・ボーイズ関連記事