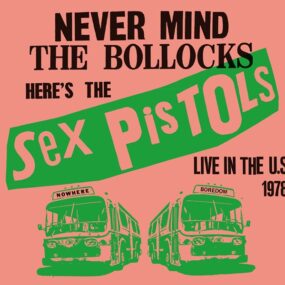Stories
“低音の革命”:UKのニュー・ウェーヴとポスト・パンクがいかにしてベースの奏法を変えたか


基盤となる部分が変われば、その上に置かれるものにも影響が及ぶ ―― それは物理と音楽の両方における基本原理である。1970年代後半から1980年代前半にかけてのイングランドでは、そのことが特に顕著だった。1960年代の革新的なベーシストたちのプレイが、ポスト・パンクやニュー・ウェーヴのサウンドに応用されるようになったのである。
<関連記事>
・早弾きだけじゃない、新たな方向性を開拓した80年代のギター・ヒーロー
・プログレッシヴ・ロック界のベーシスト・ベスト20
・史上最高のベーシスト・ベスト50
エルヴィス・コステロとブルース・トーマス
クラッシュ、セックス・ピストルズ、ダムドといったグループは、UKパンク界が送り込んだ第一の軍勢にすぎなかった。狡猾なミュージシャンたちは、そのあとで次なる一手を模索し始めたのである。「White Riot(白い暴動)」や「God Save The Queen」の衝撃が尾を引いていた1977年後半、エルヴィス・コステロは初めてアトラクションズの面々を集めてレコーディングを行った。
コステロはその前年に1stアルバムを制作していたが、同作のほとんどの楽曲でバックを務めていたのはカリフォルニア出身のバンド、クローヴァーだった。彼らはのちにヒューイ・ルイス&ザ・ニュースへと発展していくのだが、当時は器用さのあるルーツ・ロック・バンドの域を出ていなかった。
コステロは、次なるアルバム『This Year’s Model』に突飛な要素を加えたいと考えた。そこで彼は、一見まとまりのない英国人ミュージシャンたちを集めたのである。その中の一人であったブルース・トーマスは、1970年代初頭からベーシストとして活動する人物だった。
彼はそれまで、ブリジット・セント・ジョンやアル・スチュワートなどのフォーク・シンガーや、フォーク・ロック・バンドのサザーランド・ブラザーズ&クイヴァー、プログレッシヴ・ロック界で活躍したピーター・バーデンスらと共演。その中で、ポール・マッカートニーをはじめとするベーシストが”スウィンギング・ロンドン”の時代に編み出した奏法を吸収していった。それは、ベースが高音域まで自在に動き回り、リード・ギターを脅かすほどメロディアスで大胆なベースラインを奏でるスタイルだ。
「Pump It Up」や「(I Don’t Want to Go to) Chelsea」などのコステロの代表曲では、トーマスによる骨太なリフが楽曲をリードする。評論家のチャールズ・シャー・マリーは当時、NME誌の記事でこう分析している。
「ブルース・トーマスは、リズム隊と前線とを行き来する。あるいはその二つを兼ねることができるようなスタイルでベースを弾いている」
1979年、ブルース・トーマスはウイングスの『Back To The Egg』に参加し、ついに自身の影響源であるマッカートニーとの共演を果たした。
ジョー・ジャクソンとグレアム・メイビー
ジョー・ジャクソンは、英ニュー・ウェーヴ界における“怒れる若者たち”の一人として、コステロやグレアム・パーカーらと一緒に語られることが多いアーティストだ。だが、彼の懐刀であるグレアム・メイビーは、当のトーマスを脇役にしてしまいかねないほどの存在感を放つ。
ジャクソンが1979年に発表したデビュー作『Look Sharp!』でメイビーは、鋭く攻撃的な音色とメロディー性の高さが特徴のベースを披露。そのスタイルは、クリームのジャック・ブルースによるパワフルでパンチの効いた演奏や、モータウンの専属ベーシストだったジェームス・ジェマーソンによる運動量の多いプレイに強い影響を受けていた。
「Got The Time」での傑出したベースラインはとてつもない音数であり、表題曲や「Is She Really Going Out With Him?(奴に気をつけろ)」でのリフは熱がこもっている上に、何が飛び出すかわからない。そうした彼のベースは、楽曲をリードするだけでなく、楽曲全体の印象を決定付けているのだ。
1979年、ジャーナリストのチャールズ・シャー・マリーはNME誌にライヴ・レポートを寄稿し、こう綴っている。
「グレアム・メイビーはステージ上を動き回り、リフやフィル、フレーズを次々に繰り出す。その演奏は、鋭く冷たい響きのするゲイリー・サンフォードのリズム・ギターを支えながら、同時にリードしている」
ストラングラーズのジャン=ジャック・バーネル
他方、ストラングラーズはパンク界の固定観念を打破することに余念がなかった。彼らは1977年に1stアルバム『Rattus Norvegicus(夜獣の館)』をリリース。同作は、ドアーズによるオルガン中心のダークなサイケデリック・サウンドを新たな時代に合わせてアレンジしたような作風だった。
例えば、「(Get a) Grip (On Yourself)」は、デイヴ・グリーンフィールドによる遊園地のアトラクションさながらの目眩くキーボードが特徴の1曲。また、「Down In The Sewer」はパンクとプログレが融合した8分間のド派手な組曲だ。
だがそれらに共通しているのは、ほかに類を見ないほど攻撃的なジャン=ジャック・バーネルによるベースがサウンドの中を駆け抜けていくことである。その音は、ローマの宮殿を襲う屈強な西ゴート族を想起させる。また、大音量で激しく動き続けるそのベースラインは、ザ・フーのメンバーであったジョン・エントウィッスルの卓越した演奏にも似ている。
ニュー・オーダーのピーター・フック
ポスト・パンク・バンドの代表格であるジョイ・ディヴィジョンや、同グループから派生したニュー・オーダーでベースを弾いたピーター・フックは、そのジャン=ジャック・バーネルに影響を受けていた。ピーター・フックは実際、西部開拓時代のガンマンさながらに、ベースを鼠径部のあたりまで下げて構えるというバーネルのスタイルも真似ていた。
1979年に発売されたジョイ・ディヴィジョンのデビュー・アルバム『Unknown Pleasures』でピーター・フックは、泥臭くラウドなフレーズを次々に披露。そのプレイは同世代のミュージシャンたちだけでなく、彼の足跡を追う後進のベーシストたちにとっての模範となった。
だが、1981年にニュー・オーダーとして発表した1stアルバム『Movement』では、よりメロディアスで高音域を多用した演奏へとスタイルが変化していた。そのベースの音色は、時としてバーナード・サムナーのギターと判別がつかなくなるほどだった。
レゲエからの影響:ジャー・ウォブルとスティング
ジャー・ウォブルの名で知られるジョン・ウォードルは、ポスト・パンク黎明期を支えたベーシストだ。セックス・ピストルズとパンクを捨て、パブリック・イメージ・リミテッドとして未開拓の領域へと踏み出したジョン・ライドンは、ウォブルの荘厳なベース・プレイを軸に新たなサウンドを構築していった。
1978年発表の『Public Image: First Issue』に収録されている「Theme」や「Fodderstompf」といった楽曲は、うねるようなレゲエ風のベースラインを中心に進んでいく。こうした演奏からは、ウォブルがボブ・マーリーの作品におけるアストン・”ファミリー・マン”・バレットのベースから多大な影響を受けていたことがわかる。だがそれだけでなく、ウォブルのベースには攻撃性も感じられた。やがてこのスタイルは、パンクとレゲエを融合させた数多くのグループへと受け継がれていくことになる。
ジャー・ウォブルが注目を浴びるようになったころ、同じく特徴的な芸名を名乗るベーシストが現れた。スティングというその男は、ポリスの1stアルバム『Outlandos d’Amour』で、シンコペーションを多用したレゲエ風のベースラインをパンク調の楽曲に組み込んだ。
ロックのラジオ局で人気を博した「Roxanne」や「Can’t Stand Losing You」などの曲は、レゲエの影響を滲ませるヴァースから、四つ打ちのリズムによるロック調のコーラスへと流れ込む。その演奏をリードするのは、ほかならぬ彼のベースだ。その流れがごく自然なのは、ジャズの世界で腕を磨いた彼のプレイによるところもあるだろう。
その後ポリスは、そのベースのおかげで世界屈指の大物バンドへと成長を遂げていった。そうして、レゲエとロックを融合させた彼らのサウンドは、メン・アット・ワークやノヴォ・コンボをはじめとする1980年代のバンドだけでなく、ノー・ダウトら90年代の人気グループにも影響を与えたのだ。
ファンクからの影響とポップ・グループ
1980年代前半までに、ポスト・パンクにファンクの要素を組み合わせるバンドが英米両国で登場し始めた。そうしたグループは多く存在するが、ポップ・グループはその先駆けといえるだろう。
ブリストル出身の彼らは、作品に刺激的な政治性を取り入れたことでも知られる。そして、その結成メンバーであるベーシストのサイモン・アンダーウッドは、1979年のデビュー・シングル「She Is Beyond Good and Evil」に荒々しいファンキーさをもたらした。同曲は現在でも高い人気を誇っており、セイント・ヴィンセントはオリジナルの発表から30年以上を経て同曲をカヴァーしている。
ポップ・グループは、凶暴性という点では彼らに劣るギャング・オブ・フォーらとともに、ファンクの影響を取り入れた無数のニュー・ウェーヴ・バンドが活躍する素地を築いた。さらに何人かのメンバーは、ピッグバッグ、マキシマム・ジョイ、リップ・リグ&パニックなど、その系譜を継ぐグループに参加しているのだ。
デュラン・デュランのジョン・テイラー
1980年代を代表する”とあるバンド”の中心人物は、ディスコ、グラム・ロック、R&Bなどと並んでパンク/ファンクを得意とするベーシストだった。
バーミンガム出身のジョン・テイラーは、写真映えする甘いマスクで1980年代屈指の女性人気を誇った。そのルックスも人気となったが、所属グループであるデュラン・デュランを本質的な成功へ導いたのは、音数が多く最高にダンサブルな彼のグルーヴだった。
彼らは”ダンス・ロック”という言葉が生まれるきっかけとなった、1980年代前半のニュー・ロマンティック・ムーヴメントを牽引。グループは1981年に「Planet Earth」「Careless Memories」「Girls On Film」などのヒット曲を放ったが、その中でテイラーは、パンチがあり、リズミカルで、思わず体が動いてしまうようなベースラインを弾いた。そんな彼のベースがロジャー・テイラーによる力強いドラミングと合わさることで、ダンサブルなサウンドが生まれていたのである。
目新しいサウンドで途方もない成功を収めたデュラン・デュランの背中を追うグループはあとを絶たなかった。その中でも特に彼らとの関係が深かったのはカジャグーグーであろう。というのも、1983年にリリースされた彼らのデビュー作は、デュラン・デュランのキーボーディストであるニック・ローズがプロデュースしたのだ。
風変わりなグループ名と特徴的な髪型により、彼らの演奏技術は見過ごされてしまうことが多い。だが、グループのベーシスト兼リーダーであったニック・ベッグスは、大ヒット曲「Too Shy (君はTOO SHY)」などで、ファンク/ポップ/ロックが融合したジョン・テイラーのスタイルを自分なりに咀嚼してみせた。彼はフレットレス・ベースを使用することで、ダンスフロア向きのグルーヴにジャズ/ファンクの要素を持ち込んだのである。
そのほかに彼は、チャップマン・スティックを演奏することもあった。弾きこなすのが難しいことで知られるチャップマン・スティックは、プログレ界の伝説的ベーシストであるトニー・レヴィンの使用で一躍有名になった10弦の楽器である。
ミック・カーンとその後のベーシストたち
フレットレス・ベースといえば、ジャパンのミック・カーンはその流れるように滑らかな音色を活かし、まったく新たなサウンドを作り上げた。ジャパンは、のちにアート・ロック界のカルト・ヒーローとなるデヴィッド・シルヴィアンがフロントマンを務めたロンドン出身のグループだ。
初期の作品はグラム・ロックとパンクを融合させた作風だったが、1979年作『Quiet Life』を発表するころまでに彼らは音楽性を転換した。そのサウンドはドイツの諸グループに影響を受けた電子音や、アジア的な雰囲気、そして流麗なグルーヴを組み合わせたものだった。
そして、デュラン・デュランをはじめとするニュー・ロマンティックのバンドは、こうしたジャパンの音楽に深く感化されていたのである。その中でカーンは、フレットレス・ベースを使用して渦巻くような音世界を構築。そのプレイは“ニュー・ウェーヴ界のジャコ・パストリアス”と呼ぶに相応しいものだった。
当時を代表するUKの名ベーシストたちがファンキーで激しい演奏を繰り広げるようになると、ベース界の様相は一変した。あらゆるジャンルのベーシストにとって、プレイの選択の幅が一気に広がり、新たな奏法を自分の演奏に取り込めるようになったのである。
実際、1990年代に入ると、ポスト・ロック、オルタナティヴ、トリップ・ホップといったジャンルで、サッチャー政権時代の英国における大胆で型破りなプレイに親しんだベーシストが活躍。さらに2000年代に入ったあとも、ブロック・パーティ、フランツ・フェルディナンド、ラプチャー、インターポール、キラーズなどのポスト・パンク・リヴァイヴァル勢がその系譜を継いだ。
ビジネスにおいては、決算書の“一番下”に記載される純損益が何より重要だとされる。事業が成功しているのか、失敗しているのか、その程度はどれほどかといったことが、その数字に表れるからだ。音楽においても“一番下”が重要であることは変わらない。ロック界が“赤字”から脱却して“黒字”に転じられたのは、ポスト・パンクやニュー・ウェーヴのベーシストたちのおかげなのである。
Written By Jim Allen
- 早弾きだけじゃない、新たな方向性を開拓した80年代のギター・ヒーロー
- プログレッシヴ・ロック界のベーシスト・ベスト20
- 史上最高のベーシスト・ベスト50
- 最高の女性ドラマー・ベスト25:様々なジャンルのミュージシャンたち
- 最高の男性ロック・シンガー・ベスト100:伝説のヴォーカリストたち
- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達