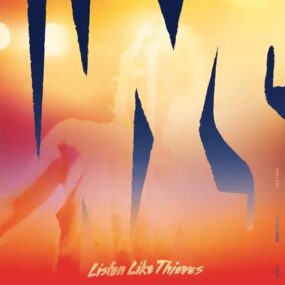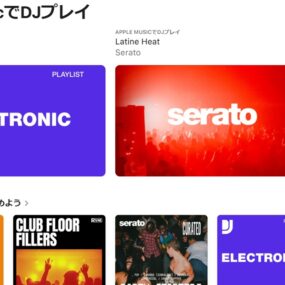Stories
80年代の音楽は思っている以上にクールなものだった


とある10年間をこき下ろすことは可能なのだろうか? 1980年代には「叩いてください」というタグがしっかりと付けられているような印象がある。誰かあの10年間のためにそのタグを取り去って助けてあげてくれないだろうか? きちんと捉えていない人のために言うが、1980年代の音楽は思っている以上にクールなものだったのだ。
1980年代が音楽史上のピークとしてではなく、コスチュームパーティ程度の陳腐なものとして記憶されているのには理由がある。非難めいた声は1980年代がまだ途中にあった時から聴こえていた。それは、“しらけ世代”と言われるベビーブーマーたちが1960年代カウンター・カルチャーのアイコンでさえMTV黎明期の明るく陽気な文体を免れないと実感したころとほぼ一致する。
グレイス・スリックが「We Built This City」のプロモで肩パッドの入った衣装を着ていたり、ボブ・ディランが『Empire Burlesque』で当時猫も杓子も採用していたゲート・エコーのかかったドラム・サウンドを聴かせていたりしたのだ。ちなみにボブ・ディランはルパート・エヴェレットと映画で共演もしている。
<関連記事>
・【特集】1980年代、ヘア・メタルがアメリカを支配した時代
・80年代を決定付けたミュージック・ビデオ・ベスト20【全曲動画付】
・80年代ポップスにおけるソウルミュージックの影響
・ゴシック・ロックの歴史:表舞台へと現れた漆黒のアーティストたち
転換期
大物ミュージシャンたちですら、”ジョーンズ”たちに追いつこうとして自虐的な行いを続けていた…ハワード・ジョーンズを筆頭とする面々のことだ。だがそれはあながちみっともないことでもない。「What Is Love?」は確かに素晴らしい曲だったではないか。正直になろう。「カジャグーグー」と誰もが声に出して言わずにはいられなかった10年。それにはそれなりの理由が山ほどあるのだ。
実は隠された秘密がある。1980年代の音楽はロックとポップスの黄金時代だった。パラシュートパンツ、ニュー・ロマンティック風味のパーマのかかった奇天烈な髪型に対するパニックを乗り越え、ユーリズミックスの「Sweet Dreams (Are Made of This)」やソフト・セルの「Tainted Love」がスーパーマーケットで流れるのを耳にして、「最低だとばかり思っていたが、実はなんて素晴らしい時代を生きていたのだろう」と気づくまでに、人生の3分の1を費やしたことだけが悔やまれる。
あらためて考えると、1980年代について最も素晴らしいこととはこのことなのかもしれない。全国規模で共有された一大転換期でありながら、とても小さくて秘められたシーン。「エド・サリヴァン・ショー」はとうの昔に終わっていたが、1980年代、「Motown 25 Special」で観たマイケル・ジャクソンのムーンウォークや、ピーター・ガブリエルの「Sledgehammer」の話題で国中がひとつになった。
それはビートルズがアメリカのテレビ番組に初めて登場したあのときに匹敵する騒ぎだった。「Purple Rain」期の、どこにいても聴こえてきたプリンスはもはや文化的現象だったわけで、それは原題の区分けされ細分化されている現代のトップミュージシャンであるドレイクであっても望もうにも叶うことのないことだ。
播種期
しかし、その現代の断片化の種は実は1980年代に蒔かれていたのだ。「インディ」という言葉が陳腐化する以前のインディ・レーベルやDIYのファンジンが盛り上がっていた、局所的なブームが一般化したのもあの時代だった。
芸術的な才能を犠牲にすることなくスタジアムでの成功を収めることができることを証明してみせたブルース・スプリングスティーンやU2のように、アメリカ全土にいとも簡単にインパクトを与えられる曲やアルバム、そしてパフォーマンスがあった。しかし、同時に、ジャームズの曲のタイトル「What We Do Is Secret」が最もよく要約している「素晴らしきマイブーム」を反映した時代が驚くほど広い裾野として開けていたのだ。
1980年代はXのデビューアルバム『Los Angeles』で始まり、ニルヴァーナのデビュー作『Bleach』で終わった10年だった。カート・コバーンは、1980年代独特の音楽とともに成長し、ハスカ・デュー、ブラック・フラッグ、ミニットメン、メルヴィンズ、ソニック・ユースを吸収し、1990年代に世界的に有名になるグランジシーンが足場を固めつつあった。
そして、セントポールとミネアポリスというふたつの地域がパンクとファンクの双子のムーヴメントを与えてくれた。ザ・タイムとザ・リプレイスメンツの両方を見ることができるあのころのあの場所に戻りたくない者などいるのだろうか。
LAではヘア・メタル・バンドとヘファー・バンドのどちらかを選ぶこともできた。例を挙げればカウパンクのローン・ジャスティス、ランク・アンド・ファイル、ブラッド・オン・ザ・サドル、さらにほぼパンクとは無関係なドワイト・ヨアカムもいた。
ニューヨークでは、アフリカ・バンバータからクラフトワークのリミックスやグレイス・ジョーンズに至るまでのありとあらゆるものに敏感なクラブ好きが集まる騒々しい毎日が始まり、スタジオ54の時代は終わりを告げた。
社会意識が高い行動主義のパブリック・エネミーの「東」と、タフなストリート感覚で実用主義のN.W.A.の「西」との間で分かれてはいたものの、社会問題に切り込むヒップホップが東西両岸で台頭していた。
そしてそれらとは別の、夢と現実のめくるめくパーティの如きビースティ・ボーイズの『Paul’s Boutique』もまったく新しい重力を備えていた。
現在アメリカーナとされているものは、休暇の目的地に南部の州を選ぶだろう人々によって形作られた。エルヴィス・コステロは『King Of America』を、そしてカナダのカウボーイ・ジャンキーズは『The Trinity Sessions』を残した。そしてIRSレーベルがインディとメインストリームのギャップを突如として曖昧にしたことでチャンスを得たR.E.M.が、「アメリカの心」に分け入り大ブレイクを果たし、おかげで南部は再び息を吹き返し始めたのだ。
「雨が降っている時だけが幸せ(*ガーヴィッジのヒット曲「Only Happy When It Rains」を引用)」なUKでは、スミス、キュアー、フォール、スージー・アンド・ザ・バンシーズ、ジョイ・ディヴィジョンらによって、1980年代の音楽が形になり始めた。ちなみにマイ・ブラッディ・ヴァレンタインは、「シューゲイザー」という単語を褒め言葉に変えてみせた。
おそらく1960年代または1970年代、そしてその後のいかなる時代と比較しても良いが、1980年代ほどアイコニックなアルバム・タイトルで溢れた時代は思い浮かばない。アーティストによる説明なり言及なりを必要としないタイトルばかりだ。
『The Joshua Tree』『Straight Outta Compton』『Born In The USA』『It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back』『1999』『Synchronicity』『Avalon』『Appetite For Destruction』『Licensed To Ill』『Full Moon Fever』『Surfer Rosa』『Raising Hell』『Rhythm Nation 1814』『The Queen Is Dead』『Kill ’Em All』
これらのうちの4つもしくは5つ以上のタイトルを聴いてもすぐに何も思い浮かばないとしたら、おそらくナインティエイト・ディグリーズかフォー・フレッシュメンを聴いて育った人である疑いが濃い。
架け橋
ポップ・ミュージックが公共施設整備の税金と突然等価になったかのように、さまざまな橋が渡されていった (ある意味、例のあのCDフォーマット変換に絡んで金銭が突然流れ込んだせいだとも言える) 。
ゴーゴーズがアメリカで愛されるようになるまでの道がいかにラディカルなものであったかを今思い出すのは難しいかもしれない。彼女たちがLAのクラブ、マスクから登場する以前の1970年代、ロック・ファンは女性ロッカーを数えるのに片手があれば十分で、ハート、ランナウェイズ、スターシップをチェックした後はファニーがまだ解散していないかを確認しなければならない状態だった (その筋に詳しい向きは、スリッツも勘定に入れていただきたい) 。
ゴーゴーズが地ならしをした場所は、彼女たちを見習ったバングルズがすぐにとって取って代わった。男連中を率いる女性としては、プリテンダーズがロックは男のものという考えを覆し、ティル・チューズデイのエイミー・マンは「Voices Carry」でただ従うだけのガールフレンドからの旅立ちの決意を歌にした。シンディ・ローパーがエールを贈りながら歌う「楽しむ女の子」はすなわち (愛するパパの顔を立てはしても) 主導権を握る女の子のことだった。
ジギー・スターダストが10年先んじて始め広めた美学を受け継いだカルチャー・クラブやデッド・オア・アライヴによって、バイセクシャルな男性像はメインストリームへ躍り出たが、バイセクシャルな女性の方は、それがユーリズミックのアニー・レノックスであれパッツィ・クラインの生まれ変わりを自認していたk.d.ラングであれ、依然として人の目を惹くショッキングな存在だった。
エイミー・マンが2010年代に入ってもアメリカきっての陰影に富んだ桂冠詩人として褒め称えられるほど耐久性のあるリリシズムの持ち主だったなどと、いったい誰が見抜けただろう。レノックスがあの射抜くような大きな瞳だけでなく、千年の歌姫になってしまうほどソウルフルな声も持っていたなどということに、まだ気付いた者はいなかった。
そして、アメリカでの音楽における人種間を結ぶ橋渡しのストーリーは、MTVがマイケル・ジャクソンを登場させないわけにはいかなくなった (それが外部からの脅しめいた圧力によるものだったのか内部での浄化意識のせいだったのかは措くとして) 1980年代初期という転換期を語らないことには終われない。
白人が黒人音楽を好むということはモータウンやディスコの時代には秘密でも何でもなかったが、MTVが黒人を容認する時代からアフリカ系アメリカ人が優位になる時代になった時には文化的な潮目が変わったのだ。以降その傾向はヒップホップがポップ・ミュージックになった現代にまで繋がっていく。まさに’「Don’t Stop ’Til You Get Enough (とことんまでやれ)」というわけだ。
カントリー・ミュージックという永遠に白い世界でも顕著な変化が進行中だった。ジョージ・ストレイト、ランディ・トラヴィス、ドワイト・ヨアカム等の台頭によって所謂ハード・カントリーが復活し始め、のどかな田舎風フレーヴァーが終焉を迎えようとしていたのだ。
また、ライル・ラヴェット、ナンシー・グリフィス、ロドニー・クローウェル、ロザンヌ・キャッシュ等も、リリカルでセンシティヴなカントリーという新しいスタイルでシーンに登場し、その後少なくとも潮目が大きく変わることになる1990年代前半まで勢いを保った。
また、まだリーバ単独ではなくフルネームで呼ばれていたころのリーバ・マッキンタイアは、ナッシュヴィルのフレッシュで素朴なフェミニズムの代表格として、バラエティーショー時代と「女だけで何でもできますから(Sisters Are Doin’ It for Themselves)」世代とを繋ぐ、素朴だがしかし強力な橋渡しの役目を担った。
そして更に、クラシカルなムードのおかげで1950年代もしくは1960年代あたりの曲かと誰もが思ってしまうカントリーを代表する永遠の名作、ジョージ・ジョーンズの「He Stopped Loving Her Today」。実は紛うことなき1980年代の作品だ。
その1980年代に私たちが遂に出会ったのが、1980年代を象徴するあのシンセ・ポップだった。
罪深き喜び
1980年代の音楽を“ゴミ同然、良く言ってもハッタリ同然”と断じたのはベビーブーム世代だけではなかった。素晴らしき青春の日々を1980年代に過ごした世代は、当時の音楽を、楽しかったがどこかしら恥ずかしいものとして捉えるように躾られたのだった。
そして現代はと言えば、1980年代の音楽はと尋ねれば学校に通う世代も含めた誰もがTOTOの「Africa」を挙げるようなことになっている。ウィーザーがこの曲をカヴァーしている (TOTOも彼らの曲をカヴァーして返礼している) のだが、果たして彼らはウケを狙っただけのことだったのか、それとも捻ったアイロニーを読み解いて予想外に真剣な思いがあってのことだと看破すべきなのか、それは誰にもわからない。彼らは1980年代との関わりについてまだ何も述べていないので正解が見えないのだ。
1980年代の「トラウマ」について彼らは何か言っていただろうか。あまりに昔のことでよく思い出せないのだが、自己中心主義の時代を生き残った人々は多くを知っている。サウンドに何でもかんでもシンセを使ったり、10代のころのコートニー・コックスと一緒に踊ったり、彼らのヒーローたちは恥ずかしい行為に手を染めたのだ。
リズムマシーンとサンプラーの登場によって、誰も彼もがテクノロジーの虜になった。アートを追求し過ぎて難解になってしまったデヴィッド・ボウイは「Let’s Dance」を大当たりさせ、その後も、後に彼自身が最も嫌いだと認めることになるアルバム『Never Let Me Down』で成功を維持した。
ポール・マッカートニーやT・ボーン・バーネットなどの大御所アーティストたちは、彼らの1980年代にリリースしたアルバムのリミックスや再レコーディングに余念がない。あの時代を決定づけたサウンド・プロダクションを取り払ってファンに作品を聴き直してもらおうというわけだ。
しかしシンセ・ポップ自体に罪を着せたくなる衝動にすぐに乗ってしまってはいけない。一発屋、もしくは二発屋でも三発屋でもいいが、彼らが当時の自然で当たり前の感覚で行なった表現それ自体は素晴らしいものではないか。
「Don’t You Want Me」から1980年代の匂いを拭い去り、脱色したとして、誰がそれを聴こうという気になるだろうか。それはもはや1980年代ヒューマン・リーグの劣化版であるだけでなく、あの時代の人間的感覚の劣化版とも言える代物だ。そして、トーマス・ドルビーを聴いて”Hyperactive! (ハイテンション) ”にならない人がいるとしたら、その人は直ちに今服用しているアンフェタミン系薬物の摂取を止めた方がいい。
“Don’t Stop Believin’”
もしあなたがある程度の年齢なら、かつてビル・ヘイリーやビートルズに特化していたはずのオールディーズ専門ラジオ局が、今ではトンプソン・ツインズも同じオールディーズ扱いにしているのかと驚き嘆くのではないだろうか。
しかし、ベルリンが最高だと言う声に自分の老いをつくづく感じながら、またはどの曲も陳腐で嘘臭いと思いながら、自分自身に鞭打ち、車を走らせるあなたはひとつの事実に気がつくのだ。強烈なフックやリフ、しっかりとしたメロディ、そして敢えて言うが正直で人間的な感情表現、そうした素晴らしさがクラシック・ポップスにはあるのだと思えるのなら、ジャニーによる「Don’t Stop Believin’」のあの時代は実は素晴らしかったのだと。
ホイット・スティルマンが果たして「The Last Days of Disco」の続編として「The Last Days Of New Romantic」を作ってくれるかどうかは知らないが、それはどうでもいい。すべてを伝えてくれる音楽こそが重要なのだ。
1980年代の音楽について考える時に混乱してしまう理由は、主にファッション・パーティの側面にある。端的に言えば1980年代はふたつあったということだ。1980年代の音楽には今でも新鮮に聴こえるものがあって、たとえばX (エックス) 、ハスカー・ドゥ、リプレイスメンツらの楽曲は、まるで昨日レコーディングされたのかと思えるほど古びていない。
そして対するもう一方は非常に時代を感じさせるもので、「シンセ・ドラムなくしては究極のスネア・サウンドは得られない」と思い込んでいたかのようなサウンドだ。そうしたものは、年代はおろか日時、さらにはレコーディングされた時刻さえ特定できそうなほど古くさい。
オマージュと呼ぶのかパロディと呼ぶのか、そのあたりは受け取り方次第ではあるが、それに相応しいのは上記のうちの一方でしかない。早い話が、たとえば1980年代を回顧するパーティを開くとして、ハスカー・ドゥのボブ・モールドの格好で参加する人はいないだろうということだ。
モノクロのファッションに身を包み、鉛筆で描かれたスケッチの中で消えていくa-haのリード・シンガーになりきって来るはずだ。「さすがにそこまでは」と思うなら、参加者全員でカツラを被ってポイズンになるのもいい。きっと愉快だろうから。
何が言いたいのかといえば、1980年代の音楽をもう一度楽しもうと思うなら、そうした路線の違いを気にする必要はないということだ。OMDとメルヴィンのどちらかを選ばなければいけないわけではないし、メリサ・マンチェスターとミッション・オブ・バーマの両方を好きになってもいいのだ (そんな聴き手はいないだろうが、それでもいいということだ) 。
そう考えてみると、「Nebraska」を書いたブルース・スプリングスティーンと、突然MTVに登場した別の男の両方にハマっても良いわけだ。誰もが、ウォーターゲート事件に振り回された1970年代の終焉と、政治的 / 社会的に変化を遂げた新時代の幕開けに対する反応も人それぞれだったのだから。
マーガレット・サッチャーが首相だったころの英国のパンクスやレーガンに懐疑的なヤンクスは、またとない時代の到来に狂喜乱舞した。一方で、かの詩人ハワード・ジョーンズのようなタイプは「怖いか」と自問し、「怖い」と答えた。
1980年代はポップス、ロック、R&Bのスターたちが互いの違いを強調する時代だった。そして番組「Yo! MTV Raps」が始まり、人々は立ち止まることなく前に進んだ。未来がとても眩しく、故に陰は必要だった。ロックバンドのティムバック3は皮肉を込めてそう言ったが、その言葉に誰もが頷いたわけではなかった。
当時の音楽界は大統領と反りが合わなかったかもしれないが、少なくとも、アメリカでのポップ・ミュージックに夜明けが到来したとする点については、意見が一致していた。
Written By Chris Willman
- 【特集】1980年代、ヘア・メタルがアメリカを支配した時代
- 80年代を決定付けたミュージック・ビデオ・ベスト20【全曲動画付】
- 80年代ポップスにおけるソウルミュージックの影響
- ゴシック・ロックの歴史:表舞台へと現れた漆黒のアーティストたち