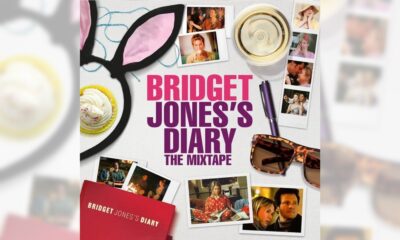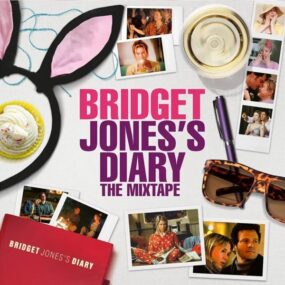Columns
トレント・レズナーとアッティカス・ロス: 『Mank/マンク』で飛躍的進化を遂げた作曲家コンビの経歴


現在Netflixで配信されているデヴィッド・フィンチャー最新作『Mank/マンク』。2021年のアカデミー賞の有力候補されているこの映画の音楽を担当したトレント・レズナーとアッティカス・ロスの作曲家コンビについて、映画・音楽関連のライター業だけではなく小説も出版されるなど、幅広く活躍されている長谷川町蔵さんに解説頂きました。
<関連記事>
・ナイン・インチ・ネイルズの20曲:トレント・レズナーが生み出した苦悩と創造力
・ジョーカーはなぜシナトラを口ずさむのか?

『Mank/マンク』
デヴィッド・フィンチャーといえば誰もが認める大物映画監督になって久しい。しかし彼の作品からは今なお新鋭のようなヒリヒリした空気が漂ってくる。ハリウッドでは嫌っている監督が少なくないデジタルカメラをいち早く導入したことでも分かる通り、一作ごとに新しい挑戦を自分に課しているからだろう。そんなフィンチャー作品にぴったりのサウンドトラックを提供し続けているのがロック・ユニット、ナイン・インチ・ネイルズ(NIN)のトレント・レズナーとアッティカス・ロスのコンビである。
トレント・レズナーの経歴と映画音楽
NINの創始者トレント・レズナーは1965年ペンシルヴァニア生まれ。少年時代はピンク・フロイドやキッスを愛聴していたそうだが、やがてジョイ・ディヴィジョンやキュアーといった英国産ニューウェイヴに耽溺していき、大学進学を機にオハイオのクリーヴランドに移住。貸しスタジオでアルバイトをしながらスタジオの空き時間を使ってデモテープを作る日々を送り始めた。
当初はシンセポップを演奏していたレズナーだったが、ノイズやヘヴィ・メタルの要素を融合したインダストリアル・メタルに傾倒して音楽性はハードなものに。レッド・ホット・チリ・ペッパーズやジェーン・アディクションらオルタナ・バンドが人気を集めはじめたロックシーンの流行に乗っかる形で、1989年にNINとしてレコードデビューを果たした。
NINは、ロラパルーザへの出演やガンズ&ローゼスのオープニングアクトとして実績を積み重ね、1994年にリリースしたセカンド作『The Downward Spiral』でブレイクを果たす。エモーショナルなヴォーカルやディストーションギターにシンセサイザーやドラムマシーンを交えた斬新なサウンドが、グランジ・ロックの次を担う音楽として、Ⅹジェネレーションと呼ばれた当時の若者から支持を集めたのだ。アルバムのラストを飾る悲痛なバラード「Hurt」は、『ハングオーバー!!! 最後の反省会』(2013)でケン・チョンがカラオケで熱唱するなど、今なお代表曲と見なされている。
『The Downward Spiral』が発表されたこの年、レズナーはオリバー・ストーン監督作『ナチュラル・ボーン・キラーズ』(1994)のサウンドトラックの選曲を引き受けている。NINの新曲「Burn」を含むアルバムは、ボブ・ディランからドクター・ドレーまでをも含むジャンル無視のコンピレーション。シリアル・キラーのカップルを主人公にしながらコメディとして仕上がっていた映画の情報量過多な魅力にひと役も二役も買っている。
1997年には『ナチュラル・ボーン・キラーズ』のサントラを聴いたデヴィッド・リンチからのオファーで、『ロスト・ハイウェイ』のサントラの選曲とプロデュースも担当した。リンチの『イレイザー・ヘッド』をフェイバリットとするレズナーにとっては夢のような体験だったはずだ。レズナーの崇拝の対象だったデヴィッド・ボウイをはじめ、マリリン・マンソンやラムシュタインのダークなナンバーがリンチの右腕アンジェロ・バダラメンティの手によるスコアの合間に挟みこまれることで、ミステリアスなムードを醸し出している。しかしこの後レズナーは映画絡みの仕事を絶ってしまう。彼の再登場にはテン年代を待たなければいけなかった。
アッティカス・ロスとトレント・レズナーの出会い
この空白期間にNINに加わったのがアッティカス・ロスである。1968年英国生まれのロスは、ロンドンのクラブ・ユニット、ボム・ザ・ベースのプログラマーとしてデビュー。NINには2005年のアルバム『With Teeth』から関わるようになったが、ドローンやシンセノイズをフィーチャーした静謐なサウンドに移行しつつあったレズナーを、アカデミックな知識を活かして好サポートし、レズナーにとって必要不可欠な存在となった。
このふたりのコンビネーションに感銘を受けたデヴィッド・フィンチャーは、ある映画のサウンドトラックのスコアをオファーする。その記念すべき作品こそが、『ソーシャル・ネットワーク』(2010)だった。映画音楽につきもののオーケストラを排したダークなエレクトリック・ミュージックは、フェイスブックの創始者マーク・ザッカーバーグを描いた映画の内容にこれ以上ないほどハマっていて評判に。アカデミー賞では初ノミネートでありながらサウンドトラック賞を獲得している。
フィンチャーの信頼を得たレズナーとロスは、続く『ドラゴン・タトゥーの女』(2011)のスコアも担当。主題歌として製作した、ヤー・ヤー・ヤーズのカレン・Oをヴォーカルにフィーチャーしたレッド・ツェッペリン「移民の歌」のエクセペリメンタルなカバー・バージョンが話題を呼んだ。同作に続いてフィンチャーがミステリー小説を原作に撮った『ゴーン・ガール』(2014)ではアンビエント・ミュージック色が増し、今にも雨が降り出しそうな曇り空のようなサウンドが映画のメランコリックなムードを増幅している。
同作までほぼフィンチャー専属の映画音楽作曲家だったレズナーとロスはこれ以降、ほかの監督の映画にもスコアを提供するようになる。こうした作品には、Netlixで記録的な視聴数を叩き出したSFサスペンス『バードボックス』(2018)や、同名アメコミの続編ながらオリジナルを超えたと絶賛された『ウォッチメン』(2019)といった話題作が含まれている。そんな中でも特筆すべき出来だったのが、エッジーな作風で話題の映画スタジオ「A24」が製作したティーンムービー『mid90s ミッドナインティーズ』(2018)と『WAVES/ウェイブス』(2019)だった。
この二本はいかにもティーンムービーらしく、多くのシーンで現実のポップチューン(前者は90年代、後者はテン年代産の楽曲)が流れるのだが、レズナーとロスはこうした楽曲の合間を縫うように、同じ音像を保ちながらも主人公の言葉にならない感情をすくい取ったようなリリカルなインストチューンを提供。これらが隙間なく流れることで、観客にまるでひとつの音楽が鳴り続けているような錯覚を与えている。現役ポップスターでもある彼らだからこそ作れたスコアだろう。
進化を遂げた『Mank/マンク』の音楽
そしてフィンチャーとの久しぶりのコラボレーションにして、目下のところの最新サントラ仕事が『Mank/マンク』(2020)である。同作で彼らは映画作曲家として飛躍的な進化を遂げている。
映画史に残る傑作『市民ケーン』(1941)の脚本家ハーマン・J・マンキウィッツの伝記映画である本作の時代設定は、1930年代から40年代にかけて。つまりいつものシンセサウンドを奏でたら違和感が生じてしまう。このため彼らはベテランのオーケストラ編曲家コンラッド・ポープとの共同作業で初めて本格的なオーケストラを導入している。
但しその仕上がりは、レトロさは微塵もなくスーパーモダン。1940年代のクールジャズやサードストリームの意匠を借りながらも、同時代の映画音楽には決して存在しないアブストラクトなサウンドスケープは、当時のムードの再現に全力を傾けながらも8Kデジタルカメラ撮影で時代を超越した作品に仕上がった映画本編と共鳴しあうものがある。やはりフィンチャーとレズナー&ロスは、志を共有するパートナーなのだ。
しかしこのジャジーでムーディーな響きはどうだ。こうなってくると、レズナー&ロスの作風には全く合っていない映画のように感じられたピクサー製作のアニメ『ソウルフル・ワールド』(2020)の映画音楽が俄然楽しみになってくる。同作は、ソウル(魂)の世界に紛れ込んだジャズ・ミュージシャンの冒険を描いたファンタジーだという。
Written by 長谷川町蔵

Netflix映画『Mank/マンク』独占配信中
公式サイトはこちら
アルコール依存症の脚本家ハーマン・J・マンキウィッツが「市民ケーン」の仕上げを急いでいた頃の1930年代のハリウッドを、機知と風刺に富んだ彼の視点から描く

『ソウルフル・ワールド オリジナル・サウンドトラック』
2020年12月23日発売
CD / iTunes / Apple Music / Spotify / Amazon Music
- ナイン・インチ・ネイルズの20曲:トレント・レズナーが生み出した苦悩と創造力
- 傑作『The Downward Spiral』が長年に渡り語り継がれる理由
- ナイン・インチ・ネイルズ関連記事
- 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の魅力と“1985年”という絶妙な時代設定
- ジョーカーはなぜシナトラを口ずさむのか?
- 80年代を決定付けたミュージック・ビデオ・ベスト20【全曲動画付】
- “現実はアートを模倣する”『サタデー・ナイト・フィーバー』の意外な真相と虚構
- 映画『メッセージ』にマックス・リヒターが使われた理由とは
- 長谷川町蔵インタビュー:映画サントラの過去、現在、未来