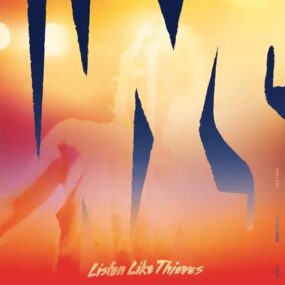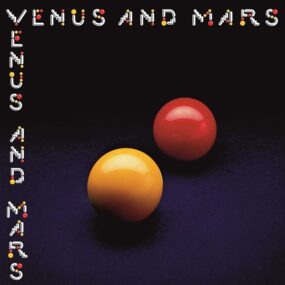News
【前編】U2のボノとジ・エッジがApple Musicに語った新作、そして音楽に見出した信仰


2023年3月に発売されたU2の新作アルバム『Songs Of Surrender』は、バンドが自身の過去の楽曲を今のアレンジで再録音した作品だ。
このアルバムの発売にあわせてApple Musicの番組『U2: The Zane Lowe Interview』にてDJのゼイン・ロウがU2のボノとジ・エッジにインタビューを実施。砂漠、そしてラスベガスへ向かうツアーバス内で行われた1時間弱の映像が、Apple MusicとYouTubeにて公開された。この記事ではその全日本語訳の前編を公開(後編はこちら)。
また、新作『Songs Of Surrender』は、U2のアルバムとして初めてApple Musicで空間オーディオとして配信されている。加えてApple Music限定でアルバムのページにメンバーのコメント入りのアルバム解説が掲載されている(*アルバムのApple Musicのページはこちら)。
<関連記事>
・U2の名曲「Beautiful Day」を振り返る:新作発売記念
・U2の名曲「Pride」を振り返る:新作発売記念
・U2の名曲「With or Without You」を振り返る:新作発売記念
・U2の名曲「One」を振り返る:新作発売記念
・U2、自身の楽曲40曲を新録音した新作『Songs Of Surrender』発売決定
ゼイン・ロウによるナレーション:はるか先まで続く開けた道は、芸術活動を行うアーティスト、ミュージシャン、映画作家にインスピレーションを与えてきた。彼らは、自らの小ささを感じるために、広大な場所に行きたいという欲求に駆られるのである。
U2は1970年代後半にダブリンから登場して、瞬く間に大きな存在になっていったが、その間もずっと、未開の地を探し続けてきた。このバンドの旅は前人未踏の道のりを歩んでいる。彼らはこの地球上のありとあらゆる場所を訪れ、意義深い足跡を残そうとしてきたように思える。とはいえU2は、とある環境、とある非常に広大で大きな広がりのある場所に絶えず引き戻されている。つまり砂漠である。今回ボノとジ・エッジがインタビューの場所として指定してきたのも、まさに砂漠だった。
インタビューのテーマは最新作『Songs Of Surrender』である。このアルバムでは、彼らがこれまで発表してきた名曲40曲が新たなかたちで再現されている。これは、常に戦いながら前へと突き進んできたバンドにとって、めずらしく過去を振り返るような内省的な作品と言えよう。2人への質問はたくさんあるけれど、幸いにして邪魔になるものは周囲にまったくなかった。
U2と砂漠
ジ・エッジ: あれを見てくれよ。ああ、砂漠は大好きだね。こういうところに来るのが大好きなんだ。
ゼイン・ロウ: U2を語るなら、砂漠に触れずに済ますわけにはいきませんよね。
ジ・エッジ: ああ。でも大事なのはこの純粋さなんだ。砂漠っていうのは本当に純粋な空間だよ。だって、ここには何もないんだからね。
ロウ: ええ。こういう場所では、自分が一番小さいと感じるんでしょうか? 砂漠に座って、そこで長い時間を過ごして楽しむには、ある種の自意識が必要ですよね。
ボノ: そうだね。それじゃ、どうぞ腰かけて……。
ロウ: カメラをまわしていないときにこんな話をしてましたよね。つまり、これまでずっと砂漠を歩いたり、砂漠で踊ったり、砂漠で写真を撮ったり、いろいろなことをしてきたけれど、このような場所でインタビューをしたことはない……そういう話でした。僕たちファンからすると、U2は砂漠や広々とした空間を見せてくれたバンドのひとつなんですが、こういう場所でインタビューをしたことがないと。
ボノ: 単にお喋りをするっていう機会はたくさんあるけれど、それをインタビューとして記録したことはないな。曲のプロモーション・ビデオの撮影を除けばね。今回インタビューすることになって、こちらとしては“こういうのは初めてだな”って思ったよ。ここは魔法みたいな風景だね。
かつて僕たちはアメリカに来て、アメリカをこの目で見ようとしたんだけど、あのころのアメリカは自らを探している時期だった。つまり、1980年代のアメリカは少し道に迷って、自分が何なのか改めて発見しようとしていたんだ。だから、あのころアメリカに到着したのは素晴らしいタイミングだった。僕たちがアメリカを知ったのは、大部分は音楽経由だったけれど、本からもいろんなアメリカを知ることができた。サンフランシスコのシティライツ・ブックストアでサム・シェパードの戯曲を読んだり、パティ・スミスとか、アレン・ギンズバーグの詩を読んだりするうちに、僕たちはヨシュア・トゥリーにたどり着いた。ギンズバーグの『アメリカ』とか『吠える (Howl)』とかね。ああいった本はどれも僕たちにとって大きな意味があった。
ジ・エッジ: それからヴィム・ヴェンダースも。
ボノ: その通りだ。
ジ・エッジ: ヴェンダースの『パリ、テキサス』にはかなり影響を受けたよ。あれはヨーロッパ人の目を通して描いたアメリカの映画だったからね。
ロウ: 当のアメリカ以外の国では、“明るく、光り輝くアメリカ”っていうイメージを常に売り込まれてきましたからね。アメリカに来れば、お金が儲かり、商品が売れるというわけです。とはいえ、ヴィム・ヴェンダースのような人たちもU2も、そうしたアメリカの中に美しくて素晴らしい奇妙なものが手つかずのまま残されていることに気付きました。人はそうしたものも探求すべきだし、慈しむべきです。というのも、こうした風景は実に崇高なものなのですから。
ボノ: さらに言えば危険でもある。この風景は、単に人を瞑想に誘うだけじゃない。ここにいると、ここで戦い、死んでいった人たちを感じることができる。
ロウ: あっちの方にはゴーストタウンがありますね。ちょっとした好奇心でいろいろ調べてみたんですが、この辺はかつてネバダ州でも最悪の無法地帯だったとか。19世紀のネバダ州にはあちこちに無法地帯がありましたが、その中でも一番の無法地帯だった場所に僕たちは今、来ているいるわけです。
ボノ: そういう無法者の多くはアイルランド人だった。たとえばジェシー・ジェームズとか、壁の穴ギャングとか、ビリー・ザ・キッドとか。アイルランド人の哀れな旅行者で、巡礼者たちだった。そして僕たちもいまだに同じことを信じている。これはポール・リクールか誰かの言葉のうろ覚えなんだけど、“正しい道連れと共に、多少の知恵を携えて、経験を積み重ねていけば、やがて罪のない純真な心を取り戻せる”っていうわけだ。
新作、過去の楽曲との“再会”
ロウ: その表現はまさに言い得て妙ですね。というのも、U2のこれまでの道のりをうまく言い表しているからです。その道のりが、今回こうして素晴らしいアルバムにつながりました。このアルバムは、どう表現したらいいのかな。個人的には“再創造 (リ・イマジン) ”という言葉は使いたくありません。あまりに客観的でアーティスティックな用語なので。ある意味これは、過去の楽曲との“再会”なんじゃないでしょうか。曲を作ってから今まで、ちゃんと聴き返したことはなかったんじゃないですか?
ジ・エッジ: ああ。楽曲のほうが“ボス”なんだ。このプロジェクト全体を通して、曲の方が僕たちに何をすべきかを指図してくれた。
ロウ: つまり、曲を作り、作品を作ると、誰もがさらに先に進んでいくわけで……。
ボノ: “楽曲は作者の子供のようなものだ”ってよく言われるけれど、それは間違いだね。曲は作者の親みたいなものなんだ。こちらにああしろこうしろと指図してくる。“仕事をするときはこういう服を着ろ”とか、“ビデオに出るときはこういう服を着ろ”とか。そうして曲のほうが立場が上になるんだけれど、しばらく経って、もし作者がソングライターとして成功したら、曲は作者ではなくほかの人の所有物になる。今回のアルバムで、僕たちはもう一度、そういった昔の曲に耳を傾けようとした感じだね。そしてまず、曲が今も通用するかどうか見きわめようとした。U2のようなロックンロール・バンドの爆発力を省略した状態でも、持ちこたえられるかどうか確かめたかったんだ。
ロウ: 皮肉なことに、もし曲が今も通用するほどしっかりしたものなら、曲が何らかの人格を持って存在するようになりませんか。そのあたりに座って、作者がそんな質問をすることについて笑っていたりして。なぜなら、曲の方も同じ質問を作者に投げかけているだろうから。お前は、今も通用しているのか? こういう曲を作り上げた後のお前には何が残っているんだ? ―― そんな風に。
ボノ: そうなると、もっとややこしい話になるな。それに対する答えは、僕にもわからない。というのも、もし曲に何がいいところがあるなら、曲は終わりがないし、永遠の命を持ち続ける。でもロックンロール・バンドはそうじゃないからね。
ロウ: だからこそ、今回のタイトルが『Songs of Surrender』になったんじゃないですか?これは素晴らしいタイトルで、あなたの本 (『Surrender』) や体験と見事に結びついていますが、それだけじゃない。タイトルにある三つの単語の頭文字を並べるとわかりますよね。“S.O.S. / 救助求む!”ですから。
ボノ: そう、「助けてくれ!」。つまり「SOS」になる。このアルバムにはぴったりのタイトルなんだ。なぜなら、僕たちはいろんなものをくぐり抜けてきたからね。新型コロナウイルスとか、ああいう不吉な病気とか、ウクライナ戦争のような何か悪いことが起こるんじゃないかという予感とかね。そういう状況を経たあとだから。それに、このタイトルはTシャツにすると見栄えがいい。
新作の「Bad」と「Dad」
ロウ: 確かに(笑)。今回の収録曲ですが、こういった曲を改めて体験するために何が必要だったのか考えてみました。聴き始めてすぐに気に入ったんですが、こうした曲の中には旅が含まれていて、そうした旅の一部はまだ完全に終わっていない。新しい考えや新しい手法がある。たとえば「Bad」のような曲は、以前は“If you”で始まっていたのに、今回のヴァージョンでは“If I”で始まっている。そういったちょっとしたひねりが気に入っています。
ボノ: この「Bad」という曲を歌うときは思わず身震いしそうになるんだけれど、その理由はこれが僕の友人について歌った曲だからなんだ。彼は、危うく命を落としそうになったことが2度あった。一度目は、子供のころ、地元の町で起きた爆弾テロに巻き込まれそうになったとき。そして2度目は、もっと成長してからヘロインに手を出したとき。僕は「これを歌ってもいいんだろうか?」と自問自答してしまう。なぜなら、僕も間違いなく何かしらの中毒であることには変わりがないからね。僕にとってのドラッグが何なのかはよくわからない。でも、手を切るべきものがあることは間違いない。それで歌詞を他人ごとのような二人称の“If you”でなく、“If I”という一人称に書き変えたんだ。こうすると、本当に歌うのが難しくなったけど、同時に本当に歌いやすくもなった。
ロウ:「Dad」もそういう曲のひとつだそうですね。あなたはまだ完成していないと思ったのに、ブライアン・イーノが強引なくらいに推したとか。
ボノ: ああ。ブライアン・イーノは「つじつまをあわせることを止めろ (Stop making sense)」というモットーで有名だからね。あれはデヴィッド・バーンの映画のタイトルだけれど、あのフレーズの陰にブライアンの存在を感じることができる。「きみの歌詞は僕の歌詞と同じように純朴なところがある。それを純朴なままにしておくというのも、いいものだよ」って、ブライアン・イーノが僕にくれたメッセージはそういうことなんだ。ジ・エッジやほかのメンバーもそれを支持してくれた。
あとになって、僕は振り返るのが耐え難いように感じた。歌詞の中には風景が描かれているけれど、それは自分がスケッチした感情的な風景なんだ。鉛筆で描いたスケッチみたいな感じ。自分では直視できなかった。でもジ・エッジは、「素晴らしい」と言ってくれる。「お前はただ見せびらかしているだけだろ。心を開いているわけでもないし、何かを明かしているわけでもない」って。まあ、こちらとしては、見せびらかすことができるなら少しでも見せびらかしたいところだけれどね。
ジ・エッジ: 歌詞は曲と切り離せるものじゃない。大事なのは、歌詞がメロディや響きとどのようにぶつかり、どのように融合していくかという点なんだ。だから、歌詞を独立したものとして見て、言葉の上の意味だけで判断することはできない。僕にとっては、感情的なインパクトが重要だね。もし何かに真実味があって、感情を伝えるものになっているのであれば、それは明らかに内容を持っている。そうでなければ、気持ちがこもってるようには思えないだろうね。
楽曲と怒り
ボノ: きみ(ゼイン・ロウ)はそもそもはヒップホップ界隈出身だけれども、ああいう世界では、リズムとか拍子とかライミングといったものが、怒りや喜び、愚かさの邪魔をすることがなかった。でも僕たちの初期作品の場合、少なくともほかにはないユニークな領域があった。そのおかげで、U2が特別なものになっていたんじゃないかな。
ロウ: 聴いている側としては、どのメンバーの演奏が一番胸に刺さるのか、ときにはわからなくなっていました。たとえばヴォーカルを聴いているつもりでも、ときには歌詞よりギターの演奏から怒りを感じることがあった。またあるときは、ヴォーカルとギターというより、ラリーとアダムの演奏に感情を掻き立てられることもあった。だから、U2がバンドとして独特なのは、メンバーそれぞれが自らの技術を通して、聴く人ひとりひとりに直接届くようなコミュニケーションを取ろうと努力している点にあると思います。それがうまく行ったときは、1+1+1+1が4よりもずっと大きなものになる。
ジ・エッジ: それに、バランスの問題もある。もし、本当に心のこもった歌詞ができた場合、バンドの側はその歌詞やメロディーの感情に対して、荒々しく、一見するとよそよそしいもので対抗してバランスを取らなきゃならない。それは、ボノの側も同じなんだ。ボノがものすごくアグレッシブでトゲのあることをやるなら、バンドはそれを引き立てるために別のスタンスを取らなければならない。つまり、すべてのバランスが重要なんだ。
ボノ: 僕たちの最初のシングルには3曲入っていた。「Out of Control」「Boy/Girl」、そして「Stories For Boys」だね。これはアルバム『Boy』に収録された曲で、10代のファンタジーのような曲じゃないかな。でも、ちゃんと骨組みを組み立てた曲じゃなかった。今回のアルバムでは、それをちゃんと組み立てた。それに加えて、ジ・エッジがこんなことを言ってたんだ。「あれはかなり安定していない」ってね。それであの曲は、まるで違う響きを持つことになったんだよ。
ジ・エッジ: でも、僕たちはこれを自分たちのことを描いた曲として作ったんだ。1979年に作り始めた当時、僕たちはまだ少年だったからね。それからこれだけの時間が過ぎ、これだけの経験を積んだ今、僕たちは安全な場所から自分たちの過去を見つめ直して、歌詞を完成させることができた。ここまでの歌詞は、当時は決して書けなかっただろうね。
U2は過去を振り返えらなかった
ロウ: 今回の『Songs Of Surrender』ではそこがとてもすごいと思いました。長年の大ファンとして言わせてもらえると、U2は過去を振り返ることに激しく抵抗してきましたよね。
ボノ: その通り。
ロウ: U2は現状に留まることを拒否するバンドで、それが高じるあまり、ありとあらゆる種類の地獄を自分たちで体験することになった。ただただ壁を突破しようとして、全員が5分以上同じ場所に止まろうとしない。そういった大変な試練をずいぶん乗り越えてきた。有名な偉人の言葉がありますよね。「ノスタルジーは過去のものである」という。しかし今回のアルバムは、過去を振り返る40曲で構成されている。こういう心境に、どうしてたどり着いたんでしょう? 激しさが控えめになり、原点に戻って、クリエイティブでアーティスティックな意味で自らの人生を追体験できるようになったんでしょうか?
ジ・エッジ: チャンスが訪れたから、それに乗じたってことだと思う。新型コロナウイルス対策のロックダウンのおかげで、突然、何のプレッシャーも期待もなく、ただ音楽を作るための余裕ができたんだ。自分たちの曲をもっと音を削ぎ落としたかたちでやってみたらどうだろう ―― そんなアイデアは以前から頭にあった。ライヴではずいぶん前からやっていたんだよ。「Every Breaking Wave」をピアノだけでやったり、「Staring At The Sun」をアコースティック・ギターとヴォーカルでやったりとか……。
ロウ: なるほど。それこそ、ファンが待ち望んでいた未開拓の領域ですね。実際、そういう領域に挑戦してみて、どうでした?
ジ・エッジ: これは絶好のチャンスだったね。こういうやり方で、どこまでやれるか確かめることができた。それに、出来が気に入らなければ出さなくてもいいというのも嬉しかったね。こちらとしては、とにかくやってみて、それがうまくいくかどうか確かめるだけだった。だから、そのプロセスを本当に楽しむことができた。驚くほど楽しかったよ。
ボノ: これは“自己満足のプロジェクト”であると同時に、“因縁の対決”でもあった。“因縁の対決”っていうのは、つまり僕たちは確かめようとしたわけだ。まあ、かえってわかりにくくなったかもしれないけどね。世の中には歴史に残る名曲がたくさんあるし、僕たちも大好きなお気に入り曲はたくさんある。自分たちU2の楽曲が、そうした傑作の数々と肩を並べることができるかどうか、はっきりさせたかったんだ。だから、肩を並べられるだろうかという点で少しばかり不安もあった。それから“自己満足のプロジェクト”というのも同じようなことだね。つまり何年も前から“歌詞を完成させていない”と言っていたわけでね。ちなみに以前、“僕は女の子みたいに歌っている”ってよく言っていたんだけど、そう言うたびにみんなに怒られていた。“そんなことは言わないで”ってね。
ロウ: 女の子みたいに歌うのが、そんなに悪いことなのかな? 素晴らしいと思うけど。
ボノ: うん。女の子みたいに歌うのは夢だよね。男がファルセット (裏声) で歌うのは、ある意味、最も男らしいことだよ。つまり、そこまで女っぽくなろうとするのはね。ジョーイ・ラモーンなんか、まるでダスティ・スプリングフィールドみたいな美しい声をしていたよ。僕の声は、シャウトしたり金切声を挙げたり、パンク・ロック・シンガーみたいなことをする必要のないところまで来ていた。それで、こう思った。「こういった曲を歌ってみよう。もし本当に上手くいけば、曲が僕のことを歌ってくれる」ってね。
新作アルバムで難しかった曲
ロウ: この中で一番大変だった曲は?
ボノ: 「Bad」が一番難しかった。それだけは間違いない。さっき話したような理由があったからだよ。それと「With Or Without You」は、1つの会話にしてみた。それに「All I Want Is You」ではちょっとしたトリックを使っている。この曲では、ミューズ (霊感を与える詩神) の視点から歌っているんだ。「You say you want a diamond on a ring of gold (金の指輪に載ったダイヤモンドが欲しいとあなたは言う)」という歌詞を聴くと、U2のファンなら、「ボノが奥さんに向けて歌っているんだ」と思う。
でも、やがて気付く。「いや、これは奥さんが“そんなのいらない”とボノに言っているんだ」ってね。だから、そういうことを明言して、テキストとメロディーを尊重することができたのはよかったと思う。僕たちは曲の作者をU2とクレジットしている。その理由は、ラリーとアダムが曲を価値あるものにしているからなんだ。だから実利的な意味がある。それに加えて、ラリーとアダムが通常、即興演奏を通して楽曲に貢献しているっていう理由もある。
ロウ: それはバンドを解散させない秘訣でもありますよね。もし4人で均等に分けたら、一緒に続けられる可能性が均等に分けない場合よりも4倍高くなる。
ボノ: その通りだ。こういうやり方は、当時のマネージャーだったポール・マクギネスの的確なアドバイスに従った結果でもある。でも一番肝心なのはね ―― これは虚栄心をひけらかすような言い方ではあるんだけど ―― ジ・エッジと僕はどんどん曲を大事に思うようになってきているんだ。以前は、「お前は何をして生きてきたんだ?」と自問自答する時、「バンドをやってきた」とか「社会的な活動をしてきた」とか「歌手として歌ってきた」という答えを返していた。
でも今なら、「ソングライターとして曲を作ってきた」というだろうね。何よりもまず、ソングライターなんだ。歌詞がすべて。メロディーがすべて。世の中には、素晴らしいソングライターのコンビ、デュオ、デュエット、デュエル (対決) が存在しているよね。ジ・エッジとは16歳のときから一緒に曲を作ってきた。彼は音楽の天才だよ。彼が魔法のようなアイデアを持ってやってくるから、僕はそれを形にしていくのを手伝う。僕は曲の中にあるものを言葉にしようとしてきた。僕の方から曲を持ち込むこともある。たいてい彼ほど天才的な曲ではないけど、彼はそれを天才的な曲にしてしまう。
4人お互いが高いハードルを設定する
ロウ: これまでの人生の中で何度も話してきたんですが、U2には全体を貫くひとつの糸がありますよね。少なくとも今回の新しいアルバムには、そういうものがある。つまり、いいものを生み出すためには、本当に深いところ、ときには本当に難しいところにまで行かなきゃならない ―― そんな姿勢がある。そういう姿勢でいる理由として、U2のメンバーがお互いにすごく高いハードルを設定している点があるんじゃないでしょうか。たとえば、優れたギターのフレーズを耳にしたら、それに匹敵するような、あるいはそれをさらに高めるようなことをしなきゃいけない。そうなると、ハードルはすごく高くなると思う。あるいは、ボノが作った歌詞を耳にしたら、それに気持ちの上で共鳴するようなメロディーを作り出さなきゃいけない。そうなると、ハードルはすごく高くなってくる。
ボノ: それと僕たちは、ギターのフレーズや歌詞を考える場合、単にひとりで考えるわけじゃない。「お前も考えろ」っていう感じで互いにプレッシャーをかけるんだ。ときには、ジ・エッジが素晴らしい歌詞を思いつくこともある。たとえば、ジ・エッジが「“I Still Haven’t Found What I’m Looking For”という曲を作れないか」なんて言ってくるんだよ。
ロウ: あれはジ・エッジが思いついたフレーズだったんですか? すごいな。
ボノ: そしてときには、僕がギター・パートを思いつくこともある。お互いにアイデアをやり取りするんだ。素晴らしいよ。まるで魔法だね。
ジ・エッジ: それから幸いなことに、僕たちは曲が高く評価されている。もしこういう立場になったら、ほかにやるべきことなんてあるかい? いい曲をさらに作るしかないんじゃないかな?

photo courtesy of Apple Music
真夜中に永遠をアルペジオを引き続けるジ・エッジ
ロウ: 曲作りのプロセスに関する点について言えば、興味深い話があります。あなたの著書『Surrender』には、朝の4時に目が覚めたときのことが書かれていますよね。そのときジ・エッジは半分寝ているか完全に眠っている状態なのに、ギターのフレーズを弾き続けていたっていう……。真のクリエイターであれば、誰でもそういうことをしたことがあるはずです。僕もベッドルームでビートを作っていて、それはジ・エッジの足元にも及ばないような程度のものなんですが、それでも眠りに落ちつつ制作を続ける。せっかく思いついたアイデアが、形にならないまま消えてしまうのは惜しいから。
ジ・エッジ: その通りだな。
ロウ: こういう制作プロセスには衝動的な部分もあるけれど、強制的な部分もある。自分で選択している部分と精神的に自らに強制している部分のバランスはどうなっているんでしょうね。何かを探り出すまで、ずっとかじりついていないといけないって自らに強いているところもあると思うんですが……。
ボノ:うん。そういう表現で間違いない。
ジ・エッジ: 僕にしてみれば、そこに何かがあることはわかっているから、それをたぐり寄せて表に出すために努力し続けなきゃいけない ―― そんな感じだね。
ロウ: あなたはその何かが姿を現すまで、ずっと続けるようなタイプなんですね。
ボノ: 本の中で紹介したエピソードは、ロンドンでのことだった。僕が宿泊した部屋は、不幸にもジ・エッジの部屋の下だった。「Song For Someone」のギターのアルペジオと同じものが上から聞こえていたんだよ。それが1時間続いていたけど、僕はベッドに入って眠りに落ちた。あの日は部屋に戻るのが遅かったから、寝たのは夜中の2時くらいだった。1時間ほどして目が覚めたら、ジ・エッジがまだ弾いている。さらに2時間後に目が覚めても、まだ同じアルペジオを弾いているんだ。
ジ・エッジ: まあ、まったく同じじゃなかったけど……。
ロウ: そこが選択と強制の分かれ目ですね! それじゃ、何時間も、何十時間もかけて探し求めていたのは、いったいどういうものなんでしょうか?
ジ・エッジ: たぶんいろんなアイデアを録音していたんじゃないかな。僕はひとりで作業することが多いから、ツアー中は宿泊先の部屋にマイクとノートパソコンを用意して、録音できるように備えている。でもあのときは、もう少しで何かにたどり着きそうな感じだったんじゃないかな。そういう状況は最悪なんだ。
ボノ: ゾッとするね。
ジ・エッジ: というのも、そういう場合、半端にできた曲を必要以上に大事に扱ってしまう場合があるからね。そして最終的には、「これだ!」と思えるものに本当にたどり着くまで苦労しなきゃいけない。だから、とにかく試しにやってみて、「これじゃない」となることもある。
ボノ: あのときのジ・エッジは、別に変なものを口にしていなかったよ。
ジ・エッジ: 何もね。
ボノ:テキーラもなかったし、アルコールの類はまったくなかった。
ジ・エッジ: 次の日にスタジオ入りするということだけはわかっていた。
ロウ: そんな行動をとるジ・エッジを、ほかのメンバーはバスの下に放り込みたくなるんじゃないですか? バスの下にはいつもスペースがありますからね。ほかの方もご一緒しますか?
ボノ: 僕も行こう(笑)。バスの下もいいものだよ。
新作に入れるのが楽しみにだった曲
ロウ: 曲作りという観点から見て、『Songs of Surrender』の収録曲の中で再び取り上げるのが楽しみだったのはどの曲でしょうか? 特に生命感を感じたのはどの曲だったんでしょう?
ジ・エッジ: 最初に目をつけたのは、あまり世間の人が知らないような曲だね。そのあたりから始めるのが楽しそうに思えたから。そうして取り上げたのが「Dirty Day」や「If God Will Send Us Angels」だった。
ロウ: ああ、あの曲をああいう文脈で聴いたことはなかったんですが、本当に生き生きとした感じに聞こえました。
ジ・エッジ: 実のところ「If God Will Send Us Angels」は、メロディーを支える伴奏が不十分だと気づいたんだ。非常に抽象的なアレンジのままで終わっていて、そういうアレンジに比べると、メロディーのほうがずっと出来が良かった。それで、「このメロディーにはもっと適切な伴奏をつけたほうがいい」と考えた。そうしてコードを変えたり、ほかにもいろんなものを変えたりしてみた。メロディーは同じだし、歌詞も同じだけれど、ずっといい曲になっている。
ボノ: 歌詞は同じじゃない。
ジ・エッジ: そうだ。歌詞も変えたね。
ボノ: これは、実のところクリスマス・ソングなんだ。「Jesus’ sister’s eyes are a blister / The High Street never looked so low」っていうフレーズとかね。でも、かなりディストピア的な暗いクリスマスの光景だね。「いやあ、手首を切りたくなるような状況だな」と思っていた。そこで歌詞を2行変えてみたら、今度はゴスペル・ソングになった。最後のサビは、こんな風に変えてある。「if God will send his angels / We sure could use them here right now / And if God can send his angels / Could he come himself right now」。
ツアーバスに乗る3人
ロウ: こうして広々とした場所にいるのも素敵ですが、このネバダ州に来たのには理由があります。どうしても行きたい目的地があるんです。そのためには、ツアーバスに乗らないといけない。ツアーバスに乗るのは久々ですよね?
ボノ: いまだに旅の途中だね。バスは久しぶりだ。こういうのはいい思い出だよ。
ロウ: 素晴らしいですね。
ボノ: 個人的には、ボーイングのビジネス・ジェットのほうが好きだな (笑)。
ジ・エッジ: ああ、バスの中はすごいね。
ロウ: この時代のバスに乗るのは、これが2台目です。確かシャングリラにあったのは、ボブ・ディランの古いツアー・バスでした。
ボノ: あれに似ているね。そのバスで録音したことがあるよ。
音楽の中に見出した信仰
ロウ: 外にいるとき、“目的地”の話をしました。あなた方は、地元ダブリンに帰ると、本当にリラックスして楽しんでいますよね。デヴイッド・レターマンと一緒にテレビ番組を作ったり。
ジ・エッジ: ああ。
ロウ: 地元に戻って、コミュニティの仲間に囲まれて過ごすっていうのは、多くの面で本当に癒されるんだと想像できます。そうしてパブに行ったりすると、それがインスピレーションに結びつく。そういうときはどんな心境なんだろうなと考えているうちに、“信仰”という言葉が頭に浮かんできました。信仰は、あなた方の人生と音楽の中で活動を推し進める原動力となってきましたよね。僕の考えでは、これはおおよそ3つの段階があるように思います。あなた方のほうがうまく説明できるでしょうけど。
まず最初の段階は、生まれたときの家庭の中にある信仰。次の段階はスピリチュアルな活動になる。この段階になると、音楽と演奏に精力を傾けて、心と心を結びつける空間をつくり出し、とてもホリスティックな感覚が生まれてきます。そして最後の段階では、信仰の実践的な使い方を発見することになる。つまり、より広い場所に出て、物事をより良くする活動や、実際に世界をよりいい場所にするためのプロセスに取り組んでいく。こういうまとめ方はどうでしょうか?
ボノ: そうだね。ソングライターや即興演奏をするミュージシャンにとっては、信仰は自分の行動の中心にあるものだよ。なぜなら、次々に音符を連ねて行く時、次の音符が何なのかわからないままジャンプしていくからね。
ロウ: ええ、本質的にそういうものですよね。
ボノ: 曲作りには信仰心が必要なんだ。ジャズ・ミュージシャンに訊いてみるといいよ。ジャズの即興演奏中は、とにかく思い切って飛び出して、ある特定のコードや場所に着地することを願うばかりだから。それに聖書にはこんな風に書かれている ―― 「存在してほしいと願っていても、目に見えないので、存在しているかどうかわからないものがある。信仰とは、そういうものが確かに存在していると確信することである」ってね。だから、子供のとき、世の中に提供できるものが何もないと感じるとき、少なくとも信仰があれば助けになる。そして自分の人生や国の中で周りに何もなさそうな場所にいるとき、人間には信仰が必要になる。
僕たちは、そうした信仰をお互いの中に見出した。音楽の中にそれを見出したんだ。僕たちは、ある種の宗教性は正しいと思っていた。ただしアイルランドは宗派の境目で分裂しているけどね。まるで内戦みたいな状態だよ。だから僕たちは伝統的な組織宗教を否定している。でも僕たちは、自分たちの道を見出した。いずれにしろ、音楽は精神の言語だ。そういうところで僕たちは自分の音楽とつながっているし、僕たちの核心には信仰がある。そして、世界は人が思っているよりも柔軟なんだ。石の中に固められているわけじゃない。蹴ったり、撫でたり、キスしたり、押したり、作り変えたりすることができる。
自分たちのことを真面目には考えてはいない
ロウ: とはいえバンドとしてのU2は、自らの信仰心と共に活動を始め、最終的には未知の領域や未体験の世界を探すことになりました。そうして、毎日毎日の活動すべてが未知の、とてつもないサーカスみたいになったわけです。バンドを辞めたいと思ったときも、もう無理じゃないかと不安になったときも、毎晩ステージをこなし続けました。『Joshua Tree』のツアーでも、その後のツアーでも、そうした活動をずっと続けてきました。世界の指導者の前に立ち、バンドとして、あるいは個人として何かを変えようとするたびに、自分が目指していたことをやり続けてきました。U2は、変化のための代理人になったわけです。
そうして互いに信頼し合う4人の友だちがこういう活動を続けていくうちに、世間の人々はより多くのことを期待し、そうした期待感は留まるところがないように思えます。こういった状況についてどう思われますか?
ジ・エッジ: だからこそ『Achtung Baby』みたいなアルバムや『Zoo TV』ツアーといったものがとても重要だったんだと思う。というのも、『Joshua Tree』の時期の真面目さや責任感が誇張されすぎて、僕らが風刺の対象になり始めていたからね。だから僕らは自白しなきゃいけなかった。「実は僕は救世主なんかじゃありません! 僕たちはとても愚かなガキの集まりです! 大げさな大人物じゃありません!」ってね。
僕たちは、U2というバンドや音楽を通して、自分たちを売り出してきた。でも、みんなが思っているほど自分たちのことを真面目には考えてはいなかった。自分たちを笑うことができたんだ。そうして『Achtung Baby』は、音楽ファンにとっても自分たち自身にとっても解毒剤になった。U2のイメージが、過度に神聖化された信心深くてクソ真面目なものになってきていたからね。自分たちの真の姿に肉付けをして、自分たちに自由を与える必要があった。
そういう面では、ボブ・マーリーがすごいと思っていた。ボブは、何の問題もなく、精神的なものと政治的なものとセクシャルなものを融合させることができたんだ。そんなことやってのけた人間はほかにいなかった。精神も政治もセックスも、別々の箱に分けるんじゃなくて、一緒くたにしていた。それらすべてが、彼の中でひとつになっていたんだ。
ニルヴァーナのパンク精神
ボノ: そう、まさにその通り。それに、ポップ・ソングから離れすぎてもいけない。偉大なロックンロールの中には、必ずそういう要素がある。カート・コバーンは「Smells Like Teen Spirit」をポップ・ソングだって表現していた。
ロウ: あの曲は、機能不全の痛々しい場所で書かれた残酷で攻撃的な童謡ですね。あんな曲だけれど、メロディーは夜な夜な子供に口ずさむことができる。
ボノ: そう、ギター・ソロがメロディーを奏でていて……。
ロウ: 文字通り、ヴァースのメロディーをそのまま演奏しているだけ。
ボノ: カートのお気に入りの曲は、ビートルズの「In My Life」だった。曲作りの基本姿勢は、“退屈させずにサビまで連れていって……”ということだ。つまりパンク精神だよ。これが曲作りの掟なんだ。バンドやアレンジへのアプローチ方法だけでなく、曲作りそのものがそうなっている。というわけで、僕たちU2の場合、“退屈させずにサビまで連れていく”という基本姿勢から離れて“プログレッシヴ・ロック症候群”に感染しそうになると、いつだってすごく不安になってくる。なぜなら、いつだってU2は、少なくともそういう精神のバンドだったからね。
「Until The End Of The World」と「Bad」の新アレンジ
ロウ: でも、だからこそ僕は『Songs Of Surrender』がすごく気に入っているんです。曲が正体を現す ―― そんな瞬間がありますからね。聴き手は「これは奇妙なアレンジだなあ。“Bad”っぽく聞こえない」という風に受け止める。今回の「Until The End Of The World」の奇妙なアレンジなんか、サビがなくなっている! その原因は、ジ・エッジ、あなたにありますよね?
ジ・エッジ: 僕たちの曲の多くは、風変わりなアレンジなんだ。ヴァースの次にサビが来て、続いてサビのあとのパートっていう風な古典的な構成になっていない。
ボノ: 「Bad」は、とても派手なサビだけどね。伝統的なサビとは違うっていうだけで。
ジ・エッジ: あれはすごく派手なメロディーだね。僕が思うに、プログレッシヴな姿勢というのは古典的なフォーマットに固執していない。そういうものに対して、常にオープンである必要があると思う。
ロウ: いろんな意味で、U2は抽象画家だと思います。本人たちがどう思っているかはともかくとして。
ボノ: まあ、僕たちは革新的で実験的な作品が好きなんだ。ブライアン・イーノやダニエル・ラノワと組んだりしてね。僕が言いたいのは、僕たちは曲が生まれるときにそういう基本姿勢に立ち返るということ。そしてインディーズ的なメンタリティに対しては、少し疎外感を感じていた。インディーズ的なメンタリティだと、自分の野心を白状したりする必要がないように思えたしね。とにかく僕は、曲がひょっこり姿を現し、僕の声やU2にピッタリはまるような歌になる瞬間が好きなんだ。僕がネバダを気に入ってるのも同じ理由だね。
(*後編はこちら)
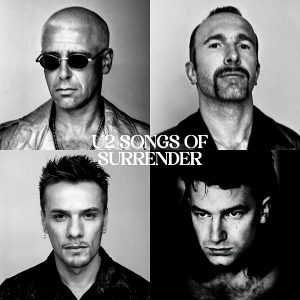
U2『Songs Of Surrender』
2023年3月17日発売
Apple Music / iTunes Store
- U2 アーティストページ
- ヨシュア”がU2を世界の頂点に導く
- U2のボノとジ・エッジ、ウクライナを訪れキーウの地下鉄駅でパフォーマンスを披露
- ウクライナ支援を求める“Stand Up For Ukraine”キャンペーンにU2が参加
- U2『All That You Can’t Leave Behind』制作秘話
- U2『Songs of Experience』解説
- 『SING/シング:ネクストステージ』はU2ファン必見の映画
- 【写真付】U2のアルバム・ジャケット写真を大解説