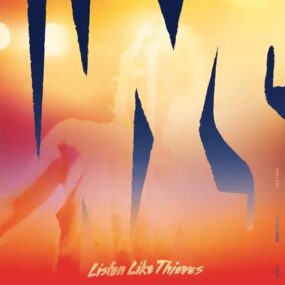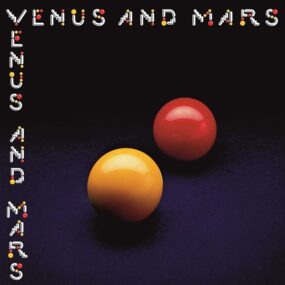Stories
エリック・ベルが語る初期シン・リジィの思い出:いきなりのヒットやライブでのエピソード


ギタリストのエリック・ベル(Eric Bell)は、アイルランドのダンス会場で伝統的な民謡やポップ・ソングを演奏するショーバンドを渡り歩く中でヴァン・モリソンのバンドに加入し、ミュージシャンとしてのキャリアを本格的に歩み出した。
だがそれから比較的間もない1969年、ベルは自らの直感に従って、フィリップ・ライノットとブライアン・ダウニーとともにシン・リジィ(Thin Lizzy)の結成に参加。エリック・ベルの特徴的な演奏スタイルは、シン・リジィと70年代前半のほかのグループを差別化する要素の一つになった。
彼は「Sarah」や「Little Girl In Bloom」といった軽やかで美しいギター・サウンドや、「The Rocker」「Mama Nature Said」といったスリリングなリフによって、フィル・ライノットの作る楽曲に彩りを加えたのである。しかし、ツアー生活による疲弊が原因となり、エリック・ベルは1973年発表の3rdアルバム『Vagabonds Of The Western World (西洋無頼)』を最後にグループから脱退した。
それから50年以上が経過したいま、ベル本人がuDiscoverのインタビューに応え、いまなお愛される先駆的なロック・バンドで過ごした当時のことを語ってくれた。
<関連記事>
・シン・リジィの“アコースティック・ミックス”が新作アルバムとして発売
本当に弾きたいようなギター
――シン・リジィに加入する前、あなたはアイルランドで人気のショーバンド、ドリームズに在籍していましたよね。脱退を決意したきっかけは何だったのですか?
ドリームズに入る前、俺はベルファストに住んでいて、昼間は仕事をし、夜はブルースを演奏する日々を送っていた。14ほどの仕事を転々としたけど、シャツ工場以外は全部クビになったよ。朝9時から夕方5時まで働くのに耐えられなかったし、責任感がまるでなかったんだ。
ドリームズでの給料はすごく高くて、高級ホテルにも泊まれたし、何もかもがプロ仕様だった。だけど、俺には”ジキルとハイド”みたいに裏の顔があった。オフの晩には家で少しばかりマリファナを吸ったり、安物のシェリー酒を飲んだり、ヘンドリックスやクリームの音楽を聴いたりしていたんだ。それなのに、ショーバンドでは「Simon Says」みたいな曲を演奏しなきゃならない。だから「ああ、俺は辞めるべきなんだ。ちゃんとした演奏がしたい」なんて思うようになった。
そんなあるとき、リハーサル室にいると、下の階でスキッド・ロウが練習をしていた。彼らは目が眩むような音楽をやっていたよ。本当に素晴らしかった。そのときゲイリー(スキッド・ロウのギタリストで、のちにシン・リジィのメンバーとなるゲイリー・ムーア)に「ショーバンドなんかで何をやっているんだ? 抜けてほかのところでやれよ」と言われたんだ。その言葉に背中を押されたのは間違いないね。
ドリームズには優れたミュージシャンが揃っていたけど、俺が本当に弾きたいようなギターは弾かせてもらえなかった。俺はある意味、囚われの身だったんだ。そのうち抜けるつもりではいたから貯金もしていたけど、腹を括るまでには少し時間がかかった。いよいよ決心を固めてマネージャーに話したら、大きな間違いだと言われたよ。あれが人生最大の賭けだったかもしれない。
フィル・ライノットとブライアン・ダウニーとの出会い
――そのあとでシン・リジィが結成されるわけですが、その経緯を教えてください。
家でぼんやりと考えていたんだ。「次は何をしよう? 外に出かけて、気合を入れてミュージシャンを探さないといけないな」ってね。それで、ダブリンの中心地にバスで出て、バーを手当たり次第に回ることにした。ミュージシャンがいないかを見て回るんだ。まともじゃなかったよ。
俺は主に、若者たちが出入りするようなグラフトン・ストリートのバーを覗いていった。店に入っていっては、若者の会話に割り込んで「ああ、どうも。いま、ベーシストとドラマーを探しているんだ」と伝えて回ったんだ。そんなやり方しか思いつかなかったのさ。そのときはまだ髪型も服装もショーバンド仕様だったから、麻薬捜査官だと勘違いされることもあった。見た目だけは品行方正な感じだったからね。とにかく心が折れそうになる経験だったよ。
エリック・リクソンのことはもともと少しだけ知っていた。俺たちは二人ともベルファスト出身だし、彼はヴァン・モリソンのゼムのオリジナル・メンバーで、トリクソンズというショーバンドにもいたからね。ある晩、俺がグラフトン・ストリートのすぐそばのザ・ベイリーというバーにいると、リクソンが入ってきて声をかけられた。「やあ、エリック。最近はどうだい?」ってね。
だから「ドリームズを抜けたところだよ」と返すと彼は「奇遇だね。俺もバンドを抜けようと思っているんだ。今夜の予定は? 酒は俺が奢るよ」と言った。それが始まりだった。それからパブが閉まる時間になると、彼が「クラブに行ってみる?」と提案してきたんだ。
ダブリンには良いクラブが7軒あって、どういうわけか――いまでもその理由は分からないけど――俺たちはカウントダウン・クラブに向かった。そのときエリック (・リクソン) がLSDを半錠くれると言うので、もらって飲んだのを覚えている。二人で会場内のバーのところに立っていると、少し変な感じがし始めた。それからバンドが登場した。俺たちにとっては予想外なことに、それはオーファネージというバンドで、演奏はすごく良かった。シンガーのフィリップ(フィル・ライノット)は、そのときはベースを弾かず歌だけを歌っていた。そして、ドラムのブライアン・ダウニーの演奏は衝撃的だった。俺はフィリップには目もくれず、ブライアンにずっと釘付けになっていたんだ。
――それから、どうやって二人にアプローチしたのですか?
彼らが休憩に入ったところで、楽屋に行って扉をノックしたんだ。中にはフィリップとブライアンしかいなくて、ベーシストとギタリストは酒をもらいにバーへ行っていた。「何か用かい?」と二人に声をかけられると、俺は笑いが止まらなくなってしまった。それを見た彼らは「大丈夫か?」と聞くので、俺は「ああ、LSDで初めてトリップしているんだ」と返した。俺はそんなことをしなさそうな外見をしていたから、二人とも信じられない様子で俺のことを見ていたよ。
俺がベーシストとドラマーを探していると伝えると二人は、ミュージシャンがたくさん集まるザ・ゾディアックという店に行くといいと勧めてくれた。だから感謝を告げて出て行こうとすると、フィリップに呼び止められたんだ。
それがすべての始まりだった。「なあブライアン、エリックとグループを組むのはどうかな?」と彼は言い出した。でもブライアンは乗り気じゃなかったようで「いや、オーファネージを続けた方がいい。決まっているライヴもいくつかあるしさ」と言った。だから俺は「確かに、それはもっともだね」と言って出て行こうとした。すると、フィリップがまた俺を呼び止めて「いいじゃないか。エリックとバンドを組もうよ」と言ったんだ。そうしたら今度はブライアンも「分かった。やってみよう」と返したってわけさ。
シン・リジィの結成
――フィリップの才能に気づいたきっかけは何かありましたか?
彼が自作曲のテープを持って俺のアパートに来たことがあった。聴かせてもらうと素晴らしい出来で、「Dublin」や「Chatting Today」もその中に入っていた。その瞬間、こいつは本物だ、と確信したよ。疑いの余地はなかった。初めて彼の曲を聴いたときから、俺のギターが入る想像がついた。それは、曲がメロディアスだったからだ。
実際、フィリップにはときどき「お前のギターはメロディアスすぎる」と言われたものだよ。ショーバンドにいたせいか、俺のプレイにはロックのギタリストには珍しいような軽やかさがあったんだ。俺は3つのショーバンドを渡り歩いて、合計で6年くらいアイルランドの音楽を演奏していた。だからブルースやロック、ときどきジャズをやるようになったあとも、ショーバンド時代のクセが抜けていなかった。それが俺のプレイの特徴にもなったんだ。
みんなで練習をし始めると、エリック・リクソンがキーボードで加わった。俺は最初から3ピース・バンドとして活動したかったんだけどね。それはともかく、ダブリン界隈での俺たちの人気は急速に高まっていった。ある会場でライヴをやって、6週間くらいしてまた同じ会場に演奏しに行くと、今度は道に人だかりができている――そんな感じだったんだ。
俺とフィリップはクロンターフのキャッスル・アヴェニューで共同生活を始めた。そのうちお互いの恋人も一緒に暮らすようになって、そのあとエリック・リクソンも転がり込んできた――そのときすでに彼はバンドを抜けていたけどね。その辺りは高級住宅街だったから、俺たちが白い目で見られたことは想像に難くないと思う。でもみんなで一緒に住んでいなかったら、毎日練習をするお金もなかっただろう。ブライアンは実家暮らしだったけど、毎日俺たちの家に泊まって曲作りをしていたから、一緒に住んでいるも同然だった。
――フィリップはどんな同居人でしたか?
彼はすごく優しい男だし、一緒にいて楽だった。でもすごく頑固で、エネルギーに満ち溢れてもいた。やると決めたらどこまでも突き詰めるタイプだったな。「これからどうなりたい?」と誰かに聞かれると彼はいつも「金持ちで有名になりたい」と言っていた。そればかり口にしていたし、その点については口を挟む余地もなかった。
フィル・ライノットとの作曲プロセス
――あなたはどのようにして、彼の作曲プロセスに関わっていくようになったのでしょうか。
俺はソファに座っていることが多くて、フィリップの寝室は下の階にあった。ときどき彼は、マリファナか紅茶を持ってこっちに顔を出すんだ。そのときに俺がアコースティック・ギターを弾いていると、彼は「それってきみの曲かい?」なんて声をかけてくる。すると俺は「いや、これはバーズの曲だよ」とか「ディープ・パープルだよ」とか返すんだ。でも俺が自作のフレーズを弾いているときは、「ちょっと来てよ」って彼に言われて、彼の寝室に二人で下りていく。そしてそれぞれのアコースティック・ギターを持って、二人で腰を下ろしてその曲を形にしていくんだ。場合によっては、それにかなりの時間がかかることもあったな。
ほかにも彼が「こんなリフとこんなコードを考えたんだけど、ここからどう進めればいいか分からないんだ」なんて言ってくることもあった。すると俺は頭をフル回転させて、何か浮かんでこないか試してみるんだ。独創性が求められるから、あれこれ考えるのは面白かったよ。しかも、その曲に合えばどんなものを加えたっていいんだ。「The Rocker」もそんな風にして一緒に作った曲の一つだね。俺たちがほかのグループより早く人気を得たのも、一つには共同生活をしていて毎日曲作りが出来たおかげだと思う。
俺たちはもともとザ・ローリング・ストーンズの「Street Fighting Man」とかを演奏していたけど、少しずつ少しずつ、オリジナル曲をセットリストに入れるようになった。それからフィリップは、パフォーマンスのスタイルを確立し始めた。ベースの先端を観客の方に向けるようになったのも、ただでさえ長い脚に細身のジーンズを履いて人目を引くようになったのもそのころのことだ。俺とブライアンもそれなりの外見になった。俺も髪を伸ばすようになったし、ブライアンの服装も変わっていったんだ。そうやってグループが変化していった。
ダブリンからロンドンへ
――そのあと、1971年にロンドンに拠点を移しましたね。カルチャー・ショックはありましたか?
控えめに言っても衝撃的だったよ。最初はロンドンに順応できなかった。観客も夜の街もアイルランドとは大違いだったんだ。故郷に帰りたいと何度も思ったよ。フィリップはロンドンに適応していたし、ブライアンも俺よりは馴染んでいたけどね。しかもすごい数のグループがいて、競争が信じられないほど激しいんだ。
マネージャーは、ロッド・スチュワート、ステイタス・クォー、T・レックスみたいなアーティストのサポートの仕事を取ってきてくれるようになった。当時俺たちはアイルランド屈指のグループだったと思うけど、ロンドンでは誰にも知られていなかった。だから、一からやり直さなきゃいけなかったんだ。俺たちが舞台に出ていくと、観客の半分は去っていってしまう。みんなヘッドライナーを見たくて来ているからね。しばらくはそれに耐えなきゃいけなかったけど、そのうちライヴに対する自信がついてきた。そのあと、ドイツ、日本、スウェーデン、デンマーク、フランスでも演奏したよ。どの国に行くのも、俺たちにとってはまったくもって新鮮な経験だった。
でもあのころは私生活で色んなことがあって、俺はボロボロの状態だった。それなのにマネージャーは休みなくライヴを入れていて、中には本当に嫌になるような会場もあったんだ。ある晩、ライヴを終えたあとフィリップがベースを床に放り投げて、膝を抱え込んでしまった。そこへツアー・マネージャーが入ってきて、「おい、どうしたんだ?」と聞いた。それに対してフィルは「どうやったらこんな日々から抜け出せる?毎晩のように高速道路を行ったり来たりするわりに、半分は出る価値すらないような会場じゃないか」と言ったんだ。するとそいつは「ヒット・レコードを出せばいい」と捨て台詞を残して出ていった。だから俺たちは座ったまま、「でも、それって一体どうやればいい?」って呆然としていたのさ。
アイルランドの古い民謡「Whiskey In The Jar」
――最初の二作のアルバムは質が高いにも関わらずヒットには繋がりませんでしたが、そのあとで「Whiskey In The Jar」がヒット・シングルになりましたよね。
あれで俺たちの人生は変わった。それは断言できるね。だけど、あれも単なる偶然だったんだ。思えば、シン・リジィのすべてがタイミングに左右されていたように思えるよ。例えば、フィリップとブライアンに会ったあの晩も、俺はあちこちを歩き回って過ごしていたかもしれない。そういう瞬間がいくつかあったんだ。
ある日、俺たちはデューク・オブ・ヨークというところで練習をしていた。一週間に一回、そのパブを使っていたんだ。そこである曲を試してみたんだけど、まるでうまくいかなかった。だから荷物を纏めて帰ろうとしていると、フィリップが口を開いた。「ダメだ。お金を払ってここを借りているんだから、その分の元は取らないと」ってね。それから彼は、色々な曲を演奏し始めた。ベースを肩から下ろしてギターを担いで、ふざけ半分に古くさい曲を歌い出したんだ。その流れで彼が茶化すように歌い始めたのが、あのアイルランド民謡だった。
俺もギターでそれに加わって、ブライアンもドラムを叩き出した。するとドアが開いて、マネージャーのテッド・キャロルが入ってきた。俺が使う新しいギター・アンプを持ってきたんだ。俺たちが手を止めてアンプの話をし始めると、彼がいきなりこう言った。「ところで、俺が入ってくる前にやっていた曲は何?」とね。そのとき俺たちはアンプに気を取られていて、彼の言葉をまるで聞いていなかった。すると「次のシングルのレコーディングはいつだっけ?」と彼が聞いてきて、そのあとはこんな風に会話が続いた。
「6週間後くらいかな」
「A面の曲はもう決まっているの?」
「ああ、“Black Boys On The Corner”だよ」
「じゃあB面は?」
「まだ決まっていないかな」
「さっきやっていた曲は何?」
それに対してフィリップが「あれが何だっていうんだよ。“Whiskey In The Jar”さ。遊びでやっていただけだ」と言うと、マネージャーは「あれを録音するべきだ」と返してきた。彼を窓から放り出してやろうかと思ったよ。「Whiskey In The Jar」から逃れるためにアイルランドを出たのに、その曲をレコーディングしろって言うんだからね。
――そこから何があったのでしょう?
6週間後にスタジオに入ってレコーディングをすると、「Black Boys On The Corner」はかなり良い仕上がりになった。それで「よし、じゃあB面はどうする?」ってみんなで考えているところに、マネージャーがまた、あの曲はどうかと提案してきた。だから俺たちは「分かった。もう二度とあの曲のことを口にしないと約束するなら、試してみるよ」と譲歩したんだ。
そして、俺とフィリップがそれぞれにアコースティック・ギターを弾き、ブライアンがドラムを叩き、フィリップが仮のヴォーカルを歌った。その録音を聴いてみると、特別な曲になりそうだとみんなが口を揃えて言った。フィリップは「ベースを足さないといけないな」と言ったんだけど、何かよく分からない理由で「いや、ベースは入れないままにしよう」という話になったんだ。
リード・ギターに関しては、何を弾けばいいかまるで分からなかった。何パターンか試してはみたんだけど使い物にならなくて結局、俺は曲のカセットを持ち帰ることにしたんだ。そのまま、俺たちはライヴ活動を再開した。その3、4日後、俺たちはウェールズからロンドンへと長距離移動をしていた。車中ではいつもフィリップがロックとかクラシックとかブルースとかジャズとか、多種多様な音楽のカセットをかけていたんだ。
その晩、彼はチーフタンズのカセットをかけ始めた。俺は疲れて酒に酔った状態で後部座席に座っていたんだけど、車の前方から聞こえてくるその音楽を心から楽しみ始めた。そのとき、イリアン・パイプス(バグパイプの一種)の音を真似るのはどうかと思い付いたんだ。それでその夜、家に帰ってAマイナーのコードとイントロを考え出した。大体一時間くらいでアイデアが形になったと思う。あとは、リフを考えるだけだった。
そのころ、みんなは俺がスタジオに現れるのを待ち続けていた。全員が俺にプレッシャーをかけてきていたんだ。そこで俺は、売れ線を狙うことにした。ビートルズや、ストーンズ、フリー、ディープ・パープルといったバンドはどれも、曲の中でリフを何度も繰り返すだろう(と言ってベルは「Satisfaction」と「Day Tripper」のリフを歌う)。
俺もそういうものを作りたかったんだ。普段はアドリブで演奏することが多かったけど、このときは「いや、今回は正攻法でいくんだ」と自分に言い聞かせた。最終的にリフを形にするまでには、さらに10日ほどかかったよ。だけどそのあとソロを考えるのはさほど難しくなかった。そうして、俺は用意された車でスタジオに向かった。あとは機材の準備をして、演奏するだけだった。
「Whiskey In The Jar」の大成功
――この“Whiskey In The Jar”は当初ヒットしませんでした。そのときの皆さんの反応はどうでしたか?
フィリップは「クソみたいなこの“Whiskey In The Jar”は録音すべきじゃないと言ったよな。“Black Boys On The Corner”をA面にするべきだったんだ」と苛立っていたよ。俺たちは、このシングルは失敗だったと切り捨てて、忘れようとしていたんだ。
そのときはドイツにいたんだけど、ライヴはうまくいかないし、俺たちは働きすぎで疲弊していた。バンドは解散寸前の状態だったんだ。そんなある朝、俺たちがどこかのホテルで朝食をとっていると、マネージャーがやってきて「みんなおはよう。ロンドンから電報が届いたぞ」と言った。それを開けて読んでみると、そこには「おめでとう。“Whiskey In The Jar”がイングランドのチャートで22位に入った。ドイツでのライヴを全部キャンセルして帰国するように」とあった。
そしてその数週間後、マネージャーに「信じないだろうが、”Top Of The Pops”に出ることになった」と言われた。俺は「冗談だろ」と返したよ。あの曲は11週くらいチャートに入って、最後には6位まで上昇したんだ。
――そうした成功はバンドにどんな影響を与えましたか?
困ったことに、フィリップはすっかり有頂天になっていた。成功に目が眩んで、現実感を失っていたんだ。ブライアンも成功を喜んでいたけど、彼はある程度冷静に状況を見ていた。一方で俺はその状況をどう捉えればいいか分からなくて、ひどく落ち込んでしまった。”Top Of The Pops”に出たんだから、浮かれていてもよかった。それなのに、俺は惨めな気持ちになっていたんだ。
――ですがそのあと、名作と評価されている3rdアルバム『Vagabonds Of The Western World』をリリースしましたよね。
俺たちの1stアルバムは、同じ年にリリースされた中で一番無名な作品と言っても過言じゃなかった。あのアルバムのツアーでアイルランドに凱旋したときも、店に並んですらいなかったんだ。フィルは憤慨していたよ。「この1stアルバムのプロモーションのためにアイルランドまでツアーをしに来ているのに、店にすらないなんて」ってね。
そのあと俺たちは2ndアルバム『Shades Of A Blue Orphanage』(1972年)を制作した。このアルバムも、誰にも支持されていないみたいだった。いまになって改めて聴くと、初期のシン・リジィは独創性に溢れていたんだと思えるし、最初の2作にも良い瞬間はある。それは間違いないよ。
『Vagabonds…』のころになると、俺たちはグループとして成熟し始めていた。それなのに俺たちは、十分なプロモーションができなかった。だからイギリスの批評家たちには相手にされなかったんだ。「アイルランド出身の3ピース・バンドである彼らは、いまだに方向性を定められないでいる。収録曲に纏まりがない」とか、「彼らもいつかは自分たちのスタイルを確立できるだろう。とはいえ、悪いアルバムではない。諦めず頑張れ、若者たち」とか、そんなことを書かれたよ。当時の俺たちへの評価はそういう感じだったんだ。
チャス・チャンドラーからのきつい言葉
――一方でこのころ、ライヴ・バンドとしての自信を深め始めてはいましたよね。何が変わったのでしょうか?
スレイドとスージー・クアトロとのツアーをやったころから変化が起こり始めた。ある意味では、それが”終わりの始まり”だったんだ。ツアー初日の会場に入ると、そこは公会堂だった。収容人数200人程度のクラブと違って、そこは3,000人が入れる巨大なホールだったんだ。俺たちにとって、そういう場所で演奏するのは初めての経験だった。
ステージに上がってスレイドの機材を見てみると、「こいつらは本物だ」という感じがした。俺たちはてっきり、ポップ・グループと一緒になってしまったと思っていたんだ。そのあと初日の晩に直接対面してみると、彼らはすごく感じの良い連中だった。
会場は満員で、フロアは人で溢れかえっていた。観客たちはマフラーを掲げて「You’ll Never Walk Alone」なんかを合唱していたよ。俺とフィルが出番前に通路で話をしていると、ベースを持ったスージー・クアトロが泣きながら俺たちの横を走り去っていった。大袈裟じゃなく、会場は暴君ネロの時代の闘技場のようだった。
自分たちの出番が来ると、俺たちは小規模なクラブでやっていたのと同じようなライヴをやった。突っ立ったまま演奏したんだ。すると観客はブーイングを始めて、ビール缶をステージに投げ始めた。そしてその一つがフィルのベースに当たった。彼は「何だっていうんだ。俺たちだって一生懸命やっているんだ、チャンスをくれよ」と食い下がったけど、しまいには「スレイドを出せ」の大合唱が始まってしまった。
それがどれだけ待ってもやまないので、俺たちはステージを降りなければいけなかった。誰も気にかけていなかったよ。楽屋に引き上げたあと、俺たちは何も言葉を交わせないでいた。するとその瞬間、扉が勢いよく開いてチャス・チャンドラーが入って来た。彼は「さっきのは一体何だ?」と詰め寄ってきたけど、俺たちは一言も返せなかった。だから彼は「お前らは観客の目を覚まさせるためにいるんだ。眠たい気分にさせるためじゃない。うまくやれないなら、帰ってもらうことになるぞ」と言って、ドアをピシャリと閉めて出ていったんだ。
フィリップにとってチャス・チャンドラーは、憧れのジミ・ヘンドリックスのマネージャーを務めていた人物だ。そんな人にまったくの役立たずだと言われた辛さは想像に難くないと思う。ツアーが再開すると、俺たちは見応えのあるライヴをしなきゃならないという凄まじいプレッシャーに晒されることになった。だからスローな曲をセットリストから外して、ロックに徹することにした。それが事の経緯だよ。
バンド脱退の理由
――あなたがグループを離れることになったのはなぜだったのですか?
俺はひどい憂鬱に悩まされていて、精神安定剤を飲んだり、ウィスキーを飲んだり、マリファナを吸ったりしていた。そういうものをいっぺんに摂取していたんだ。気分が落ち込むせいで酒の量が増えて、それが段々エスカレートしていった。そのあとでマリファナを吸うようになって妄想を抱くようになり、さらに酒を飲むようになった。当時の俺はそんな具合で、悪い流れを断ち切れなかった。
そして故郷のベルファストにあるクイーンズ大学でのステージが、俺の最後のライヴになった。俺は完全に酩酊状態だったんだ。その一つの理由は、会場に着いたとき、俺のほかに誰もいなかったことだった。機材もローディーも到着していなかったんだ。すると、ある男が俺の方にやって来て、楽屋へ案内してくれた。これについていったのが大きな間違いだった。
その部屋の真ん中には布のかかった大きなテーブルがあって、その下にはもちろん、思い付く限りのあらゆる酒が置いてあった。俺は「よく聞け、落ち着くんだ」と自分に言い聞かせたけど、ご想像の通り、1時間後には何も覚えていないほど酔っ払ってしまった。
出番が来たときはすでに、自分が誰かも分からないし、何を弾いているかも分からない状態だった。完全にゾンビのような状態でステージに上がったよ。演奏が始まっても、俺は何も弾けなかった。曲のコーラス・パートさえ思い出せなかったし、リード・ギターのフレーズも思い出せなかった。ソロを弾いたのかも、何の曲の最中なのかも分からない状態だったんだ。会場には1,000人の観客がいたけど、そのうち頭の中で声が聞こえ始めた。「いますぐここを出ろ」とか「お前はもう死んでいる」とかね。
じきにその声は消えたけど、演奏を続けているとまた聞こえ始めるんだ。最終的に、俺はギターを空中に放り投げた――ありがたいことに、いまでもそのギターを弾くことができているし、いまでは罪を償えたつもりだ――。それからアンプを全部ステージから蹴落し、よろよろと歩き出した。そして俺は、舞台の下に積み上げられていた運動用のマットの上に落下した。
するとツアー・マネージャーのフランク・マレーがステージの下を這ってきて「早く舞台に立って、このライヴを終わらせろ」と言った。だから「俺はおしまいだ。これで終わりだ、終わったんだ」と返した。それでも彼らは俺の両脇を抱えて立たせ、ステージへの階段を歩かせて、ギターを持たせた。チューニングは完全に狂っていたよ。ゾッとするような光景だったと思う。それ以外のことは何も覚えていないな。
――シン・リジィの一員だったころのことについて、いま振り返ってどう感じますか?
俺は時間をかけて当時のことに向き合えるようになって、自分の頭の中で折り合いをつけてきた。当時はとにかくああいう時代だったんだってね。でも一つ忘れちゃいけないのは、音楽業界は時としてすごく恐ろしい場所になり得るということだ。
俺は完全に更生したし、年を重ねる中であのころみたいな生活を続けられるはずはない。いまではギネスを1パイントだけ飲んで、ステージで演奏を楽しむことができるようになった。観客の前でギターを弾くのがいまでも大好きなんだ。それに、これだけの時間が経って、若い人たちがリジィの最初の3作のアルバムを聴くようになっているなんて信じられないような話だ。しかも、当時俺たちがやっていたことをすごく褒めてもらえるんだ。そうすると「その通り。俺たちは良いバンドだったんだ」なんて思えるのさ。
Written By Jamie Atkins
エリック・ベルが参加した初期楽曲のアコースティックアルバム

2025年1月24日発売
CD(1曲多い限定版) / LP