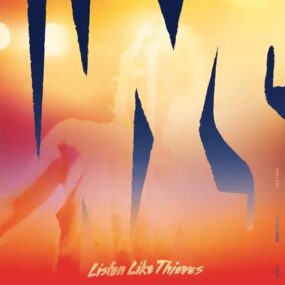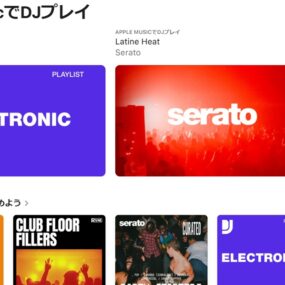IN-DEPTH FEATURES
ロックは死んだ?そんなことを言うのは本気で聴いていない人間だけ


ロック・ミュージックは死んだのか? どうもメインストリームの音楽メディアは毎年、ロックに弔いの鐘を鳴らしたくて仕方ない様子だ。“ロックは死んだ。ありがたや”と大見出しは絶叫する。“ロックン・ロールは死んだ。いや、今度こそ本当だ”とオオカミ少年たちは言う。けれど来る年も来る年も、彼らの主張の裏付けとしては同じ証拠が示されるばかりで、結局のところ問題の核心に迫る結論は一度も出されたことがないのだ。
最初に槍玉に挙げられるのは古参のアーティストたちだろう。彼らは今より若返ることは決してないわけで、ボックス・オフィスでは相変わらず圧倒的観客動員数を誇っていても、現状のまま永遠に活動を続けられるわけではない。すると当然のことながら、もっと若い世代で簡単に大勢の客を呼べるロック・アクトはどうか、という話の流れになってくる。となると、単独でアリーナを埋めることのできるであろう若手有望株に、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ、ブラック・ストーン・チェリーやトゥエンティ・ワン・パイロッツ等々、はいるものの、彼らがフェスティバルのヘッドライナーを務めるような別格の存在になれるかは未だ不透明なのだ。
[layerslider id=”0“]「玄人」の言い分
時にはその道の権威が口を挟んで来たりする。業界の“玄人”たちが、ロックは死んだか否かの議論に多少なりとも重みを加えようと、自らの個人的な考えや意見をぶつけて来るのだ。ミュージシャンたちはロック・バンドが皆いかにして昔の常套句的なリフや使い古されたアイディアを使っているかを語ることで、それを何とか切り返す。しかし結局のところ、彼らこそが船の進路を変えさせ、行く手にある氷山にぶつからないようにすることのできる立場にいるのではないのだろうか?
だが2017年、音楽は変わった。アメリカのニールセン社[訳注:TV視聴率等の調査統計の最大手]の調査によればこの年初めて、ヒップホップとR&Bがロックを抜き、最も消費力の活発なジャンルになったのである。アルバム・セールスとダウンロード数、オーディオ/ビデオのストリーミングを踏まえると、年間トップ10でヒップホップでもR&Bでもないアーティストはエド・シーランとテイラー・スウィフトの2組だけだ。これらのジャンルの躍進には、アメリカのオン・デマンドのストリーミング・サービスも一役買っているとみられる。

自滅の道とは遥か縁遠く、メタリカは2017年度の年間ベスト・パフォーミング・ロック・アーティストに輝いたロック・バンドとなった。写真:Herring & Herring
同時に、この統計で判明したのは、メタリカが2017年度のベスト・パフォーミング・ロック・アーティストとなったことで、彼らは2016年のアルバム『Hardwired… To Self-Destruct』のリリースの勢いを駆り、スラッシュ・メタルの歴史的名盤『Ride The Lightning』や『Master Of Puppets』をはじめとする、過去の作品を新たなパッケージ形態で内容を充実させたリイシュー盤を立て続けにリリースした。こうしたバック・カタログの再発売も、彼らが息長く活動していることの賜物だろう。何故なら言うまでもなく、ロックの真の強みはアルバム・セールスにこそあるからだ。
マイケル・ジャクソンは今も『Thriller』で、アルバム売り上げカテゴリーでの推定6,600万枚という空前のセールス記録によって、全ての年代を通じてNo.1の座を守り続けている(ベスト・アルバムを除く)。しかしながらそれ以外にも、4,000万枚を突破したアルバムはイーグルスの『Their Greatest Hits (1971-75)』に『Hotel California』、AC/DCの『Back In Black』、ピンク・フロイドの『The Dark Side Of The Moon』、ミート・ローフの『Bat Out Of Hell』、そしてフリートウッド・マックの『Rumours』があり、ホイットニー・ヒューストンとビー・ジーズもアルバム単体で4000万枚の壁を超えた実績を持つ二組である。
もう少し深く掘ってみよう(Dig a little deeper)
だが、これらロックに特化したアルバムはいずれも70年代にリリースされた作品であり、要は売上枚数を稼ぐのに40年以上の時間があったのだ。レコード・セールスは自由落下の放物線を描き、チャートの順位はストリーミングのデータやラジオのエアプレイでしかテコ入れしようのない今の時代、ロック・ミュージックにとって、状況は何とも厳しいものがある。だがもう少し深堀りすれば、地面の下からは年老いた犬の心臓がまだまだ強く鼓動していることを伝える地響きが確かに聴こえるはずだ。
イマジン・ドラゴンズがよい例である。2018年8月、ラスヴェガスを拠点に活動する4人組は、全米ロック・ソングス・チャートにおいて、バンド史上初めて1位から4位までのTOP4すべてを独占した、という記録を作った。しかもこれは一度では終わらなかったのである。彼らの最新シングル「Natural」は発売第一週目に第4位で初登場したが、3位から上に並んでいたのはいずれも彼らがそれ以前に最新アルバム『Evolve』からシングル・カットされた楽曲「Thunder」 「Whatever It Takes」 そして「Believer」であり、その3曲ともそれぞれに22週、17週、19週とNo.1の座を守り続けていたのだった。
彼らは長い下積みの末に成功を掴んだバンドである。2008年、ユタ州のブリガム・ヤング大で学んでいたフロントマンのダン・レイノルズが、ドラマーのアンドリュー・トルマンと出逢ったのを機にバンドを結成した二人は、その後ギタリストのウェイン・サーモンとベーシストのベン・マッキーを引き入れ、2009年から3作のEPリリース経て、2011年に大きなチャンスが巡って来た。だが、このエレクトロ・ロック・バンドが本格的に注目を集めたのは2014年、シングル「Radioactive」がブレイクし、実に18ヶ月にわたって全米HOT100を出たり入ったりした挙句、グラミー賞のベスト・ロック・パフォーマンス部門で最優秀アーティストに輝いてからのことである。
現在までに3枚のアルバムを出しているイマジン・ドラゴンズは、ロックとエレクトロ・ポップとR&Bそれぞれの中間点に座っている。時にポップ色の強いサウンドが持ち味の彼らを、ロックの偉大なるレジェンドの正当な後継者として認めるに相応しいかどうかには異論もあるだろう。だがそれを言うなら、ボン・ジョヴィが80年代半ばから後期にかけて、頻繁にシングル・チャートの上位を賑わせていたり、U2がはばかることなく、シンセ偏重のポップ・サウンドに挑戦したりしていたように、ロックは昔から絶えず片足をシンセサイザーの世界に突っ込み、よりラジオ志向のサウンドを模索したいという衝動を持っていたのである。このアプローチは60年代に「Love Me Do」から変わり種の「I Am The Walrus」、大ヒット曲「Back In The USSR」まで、そのキャリアの中で様々な影響を分け隔てなく自分たちの音楽に昇華させてきたザ・ビートルズまで遡ることができる。
イマジン・ドラゴンズをロックのハイブリッド・サウンドと呼ぶかどうかはさておき、それが彼らを世界中のアリーナに打って出る原動力になっているのは紛れもない事実である。そして、ともすれば会場が大きくなるにつれ、ファンはバンドとの距離が離れてしまったように感じるものだが、彼らはいまだに音楽を介し、リスナーたちとパーソナルなレベルでの繋がりを失くさずにいる。恐らく、その共感レベルこそが、このネバダ州出身のロック・バンドに息の長い活動が期待できる要因である。結局のところ、一番最後まで永らえるのは間違いなくじわじわと燃え続けるタイプなのである。
シェイクダウン・スペシャル(Shakedown Special)
もう少し肝の据わったところを挙げるなら、2000年代初期から半ばにかけて、ブラック・レベル・モーターサイクル・クラブのようなガレージ・ロッカーが偉大なる救い主だと思われていた頃を想起させるタイラー・ブライアント&ザ・シェイクダウンだろう。彼らが活動拠点として選んだテネシー州ナッシュビルらしい伊達っぷりも見受けられながら、ブライアントとその仲間たちの由緒正しさと彼らの積み上げてきたキャリアの軌跡は、ちょっとやそっとでは折れない持久力を示している。
ブライアントがロックの偉人たちの系譜に入る運命を自覚したのは6歳でギターを手にし、酸いも甘いも噛み分けたベテラン・ブルーズマンのルーズベルト・トゥッティを師匠と仰いで教えを受けた時だった。幼いブライアントは早々に才能を開花させ、ギター界のレジェンド、エリック・クラプトンの目に留まり、その招きによって2007年、まだ15歳だった彼はシカゴで行なわれたクロスロード・フェスティバルのステージで演奏を披露したのである。
ザ・シェイクダウンが結成されたのは、17歳になったブライアントが生まれ故郷のテキサス州ハニーグローヴからナッシュビルへと拠点を移してからのことだった。引っ越して一週間目に、シンガー兼ギタリストはドラマーのケイレブ・クロスビーと出逢って意気投合し、現在のバンドの基礎が出来あがった。その後、ギタリストのグレアム・ウィットフォード(エアロスミスのギタリスト、ブラッドの息子)と知り合った二人は、故郷のボストンからナッシュヴィルへ移って来るよう彼を説得し、更にベーシストのノア・デニーがラインナップに加わった。
サザン・ロックとブルーズ、ルーツ・ロックの濃密な融合である彼らの音楽を引っ提げ、タイラー・ブライアント&ザ・シェイクダウンは昔ながらのやり方でその基盤を固めている。つまり過酷なツアーである。彼らのライヴ・デビューはアマリロでのREOスピードワゴンの前座で、以来AC/DC、エアロスミス、BBキング、ジェフ・ベック、そしてZZトップといった錚々たるメンツと同じステージに立ち、ガンズ・アンド・ローゼズの『Not In This Lifetime… 』ツアーでも数日間のオープニング・アクトに抜擢された。このバンドはハード・ロックの大物たちと肩を並べ、互角に渡り合っていくだけの器量を持っているのだ。
タイラー・ブライアント&ザ・シェイクダウンのように特定のジャンルに当てはめることが可能なバンドがいる一方で、全くの突然変異的なグループも存在する。そのひとつがブロークン・ウィット・レベルズだ。彼らのバンド名をそのままタイトルにしたデビュー・アルバムを一聴して鮮明に浮かぶイメージはつばの広いカウボーイ・ハットとカウボーイ・ブーツだが、オープニング・トラックの 「Loose Change」は、いかにもナッシュヴィルのいかがわしい場末のバーで、BGMにかかっていそうな雰囲気を持っている。一方「Shake Me Down」には、ジョージアやミシシッピ辺りで育った人間にしか生み出せないようなソフトなサザン・グルーヴがある。
さらに、彼らの歌詞はそういったイメージを強めるばかりだ。例えば「Snake Eyes」には、
Here in the south/Where the river runs dry/I’m gonna hang from the noose, baby/If you tell me no lie
ここ南部は/川も干上がっちまう/俺は縛り首だぜ/お前が俺にウソをつかなければ
とある。これを歌うブルーズ・ロッカーたちが南部以外の出身であるはずもないという地理的不文律が感じられはしないだろうか?その意味では、フロントマンのダニー・コアがイングランドのバーミンガム出身のペンキ塗りと内装を手掛ける職人だったという事実に驚く人々は少なからずいるに違いない。
2013年に結成されたブロークン・ウィット・レベルズは、自らを兄弟同然のバンドだと語る。コアとベーシストのルーク・デイヴィスは小学校時代からの友人であり、二人は内装業者として働くかたわらバンド活動を始めたのだった。また、サザン・ロックのヴァイブにとどまらず、ギタリストのジェームス・トランターが持ち込んだブルーズとハード・ロックの影響に加え、彼が愛聴するジミ・ヘンドリックスやジミー・ペイジ、エリック・クラプトンにオアシスといったメインストリーム的センスも持ち合わせている。実際に、彼はそうしたアーティストたちに触発され、大学で音楽を専攻して優秀学位を取得した。
しかし、このミッドランド出身のロッカーたちには、うわべだけのサウンドに留まらない深みがある。彼らの醸し出すソウルフルなクオリティは、単なる猿真似で作り出せる類のものではない。ソウルというものは譜面を通して身につけられるものではなく、その体内から湧き上がるものなのだ。そしてもうひとつ、内から湧き起こるものと言えば、バンドとして大きな成功を手にしたいという不撓不屈の決意であり、彼らはそのために日銭を稼ぐ仕事を辞めて、自分たちの名前と音楽を聴いてもらうことが保証されている唯一の場所であるツアーに出た。
しかしながら、一体彼らの実力とはどれほどのものなのか?このバンドが自称するところを信じるなら、彼らは素晴らしいに違いない。だが彼らがそれを口にする時、そこにはひとかけらのエゴも高慢さも感じられない。これは自分たちは何か良いものを作り上げようとしているという自覚を持ち、それを実行するために、更なる努力を重ねる意志を固め、果てしないツアーを通して、そのことを証明しつつあるバンドの断言なのだ。最もそれは、彼らが飽くなき音楽への情熱を持て余している時の話だが、彼らは2枚目のアルバムのレコーディングを、デビュー・アルバムのリリースから僅か一年足らずで終わらせた。彼らのその小僧的なルックスと、ツアーで実際にプレイしている音楽との間にはかなり大きなイメージの乖離があるかも知れないが、それはつまり彼らの音楽が本来生まれるべきところ、魂から来ているという何よりの証拠だろう。まして、キングス・オブ・レオンを思い起こさせる商業的なセンスまで持ち合わせているとするならば、同様の規模での成功が期待できるだろう。
天職(Born To Do It)
商業的センスを群を抜くためのひとつの基準とするなら、生まれながらに優れたソングライティングの才能に恵まれているかのような若者たちも目につく。その中のひとりがナッシュビル生まれのジャレン・ジョンソンで、彼がキース・アーバンやティム・マッグロウ、ジェイク・オーウェンといったカントリー界のスーパースターたちのヒット・シングルを手掛けていない時にフロントマンとして率いているのがザ・キャディラック・スリーである。80年代のカントリー・グループ、バンダナのドラマーだったジェリー・レイ・ジョンストンの息子として生まれた以上、その将来は運命的だった言っても過言ではないのかも知れない。
ジョンストンはアメリカン・バングというバンドでそのキャリアをスタートさせている。ワーナー・ミュージックと契約を交わし、2枚のスタジオ・アルバムとシングル 「Wild And Young」で僅かながらチャートを賑わせるなど、グループとしてはそれなりの成功を収めた。その後バンドが解散を決めると、ジョンストンは高校時代の友人で、アメリカン・バングでバンド仲間だったケルビー・レイとニール・メイソンと共に、後にザ・キャディラック・スリーとなるバンドを結成する。そして、高い実績を持つ彼ら(メイソンはジェイク・オーウェン、ケリー・クラークソン、ラスカル・フラッツといったアーティストたちに楽曲を提供していた)の手によって、続々と楽曲が作り出されていった。
ザ・キャディラック・スリーにとって、カントリーとサザン・ロックは、カウボーイブーツとそれを履く足のように、しっくり馴染むものだった。結果として生まれた音楽は、ベランダであおるウィスキーのように即効性があり、そのヴァイブが歌の内容にも浸透している。サザン・ロックの三種の神器(ウィスキー、女、そして南部出身であるということ)から大きく逸脱することはあまりないが、まるで穿き古したジーンズのように、過去何十年にもわたって受け継がれててきた懐かしのスタイルであり、それがこの上なく心地良いのである。
まるで顔ぶれを刷新した21世紀版レイナード・スキナードやオールマン・ブラザーズ・バンドのように、ザ・キャディラック・スリーは大西洋を股にかけてただひたすらギグをこなし続けることに没頭してきたバンドである。2015年、彼らはある週の金曜日のアメリカでのライヴ後、そのまま土曜日に行なわれるダウンロード・フェスティバルに飛行機で向かった。更にそこで自分たちのセットを終えた後、再びアメリカにとって返し、日曜日には別のフェスでプレイしたのである。
彼らは決してロックンロールを立て直そうとしているのではない。そもそも壊れてもいないものを何故直す必要があると言うのだろう? ケルビー・レイは彼らの音楽にある誠実さが、ファンとバンドを結び付け、多くの人々を惹きつける最大の武器であると主張する。彼らはいつでもありのままに思いの丈を伝えるのだ。結局のところ、そもそもロックン・ロールの本質とは、どんな時も楽しもうということだったのではないだろうか。
最新アルバム『Legacy』では、タイトルが語る通り、彼らは音楽に対して自分たちが何を残せるか、何をもって記憶されるかという観点でアプローチしている。そして、卓越した2人のソングライターを擁するザ・キャディラック・スリーには、彼らの生み出した作品の中から最高のものを選りすぐる贅沢が与えられているのだ。実のところ、タイトル・トラックは元々ティム・マッグロウやフェイス・ヒル、エリック・チャーチといったアーティストたちへ提供するために作られたものだったが、曲を聴いたメイソンが、自分たちのものにしてしまおうと提案したのだった。彼にとっては理屈抜きでピンと楽曲だったのであろう。その気になればスマッシュ・ヒットなど朝飯前で作り出せてしまうだろうと思えるザ・キャディラック・スリーにとっては、自らの成功の見込みも天井知らずといったところだろう。
心地良いサザン・ロックにはウィスキーが切っても切れない友である一方、多くのミュージシャンにとって諸悪の根源ともなり得るのがアルコールだ。元バンドメイトがアルコール依存症との戦いの末に命を落とした時、リッチ・モスは自分のミュージシャンとしてのキャリアは終ったと思った。だが、一度ロックン・ロールの虫に噛まれたら、その感覚を拭い去るのは容易なことではないのである。4年間シーンから遠ざかった後、2013年にリッチ・モスはストーン・ブロークンを結成した。

Photo: Paul Harries
彼が新しいバンド仲間であるギタリストのクリス・デイヴィス、ベーシストのキーロン・コンロイ、ドラマーのロビン・ヘイコックと一緒に書いた最初の曲は 「This Life」というタイトルで、このミッドランズのバンドのテーマ曲となった。「これは自分の得意なことを見つけて、そいつを前に進むための道具として使おうって歌なんだ。だって誰にとっても人生は一度きりだからさ」とモスは語る。「俺たちはみんな、このバンドに入るまでに色んな経験をしてきて、この業界についても昔より遥かに多くの知識が身についてる。そうして取り交わした俺たちの間での共通理解は、中途半端や妥協は一切なしってことだ」。
デビュー・アルバム『All In Time』のリリースを受け、ロック系のラジオ局はストーン・ブロークンのキャッチーなリフとそれを上回るキャッチーさを持つコーラスとで心を鼓舞するようなハード・ロックをプレイリストに加えようと我先に押し寄せた。ザ・キャディラック・スリーは当初ラジオのエアプレイを獲得するのに大層苦労したものだが、どうやらストーン・ブロークンは彼らにとっておあつらえ向きのサウンドだったらしい。この道はまさに80年代にデフ・レパードが『Pyromania』と『Hysteria』 で切り拓き、踏みしだいてきた道だった。そして今ここに、35年の時を経て、新たなブリティッシュ・ハード・ロック・バンドが、悪びれることなくコマーシャルな魅力を振りまいているのである。
ストーン・ブロークンのセカンド・アルバム『Ain’t Always Easy』には、脳天杭打ちをかますような強烈なリフと分厚いコーラスがどっさり詰まっている。彼らが自分たちのあるがままの姿と、自分たちが目指すところに対して大いに自信を持っていることはサウンドからも十二分に窺える。彼らは自分たちに影響を与えてきたバンド、ブラック・ストーン・チェリーやアルター・ブリッジのような、アリーナ・アクトを目指しているのだ。「Worth Fighting For」や 「Let Me See It All」、「I Believe」といった曲は 聴けば自然に身体が動くようなナンバーばかりで、バンド自身に現在地と次に向かっている場所を明確に思い出させてくれる。彼らにはもうアリーナを満杯にするだけのビッグなメロディもリフも揃っているわけで、既に半分勝ったも同然だ。
伝説的なステータスを狙って(Aiming for legendary status)
同時代のアーティストたちと同列に並ぶことで個性を際立たせようとするバンドもいれば、最初から純粋に伝説的なステータスを狙うバンドもいる。グレタ・ヴァン・フリートがまだメインストリームのレーダーにかかる術を見出していないとしても、彼らが現在起こしている波の大きさから察するに、皆が彼らの噂をし始めるまでにはもうそれほど時間はかからないはずだ。
ヴォーカルとギターをそれぞれ担当する双子のジョシュとジェイク・キスカ、そして彼らの弟でベーシストのサム・キスカによって2012年に結成されたバンドは、翌年兄弟たちの幼馴染であったドラマーのダニー・ワグナーをラインナップに加える。このミシガン出身のハードロッカーたちの初期の楽曲が地元のシヴォレーのCMに使用されたこともあったが、本当の意味で話題に火が点いたのは2017年に入ってからのことだった。最初の波紋が生まれたきっかけは、彼らの楽曲「Highway Tune」が2016年1月、TVのコメディ・ドラマ・シリーズ『Shameless』のアメリカ版に使用された時で、うねりは徐々に勢いを増し、その一年後に同曲が配信されると、グレタ・ヴァン・フリートはアーティスト・オブ・ザ・ウィークに選ばれた。そこから一気に堰を切ったようにすべてが動き出したのである。その年が終わる頃には、彼らは数々の賞に輝き、伝説のロッカー、ボブ・シーガーのオープニング・アクトも務めた。そして言うまでもなく、彼らのデビュー・ツアーは僅か5分で全てのチケットがソールドアウトになった。
では、まずは言わずもがなのところを片付けるとしよう。ヴォーカリストのジョシュの声は確かに異様なほどロバート・プラントに似ている。何しろレッド・ツェッペリンのシンガー本人がその事実を公に認めるほどなのだ。だが過去にどれだけ多くのヴォーカリストが、かの伝説的フロントマンを真似しようとして失敗に終わったことだろう。一方ジョシュの場合は彼に似せようとしていたと言うよりも、単純に彼が口を開けて歌を歌おうとする度に、その肺が押し出す音が偶然にも彼に近かったというだけの話なのである。そして、若き4人組は決してかのブリティッシュ・ロックの雄に対する好意や敬意を否定することはないもの、レッド・ツェッペリンだけが彼らの受けてきた影響ではないとその都度丁寧に説明しているのだ。
メンバーたちが絶えずレコード盤に囲まれた子供時代を送ってきたことを思えば、グレタ・ヴァン・フリートのサウンドが多くの60年代や70年代のアーティストたちの影響を採り入れていることも、そのアーティストたちが殆どロックやブルーズのアクトで固められていることも、さしたる驚きではないだろう。しかしザ・フーやクリーム、ジミ・ヘンドリックス、ブラック・サバス、ディープ・パープル、ジャニス・ジョプリン、ジョン・リー・フッカーにマディ・ウォーターズといったところを主なインスピレーションとして挙げつつも、彼らは決して最初からただロックン・ロール・バンドをやることを目指していたわけではないのだ。ロックン・ロールはあくまで、頭ではなく、心でプレイすることにより生まれる自然発生的なケミストリーの産物なのである。
現時点(2018年9月)でグレタ・ヴァン・フリートはまだデビュー・アルバムをリリースしていないが(今公式に出ている音源はダブルEPの『From The Fires』のみ)、彼らは自らに厳しく高い基準を課している。歴史に残る鮮烈なファースト・アルバムをリリースしたことでその名を轟かせたバンドとして、グレタ・ヴァン・フリートはヴァン・ヘイレン、ザ・ブラック・クロウズ、レッド・ツェッペリンを挙げており、彼らもそれに続きたいと考えているのだ――誰もがすぐには忘れてしまいたくないと思うようなデビュー・アルバムをリリースしたいというのが彼らの野望なのである。
見た目には派手なところは殆どない、ミシガン州フレンケンマスという小さな田舎町出身のこのバンドは、現在ロック界で大きな話題を振りまいているところだ。グレタ・ヴァン・フリートがUKライヴ・デビューを果たしたのは2017年9月、カムデンのザ・ブラック・ハートの裏路地にひっそりとあるちっぽけなパブでのことだった。それでも、から騒ぎや大げさな広告など何もないまま、デビュー・アルバム『Anthem Of The Peaceful Army』のリリース予定日より1ヶ月も前に、若きロッカーたちが2019年4月にケンティッシュ・タウン・フォーラムで行なう2ナイトの公演は既に完売しており、追加公演も発表された。そして、おそらく今後何ヶ所も巡るUKツアーが発表になるだろう。
もっともグレタ・ヴァン・フリートに関して、恐らく何よりも感慨深いのは、彼らがまだ19歳(サムとダニー)と22歳(双子)であるという事実だ。何も年齢がハンディキャップになると言いたいわけではなく、これはつまり、彼らはまだこれから相当な成長の余地があるということであり、一方でその時間と経験から得られるものを想像するに、彼らが最終的にどんな形に落ち着くかを現時点で予言するのは限りなく不可能に近いということである。果たして彼らはメディアや、フェスのプロモーターたちが必死になって探し求めている、ロックの救世主になり得るのだろうか? まあ結果がどうあれ、少なくともこれまでの歴史が指し示すところによれば、この先グレタ・ヴァン・フリートのライヴを観たと証言する人間は、彼らが最初に英国で開催した会場、ブラック・ハートのキャパである100人を軽く超えてくるに違いない。
ロック・ミュージックは死んだのか?……ちゃんと見てろ!
アルバム・セールスが確実に減少の一途を辿る近年、マイケル・ジャクソンの史上最も売れたアルバムを持つアーティストという栄誉が奪われることは永遠にないように思われる。そしてヒップホップもR&Bも、ストリーミングやラジオのエアプレイで欲しいままに日の当たる場所を占拠すればいいのだ。何故なら、ロックというものが他の何よりも輝く場所は、昔も今もやはりライヴ会場なのだから。2017年、ガンズ・アンド・ローゼズは『Not In This Lifetime… 』ツアーで約5億ドル(約557億円)の興行収益を叩き出した。これはツアー総収益としてはコールドプレイ、ザ・ローリング・ストーンズ、U2にぐ、音楽史上4番目の記録である。
結局のところ、ロックとは音楽界における最も偉大なサバイバーであり、この約70年余りの間、どれだけ目まぐるしく流行が変わろうともその嵐をしのいできた音楽なのだ。レジェンドと呼ばれる人々は一夜にして生まれるわけではなく、今では信じられないかも知れないが、レッド・ツェッペリンやザ・フー、ザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズやブラック・サバス等々といったバンドが出て来る前にも世界は存在したのである。彼らとて最初は皆無名のバンドだったのであり、彼らがここまで時代や世代を超えた魅力を発揮するようになったのは、ひとえに積み重ねてきた時間、そしてその時間を超越する力の賜物に他ならない。カルチャー上のトレンドがどれだけ移り変わろうとも、ロック・ミュージックは生き続ける。何故ならそれこそが現存するすべてのバンドが抗い、闘い続けてきたものだからだ。果たして、ここまで挙げてきた名前の中に、2028年のロック・フェスティバルでヘッドライナーを務めるバンドはいてくれるだろうか? タイムマシーンさえあれば確かめられるのだが。
Written By Caren Gibson
- “ロックの最高傑作”ベスト100
- ロックとポップの秘められた歴史
- ロックン・ロールについて歌われた楽曲ベスト12(視聴リンク付)
- ロックのスピリットを燃やし続ける現在進行形のバンド10組
- ロック界最高のパワー・トリオ10選(ビデオ付き)