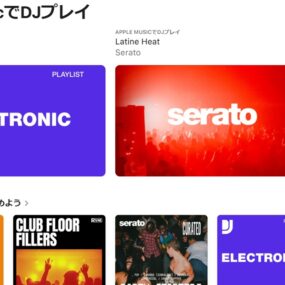IN-DEPTH FEATURES
アップル・レコード物語:幅広いスタイルが同居する折衷的な多様性


「アップル・レコード」は、幅広いスタイルが同居する折衷的な多様性で有名だ。このレーベルからリリースされた作品には、クラシックなロックやポップスから、穏やかなフォーク、ファンキーなソウル、宗教音楽、現代クラシックやモダン・ジャズまで、魅力的な種々のジャンルが混在している。メリー・ホプキンや、ビリー・プレストン、ジェイムス・テイラー、ジョン・タヴナーら、後に誰もが知るようになったアーティストの中には、アップルでデビューした、もしくはアップルによって弾みのついた者達がいた。
自由主義的なこのレーベルには、モータウンやスタックスのような、“アップル・レコードらしい”サウンドというものは存在していなかった。とはいえ、アップルの創設者であるザ・ビートルズの音楽を聴いて育った人なら、音楽というひとつの傘の下で様々な幅広いスタイルが心地良く落ち着いているという考えには、恐らく慣れっこなはずである。
[layerslider id=”0“]
通称『White Album』ことアルバム『The Beatles』は、ザ・ビートルズがアップルからリリースした最初のLPで、少数精鋭のアップル・アーティスト達からやがて世に送り出される作品群がどれほど多彩な喜びを与えてくれることになるか、それを余すところなく予示していた。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリソン、そしてリンゴ・スターの4人は、見開きジャケットに収められたこの2枚組アルバムで、ソロのアコースティック・バラードから、直球のポップス、パスティーシュやパロディ、実験的なサウンド・コラージュ、そしていつの世も変わらぬ一級のクラシック・ロックまで、真の多様性を発揮していた。
このように、手当たり次第に撃ちまくる散弾銃式の輝かしい戦略を特定の1作で再現した者が、他のアップル・アーティストにいなかったのは驚くことではない。だがその役割をこなしたアルバムが1作だけあった。複数のアーティストの曲が収められたコンピレーション・アルバム『Come And Get It – The Best Of Apple Records(邦題:ベスト・オブ・アップル)』がそれだ。同アルバムには、メリー・ホプキン、ビリー・プレストン、バッドフィンガーらの思い出深いヒット曲を収録。また、「Those Were The Days(邦題:悲しき天使)」や「Goodbye」「That’s The Way God Planned It(邦題:神の掟)」、「Come And Get It(邦題:マジック・クリスチャンのテーマ)」「Day After Day」等に加え、ジャッキー・ロマックス、ドリス・トロイ、ラダ・クリシュナ・テンプルらの極上のシングル曲が収録、いずれも1968年から1972年にかけ、全英チャートで栄えあるトップ10入りを果たした曲ばかりとなっている。
『Come And Get It』収録のジェイムス・テイラーの代表曲「Carolina In My Mind(邦題:思い出のキャロライナ)」は、1968年版のオリジナル・ヴァージョンだ。大多数のファンにとっては、1976年発表のレイドバックした再録音ヴァージョンの方がお馴染みだろうが、このアップル・ヴァージョンからは若々しい青春の輝きが放たれている。ストリングス編曲者リチャード・ヒューソンが手がけたバロック調の装飾も、プロデューサーのピーター・アッシャーによって磨きがかけられて、その魅力に輪を掛けていると言えよう。

『Come And Get It』のみで聴ける楽曲の中でも殊に重要なのは、アップルからはアルバムをリリースしなかったアップル・アーティストによる、1回限りのシングル選だ。この選集は、“折衷的”という単語が正に定義する通りとなっており、そのルーツを1816年にまで遡る北部イングランドの伝統的ブラス・アンサンブル、ブラック・ダイク・ミルズ・バンドが鳴らす古来の音までをも収録。彼らの「Thingumybob」は、短期間のみ放送されたテレビのシットコム番組用にポール・マッカートニーが書いた、知る人ぞ知る曲だ。
それから、ニューヨークの不条理主義者ブルート・フォースによる、60年代の奇抜さが表れた素晴らしい賛歌「King Of Fuh」がある。この曲は、“ザ・ファー・キング”(※訳注:放送禁止用語とほぼ同じ発音)というフレーズを繰り返す歌詞で悪名を馳せ、英国内の公序良俗を監視する猥褻用語の苦情処理団体によって放送禁止の措置が取られた。「King Of Fuh」はラジオで一度もかからなかっただけでなく、アップルの配給を手掛けていたEMIもレコード盤の製造を拒否。ザ・ビートルズは、代わりにこのシングルを私的にプレスしたが、それでも店頭に並ぶことはなかった。ザ・ビートルズ関連の中で最も希少性の高いレア音源の1つが生まれたのは、このような経緯からだった。近年では、アップルのオリジナル・レーベルが付いたヴィンテージのアナログ盤が、数千ポンドで取引されている。現在では幸いにも、事実上ほぼ全ての人々に向け、この曲を流すことが可能となっている。
アップルから2枚のシングルをリリースしたスコットランド出身バンド、ホワイト・トラッシュ(※訳注:下層白人、貧乏白人の意)もまた、物議を醸した。ポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ)というものは、テレビ番組での風刺の範囲内なら幸いなことに適用を免れていたが、ロック・ミュージックの場合は、逆人種差別を連想させただけでも、当時の文化監視者達から袋叩きに遭った。そのため彼らは、アップルからの2枚目のシングルで(彼らの後ろ盾である)ザ・ビートルズのカヴァー曲「Golden Slumbers / Carry That Weight」をリリースする際、バンド名を“トラッシュ”と縮めることにした。
70年代のディスコ・キング、ホット・チョコレートで大人気を博したリード・シンガーの故エロール・ブラウンが、その声を初めてレコード盤に乗せて世に送り出したのは、アップルのおかげであった。 1969年、ホット・チョコレート・バンドはジョン・レノンの「Give Peace A Chance(邦題:平和を我々に)」のレゲエ版カヴァーを作り、承認を得ようとその音源をアップルに送付。それを大変気に入ったジョン・レノンが、直ちにリリースするようレーベルに指示したのだった。このレコードは実に面白いことに、プラスティック・オノ・バンドがリリースしたジョン作のこのアンセムの、コピーの枠を超えたものとなっている。アップルのオリジナル版との歌詞の違いをぜひ確認していただきたい。

アップルからシングルをリリースしたアーティストは、必ずしも新人とは限らなかった。ロニー・スペクターは、レコード・プロデューサー界の大立者フィル・スペクターの当時の妻で、1964年にザ・ビートルズと一緒にツアーをしたあの素敵なロネッツのリーダーであった。ジョージ・ハリスンが作詞・作曲を、ハリスン=スペクターがプロデュースを担当した、ロニーの「Try Some, Buy Some」は実に素晴らしいシングルで、出来に満足したジョージがロニーと同じバッキングを用いて同曲を再録音するに至っただけでなく、同じくフィル・スペクターがプロデューサーを務めているマンドリンを多用したジョン・レノンの「Happy Xmas (War Is Over)」のインスピレーション源ともなった。
クリス・ホッジは、リンゴ・スターを後見としてレーベルにやって来た、数少ないアップル・アーティストの1人だった。 70年代初頭、新たに湧き起こったT・レックスを取り巻くファンの熱狂ぶりに魅了されたリンゴは、マーク・ボランと組み、映画『ボーン・トゥ・ブギー(Born To Boogie)』をアップル・フィルムズで制作。この時マークは既にスターであったが、クリス・ホッジはレコード契約を探しているところであった。マーク・ボラン同様、クリス・ホッジも天の世界に関心を寄せ、そこからインスピレーションを得ており、生み出すサウンドも(マーク・ボランほどの震え声ではないが)大きくかけ離れたものではなかった。襟元の折り返しと靴には星の飾り、頭は空想に浸っていたクリス・ホッジ。UFOをテーマにしたシングル「We’re On Our Way(邦題:星空の天使)」を「極めて宇宙的」と評していたのは、キャッシュ・ボックス誌だ。確かにそれは、宇宙時代のグラム・ロックの傑作である。
折衷主義そのものが金星を獲得したのは、サンダウン・プレイボーイズの「Saturday Nite Special」だ。浮かれ騒ぐアコーディオンとフィドルが特徴的な、一度聴いたら病みつきになるこの曲には、米ルイジアナ南部のケジャンの伝統が受け継がれている。幾つもの世代を超えてきたこのコンボは、古さの度合いではブラック・ダイク・ミルズ・バンドには敵わなかったかもしれないが、今もまだ現役で、数世紀とは言わないまでも、少なくとも1945年から80年前までは遡ることが出来る。地元でリリースした「Saturday Nite Special」のシングルをアップルに送ったのは、やはり当時18歳のパット・サヴァントで、それがジョージ・ハリスンの注目を引いた。
より最近では、モリッシーが「Saturday Nite Special」を支持。個人的なお気に入り曲をまとめた編集盤シリーズ『Under The Influence』(2003年)のオープニングとして、この曲を選んでいる。その他、同作に収録されているのは、パティ・スミスや、ラモーンズ、ニューヨーク・ドールズらの曲だ。
ビル・エリオット&エラスティック・オズ・バンドの「God Save Us」は、実質的にプラスティック・オノ・バンドのシングルだ。この曲は、アングラ誌『オズ(Oz)』の資金調達のため、ジョン・レノンが書いたもの。1971年に同誌の編集者達が、語り尽くされたテーマではあるが、いわゆる猥褻罪で告発され、法廷の被告席に立っていた。1970年5月の『スクールキッズ』号で彼らが犯したとされる犯罪の中に含まれていたのが、性的に興奮している“くまのルパート”が登場するポルノ漫画だ。良い子で知られるそのクマは、漫画家ロバート・クラムによって腰から下が下品なキャラと化しており、現行犯で下半身を露出していた。編集者達は有罪判決を受けて短期間服役したものの、上級審で逆転勝訴している。

ジョン・レノンの曲「God Save Us」は当初、より露骨なタイトルの「God Save Oz」として誕生したが、脚光を浴びるのを避けるため、ジョンが自ら歌っていた部分がビル・エリオットのヴォーカルに置き換えられた。ビル・エリオットは、アップルの契約バンド、スプリンターのヴォーカリストだったが、スプリンターの作品は結局、ジョージ・ハリスンのレーベル<ダーク・ホース>からリリースされている。
ロン&デレク・ヴァン・イートンの「Sweet Music」は、より罪のない代物で、ジョン、ジョージ、リンゴのザ・ビートルズ3人から称賛を受けた、ミッド・テンポの暖かいソフト・ロックだ。この曲は実際、ジョージがプロデュースを担当、リンゴがセッション・ミュージシャンの巨匠ジム・ゴードンと共にドラムを叩いている。ザ・ヴァン・イートンズは、サヴィル・ロウ3番地の地下にあった最先端のアップル・スタジオでレコーディングを行った最初のアップル・アーティストだった。アップルから発表した彼らのアルバム『Brother』は、ソングライティング、パフォーマンス、プロダクションの点で、一貫して高い評価を受けている。プロデュースの大部分を手掛けたのは、ザ・ビートルズの長年の仲間であるクラウス・フォアマンであった。
アップルのアルバム一覧に話題を移せば、今はマウスをクリックするだけで、少なくとも16作以上の作品にここからアクセス出来るようになっている。その一覧を最多の4作(『Magic Christian Music』『No Dice』『Straight Up』『Ass』)で占めているのが、バッドフィンガーだ。メリー・ホプキンは2作で、アップル在籍期の最初の『Post Card』と、最後の『Earth Song-Ocean Song』。ビリー・プレストンも、『That’s The Way God Planned』と『Encouraging Words』の2作が挙がっている。非ロック部門では、モダン・ジャズ・カルテットと作曲家ジョン・タヴナーの2人から、それぞれ2作ずつを選出。前者は『Under The Jasmin Tree』と『Space』、そして後者は『The Whale』と『Celtic Requiem』だ。ジェームス・テイラー、ドリス・トロイ、ラダ・クリシュナ・テンプル、そしてジャッキー・ロマックスは、それぞれアップルからの1作ずつ。ジャッキーのアルバムが『Is This What You Want?』というタイトルである以外、他の3人の作品には全て自身の名前が冠されている。
バッドフィンガー

売り上げや音楽的影響について語るなら、バッドフィンガーはアップル・レコード最大の財産だ。1970年から1972年にかけて彼らがアップルからリリースしたシングル、つまり「Come And Get It」「No Matter What」「Day After Day」は、全て英国、米国、カナダでトップ10入りを果たした。一方、英国以外で発売された「Baby Blue」は、米国およびカナダでトップ20ヒットとなっている。アップルから発表した彼らのデビュー・シングル「Maybe Tomorrow」は、当初のバンド名であったアイヴィーズ名義でリリースされ、米国ではマイナー・ヒットとなり、コンピレーション・アルバム『Come And Get It』に収録されている。
サウンド的にはビートルズの影響を強く受けていたものの(むしろ、そうでない者などいただろうか?)、バッドフィンガーはパワーポップの元祖であり、完成度に磨きをかけたソングライティング、心のこもったパフォーマンス、そしてひたむきなミュージシャンシップに真剣に取り組むという点で、草分けであった。とは言え、彼らの最も愛された曲は、バンドの公式シングルですらない。その「Without You」は、元々アルバム『No Dice』のA面最後の曲で、1972年にハリー・ニルソンがカヴァー・シングルをリリースすると、英国、米国、その他の4ヶ国で1位を獲得(さらにハリーがグラミー賞を受賞)。また1994年のマライア・キャリー版も、英国およびその他の4ヶ国で1位に輝いた。マライアによる歌姫スタイルのヴァージョンは100万枚以上を売り上げ、5ヶ国でゴールド・ディスクを、3ヶ国でプラチナ・ディスクを獲得している。
バッドフィンガーのソングライティング力は、どの曲もほぼ「Without You」と同等以上の水準を保っている。しかし最大の成功を収めたシングルは、皮肉にも彼らが録音した唯一のカヴァー曲であった。だが、所属レーベルからの提案で曲をカヴァーしなければならないとしたら、それが史上最高のソングライターの1人、つまりポール・マッカートニーの曲であるに越したことはない。そこで彼らは「Come And Get It」をカヴァーし、プロデュースもポールが担当。ポールはこの曲をピーター・セラーズとリンゴ・スターが主演する映画『マジック・クリスチャン』のために書いたのだが、自身でレコーディングすることを辞退した後、バッドフィンガーに提供したのであった。バッドフィンガーは同映画に、騒々しく喚き散らす「Rock Of All Ages」と、哀愁を帯びた「Carry On Till Tomorrow(邦題:明日の風)」を提供。両曲共にポール・マーカートニーがプロデュースを行い、後者はジョージ・マーティンがストリング・アレンジと指揮を担当した。
バッドフィンガーがアップルから発表したアルバムは、いずれも非常に安定感がある。埋め草的な曲はほぼ見当たらず、揺るぎない伝統的アプローチを取っていたおかげで、その時代だけの儚い流行のサウンドの痕跡は、たとえあったとしてもほんの僅かしかない。そのため彼らのアルバムは、何十年もの時の試練に耐え、最新の編集盤のタイトル(『Timeless… The Musical Leegacy』)が示唆する通り、今では完全に時代を超越した曲のように思えるのだ。アルバム『No Dice』には、ザクザクと鳴る冒頭のリフでパワーポップの誕生を告げる「No Matter What(邦題:嵐の恋)」や、「The Midnight Caller」「We’re For The Dark」「Without You」といった重要曲を収録。また「Love Me Do」もここに収められている。とは言っても、これはあの曲のカヴァーではなく、ギタリストのジョーイ・モランドが書いたオリジナルだ。
1972年の『Straight Up』はバッドフィンガーにとって、今も昔も最も愛されているアルバムである。同作のレコーディングは複雑な経緯をたどったが、詳細なスタジオ・データの中で特に目立っているのは、最終的にリリースされた盤でジョージ・ハリスンが4曲の、つまり「I’d Die Babe」「Name OF The Game」「Suitcase」「Day After Day」のプロデュースを行っているということ、そして「Day After Day」では彼のトレードマークであるスライド・ギターを弾いていると共に、ピート・ハムと互角のデュエットを披露しているということだ。この曲は全米チャートで最高位4位を記録し、バンドにとって唯一のゴールド・ディスクを達成した。このアルバムのジャケット写真は、関わった誰もが恐らく偶然だと言うだろうが、小柄なドラマーが他の3人より一段下にはみ出している、『With The Beatles』の70年代アップデート版(メンバーが70年代らしいスウェードとレザーの服を着用)となっている。
バンドがアップルから出した最後のアルバム『Ass』は、それまでの作品よりもヘヴィだったものの、当時は従来作ほどの人気は得られなかった。1973年に米国で、翌1974年に英国で発売された同アルバムは、ジャケットがシュルレアリスム風の絵画であるという点で、『マジック・クリスチャン・ミュージック』を踏襲。『Ass』がリリースされた頃、バッドフィンガーは既にアップルを離れ、ワーナー・ブラザーズとの不運な契約期に入っていた(先に同様の移籍を行っていたジェイムス・テイラーは商業的に順調にやっていたが、ジャッキー・ロマックスはそうではなかった)。ジャケットに描かれたロバと、空一杯に浮かぶ巨大な人参は、手の届くことのない報酬を目の前にぶら下げられていることを視覚的に表現しており、不思議なほど預言的なものであった。このバンドに起きた事実を伝えるとすれば、アップルからの移籍後、彼らの潜在的な可能性は、吐き気のするような恐ろしいビジネス的策謀によって途中で断ち切られてしまっている。だがそれ以前ですら、同アルバムのオープニング曲であり、アップルからの最後のシングル「Apple Of My Eye」で証言している通り、彼らは移籍を後悔していた。
メリー・ホプキン

メリー・ホプキンは、アップルで大きな成功を収めた最初のアーティストだった。ポール・マッカートニーがプロデュースした彼女のデビュー・シングル「Those Were The Days」は、世界中で600万枚以上のセールスを達成。ポールは彼女の次のシングル「Goodbye」も手掛け、アップルの力を使い、この曲は世界40ヶ国近くで売り出された。アップルから発表したメリーの2枚のアルバムは、それぞれ事情が非常に異なっている。1969年の『Post Card』は、ポール・マッカートニーがプロデュースを手掛け、収録曲の大部分の選択も彼が行った。アップルと契約した時、わずか17歳だったメリーは、切子硝子のような透明感のある歌声をひとつの楽器にまで高めたが、曲作りという冒険にはまだ足を踏み入れていなかった。その代わりアルバムは、ドノヴァンやハリー・ニルソンら、ポール・マッカートニーのお気に入りのソングライター陣に大きく依拠。また「Inch Worm」や「There’s No Business Like Show Business」といった戦前期の曲が、「That Were The Days」によって形作られた即成の郷愁感という枠組みにぴったり嵌まっていた。
メリー自身は、2作目『Earth Song – Ocean Song』の方を遥かに気に入っていると公言している。このアルバムには、彼女が自分で選んだ曲、ハーヴェイ・アンドリュースや、ラルフ・マクテル、キャット・スティーヴンス、リズ・ソーセンといった、主にコンテンポラリー・フォーク勢による楽曲を収録。リズ・ソーセンは、アルバム・タイトルの由来となっている2曲を手掛けている。デヴィッド・ボウイとマーク・ボランというスーパースター2人との仕事を終えたばかりだった、スタジオの魔術師として名高いトニー・ヴィスコンティが、穏やかで心のこもったこのフォーク・アルバムを丁寧かつ精巧にプロデュース。その後間もなくトニーとメリーは結婚し、全てにおいて(しばらくの間は)実に幸せな大団円を迎えた。
ジェイムス・テイラー

米母国から英国に渡り、サヴィル・ロウ3番地の常連になった時、ジェイムス・テイラーは弱冠20歳でありながら、音楽面では既に完成されていた。アップルから1968年にリリースされた、彼自身の名を冠したデビュー・アルバムの収録曲は、「Rainy Day Man」「Knocking ‘Round The Zoo」「Something’s Wrong」「Night Owl」「Brighten Your Night With My Day」等、多くがその数年前に、彼のバンド、ザ・フライング・マシーンのために書かれたものであった。 ジェイムスはこれらの曲をアップル向けに再録音。そこでプロデューサーのピーター・アッシャーが、シングル曲として選び取り易いものをただ並べるだけなく、1つのコンセプトとしてアルバムをまとめるために曲間を風変わりな形で繋げるという、『Sgt Pepper』の後を受けた一連の手法を取り入れた。「Carolina In My Mind」が、少なくとも英国では1969年にシングルとしてリリースされなかった理由は、それで説明がつく。カタログ番号[Apple 32]の同シングルが英国でシングルとしてリリースされたのは1年後、2作目『Sweet Baby James』が大成功を収めたことにより、アップルが1作目『James Taylor』を再発した時だった。
その後マルチ・プラチナを獲得し、5つのグラミー賞を受賞したジェイムスのキャリアを踏まえれば、このアップルでのデビュー作は見落とされがちだ。しかし全ては、このアルバムから始まった。そしてここにある全てが—— 曲、ソングライティング、黙想的なヴォーカル、クラシックを熟知した見事なフィンガー・ピッキング・ギタースタイルが——その後数十年にわたってラジオからテレビまでを支配するよう準備を整え、待ち構えていたのである。もしあなたがジェイムス・テイラーを好きで、まだこの『James Taylor』を聞いていないなら、ぜひストリーミングしていただきたい。
ジャッキー・ロマックス:
ジャッキー・ロマックスもまた、バンドの一員としての下積み時代を経てアップルにやって来た1人だ。ジャッキー・ロマックスの場合、そのバンドとはアンダーテイカーズのこと。キャヴァーン時代、リヴァプールで共に経験を積んだ、ファブ・フォー(ザ・ビートルズ)の親しい仲間であった。ジャッキー・ロマックスは実際、シルヴァー・ビートルズで1度ドラムを叩いたことすらある(「1曲だけね。僕の出来は酷いものだったよ」)。ジョン・レノンのアドバイスに従い、ジャッキー・ロマックスはソロに転向。1967年に新しく設立されたアップル・パブリッシングとの契約を手助けしてくれたのもジョン・レノンだ。だが、レコーディング・アーティストとしてジャッキー・ロマックスをアップル傘下に引き入れ、アルバム『Is This What You Want』をリリースさせたのは、別のビートルズ・メンバー、ジョージ・ハリスンであった。
ジャッキーのバック・バンドとしてジョージが招集したのは、自身(プロデュースも担当)の他、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、エリック・クラプトン、クラウス・フォアマン、そしてスーパー・セッション・キーボーディスト王のニッキー・ホプキンスら、錚々たる大物達。曲の大半をジャッキー・ロマックス自身が書き、その結果完成したのは、微妙なサイケ感が漂う中、ソウルフルなヴォーカルが響く、60年代後半ならではのロック/R&B作で、一貫して聴き応えのある1枚となっている。唯一の非オリジナル曲は、ジョージ・ハリスンが書いた「Sour Milk Sea」で、これがジャッキー・ロマックスにとって最初のアップル・シングルとなった。これは『White Album』時代に書かれた強力な曲で、ザ・ビートルズの作品に収められていたとしても恐らく違和感がなかっただろう。実際、この曲でバック・バンドとして演奏しているのはポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターであるため、実質的には、ゲスト・ヴォーカリストを擁したザ・ビートルズの曲と言える。ザ・ビートルズのファンと称する人なら、誰しもが聞いておくべき曲だ。
ビリー・プレストン:
ビリー・プレストンが人々に懐かしく思い出されるのには、多くの理由がある。彼は、サム・クックからリトル・リチャード、ジョー・コッカー、エルトン・ジョン、最も有名なところでザ・ローリング・ストーンズ、そしてもちろんザ・ビートルズ自身と一緒に仕事をしてきた伝説的なサイド・マン(伴奏者)だが、“サイド(脇)”という単語は、他の人々の作品に対する彼の貢献度を十分に言い表しているとは言えない。彼は早熟の天才として知られ、僅か11歳の時にナット・キング・コールとのデュエットで米国のテレビに出演。また「Outta-Space」「Will It Go Round in Circles」「Space Race」「Nothing From Nothing」等、全米No.1シングルを含む数々の大ヒットを飛ばした。
彼の名は、ザ・ビートルズ自身のシングル「Get Back」でも神聖な位置を占めており、ピアノとオルガンを彼が弾いていたことは有名だ。同じ年、ジョージ・ハリスンがプロデュースした「That’s The Way God Planned It」がアップルからリリースされ、全英トップ10ヒットとなっている。
ビリー・プレストンの音楽には、ゴスペル、ソウル、R&B、ファンクからの影響が染み渡っており、こういった要素の全てが、ジョージ・ハリスンがプロデュースしたアップルでの2枚のアルバム『That’s The Way God Planned It』と『Encouraging Words』で、この上なく壮観な形で融合している。これらのアルバムに備わっている持ち前の傑物感は、ざっと一聴しただけで明らかだ。ビリー・プレストンがレコーディングした作品の大部分は、彼自身が書いた印象的なオリジナル曲だが、ボブ・ディランの「She Belongs To Me」や、WC・ハンディの「Morning Star」、レノン=マッカートニーの「I’ve Got A Feeling 」、そしてジョージ・ハリスン自身の「All Things Must Pass」など、カヴァー曲を選んだ際も、そこに魔法をまぶして自分自身のものにし切っている。またジョージ・ハリスンは、自分でもまだリリースしていなかった「My Sweet Lord」をも、ビリー・プレストンに提供していた。
ビリー・プレストンとジョージ・ハリスンの間からは、数あるアップルの傑作の中でも最高の曲のひとつが生み出された。つまり、「Sing One For The Lord」のことだ。精神的な高揚感をもたらしてくれるゴスペル調のこの曲は、「That’s The Way…」と「My Sweet Lord」との間の音楽的な架け橋となっている。正に必聴の曲だ。
ドリス・トロイ

ドリス・トロイは、60年代の英米ソウル界の陰のヒロインだ。 ニューヨーク在住だった60年代初頭、ハーレムのアポロ劇場でジェームス・ブラウンに才能を見出された彼女は、アトランティックから「Just One Look」をリリースしており、この曲は英国ではホリーズがカヴァーしてEMIから発売されていた。60年代末に英国に移住した彼女は、ロンドンのセッション・シーンで人気バック・ヴォーカリストとなり、同様に才能のあるマーシャ・ハントとマデリン・ベルと共に、拘束力のない3人組を結成した。彼女のバック・ヴォーカルは、エドガー・ブロートンやニック・ドレイクから、ザ・ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイドまで、あらゆる人々の作品で聴くことができる。
ジョージ・ハリスンがドリスをアップルに招き入れたのは、ビリー・プレストンのセッションでジョージ・ハリスンが彼女に会った後のことだ。彼は既に彼女のファンで、1963年にアトランティックからリリースされていた、覚えやすいタイトルのアルバム『Doris Troy Sings Just One Look & Other Memorable Selections』をよく知っていた。彼女は、自身の作品の芸術的方向性について、主導権を完全に握ることが出来るアップルとの契約のチャンスに飛びついた。かの有名なジョージ・ハリスンのアドレス帳から、リンゴ・スター、エリック・クラプトン、クラウス・フォアマン、ピーター・フランプトン、デラニー&ボニー、ボビー・ウィットロック、ジム・ゴードン、そしてスティーヴン・スティルスら、錚々たるゲスト・ミュージシャン勢が参加することになった。
アルバム『Doris Troy』は、至福のファンキー・ソウル・R&Bの塊だ。ペンテコステ派の霊歌のように聴き手を高揚させ、ソウル界のゴッドファーザーことジェームス・ブラウンが放つグルーヴのようにフロアを埋め尽くしながら、豪華スターが勢揃いしたラインナップと超一級の楽曲群で、この分野について十分な知識のない人々をも熱狂させることが出来る。ここには極めて稀な驚きのコラボレーション曲:「Ain’t That Cute」(ハリスン=トロイの共作)や、「I’ve Got To Be Strong」(ロマックス=トロイ)、「Gonna Get My Baby Back」および「You Give Me Joy Joy」(何れもハリスン=トロイ=スターキー=スティルズの共作)も収録。何らかの不可思議な理由により、このアルバムは、本来受けるべき評価を得られないことがしばしばあった。インターネットを通じていつでも聴くことが可能になった現在、そういった残念な状況が続かねばならない理由が1つ減ったと言えよう。
モダン・ジャズ・カルテット:
もちろんザ・ビートルズは、モダン・ジャズに対して何の抵抗もなかった。抵抗など持つ理由もないだろう。だが、モダン・ジャズに特別な情熱を持っていることで知られた特定のメンバーもいなかったと言って間違いない。その代わり、その素晴らしいジャンルにおける傑出したアンサンブル、モダン・ジャズ・カルテットが、レーベル初の責任者であり、物腰柔らかで洗練されたロン・キャスのおかげでアップルにやって来たのだった。
アップルは、あらゆる点で新しいものを重視することが多かったが、それほど新しくないものを新規のリスナーになり得る可能性のある人々に提供することも大事にしていた。 MJQの歴史の始まりは遥か1940年代に遡り、このコンボが1970年代半ばに解散するまで(結局は後に再結成を果たしているが)継続。その間、とりわけ50年代に、彼らはモダン・ジャズの形成に一役買っている。また彼らは、ジャズが即興というプリズムを通してクラシック音楽と出会う、サード・ストリーム・ミュージックの初期のパイオニアでもあった。
MJQがこれまでに発表してきた25作程のスタジオ・アルバム(その大部分がアトランティック・レコードからのリリース)のファンであれば、アップルから出た『Under The Jasmin Tree』と『Space』を聴いて失望する人はほとんどいないはずだ。ジョン・ルイスのピアノと、ミルト・ジャクソンのビブラフォン、パーシー・ヒースのベースと、コニー・ケイのドラムスとが、継ぎ目のない織物のように完全に一体化しているこの作品は、60年代だけでなく、50年代や70年代に発表されていたとしてもおかしくないような、予言的な楽しさに満ちた内容となっている。
ラダ・クリシュナ・テンプル

ポップ・チャートを飾るとは到底思えなかったようなグループの1つが、ラダ・クリシュナ・テンプルだ。彼らとよく似た名前のアシュ・ラ・テンペルやアシッド・マザーズ・テンプルとは異なり、彼らは実際に“寺院(テンプル)”であった。彼らがアップルからリリースした2枚のシングル、1969年の「Hare Krishna Mantra」と1970年の「Govinda」は、共に全英トップ30ヒットを記録。パワフルで胸を打つ「Govinda」はアルバム『Come And Get It – The Best of Apple Record』で聴くことが出来る。ラダ・クリシュナ・テンプルは、インドのヒンズー教で信仰されている数多くの神々の中でも特に重要な鍵となっている二柱の神、つまり“すべてを魅了する”クリシュナとその妃ラダを祀る宗教集団で、今も存在。この神聖なカップルの像は、アップルのアルバム『The Radha Krsna Temple』ジャケットに描かれている。
既にザ・ビートルズは、マハリシとの結びつきや、ジョージ・ハリスンのインド音楽の実験、「I Am The Walrus」におけるクリシュナへの具体的な言及等を通じて、英国の街頭で展開されていたハレ・クリシュナ運動が世間に受け入れられるための後押しとなるような、土台作りを行っていた(「ハレ・クリシュナ」というフレーズはすぐに大衆文化に取り入れられ、テンプルズのLPがリリースされる前に、ファッグスやティラノザウルス・レックスといったバンドの曲や、ミュージカル『ヘアー』の中に登場していた)。
1968年にテンプルズが米国からロンドンに到着した時、ラダ・クリシュナ寺院の地元の指導者ムクンダ・ゴスワミと彼の帰依者達は、彼らの宗教に対して興味と確かな愛情を公に示していた最も有名な英国人、ジョージ・ハリスンに自然に引き寄せられた。ジョージ・ハリスンはそれに暖かく応え、この寺院の儀式においては音楽が不可欠な要素であったことから、考えるまでもなく、サンスクリット語の賛美歌をレコーディングし、アップルからアルバムとしてリリースすることに着手。ジョージ・ハリスンがプロデュースを、ムクンダが編曲を担当した。このアルバムを楽しむためには、毎日瞑想する必要もないし、クリシュナ意識運動で表現されていた宗教的な教義を信じる必要もない。これは、1969年以来全く古びていない、卓越したスピリチュアルなチルアウト音楽なのだ。そのインスピレーションの源が、5000年前のバガヴァッド・ギーターの聖典に由来していることを思えば、それもほとんど驚くには当たらない。
ジョン・タヴナー:
アップル唯一のクラシック音楽作曲家であるジョン・タヴナーの音楽に充満していたのは、全く異なる性質の宗教的表現だった。アルバム『The Whale』と『Celtic Requiem』の生命線となっていたのは伝統的な西洋キリスト教で、この類稀な2作品は、ほとんどのクラシック音楽がそうであるように、まず最初にオーケストラ演奏用に書かれたものの、その後レコーディングを行うに当たり、ロックの伝統におけるところの作品そのものというよりも、むしろ音声記録として見なされるようになった。
ジョン・タヴナーは60年代、現代クラシック音楽界の“恐るべき子供”(=成功した若き前衛芸術家)で、ロック界でのビートルズがそうであったように、彼自身のジャンルにおける若き扇動者であった。Aラインのスカートを翻していた戦後のポピュラー・ミュージックを蹴散らしながら、ロックン・ロールが勝手放題にやっていたのと同様、実験的で尖った、そしてしばしば無調のジョン・タヴナーの曲は、言ってみれば、マーキーや100クラブといったライヴ・ハウスよりも、荘厳なロイヤル・フェスティバル・ホールを好むような人々を苛立たせていた。
伝統的なキリスト教との関連は、ジョン・レノンの心を掴んで当たり前の方法ではなかったはず。にも拘らず、コンセプチュアル・アートの愛好家であるジョン・レノンとオノ・ヨーコは、タヴナーの美学を心から受け入れた。恐らくもっと驚くべきことだろうが、リンゴ・スターもまた、その追随者となっている。実際リンゴは、特に熱心な『The Whale』推進派で、70年代半ばには、自身が立ち上げたものの短命に終わったレーベル<リング・オー・レコード>から、このアップル作品を再発している。耳を澄ませば、『The Wale』の冒頭から7分44秒目のところで、彼が拡声器を通じ「…そして窒息を引き起こす!」というフレーズを大声で叫んでいるのが聞こえるはずだ。作品全体の文脈の中でその短い一場面の意味を理解するには、この真面目な作品について少々真剣な考察を行う必要があるかもしれないが。
『The Whale』は、クジラに飲み込まれた後で吐き出されたという紀元前8世紀の預言者ヨナの聖書の逸話を基にしたカンタータである。一方、『Celtic Requiem』は、アイルランド史における過ぎ去りし時代の伝統的な死の童謡を軸にした、宗教的なサウンド・コラージュだ。前者の音楽の鋳型となったのはイーゴリ・ストラヴィンスキーだった(かつてジョン・タヴナーは「ストラヴィンスキーだけ」と強調)が、後者を支えていたのは変ホ長調のみである。この作曲家はエレクトリック・ギターやベース・ギターといったポピュラー音楽の楽器を自身の演奏に組み込むことを好んでいたが、これは明らかにポップ・ミュージックではない。
ジョン・タヴナーの名声は70年代を通じて着実に高まり、最終的にはチャールズ皇太子のお気に入り作曲家として賞賛を受け、彼の作った曲の一つはダイアナ元皇太子妃の葬儀で演奏された。 2000年、エリザベス女王は音楽に対する彼の貢献に対し、ジョン・タヴナーにナイト爵位を授与。これは間違いなく、アップルに所属したアーティストに与えられた中でも最高の賞であり、音楽的スペクトラムの色が何であれ、類稀な才能を育てるに当たり、このレーベルがどれほど正しいことを行ってきたかを示唆している。
Written By Andy Davis
- ザ・ビートルズ関連記事を見る
- アップル・レコーズ関連記事
- iTunes : Come And Get It – The Best Of Apple Records
- Spotify : Come And Get It – The Best Of Apple Records