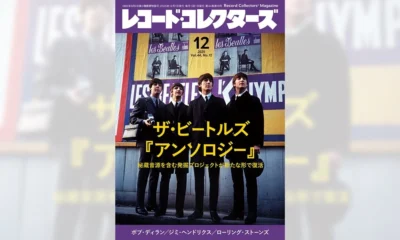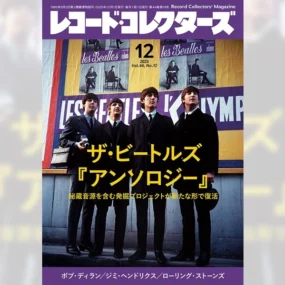Columns
【公式文字起こし】芸人・永野のYouTubeでのザ・キラーズ特集:ゲスト粉川しの


急遽出演キャンセルとなったSZAの代わりに、2024年のフジロックフェスティバル初日のヘッドライナーとして出演したザ・キラーズ(The Killers)。
2018年の単独公演以来の来日公演、そして20年振りのフジロックのステージに立つことを記念して、芸人・永野さんのYouTubeチャンネルにて、音楽ライターの粉川しのさんが出演。33分の長さの動画ながら、公開2週間で10万再生を超えたこの動画を抜粋した文字起こしを掲載します。
<関連記事>
・【ライブレポ】ザ・キラーズ、フジロックでの素晴らしいステージ
・The Killersはようやく日本でブレイクするのか?
・ザ・キラーズのベスト・ソング20:アメリカが誇る最高の“ブリットポップ・バンド”
洋楽誌『rockin’on』
永野:今回は豪華ゲストをお迎えしまして、ザ・キラーズについて教えてもらおうという企画です。ということで、ゲストは粉川しのさんでございます。よろしくお願いします。
粉川:よろしくお願いします。
永野:粉川さんのことはディレクターさんたちも知ってましたからね。徹夜で覚えたとかじゃないですよ?「えっ、あの人じゃん!」って思いましたから。だって『rockin’on』(の元編集長)じゃないですか。
粉川:そうですね、『rockin’on』で書いていますね。
永野:僕、2000年ぐらいからあんまりそういう雑誌を読まなくなったんですけど、1997年ぐらいには読んでたんですよ。その時期っていうのは(『rockin’on』に)在籍されてたんですか?
粉川:90年代初頭に『rockin’on』で、2000年代初頭に『BUZZ』っていう雑誌を作っていて、2000年代半ばにもう1回『rockin’on』に戻って……っていう感じです。
永野:なるほど。あの時代、田舎者は『rockin’on』と『CROSSBEAT』から情報を得てたんですけど、当時は結構ライバル感あったんですか?
粉川:90年代にはまだ(ライバル感が)あったかもしれないですね。90年代まで洋楽はすごく元気で、『CROSSBEAT』『rockin’on』『MUSIC LIFE』等たくさん雑誌があったんです。そうすると、競合するじゃないですか。でも2000年代以降はそういった雑誌がどんどん無くなっていっちゃうんですよ。『BUZZ』も無くなっちゃったし……となると、もうライバルとか言ってられないんですよね。みんなで(洋楽を)盛り上げないといけないと、っていう(笑)。
00年代の洋楽
永野:いきなり重いこと聞くんですけど、なんで2000年代になったらあんなに洋楽が流行んなくなったんでしょうね?
粉川:永野さんって(音楽的には)結構90年代育ちですよね?
永野:そうですね。年齢的にも、2000年代入ってからの“オルタナの未来”なんて考えてる暇がなかったというか。人生が始まっちゃってて、よく来日してるボロボロの人たち(ミュージシャンたち)より金が無かったんです。だからどうでもよくなったんですよ、そのミュージシャンの「4枚目の苦悩」とか(笑)。
粉川:うんうん(笑)。
永野:あとね、僕はニルヴァーナ前ぐらいからロック雑誌を読んでたんですけど、最後、日本でミクスチャーやラウドロックみたいなものが流行ったあたりで、(ロック雑誌が)エミネムとかも特集しだしたんですよ。いわゆる「ロック逃げ」をし出した時期があって、自分はそこ(ロック雑誌)から逃げました。
粉川:なんかもう、「無邪気に」というか、2000年代からは調子に乗れなくなったんですよね、ロックが(笑)。1990年代後半から末って、ラップメタルとかヘヴィロックの時代ですよ。で、めちゃくちゃ重くて、熱くて、激しくて、っていうものがどんどんマンネリ化していくわけです。
永野:そうそう、マンネリ化しましたよね。
粉川:産業化していっちゃったんです。ロックってカッコよくないといけないし、尖ってないといけないし、ある意味でオルタナティブでないといけないのに、1990年代~2000年前後にかけてどんどん体制側になっていってしまったんですよね。最後にヒットしたのは多分、リンキン・パークの『hybrid Theory』とか、リンプ・ビズキットの『Significant Other』とか。それを境にして、ヘヴィロックやラップメタルはどんどん終息していきました。
永野:はいはい。
粉川:そんな中で、90年代のビッグネームが自己反省し始めるんですよ。例えばレッド・ホット・チリ・ペッパーズの『Californication』。かつておバカなファンク・ミクスチャーの“ソックス”(※股間に靴下をはめるパフォーマンス)とかやってた人たちが、メロウに行き着くわけです。
永野:行き着きましたよね。
粉川:で、ベックは『Sea Change』ですよ。歌詞でLo-Fiなことをやって、ちょっとウィットのきいた『Odelay』みたいなことをやってきてたのに、超Hi-Fiなよくできたフォークポップに行くわけです。グリーン・デイは『American Idiot』を出すんですよ。
永野:なんか涙が出そう……(笑)。「負けたんだ、この戦争は!」みたいな話ですね。我々は何のために戦ってたんだ?!みたいな(笑)。
粉川:おバカなパンクロックでイェ~イ!ってやってられなくなって、コンセプトアルバムを作るわけです。極め付きがレディオヘッドの『Kid A』ですよ。あれで「ロックはゴミだ」って言うわけじゃないですか。……という流れの中に、リンプ・ビズキットとかグッド・シャーロットが置いて行かれちゃうんですよね。
永野:愛おしいですけどね、今から考えると。「どっちがロックだ?!」ってね。
ガレージ・リバイバル/ポストパンク・リバイバル
粉川:それ以降、どんどんロックがニッチな存在になっていくんです。そこで出てくるのがザ・ストロークスとかザ・ホワイト・ストライプスとかのガレージ・リバイバルやポストパンク・リバイバル。
永野:ああ出た!はいはい。
粉川:あれは一体何なのかっていうと、恐竜みたいになっちゃって、ドン臭くなってしまった“ロック”を1回リセットしましょうということなんです。1回全部そぎ落として、骨格だけに戻して、スカスカの所からもう1回ロックを再構築していきましょうよ……っていう文脈だったんですよ。ザ・ストロークスの『Is This It』なんて、もう“ゼロ”みたいじゃないですか。水の透明度を競うみたいなアルバムです。そういう所から始まったのが、2000年代のロックなんです。
永野:でも、それが(ロックの)勢いを取り戻すきっかけにはならなかったんですか?
粉川:ガレージ・リバイバルなどはバンバン出たんですけど、商業的な成功はどのぐらいだったかって言うと、かつてのリンプ・ビズキットみたいな売れ方はしなかったんです。やっぱり、すごくインディーでオルタナティブなカッコいいものって売れないじゃないですか。そこで出たのがザ・キラーズです。
永野:ハァ~!気づかなかったな~!
粉川:売れなかったニュー・ウェイヴ・リバイバルの中で最も売れたバンドがザ・キラーズなんですよ。
「(音楽には)トラウマがないとダメ!」
永野:へ~!……なんか、『rockin’ on』なんていうのはもう、“思想書”じゃないですか。編集長やられた方に言いたいんですけど、それこそコーンとかナイン・インチ・ネイルズとか、あの辺りまでは「音以外の怨念も聞け!」みたいに言ってくるわけですよ、『rockin’ on』が(笑)。インタビューでも、あちらのアーティストってみんな何かしらのトラウマがあるわけです。
粉川:だいたい子供時代にトラウマがあるんですよね。
永野:そうそう。で、「(音楽には)トラウマがないとダメ!」ってほんとに思ってたんですよ。
粉川:コーンなんてトラウマの塊じゃないですか。
永野:コーンはトラウマを歌ってますよね。もう“トラウマ芸”というか。それが面白かったんです。でも、それは日本のリスナーにとっての『rockin’ on』の悪影響だと思うんですよ(笑)。
粉川:ハハハ!(笑)。
永野:日本のリスナーで、お腹いっぱい食って生活してて、銃で撃たれる危険もないのに、なんか“そういう(鬱屈した)気分”で生きてて、コレが1番かっこいいんだ!ってなるんですよ。だけどこの歳になると、クラブでなんとなく音を聞いてたり、パンクを音として聞いてた人のほうがカッコよく見えてくる……って逆転が生まれるんです。自分みたいな『rockin’on』と『CROSSBEAT』を読んでた人が1番カッコ悪くて、時代に取り残されたみたいになってて(笑)。でも、2000年ぐらいまではアレが楽しかったんですよね。「ジョナサン・デイヴィスはこんな虐げられてたんだ!」みたいな。
粉川:「虐待されていた!」みたいな。
永野:で、粉川さんたちが“虐待解説”をするんですよね(笑)。今考えたら、お笑いでもノリで考えたネタがヒットしたりするんですけど、あの時は粉川さんを中心にライターとかインタビュアーが「ロックミュージシャンっていうのは1枚出すためにまず前作を経て苦悩がなければいけない」とか、「誰か知人に訃報が無いといけない」とかみたいにするから、ソッチでスタートしちゃうんですよ。あなた(粉川)の先輩のライターのせいで(笑)。
粉川:そうね、そうかもしれないですね(笑)。
永野:訃報・トラウマ・メンバー間の確執(笑)。で、ダメな時期乗り越えて、(たとえば)7曲目のアレをきっかけにスピードかかってアルバムが出来上がった……とか、大体そういう流れなんですよ。当時はバカだから気づかなかったんですけど、今考えたら「なんで毎回そんな感じなんだよ!」ですよね(笑)。あと、これはよく言ってることなんですけど、粉川さんにも言わなきゃいけないことがあります。
粉川:言わなきゃいけないこと。なんでしょう。
永野:僕のYouTubeチャンネルでは“『One Hot Minute』問題”というのを取り上げてるんです。レッド・ホット・チリ・ペッパーズがアルバム『One Hot Minute』を出したとき、粉川さんたちを中心とするライターが「最高傑作だ!」って言ってたんですよ。
粉川:待って、そこは言わせてもらいますけど、そのとき私まだ『ロッキング・オン』入社してないです(笑)。
永野:入社してないですか。失礼しました(笑)。粉川さんたちの先輩たちがね、あのアルバムを「最高傑作だ!」と言うんですよ。僕が聴いてても良いアルバムでした。良かったです。バカだからデイヴ・ナヴァロとジョン・フルシアンテの音の違いも「分厚いな」くらいしかわかってなかったんですが、ライターや評論家は「最高だ」って言ってたんです。そう言ってたのに、次のアルバムの『Californication』になったら、みんな「前作の失敗を~」とか言い出して。(笑)こいつら一生信用できない!と思いました。
粉川:“あるある”ですね(笑)。
永野:“あるある”ですよね。それも含めて『Californication』の敗北もドラマのひとつとして見てたんですけど、俯瞰で見てて、ザ・ストロークス以降ってそういう“怨念”みたいなのを感じないんです。
粉川:まさにおっしゃる通りで、そういうロックの“怨念ドラマツルギー”が2000年で終わったんです。
永野:あ、ほんとに終わったんですか?そこで。
怨念からの解放されたロックとヒップホップ
粉川:例えば『Kid A』は感情を全く込めずに歌うために、歌詞カードを全部シャッフルして、あえて特に意味のない歌詞を歌うみたいなことをしてたりもするんですよ。しかもザ・ストロークスってトラウマを持ちようがないじゃないですか。ニューヨークのアッパーイーストサイドに育った超ボンボンだし。
永野:そこ(経歴)は本人たちも嘘をつかないんですか?
粉川:(嘘を)つけないんですよね。苦悩とか言えないですよ。スイスの超有名な、学費が1年間に1,000万円くらいかかるような宿舎の学校に入ってたりする、凄まじく“上澄み”の人たちなんですもん。ニューヨークのお坊っちゃんたちなんですよ。 それが「とりあえず、とにかくカッコいいことをやろう」とする。だって「僕の悩み」とかは無いから(笑)。かつてのなんかトラウマとか何とかっていうのを全部脱ぎ捨てたのがガレージ・リバイバルです。
永野:それで言うとですよ?(ロック雑誌を読んでいた)最後の方、『rockin’on』や『CROSSBEAT』で「エミネムのトラウマ」みたいな記事があったじゃないですか。母親とのどうのこうのっていう。 それを読んで「ラップもそうなんだ」って思ったんです。これまではビースティ・ボーイズとかで知った気になってたくらいだったから。
粉川:だから、その(今まではロックが持っていた)トラウマ的な文学が、ヒップホップのほうに行っちゃったんですよね。かつて「大人はわかってくれない」みたいな不良の文学・思春期の文学的なものがロックやパンクだったんですけど、それが全部ヒップホップに行っちゃったのが2000年代なんです。つまり(ロックやパンクは)ユースカルチャーの中心じゃなくなっちゃったんですね。
永野:でも、ですよ?たとえば、トラウマやストーリーがある人が日本や海外にいたとして、それをギターサウンドと歌詞にする方向にはならないんですか?
粉川:ならないです。どう考えてもヒップホップのほうが(音楽として発表するまでにかかる時間が)早いですもん。ヒップホップはひとりでできるし。バンド組むにはお金もかかるし。
永野:でも、ヒップホップを否定するわけじゃないんですけど、ギターって「爆音だけで攻撃できる」じゃないですか。ヒップホップは“言葉(リリック)を書く時間”っていうタイムロスがあるけど、ギターは変な話、(コード進行を他の曲から)盗んで鳴らせば10秒でできると思うんですよ。もう1個疑問なんですけど、ロックではカート・コバーンとかがヒョロヒョロのまま“攻撃”をしたのが痛快だったんです。でもヒップホップって“証明”をし続けるじゃないですか。エミネムもどんどんマッチョになっていくし。だからヒップホップって、結局マッチョ(マッチョイムズ)なのかな?って。
粉川:それはケンドリック・ラマーとかフランク・オーシャンとかが出てくるまではそうだったかもしれないです。2010年代以降になって、フランク・オーシャンがカミングアウトして、ヒップホップのマッチョイズムみたいなものがようやく崩れていきました。
永野:ヒップホップの表現が何でもアリになったんですね。じゃあもう、終わり……「完!」じゃないですか(笑)。
粉川:2000年代がほんと大変なんですよ。
永野:粉川さんは「ロックは終わった」って伝えにきてくれたんですね?(笑)。 ギターウルフとツーマンというか、ネタをやったときに、僕がなんか言ってギターを持たされて……っていうシーンがあったんですけど、やっぱり面白かったんですよ。僕はギター弾けないけど、ネック上げたり動かしたりしてたら場を誤魔化せるし。あれを多分みんな知らないだけなんじゃないかな?と思うんですよね。あと、ヒップホップはマイク持ってワーって言う(喋る)じゃないですか。でもなんか、日本人っぽいこと言ったら、あんまりたくさん喋んのって……野暮じゃないですか。(笑)僕「喋り過ぎるのは野暮」っていう教育を受けてたんで、ヒップホップに対して、ずっとそう思ってたんです。
粉川:それを言ってしまったらもう、“そう”ですよね(笑)。
永野:ならパワーコードで3つぐらいで(ロック)やればいいじゃないですか。
粉川:ジャーン!バーン!ドカーン!っていうのに初期衝動的カッコよさがあったのですが、それがスタイルになっちゃったんですよね、ラップメタルの最後らへんで。
永野:うんうん。あと、ラップメタルって巧いですもんね。練習しないといけないじゃないですか。
粉川:スポーツみたいですよね。
永野:こういうとアレですけど、(ラップメタルは)“リアル”な感じではないですよね。
エモの登場とザ・キラーズの大ブレイク
粉川:ですよね。だからやっぱり2000年代には、すごくライブ感のある、生っぽい音した、ガレージやポスト・パンクみたいなものをロックに入れて行こう!みたいなものがオルタナティブな流れとしてあったんですよ。そしてもうひとつ、2000年代にロックの大きな流れとしてメインストリームでめちゃくちゃ流行ったのが「エモ(エモロック)」なんです。エモ、ポップ・パンク。パニック!アット・ザ・ディスコとかフォール・アウト・ボーイですね。あそこらへんが跳ねた。その理由は『Myspace』っていうSNSです。SNSで「Do It Yourself」のパンク精神が行われたわけですよ。ファンのコミュニティの中で、「これイイよ」「あれイイよ」みたいな話がどんどん回って、レコード会社のプロモーションを通さずにヒットしちゃうみたいな。
永野:そういう流れがあるにはあったんですね。じゃあ、ザ・キラーズはどの文脈にあるんですか?
粉川:メインストリームには大ブレークした「エモ」があって、その下にインディー・オルタナティブでかっこいいけど、メインストリームまでは入れなかったニューウェイヴ/ポストパンク・リバイバルの流れがあります。ザ・キラーズは、そのふたつの流れの中間なんですよ。
永野:へ~!
粉川:キラーズはエモが好きな人たちにも聴かれました。元々はニュー・ウェイヴ出身なんだけど、楽曲を聴くとめちゃくちゃエモっぽかったりするんです。だからニュー・ウェイヴ・リバイバルなのに、エモに匹敵するぐらい売れたんです。
永野:本人たちの狙い通りだったんですか?
粉川:本人たちはめちゃくちゃザ・キュアーとかジョイ・ディヴィジョンとか、ああいうUKの80’sニュー・ウェイヴが大好きなんです。でもザ・キラーズってラスベガス出身なので、どうしてもサービスしちゃうんですよね(笑)。サービス精神旺盛な所が隠せないんです。
永野:イイですね!サービス精神、大事(笑)。
粉川:でも、当時のニュー・ウェイヴ・リバイバルって「カッコいいもの」だったんですよ。例えばギャング・オブ・フォーとかトーキング・ヘッズみたいなカッコいい80’sをリバイバルをしてたんです。 だから(爆発的には)売れないんですよね。でも、ザ・キラーズの80’sってデュラン・デュランなんです。
永野:あ~、ちょっと庶民的というか。
粉川:ニューウェイブ・リバイバルの中でもデュラン・デュランをリバイバルしたら、そりゃ売れるよな!みたいな(笑)。それが(ザ・キラーズの)最初のアルバムだったんです。
永野:このバンド(ザ・キラーズ)ってアメリカですよね?今までイギリスのバンドだと思ってました。
粉川:アメリカのラスベガス出身です。ザ・キラーズのブランドン・フラワーズ(Vo)はめちゃくちゃUK好きなんですよ。アメリカ人なんですけど、「俺がロックスターになるって決めたのは、オアシのライブを見たから」って話すような人なので。だからザ・キラーズって今でも、アメリカ本国よりイギリスですごく人気があったりします。
永野:へ~!不思議なバンドですね。
粉川:全アルバムが全英1位を獲ってるんです。もちろんアメリカでも大ブレイクしてるんですけど、イギリスの国民的バンドとも言われてます。
永野:なんでイギリス人はこのアメリカのバンドを認めたんですか?
粉川:やっぱりベースにあるのがUKニュー・ウェイヴですし、イギリス人ってメロディアスなものが好きで、めちゃくちゃキャッチ―ですから。例えばザ・キラーズの1番のヒット曲「Mr. Brightside」はSpotifyで22億回再生以上されてます。ザ・ストロークスの1番有名な曲は多分「Last Nite」ですけど、こっちは6億3000万回再生。それくらい差があります。
永野:(「Mr. Brightside」の音源を聴いて)ああ、こんな感じなんだ。なんかイメージと全然違いました。広がりというか、大きい会場で聞ける音楽ですね。
粉川:そうなんですよ。デビューシングルなのに音の分厚さとキラキラした感じがアリーナ・ロックみたいになってるんです。あとこのバンド、ヴォーカルがキーボード担当なんですよね。シンセがバンバン鳴ってる感じが、ストロークスの“ギター・ベース・ドラム・ヴォーカルのみ”みたいなシンプルな感じと比べると、わかりやすいじゃないですか。
永野:変な言い方ですけど、(ザ・キラーズは)お客さんに対して「良かれと思ってやってる」っていう感じがしますね。ザ・ストロークスもかっこいいですけど、 あの系統ってちょっと「わかるヤツだけ来いや」みたいな感じするから。
粉川:ザ・ストロークスは別に「売れよう」と思ってないですから。ハングリー精神が無いわけですよ。
永野:(ザ・キラーズの曲は)「あなたに捧げます!」みたいな感じしません?
粉川:はい、「みんなで一緒に歌いましょう」なので。
永野:全然違うんですけど、マイ・ケミカル・ロマンスを聴いたときのことを思い出しました。
粉川:あー、もう、おっしゃる通りです。マイケミっていうのは、言わばエモなんですよ。ザ・キラーズとは逆のパターンです。ザ・キラーズはニュー・ウェイヴ出身でエモまで行ったパターンですが、マイケミはエモなんだけども元々はザ・キュアーとかが大好きで、根っこにあるのはニュー・ウェイヴなんです。マイケミとザ・キラーズは別の出自から同じ場所でヒットしたんです。
永野:マイケミの「Welcome To The Black Parade」、いい曲ですよね。キャッチーで、みんなを楽しませたい!みたいな感じがして。それにしても、ザ・キラーズがこんなバンドだとは思ってなかったです。キラーズ(殺し屋)って名前で、もうちょっとカッコつけてると思ってたら、全然違いました。
粉川:全然違うんです。カッコつけないんです。ベタなんです。
永野:2枚目のアルバムの『Sam’s Town』のビジュアルを撮影したのが、アントン・コービン(※U2やデヴィッド・ボウイらの作品を手掛けてきた写真家)なんですよね。
粉川:ザ・キラーズはアルバムごとに全然違って、1作目でキラキラのシンセポップをやるんですけど、2作目ではルーツのアメリカン・ロックに戻るんですよ。ちょっと煤けた感じの、ブルージーでヒューマニックでオーガニックな音に戻る。彼らは2ndアルバムでブルース・スプリングスティーンやU2みたいなことやりたかったんです。極論言うと、この作品はU2の『The Joshua Tree』です。
永野:へえ~!じゃあもう、ザ・キラーズは1stと2ndだけで世界狙ってるってことですね。
粉川:そうなんです。
永野:変な言い方ですけど、“俺たちはこれでいいんだ系バンド”っているじゃないですか。でも、ザ・キラーズはビッグになりたいんですね。ショウ(ライブ)としてはどうなんですか?
粉川:“エンターテイメント”です。キーボードも電飾ギラギラしてて、フロントマンのブランドンはエルヴィス・プレスリーみたいで。
永野:そういうの、好きなんですよ。やっぱり楽しませてくれる人が好き。ザ・キラーズはオアシスが好きって言ってましたけど、僕は昔1stしか出してないくらいの時期のオアシスのライブ映像を観て、「なんてつまらないライブなんだ」と思いました。泥棒みたいな顔した兄弟が「オオァァ~」とかやってて(笑)。オアシスって、曲が良いのはわかるんですけど、僕が他のみんなほど熱くなれないのは、ライブが面白くないからなんですよね。
粉川:オアシスはサービスしないですね。リアム・ギャラガーの名言に「ライブは戦いだ。オーディエンスより俺の方が上だと見せつけるために演ってる」というのがあります。
永野:ザ・キラーズは「オアシスが好き」って言ってますけど、僕はUKのロックよりアメリカのロックのほうが好きだから「ザ・キラーズ、好きだな」と思いました。この、ちょっと大味な感じというか。
粉川:わかります。ザ・キラーズはUKがベースにあるんだけど、やっぱり大味な感じはします。大地を5~6時間ドライブしなきゃ次の州に行けないみたいなスケール感がありますよね。
永野:U2もEcho & the Bunnymenとかと一緒に出てきたけど……。
粉川:U2はスタジアムに行けたけど、Echo & the Bunnymenは行けませんでしたね。
永野:U2はちょっとイジられる存在じゃないですか。
粉川:U2はアイルランド人なのにアメリカンな『The Joshua Tree』を出すんですよ(笑)。
永野:あれ、今考えたらただの生意気なガキですよね(笑)。28歳くらいのヤツが変なカウボーイハットかぶって、B.B.キングと一緒に演って。
粉川:でも、あのくらいの厚顔無恥さというか、自分に対する確信がないとスタジアムには行けないわけですよ。ザ・キラーズもそういうバンドなんです。
永野:それで言うと、オアシスもそうなんですか?
粉川:オアシスは時代背景として“ブリット・ポップ”だから、大してアメリカ目指してないです。あれはアンチ・グランジ、 アンチ・ヤンキー(アメリカ)から始まった文化なので。たとえば「Live Forever」って曲があるじゃないですか。あの曲はグランジの「俺はもう死にたい」「俺はもう負けだ」ってメンタリティが本当に嫌いだからできたんです。
永野:そうなんですか?
粉川:「“死にたい”とか何だかんだ言えるのはお前が恵まれてるからだ」「俺は今、失業保険もらってギターも買えないような状況なんだから、明日をより良くするために、将来成功するために歌ってるんだ」って感じです。
永野:あ~、だからオアシス合わなかったんだ。僕、仕送り貰って悩んでたようなヤツなんで(笑)。なんか僕って、“最後のグランジ”なんですよね。3食ご飯を食べながら、ずっと憂鬱な気分でいたいんですよ、今も。だから一生オアシスの気持ち、わからないかもしれない。Live Foreverって言われるより、「死にたい~」とか言いながら高いお肉食いたいです、スイマセン!(笑) でも、前YouTubeチャンネルで言いましたよね。「オルタナとグランジは金持ちの道楽」って。ザ・キラーズはどうなんですか?
粉川:どっちでもないです。ザ・キラーズはもう“その次”の段階です。ロックバンドのハングリー精神とか、ロックバンドの悩みとか、病んだ感じとかっていうものの、さらに次の段階です。もうポップスとして売れますよ。歌詞とかあんまり意味ないですから。
キラーズはデュラン・デュラン
永野:昔のバンドでいうとザ・キラーズは誰にあたるんですか?
粉川:うーん……デュラン・デュラン(笑)。
永野:やっぱりデュラン・デュラン(笑)。それで、ザ・キラーズはフジロックに来るわけですね。
粉川:はい。初日のヘッドライナーです。彼らはライブが凄いバンドなんですよ。というのも、2007年から毎年さまざまなフェスのヘッドライナーをしています。毎年5回とか10回とか。そんなバンド、今この世界にいませんよ。
永野:これはもう楽しみですね。ザ・キラーズ、盛り上がるでしょうね。
粉川:しかも、日本の特殊事情として、ザ・キラーズは日本でだけ人気が無かったんですよね。
永野:マジで何故?だって数曲聴いただけで凄かったのに。
新井D:永野さんもさっき「こんな音じゃないと思ってた」って言ってたじゃないですか。僕も最初、そう思いました。インディーズのちょっと尖ったバンドだと思って聴いたら、思ってたのと違って。
粉川:そうなんですよ。2004年当時、ユニバーサルはザ・キラーズをザ・ストロークスやフランツ・フェルディナンドみたいな、オシャレで尖ったカッコいいニュー・ウェイヴ・リバイバルバンドとして売ろうとしたんです。でも、ザ・キラーズはデュラン・デュランなんですよ(笑)。
永野:当時「これは令和のデュラン・デュランだ!」くらい書いてれば良かったかもしれませんね(笑)。
粉川:それについては私も当時『rockin’on』にいたので、自分も同罪だと思ってます(笑)。やっぱりポスト・パンクとして(評論を)書いてましたから。
新井D:当時、粉川さんのその文章読んで「違うなあ」と思ってました(笑)。
永野:実際には映画『007』の主題歌とかもイケそうなタイプですよね。ちょっとこれ、ここから(日本での評価)取り返しましょうよ。だって世界ではフェスの大トリやってるんですよ?
粉川:(ライブ)見て貰えば「凄い!」ってわかります。
永野:(日本のオーディエンスを)ビックリさせたいですよね。民族衣装着てゴミ拾いしてる“麻系カップル”を集めて(笑)。
粉川:あと、音楽聞かずに川遊びしてる人たちも(笑)。
永野:ザ・キラーズを聴いて身体が動き出すけど、彼氏の前では変拍子が好きなフリしてたから我慢しちゃって、でも最後の曲では解放されて、「自分は元々こういうのが好きだったんだ~!」ってなってくれたらいいですよね(笑)。でも日本でのザ・キラーズの評価は、粉川さんもユニバーサルも含めて、(日本の音楽業界)全体の罪だと思います。
粉川:それは認めます(笑)。
永野:粉川さんもそのときは民族衣装着てたんですよ(笑)。本当は粉川さんだって「デュラン・デュランみたいでカッコいい!」って書きたいのに……。
粉川:そのときは「ザ・キュアーの影響を受けて~」って書いちゃったんです(笑)。「令和のデュラン・デュランだ!」くらい書けばよかった。
永野:もうやめよう!無理すんの!フジロックをいい機会として(笑)。最後に粉川さんに聞きたいんですけど、ザ・キラーズを知らない人が初めて聴くとしたら、どのアルバムからがいいですか?
粉川:ベスト盤から。ロックバンドって“アルバム縛り”みたいなものがあるじゃないですか。アルバム至上主義というか、「アルバム単位で聴かないといけない」的なやつ。でもザ・キラーズに関しては、そういうのは特にないです。曲単位で聴いてください。曲がとにかく良いので。
永野:そうですね、令和のデュラン・デュランですからね(笑)。ということで粉川さん、今回はありがとうございました。またお話しましょうね。
粉川:ぜひオルタナ話しましょう。マニック・ストリート・プリーチャーズの話したいです(笑)。
永野:マニックス!じゃあ今度はマニックス対談しましょう!
YouTube永野チャンネル
https://www.youtube.com/@nagano-channel
ザ・キラーズ「FUJI ROCK FESTIVAL’24」セットリスト
Apple Music / Spotify / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube
- ザ・キラーズ アーティスト・ページ
- 【2020年の記事】なぜ、ザ・キラーズは日本でブレイクできないのか?
- The Killersはようやく日本でブレイクするのか?
- ザ・キラーズとブルース・スプリングスティーンの初の共演曲が公開
- コロナ禍での最新作『Imploding the Mirage』の魅力とは
- ザ・キラーズ『Hot Fuss』解説 :「Mr. Brightside」とデビュー盤
- ニルヴァーナのベスト・ソングス20曲:グランジを代表した世代の代弁者