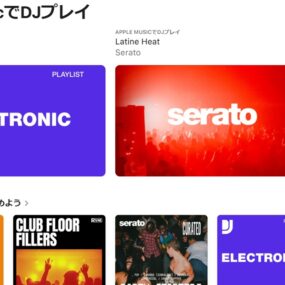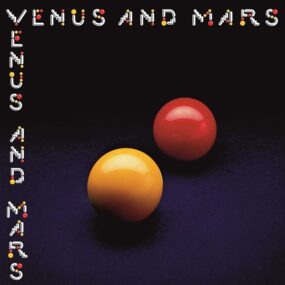IN-DEPTH FEATURES
バンド後にも人生がある:ソロとなり、ナンバー・ワンの地位を築いたアーティスト達


ポピュラー音楽界において、ソロになるということは、最も恒久的な通過儀礼のひとつだと言えよう。成功を収めたバンドやグループの主要メンバーであれば(もしくは、そこまで中心的というわけではないメンバーであっても)、遅かれ早かれ“ソロ”という熱病に感染するものだ。今回は、バンド脱退後もしくは解散後、ソロ・アーティストとしてより大きな栄光を掴むこととなった重要アーティストの幾人かに敬意を表していきたい。
フロントマンがソロに転向するという伝統には、ロックン・ロールそのものと同じくらい古い歴史がある。その代表例が、アメリカ初の偉大なる“自己完結”型ロック・バンド、ザ・クリケッツのリーダーだったバディ・ホリーだ。 バディ・ホリー率いる公式バンド、ザ・クリケッツ(ベーシストのジョー・モールディン、ドラマーのジェリー・アリソン、そして初期にリズム・ギターを担当していたニキ・サリヴァン)は、僅か1年(1956〜57年)という短い活動期間にもかかわらず、ロックン・ロールの礎として十分過ぎるものを生み出したのだ。
[layerslider id=”0“]しかし、ホリーはバンド活動と並行してソロ曲を録音しており、クリケッツは彼のソロ作品の方でも演奏していたため、その2つを区別するのは難しかった。「Peggy Sue」と「Words Of Love」がバディ・ホリーのレコードだった一方、「That’ll Be the Day」と「Oh Boy」は公式にはザ・クリケッツのレコードで、1957年にはその4枚のシングルが全てチャート入りを果たしている。ホリーは1959年に飛行機事故で命を落とし、22歳の若さでキャリアを断たれたが、そこに至る前、バンドとは徐々に距離を置くようになっており、「It Doesn’t Matter Anymore」を手がけたポール・アンカを含む他のソングライターと協力して、クリケッツとは異なる大人向けのサウンドを作り出していた。ホリーが次に目指していたものが世界の人々の耳に届くことはなかったが、彼が踏み込んだ領域——即ち、バンドからゆっくりと少しずつ離れ、その後、新しいコラボレイターを見つけ、音楽的に新たな分野へ手を広げること——は、ソロ・キャリアに乗り出す際のテンプレートとなった。
他にも2人の初期ロッカーが、長期に渡る(そして実際、今も現役で)ソロ・アーティストとしてのキャリアを成功させている。ディオンことディオン・ディムーチは、60年以上に渡り数多くの作品を世に送り出しているため、彼が最初に飛ばしたヒットが、ニューヨークを拠点とする典型的なドゥーワップ・グループ、ディオン&ザ・ベルモンツのフロントマン時代であったことは忘れられがちだ。ディオンはヘロイン中毒から立ち直った後(そう、彼はその点でも時代を先取りしていた)、当時はそれほど前途を見込まれていないまま、1960年にソロ・シングルをリリース。その「Lonely Teenager(邦題:恋のティーンエイジャー)」はヒットしたものの、典型的なお涙頂戴モノのティーン・アイドル・ソングのように聞こえ、それまで彼のトレードマークとなっていた荒っぽいやんちゃさが欠けていた。だがディオンは翌年、その後数十年に渡って“やんちゃさ”の手本となったシングル「The Wanderer」を発表。批判的だった人々をも引っくるめ、世間を黙らせた。
フォー・シーズンズのフランキー・ヴァリが1967年に「Can’t Take My Eyes Off You(邦題:君の瞳に恋してる)」でソロ・ヒットを飛ばした際、グループはまだ活動中であったが、グループの方の曲の売れ行きは徐々に下火に向かっていた。彼のソロ曲は、グループと同じプロデューサー、同じアレンジャーが担当し、同じレーベルからリリースされていたものの、フォー・シーズンズの作品とは異なっていることは明らかであった。そのサウンドは基本的に、フォー・シーズンズのソングライターだったボブ・ゴーディオによるバート・バカラックへのオマージュとなっており、ファルセットも全く用いられていない。年を経るごとにフランキー・ヴァリが優先されるようになると、フォー・シーズンズは目立たない位置へと追いやられていき、フォー・シーズンズとフランキー・ヴァリの両方がそれぞれ再びヒットを飛ばしたディスコ時代(前者の「Who Loves You」と、後者の「Swearin’ To God」)ですら、それに変わりはなかった。現在では、フォー・シーズンズと言えば、フランキー・ヴァリがステージに立つ際のバックアップ・シンガー陣に与えられる名前にすぎなくなっている。
60年代にソロで成功したアーティストは数少なかったが、70年代が目前に迫った頃、史上最も重要な解散劇が現実のものになろうとしていた。ザ・ビートルズが解散を発表したのは、1970年4月のこと。だが同年には、ザ・ビートルズの元メンバー達により、それぞれソロ・アーティストとして5作のアルバムが生み出されてもいる。リンゴ・スターの『Sentimental Journey』(その半年後には、2作目『Beaucoups Of Blues』を発表)、ポール・マッカートニーの『McCartney』、ジョン・レノンの『John Lennon/Plastic Ono Band』、そしてジョージ・ハリスンの3枚組LP『All Things Must Pass』がそうだ。よって数的には、5枚以上のアルバム(加えて、ジョン・レノンによるアルバム未収録の名曲シングル「Instant Karma!」)が、1年以内にファンのもとに届けられたことになる。それは最悪の時代における、最高の時代であった。ジョン・レノンの『Plastic Ono Band』や、ジョージ・ハリスンの『All Things Must Pass』といった傑作、そしてポール・マッカートニーの「Maybe I’m Amazed」といった名曲は、それぞれ同等に感銘を与えてくれる音楽的な成果として実を結んだと言えよう。
https://www.youtube.com/watch?v=tlKX-m17C7U
それとほぼ同じくらい重大な事件が1968年後半に起きた。クリームの解散だ。翌年には、ブラインド・フェイスが始動。エリック・クラプトンはその直後からソロ・キャリアに乗り出し、以後ライヴを行う際は、クリームの曲を少なくとも1曲は演奏するのが常となっている。ジャック・ブルースとジンジャー・ベイカーのソロ作品は、商業的にはそこまで大きな波は起こさなかったものの、ブルースはジャズ・ロック・フュージョンの誕生を先取り(彼の2作目のソロ・アルバム『Things We Like』には、マハヴィシュヌ・オーケストラ結成前のジョン・マクラフリンが参加)しており、またジンジャー・ベイカーはフェラ・クティと定期的にコラボレーションするなど、アフリカ音楽の豊かさを発見した最初のロック・スターの1人となった。エリック・クラプトンがジンジャー・ベイカーと結成したブラインド・フェイスの一員だったスティーヴ・ウィンウッドもまた、当時ソロ・アーティストの道を進もうとしていたが、彼の最初のソロ作になる予定だったアルバム(楽器演奏の大半を彼自身が担当)は、代わりにトラフィックの3作目『John Barleycorn Must Die』として、第二の命を与えられた。現在まで続いているソロ活動をウィンウッドが本格的に開始したのは、1977年になってからである。
また、60年代後半に結成されたクロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングは、それぞれがソロ・キャリア(及び2人組として、そして3人組としてのキャリア)を追求するのに忙しく、グループとしての活動に多くの時間を費やすことが出来なかった。1970年に彼らが発表した『Déjà Vu』は、文化的な流れに大変革をもたらしたアルバムであり、台頭しつつあったシンガーソングライター・ムーヴメントにおける歴史的な作品だ。しかし程なくして、バッファロー・スプリングフィールド解散後に既にソロ・アーティストの仲間入りをしていたニール・ヤングを含め、メンバーそれぞれが皆、好機を捉えてソロ・アルバムを制作。その後クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングはバンドとして、全く理屈に合わない行動に出た。彼らは、完成してもいなければリリースされてもいない1974年に発表予定だったアルバム、仮題『Human Highway』を軸にした大規模なスタジアム・ツアーを行うという、グループとして前例のない務めを果たすことになったのである。彼らはその後、30年の間に2度、スタジオで再結成を果たした。しかしメンバー達が常にどれほど疎遠に見えようと、ファンはこれからももっと多くを期待していくことだろう。
70年代初頭、文化的重要性という意味において、ザ・ビートルズに匹敵可能なものが米国にひとつあったとするなら、それはモータウンだ。そしてモータウンの創業者ベリー・ゴーディは、グループとはある意味、ソロ・アーティストが名を上げるための足掛かりに過ぎないと考えていた、と言っても過言ではない。ダイアナ・ロス&シュープリームスほど華々しい幕切れを飾ったグループは当時初めてで、ダイアナ・ロスは1970年1月、ネバダ州ラスベガスで行われたフロンティア・ホテル公演を最後に脱退。同コンサート全体が2枚組アルバム『Farewell』に収められているが、そこではこの公演の特別感が実際の音楽を凌駕している。新たなリード・シンガーとしてジーン・テレルを迎えた新生シュープリームスのキャリアが当初、ダイアナ・ロスのソロ活動よりも強力なものだったことは忘れられがちだ。彼女達が非の打ち所のない「Up The Ladder To The Roof」でヒットを飛ばしていた頃、ダイアナ・ロスはまだ雌伏の時を過ごしていた。だが同年後半、ダイアナ・ロスがシングル「Ain’t No Mountain High Enough」で全米1位を獲得すると、その競い合い、そして、シュープリームスのグループとしてのキャリアの大部分は永遠の終わりを告げることとなる。
結局、モータウンのグループでフロントマン/ウーマンを務めていた人々の大半が、最後にはソロ・アーティストとしての腕を試すに至った。テンプテーションズの元リード歌手であったデヴィッド・ラフィンとエディ・ケンドリックスは、グループ在籍中に、それぞれソロ・ヒット(前者の「My Whole World Ended」と、後者の「Keep On Truckin’」)を飛ばしている。スモーキー・ロビンソンの場合は、1972年にザ・ミラクルズを脱退後、今ひとつ結果の出ない状況が続いており、彼が「Cruisin’」でトップ10に返り咲くまでには、7年の歳月を要した。先に成功を収めたのは、ディスコ調の「Love Machine」がヒットした、新生ミラクルズの方だ。モータウン所属グループのリード・シンガーは、ソロにならなかった場合でも、少なくとも自身のグループで主役を務めていた(例えば、スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズや、マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラスなどの名義を見れば分かる)。そして言うまでもなく、ジャクソン5で歌っていた“あの子供”は、1人でもかなり大きな成功を収めた。その手始めが、1972年の「Got To Be There」であった。
70年代に台頭したもうひとつのR&B大国が、ジョージ・クリントンのファンキー帝国だ。ジョージ・クリントンは多才な人物であったが、中でも彼は、契約の際に相手を煙に巻くことにかけては達人であった。パーラメントとファンカデリックは本質的には同じバンドであったが、にもかかわらず両者を別々のレーベルと契約させた上、同じメンバーで更に、その華やかなベーシスト(ブーツィー・コリンズ)を前面に据えた、ブーツィーズ・ラバーバンド名義でもグルーヴィーな作品をレコーディングしている。また、Pファンクのミュージシャン勢(エディ・ヘイゼル、バーニー・ウォーレル、フレッド・ウェズリーら)をソロ・アーティストにするためにも、幅広い取り組みが続けられた。80年代、ジョージ・クリントンが自身の名義でレコードを作り始めた際も、同じ顔ぶれの多くが演奏に参加したため、結局、構成メンバーの大幅なシャッフルには至っていない。彼の最初のソロ・ヒット・シングル「Atomic Dog」(アルバム『Computer Games』収録)は、実際にはファンカデリックの最後のアルバム・セッションの使い残しであり、ジョージ・クリントン名義のアルバムには常に大勢のゲスト・スターが参加。近年、彼はその全てを引っくるめ、ジョージ・クリントン&パーラメント・ファンカデリックとしてツアーを行っている。全てまとめて、グルーヴの旗の下に結束している一国家なのだ。
一方、異なる世界では、プログレッシヴ・ロックの系図が凄まじい勢いで分岐し拡大していた。キーボード奏者のリック・ウェイクマンがイエスを離れ、オーケストラから、ナレーター、合唱団、そして空気を入れて膨らませる怪物達までを使って繰り広げた壮大な公演を行い、それを収めたライヴ・アルバム『Journey To The Centre Of The Earth(邦題:地底探検)』を1974年に発表すると、度を超えた壮麗さのレベルは更に新たな高みに達した。同作は商業的にも大ヒットし、全米3位を記録。アメリカでは、その時点までにイエスがリリースしていたどの作品をも上回る結果となった。それに負けじと、イエスの当時のメンバー5人全員がソロ・アルバムを作ることが出来るよう、バンドは一時的に分裂。自身ではヴォーカルを取らないドラマーのアラン・ホワイトまでもが、パブ・ロック時代の旧友達を集めてソロ・アルバム『Ramshackled』を制作した。このような傾向はプログレッシヴ・ロック界隈でちょっとした流行りとなり、ムーディー・ブルースやエマーソン、レイク&パーマーも、この頃一時バンド活動を停止し、それぞれのメンバーがソロ・アーティストとして活動。両ケースで大きな疑問となったのは、歌を担当しないドラマーが何をやろうとしていたのか?ということだ。カール・パーマーのソロ・アルバム(最終的には、1977年に発表されたELPの2枚組アルバム『Works Volume 1』として結実)では、彼がビッグ・バンドを率いていたのに対し、ムーディーズのグレアム・エッジは、エイドリアン・ガーヴィッツと組み、彼にヴォーカル/ギターの重労働を任せて2枚のソロ・アルバムをリリースしている。驚くことではないが、バンドの再集結前、最もムーディーズに近い作品を制作していたのは、フロントマンのジャスティン・ヘイワードとジョン・ロッジ——まずは共にブルー・ジェイズとして、その後は別々にソロとして——であった。
“歌わないドラマー”の苦労とは全く無縁だったプログレッシヴ・バンドとして、際立っていたのがジェネシスだ。フィル・コリンズのソロ活動は恐らく大規模なものになるだろうと、ファンは予想していただろうが、実際あそこまでの大成功を収めるとは思っていなかったかもしれない。特に彼のソロ・デビュー作『Face Value』が、離婚という辛い経験を受けて、胸のつかえを下ろすための作品として着手されていたからだ。フィル・コリンズと、ジェネシスの元ヴォーカル担当だったピーター・ガブリエルは、80年代にソロ・アーティストとして、予想外なまでの大々的な商業的成功を収めた。とは言え、『The Lamb Lies Down On Broadway(邦題:眩惑のブロードウェイ)』を聴いていた人の中に、ピーター・ガブリエルの「Sledgehammer」やフィル・コリンズの「Sussudio」を予測し得た者が誰1人いなかったとしても無理はない。更に驚いたことに、ジェネシスの中で最も控えめなメンバーだったギタリスト兼ベーシストのマイク・ラザフォードもまた、マイク&ザ・メカニックスで大きな成功を収めた。同じく驚いたのが、キーボード担当のトニー・バンクスのソロ活動が、そこまで成功しなかったことだ。というのも、ジェネシス全盛期に作曲の中心を担っていたのは、彼だったからである。それでも、プログレ時代への回帰を切望していたジェネシス・ファンは、バンクスのソロ作をチェックせねばならない。うち2作は、バンドが最終的に解散した後に制作した、クラシック音楽のアルバムとなっている。
ロキシー・ミュージックとフェアポート・コンヴェンションもまた、60年代末から70年代初頭にかけて最も重要なソロ・アーティストを生み出したバンドの座を競い合う、2大グループだ。ブライアン・イーノは、他の誰かのバンドに所属していたような風情を全くといって感じさせなかった。彼はロキシーで2枚のアルバムを制作後、バンドを脱退。ダチョウの羽が付いた衣装を洋服ダンスにしまい、ロバート・フリップやドイツの実験音楽家クラスターといった実験音楽仲間と共に、様々な音の戦法を試し始めた。その後、トーキング・ヘッズやU2といった注目のバンドが彼に声を掛けるようになり、イーノは突如として、世界で最も人気の高い、そして最も興味深いプロデューサーの1人となったのである。一方、フロントマンのブライアン・フェリーは当初、ロック以前の時代のスタンダード曲を皮肉まじりに取り上げたソロ作を発表したが、ロキシーがバンド活動を終えた後は、ロキシー伝統のエレガント・ポップを継承していった。
英国の伝統的な民謡や古謡をカバーすることで知られていたフェアポート・コンヴェンションからは、世界的に有名なシンガーソングライターとなるソロ・アーティストが少なくとも2人輩出されている。一時代を代表する声の持ち主だった故サンディ・デニーが、現役時代にスーパースターの座を得なかったのは理解しがたいことで、彼女は現在まで、とりわけ「The Battle Of Evermore」で彼女の声を聞いたレッド・ツェッペリンのファンから愛され続けている。伝説によると、リチャード・トンプソンの1972年のソロ・デビュー作『Henry The Human Fly』は、当時ワーナーからリリースされたアルバムの中でも最低の売れ行きであったという、彼はこのことに誇りを持っており、その後長年の間、インタビュー等で何度かそれに言及していた。だが最後に笑ったのはリチャード・トンプソンであると言っても過言ではない。彼はその後40年以上に渡り、ロック界で最も称賛されたソングライター/ギタリストの一人となったのだから。だが、忘れてはならないのが、フェアポート・コンヴェンションのオリジナル・ヴォーカリストだったイアン・マシューズだ。彼に対する評価はカルト・レベルに留まっているかもしれないが、同時に彼は、シングルがトップ40入りした唯一のフェアポート・コンヴェンションのメンバーでもある。つまり、1971年にマシューズ・サザン・コンフォート名義でリリースした「Woodstock」と、その7年後に発表したソフト・ロック・ナンバー「Shake It」がそれだ。
ソロ・キャリアの中には、楽々と成し遂げたように思えるものもある。『Synchronicity』を最後にポリスは活動を停止したが、その頃までには、スティングが別の方向に、即ち歌詞的により深く、もっとジャズ寄りで、レゲエ色を薄めた方向に進みつつあったことは明らかだった。従って、彼がソロ・キャリアに乗り出すに当たっては大きな急転が起きたわけではなく、ポリス・ファンの大部分がついてきたことに驚きはない。同様にダイアー・ストレイツもまた、最後のアルバム『On Every Street』を出す頃までには、マーク・ノップラーが主導し、他がそこに手を貸す形へと急速に変化を遂げていた。より穏やかなカントリー調となったそのスタイルは、ノップラーのソロ・デビュー作『Golden Heart』や、その後の彼の大半の作品群への自然な橋渡し役となった。一方、ベーシストのジョン・イルズリーによるソロ・デビュー作『Never Told A Soul』は、ノップラーの大部分のソロ作品と比べ、旧来のダイアー・ストレイツにより近いものだと言える。
ブロンディでソロとして成功を収めた唯一のメンバーは、正に誰もが予想する通りの人物だ。実際、デボラ・ハリーのソロ・アルバムは、ブロンディにおける彼女のパートナー、クリス・スタインが全作に参加していることから、事実上ブロンディのアルバムと言って差し支えない。彼女のソロ・デビュー作『Koo Koo』と言えば、スイス人アーティストのH・R・ギーガーによるシュールなジャケットで有名だろう(H・R・ギーガーが手掛けたアートワークには、後にデッド・ケネディーズを大きなトラブルに巻き込むことになった作品もある)。しかし、同アルバムのファンキーなニューヨーク・サウンドは、「Rapture」時代のプロンディとさほど遠くないものであった。だが、彼女のソロ作品の中でも、とりわけ“埋蔵された宝物”と言えるのが、1989年のアルバム『Def, Dumb & Blonde』だ。ガール・グループ調ポップのみならず、パンクやファンクをも思い出させてくれるこの作品。ジャケットにバンド名が書かれていないことを除けば、そこにはブロンディ・ファンに訴えかける全てが備わっていた。
本来なら、ロック・スター的な態度を完全に消し去らなければならないはずのパンクですら、それ相応のソロ・アーティストを生み出している。当初セックス・ピストルズに衝撃を受けた人の中に、ジョニー・ロットン(ジョン・ライドン)が将来長期に渡って、音楽的な革新者となることを予見していた者は誰もいなかったと言って間違いない。しかしながら、パブリック・イメージ・リミテッド唯一の不動のメンバーかつリーダーとして、彼は正に音楽的革新者であり続けている(ちなみに、ピストルズのギタリストだったスティーヴ・ジョーンズは、現在ではハリウッドでお馴染みの顔となり、ラジオ番組の司会者として人気を得ているが、それは恐らくそこまで困難な仕事ではないだろう)。一方、ラモーンズは、史上最も風変わりなソロ・アルバムを世に送り出したのではないだろうか。ここで話しているのは、ディー・ディー・ラモーンの『Standing In The Spotlight』のことだ。言うなれば、これはカルト的な名盤であり、ディー・ディー・ラモーンはそこで、ラッパーのディー・ディー・キングに変身していた。だが、着実なソロ・キャリアへの道を歩んでいたように思われたジョーイ・ラモーンには、涙を禁じ得ない。現実と病とが、それを阻んだのである。彼の唯一の公式ソロ・アルバム『Don’t Worry About Me』は、どんな名義であれ、最高のラモーンズ作品であった。
公衆の面前で成長を遂げたパンク・ロッカーが、もう1人いる。イギー・ポップだ。彼は、大混乱に陥った1974年のツアー中、ストゥージズが内部分裂を起こした(公式ブートレグの『Metallic KO』に、その内情が記録されている)後、“霞んで消えていくくらいなら、いっそ燃え尽きた方がいい”という考えを実現した。デヴィッド・ボウイという名のイギー・ポップの大ファンに説得され、彼がスタジオに戻ったのは、その3年後。イギーとジギーは手を組んで、1977年に『Lust For Life』と『The Idiot』という2枚のアルバムを作った。
イギー・ポップが不朽の名声を得ているのは、彼が何であれ自分の好きなことを——つまり、パンク・アルバムであれ、アート・ノイズ・アルバムであれ、フレンチ・シャンソン・アルバムであれ、何でも望みのままに作り続けているからだ。もし彼が示唆していた通り、2016年の『Post Pop Depression』(クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのジョシュ・ホーミが参加した、モダン・ロックン・ロール作)が彼の最後のアルバムになるとしても、キャリアの締めくくり方としては悪くないだろう。
そして、ポール・ウェラーにも喝采を送ろうではないか。彼もまた、一度ならず変身を遂げてきたパンク・ロッカーの1人だ。ザ・ジャムの伝説が年を追うごとに強力なものになっていくのと同じくらい、バンドの再結成は絶対にあり得ないというポール・ウェラーの主張も強固なものになっている。彼は自身のライヴで、ザ・ジャム時代のヒットを2、3曲披露はするが、それが全てだ。周りに何を言われようとも、ポール・ウェラーは自らのアーティストとしての信念を守り続け、掲げてきた理想に忠実であり続けている。モッズにとっては、先を見据えるというのが全てであり、後ろを振り返ることに意義はない。そして、2017年のアルバム『A Kind Revolution』を含め、彼の進化を追ってきた人々にとって、それはノスタルジーに浸るより、遥かに大きな報いとなっている。
現時点では、伝説的なバンドのスター達の中で、ソロ・アーティストとして活動したことのない人の名前を上げる方が簡単かもしれない。アクセル・ローズは『Chinese Democracy』を数に入れないとすれば1枚もソロ・アルバムを出していないし、ボノが思い切った賭けに出たこともない。だが、彼らにはもう少し時間をあげよう。何しろ彼らは、それぞれまだ32年間と43年間しか、自身のバンドのフロントマンを務めていないのだから。
Written By Brett Milano