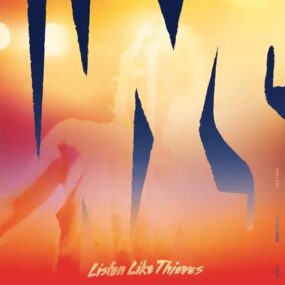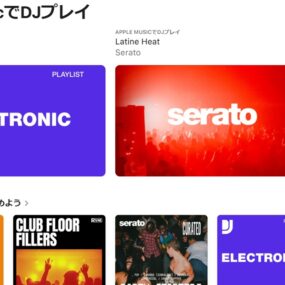News
【特集】ミュージカル映画の栄枯盛衰の歴史を魅力的名作たちとともに振り返る


ミュージカル映画は最も純粋なるアメリカ的アート・フォームのひとつであり、やがて世界中へと輸出されることになった。西部劇は元々カウボーイを主人公にした三文小説から生まれたが、ミュージカルはハリウッドそのものと二人三脚で発展してきたものである。過去90年以上、この映画ジャンルは自由と、自己表現と、人生と言うイエロー・ブリック・ロードを辿って夢を追い求めるという行為を讃えてきたのだった。
ミュージカル映画は芝居の合間に歌が入るというより、メインの登場人物による歌やダンスがたっぷりと盛り込まれている。このジャンルには、各年代毎に様々な浮き沈みがあった。絶頂期は間違いなく、フレッド・アステアやジュディ・ガーランドのようなスターたちが、数え切れないほど多くのヒット映画でスクリーン狭しと歌い踊っていた30年代で、そして舞台劇にインスパイアされたミュージカル映画が華やかなりし50年代から60年代も黄金期だった。1990年代という端境期とみなされる年代においてさえ、『エビータ(原題:Evita)』のような珠玉のミュージカル映画が生まれている。
年を経て、ハリウッドのミュージカルはまさしく気晴らし的エンターテインメントの縮図を形成するまでになった。例えば『雨に唄えば』や 『サウンド・オブ・ミュージック』、あるいは『ラ・ラ・ランド』などは明らかに現実逃避的とは言え、映画そのものを最も象徴的に表わす作品と言えよう。『スタア誕生』がレディー・ガガの主演で4度目のリメイクが行なわれたという事実は、業界の嗜好性が殆ど変わっていないことを示す何よりの証拠である。
<関連記事>
・映画音楽作曲家とサントラの歴史
・ジュディ・ガーランドはなぜゲイの人々から支持されたのか?
・ハリウッド史上最高の映画挿入歌50選
1920年代:ミュージカル映画の誕生
音楽と映画は昔から常に切っても切れない関係にあった。ルドルフ・ヴァレンティノが1921年の映画『黙示録の四騎士』でタンゴを踊った僅か5年後には、 ジョン・バリモアの主演で史上初のヴァイタフォーン[訳注:音声に録音盤を用いた最初期の有声映画のひとつ]によるショート・フィルムで、107人編成のニューヨーク交響楽団の演奏によるスコアが使用されている。
その1年後、最初の長編“トーキー”映画が登場する。1927年、ワーナー・ブラザーズが製作したアル・ジョルスン主演の『ジャズ・シンガー』には、7つの楽曲とスクリーンで登場人物が交わす数行の会話がフィーチャーされていただけだったが、その衝撃度は絶大だった。
しかしハリウッドは客に映画を見せる方法に抜本的な構造変革が必要であることも自覚した。というのも常客たちは音楽をライヴ・ドラマ形式(ヴォードヴィル演芸/寄席の伝統の肝である)で観ることには馴れていたが、当時まだ音響設備の整っていなかった多くの映画館では、『ジャズ・シンガー』は残念ながらサイレント映画として上映する他なかったのだ。
1928年、アル・ジョルスンの2作目の主演映画『シンギング・フール』が封切られる頃には、 殆どの映画館で新しいサウンド・システムが完備。この“ミュージカル・トーキー”映画は、その後『風と共に去りぬ』に取って代わられるまでの11年間、ボックス・オフィスにおける興行成績歴代1位の座を守り続けた。
1930年代:ミュージカル映画の黄金期
変化のペースは劇的だった。1929年、メトロ・ゴールドウィン・メイヤーズ・スタジオ(MGM)がようやく追いつき、映画『ブロードウェイ・メロディー』でミュージカル映画として初のオスカーを獲得する。その後の10年間、某有名映画歴史研究家の言葉を借りれば、「映画会社はソーセージのように次から次へとミュージカル映画を配給した」。
これはひとつには大恐慌と言う社会背景も影響している。1929年のウォール・ストリート・クラッシュ勃発後、ニューヨークの劇場の多くは閉鎖を余儀なくされた。舞台のスター役者たち――フレッドとアデル・アステアをはじめ、ファニー・ブライス、エディ・カンター、モーリス・シュヴァリエ、マリリン・ミラー等々――はアル・ジョルスンに続けとばかり次々にハリウッドに向かったのだ。また、ブロードウェイの音楽ライターや脚本家たちも、魅力的な契約条件に釣られて新しいメディアへと足を踏み入れた。当時の状況下では、ブロードウェイのプロデューサーたちに舞台の映画化権を売り渡すよう説き伏せるのはたやすいことだった。
同じひとつの映画を何千万という映画館で公開することが可能になり、ハリウッドはブロードウェイとはケタ違いの経済的スケールで機能し始めた。作曲家たちは金の匂いを追いかけ、ハリー・ウォーレンをはじめとするティン・パン・アレイの大物たちもこぞって多くの新作映画に楽曲を提供するようになった。高名な舞台音楽の作曲家ジョージ・M.コーエン(いみじくも ‘Give My Regards To Broadway’[直訳:ブロードウェイによろしく]を書いた人物)が大恐慌中には40本の映画に楽曲提供する一方で、音楽を書き下ろした舞台は僅か6本だったというのは、当時の変化を最もよく表している例かも知れない。
だがハリウッドにとっては、何もかも未経験のことばかりだった。ミュージカル映画の製作においては、確実に成功できる方程式もなければ、確立されたメソッドなども一切なかった。サウンド・エンジニアもいなければ、音声収録機能つきのカメラの扱いに長けた撮影技師(シネマトグラファー)すら存在しなかったのである。これは障害にもなったが、同時に舞台演劇の世界から越境してきた人々にとっては、クリエイティヴな意味で大いなる自由とチャンスを与えられることにもなった。
1930年代に重視されていたのはダンスの要素だった。この10年だけで合計19本のミュージカル映画の振り付けを担当、あるいは監督を務めたロサンゼルス生まれのバズビー・バークリーは、ダンサーたちを鳥の視点のように高い所から撮影し、万華鏡のような画面に仕立てる特徴的かつ官能的な撮影手法を生み出した。
『四十二番街』(1933)のような代表作でフィーチャーされたバズビー・バークリーの躍動感のあるカメラワークは、観客にも自らが振り付けの一部に組み込まれたかのような感覚を与えた。彼は急降下するクレーンを利用したり、舞台の下の奈落にカメラをセットしたり、縦横無尽なショットを実現するために特殊なカメラ用レールを敷設したりと、画期的な撮影手法を幾つも編み出した。また、豊かな想像力が駆使された彼独特の“ムーヴィング・ピクチャーズ”には、ネオンで光るヴァイオリンや巨大な花、滝といった小道具が登場している。
30年代、ワーナー・ブラザーズのバズビー・バークリー映画の唯一のライヴァルと言えば、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースをフィーチャーした一連のRKO(レイディオ・
30年代に作られたミュージカル映画にはいまだに傑作と呼ばれるものが少なくないが、その理由は観客の現実逃避願望が、最上級のエンターテインメントの形で見事に昇華されている点にある。『トップ・ハット』(1935)のフレッド・アステアとジンジャー・ロジャースはまさに絶頂期だった。この映画には圧倒的な力で観客を惹き込むアーヴィング・バーリンの「Cheek To Cheek」や「Isn’t This A Lovely Day?」といった名曲たちが惜しげもなく使われ、贅を凝らしたセットとウィットに富んだプロットは純粋なる歓喜をもたらすものだった。ちなみに、観る者の心を掴んで離さない楽曲は当時、この業界では“Charm Songs”と呼ばれていた。
名作『オズの魔法使』
30年代の終わりに、映画史において未だ最も愛され続けているミュージカル映画のひとつが登場する。ルビーのスリッパその他でもお馴染みのテクニカラー作品『オズの魔法使』(1939)だ。我が家の大切さを謳う温かなファンタジー物語の中で、魅力的なドロシーを演じたのは、ティーンエイジャーだったジュディ・ガーランドだった。映画は無邪気な魅力に満ち、 ハロルド・アーレン作曲、イップ・ハーバーグ作詞による「Somewhere Over The Rainbow(虹の彼方に)」は、今も映画音楽史上屈指の名曲である。
『オズの魔法使』のようなミュージカル映画はリアリズムとは無縁だったので、製作側は荒唐無稽な登場人物たちが様々に歌う曲について、それがどのようにして生まれたものかを説明する必要もなかった。バート・ラール演じる臆病なライオンが唐突に歌い出す前に言う通り、「こいつはもうずっと前から僕の中にいるんだよ。だからとりあえず出してやらなきゃいけないんだ」というわけだ。
『オズの魔法使』はミュージカルが与えてくれる、あるひとつの大いなる喜びが凝縮された作品だ。そして、一種逆説的ながら、恐らくそれこそがミュージカルが最も悪しざまに言われる映画ジャンルのひとつに数えられる理由なのだが、それはつまり、そこは時間が止まり、日常がめくるめく音楽の渦の中に消えて行ってしまう、すべてを超越した非現実の世界であるということだ。
この例は飛行機の翼の上でコーラス・ガールたちが踊る『空中レヴュー時代』 (1933)から『ラ・ラ・ランド』冒頭のハイウェイでの勇壮華麗な連続シーンまで、枚挙のいとまがない。結局のところ、ミュージカル映画の歴史を総括すれば、ジーン・ケリーの『雨に唄えば』での台詞、「踊らずにはいられない」の一言に集約されてしまうのかも知れない。
戦中・戦後のミュージカル映画
第二次世界大戦の開戦も、ミュージカル映画に対する人々の飢餓感を萎えさせることはなかった。このメディアにおいて変わらぬ影響力を誇ったのはジュディ・ガーランドで、『オズの魔法使』に続き、『ブロードウェイ』、『美人劇場』(どちらも1941年公開)、 そして『若草の頃』(1944)と立て続けに主演をこなす。40年代のジュディ・ガーランド出演映画の中で、恐らく芸術的価値よりも商業的な面で意義深かったのは、1946年に公開された作曲家ジェローム・カーンの伝記映画『雲流るるはてに』だろう。ロバート・ウォーカー主演のこの作品は、サウンドトラック・アルバムが制作された最も古い映画のひとつである。
MGMレコードがプロデュースしたこのサントラ盤には、ジュディ・ガーランドやダイナ・ショア、トニー・マーティンらの曲が収録され、当初は4枚組の78回転盤コレクションのうちの1枚としてリリースされた。後にこの音源がLPとしてリリースされると、その成功を受けて、ハリウッドでは映画の補助的な商品としてサウンドトラック・アルバムをリリースすることが慣例となったのである。
当時、ハリウッドにおいて権勢を誇っていたのがアーサー・フリードだった。かつて作詞家として活躍し、『オズの魔法使』ではアソシエイト・プロデューサーを務めたアーサー・フリードは、その同じ年に『青春一座』でも大成功を収める。
MGMにおける彼選抜の “フリード・ユニット” は、トップクラスの俳優、監督、振付師、作曲家、セット・デザイナーを擁するチームだった。彼らは40年代から50年代にかけて、『アニーよ銃をとれ』(1950)、『巴里のアメリカ人』(1951)、『ショウボート』(1951) 、『Gigi 』(1951)をはじめとする40作以上のミュージカル映画の傑作を手掛けた。もっともすべてがMGMの欲しいままと言うわけではなく、この年代において出色のミュージカル映画と言えば、RKOの『オクラホマ!』は確実にその中に食い込んでくる作品だ。
大戦中、アーサー・フリードは新しいミュージカル・スターをブロードウェイからハリウッドへと迎え入れるという大役を果たした。そのスターこそ誰あろう、圧倒的カリスマ性と優美さを兼ね備えたアイルランド系アメリカ人俳優、ジーン・ケリーである。
ジーン・ケリーはダンサーとして、数々の映画に斬新さとバレエのような動きによる生命感を与え、中でもジョージとアイラ・ガーシュウィンの曲を元に製作されたミュージカル『陽のあたる場所 』(1951)は、アカデミー賞で5部門を制覇した。
しかしながら、MGMの傑作は何と言ってもミュージカル映画史上不朽の名作に数えられる『雨に唄えば』(1952)である。徹底的に洗練されたスタイリッシュなフレッド・アステアに対し、ジーン・ケリーには素朴で気取らない魅力がある。映画のタイトル曲をバックに、傘を見事に使いこなし、水たまりでステップを踏む彼のソロ・ダンスは、全映画史を通して最も心躍るシーンのひとつと言えよう。
サイレント映画からトーキーの台頭へのカオティックな移行期を描いたこの作品では、その他の 「Make ’Em Laugh(笑わせろ)」や 「Moses Supposes(モーゼズ)」を含む楽曲もいずれ劣らぬ出来栄えだ。そして、オープニングの「Good Morning」で、ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ、ドナルド・オコーナーの3人が披露する、引っくり返ったソファーを巧みに利用したダンス・ルーティーンを誰が忘れられるだろう?
ロックンロールとミュージカル映画
50年代のミュージカル映画もまた、パワフルな歌唱スタイルを持つスター俳優や女優たちの実力発揮の場だった。ドリス・デイが『カラミティ・ジェーン』(1953)で銃を携え、ムチを鳴らす開拓時代の女性はまさにハマリ役であり、一方マリリン・モンローも同じ年に『紳士は金髪がお好き』で自らの魅力を最大限に振りまいた。
この年代はまた、リチャード・ロジャーズ&オスカー・ハマースタイン2世の『オクラホマ!』(1955) 『回転木馬』(1956)、『王様と私』(1956)、『南太平洋』(1958)といったミュージカルの名作が上質の映画となってスクリーンに登場した10年でもある。中でも『南太平洋』のサントラ盤は空前の大ヒットとなった。アルバムは全米・全英ともにNo.1に輝き、全英チャートでは実に115週にわたってその座を譲らなかった。
時には映画化プロジェクトにリアリティと魅力的な深みを加えるために、ジャズ・ミュージシャンがスクリーンで主役をはることもあった。例えば『上流階級』(1956)のルイ・アームストロング、その数年後の『セントルイス・ブルース』のナット・キング・コールのように。
しかしながら、この年代における大きな変化は、映画産業がロックン・ロールをブレイクさせ、新たなカルチャーとして定着させる上で大きな役割を果たしたメディアのひとつとなったことだろう。ロックン・ロールが“グレイト・アメリカン・ソングブック” の牙城を突き崩したように、ロック・ミュージカルも昔ながらのミュージカル映画に取って代わったのである。
チャック・ベリー、ファッツ・ドミノ、ジーン・ヴィンセント、リトル・リチャード、エディ・コクランといったロック創生期に人気を博したスターたちは、いずれも様々な映画に出演していた。ミュージカルにおけるパフォーマンスの表現方法にも変化が表れた。ステージ・ショウ的なダンスは姿を消し、代わりに登場したのはチャック・ベリーと、かの悪名高き“ダック・ウォーク”だった(映画『ゴー・ジョニー・ゴー』で観ることができる)。
加えて、サウンドトラックにロック・ミュージックを使用することで、レコード購買熱に火を点けることが可能であるとも確認された。社会問題を扱った映画『暴力教室(原題:The Blackboard Jungle)』で、ビル・ヘイリーの「Rock Around The Clock」が使われた際に起こった社会現象はまさにそれだった。
とは言え、ロックが生んだ最大の映画スターと言えば、何と言ってもエルヴィス・プレスリーである。銀幕はザ・キングと彼の悩ましい腰つきを愛して止まなかった。彼は1956年から71年の間だけで、31本の映画に出演を果たしている。その多くの内容はワンパターンで、記憶に残るようなものではなかった――若い男女の出会いと恋が数々のヒット曲を絡めて描かれる――ものの、スタジオにとっては確実なドル箱作品だった。
試算によれば、エルヴィス・プレスリー映画は総額200億ポンド以上を超える興行収入を挙げたと言われている。映画の芸術的価値の曖昧さに、主演アーティスト自身がフラストレーションを味わうことが少なくなかったものの、『監獄ロック』 (1957)のような作品では、何よりも若きスター・ミュージシャンの強い磁力がそのまま画面に表れている。
50年代は決してエルヴィス・プレスリー映画一強の時代ではなく、また劇場版ミュージカル映画化やロック・ミュージックを利用した作品ばかりというわけでもなかった。ディズニーは『わんわん物語』(1955)や『眠れる森の美女』(1959)のような、音楽をベースにしたヴァラエティに富んだ良質なアニメーション映画を続々と公開。また『シェルブールの雨傘』(1964)に代表される、野心的かつクリエイティヴなミュージカル映画も作られた。ジャック・ドゥミによる全編歌い通しの魅力的なオペレッタはカトリーヌ・ドヌーヴ演じる子供を身ごもる売り子役を中心に書かれた作品だ。
1960年代:音楽スターが映画スターに
このパターンを踏襲したミュージカル映画は60年代初期まで続いたが、映画版の『ウエスト・サイド物語』(1961)が舞台版のレナード・バーンスタインの音楽とスティーヴン・ソンドハイムの歌詞をそのまま使い、殆どブロードウェイ・ヴァージョンと変わらないプロダクションで成功すると映画スタジオ式システムは凋落の一途を辿ることになった。というのも莫大な予算をかけたミュージカル映画に対する大衆の倦怠感が、60年代にそうしたプロダクションを激減させ、また寡作にしたのである。
だが、ブロードウェイのヒット作だった『サウンド・オブ・ミュージック』(1965)や『オリバー!』(1968)の映画版が大成功を収めたことからも分かる通り、内容として的を射た作品であれば、市場は確実に反応した。バーブラ・ストライザンドが『ファニー・ガール』(1968)映画版で舞台版と同じファニー・ブライス役を演じてオスカーを獲得したように、人々の頭の中では時に両方のヴァージョンに対する評価が肩を並べることもあったのだ。
60年代のミュージカル映画において重要な転換点をもたらしたのはザ・ビートルズだった。彼らは自らの映画を通して、この時代の夢物語を描き出して見せた。また彼らは、映画の封切りに合わせてリリースするサウンドトラック盤でも、ジョン・レノンとポール・マッカートニーによる珠玉の楽曲にモノをいわせ、圧倒的な成功を収めた。
バンドの映画第一作『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』(1964)(*訳注:後に『ハード・デイズ・ナイト』に邦題を改題)で、監督のリチャード・レスターはザ・ビートルズの面々が60年代のスウィンギング・ロンドンへと向かいながら、自分たちの世界的人気の不条理さを探求するという筋の中で、4人のミュージシャンたちの飾らないウィットと魅力を巧みに捉え、後の長編ポップ・ヴィデオのお手本とも言うべき映像作りを実現している。
このアナーキー的な自由奔放さは、続く『ヘルプ!』 (1965)にも通じる部分があった。『マジカル・ミステリー・ツアー』(1967)はシュールレアリスムとサイケデリアに溢れ、アニメーション・コメディの『イエロー・サブマリン』 (1968) を経て、最後を飾るのがかの有名な即興的屋上コンサートの模様を収めた1970年のドキュメンタリー作品『レット・イット・ビー』だ。
『レット・イット・ビー』は決して史上初の音楽ドキュメンタリー映画ではないが、間違いなく最もよく知られた1本である。ちなみにこのジャンルには確固たる独自の歴史があり、素晴らしいコンサートの模様を収めたザ・バンドの『ラスト・ワルツ 』から、フィル・ジョアノウによる心疼くほど美しいドキュメンタリー『魂の叫び』まで、内容は幅広い。
この他にも ボブ・ディラン、ザ・ローリング・ストーンズ、ボブ・マーリー、ニール・ヤング、ジミ・ヘンドリックス、マドンナ、ザ・クラッシュ、グレン・キャンベルにトム・ペティ、2015年のエイミー・ワインハウスまで、生き生きとしたドキュメンタリー作品が多数ある。
中には、例えば『ラスト・ワルツ』を手掛けたマーティン・スコセッシや、ストーン・ローゼスのドキュメンタリー『ザ・ストーン・ローゼズ:メイド・オブ・ストーン』のシェイン・メドウズのように、音楽系の映像作品では知られていないが映画監督としては既に名を挙げている監督たちの作品もある。
ザ・ビートルズは新たなロック及びポップ・ミュージカル映画のスタンダードを示し、彼らが最初の2本の映画で確立したフォーマットは、プリンスの『パープル・レイン』や、『スパイス・ザ・ムービー』等、その後半世紀の間に折りにふれアップデートされてきた。21世紀に入ると、エミネムの『8マイル』や50セントの 『ゲット・リッチ・オア・ダイ・トライン』が、かつて映画の中でプリンスやポッシュ・スパイスとその仲間たちがやっていたことをヒップホップの世界に応用する姿が観られた。
ミュージカル映画冬の時代
60年代後期から70年代初期はミュージカル映画にとって冬の時代だった。中にはまだこのジャンルで大金を稼ぐ可能性があることを示す作品、例えば『チキ・チキ・バン・バン』もあったものの、ザ・ビートルズ映画の最後の時期辺りに公開された莫大な製作費をかけた映画の多くはボックスオフィスでは鳴かず飛ばずだった。『ペンチャーワゴン』『フィニアンの虹』『ドリトル先生』といった作品は、業界においては警告として受け止められたのである。
加えて、一部の低品質な作品、アンドリュー・L.ストーンの『Song Of Norway』やピーター・ボグダノヴィッチの『At Long Last Love』は恥さらしな失敗作と見なされている。このような作品の出現は、ジャンル自体の疲弊を印象付けることになった。また更に、昔ながらのブロードウェイ・ミュージカルが謳ってきたような価値観は、フェミニズムの第二波が押し寄せ、ヴェトナム戦争と人種差別をめぐる暴動、暗殺といった社会問題を背景に抱える時代にはそぐわないという判断もあった。
ミュージカル映画は70年代にも製作されたが、その成功――『屋根の上のバイオリン弾き』、『キャバレー』、『ザッツ・エンターテイメント』(MGM社史を通して、最大の興行成績を記録したミュージカル映画)、そして『グリース』(50年代に対するノスタルジアの波に乗って作られた)――はあくまで例外であり、当時の流れではなかった。
アニメーションのミュージカル
80年代に入ると、ニール・ダイアモンドの『ジャズ・シンガー』 やロス・ロボスが音楽を担当したリッチー・ヴァレンスの自伝的映画『ラ・バンバ』など、一部の映画がケタ外れのヒット・シングルとサウンドトラック盤を生むという現象が起こる。だがそれは決して継続的な流れでもなければ、この10年がミュージカルのヴィンテージ年代だったからということでもなかった。
この時期、音楽が印象的だった映画は幾つもある――軽妙洒脱な『ブルース・ブラザース』、爆発的人気を呼んだ『フットルース』(1984) と『ダーティ・ダンシング』、クリント・イーストウッドが伝説のジャズ・ミュージシャン、チャーリー・パーカーを題材に製作した『バード』、『アマデウス』、『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』、そしてキラキラのサザン・ソウルをちりばめたサウンドトラックを擁する『ザ・コミットメンツ』――だが、ミュージカルが確かな実入りを保証できるようになるには、これまでとは違う新しいアプローチが必要だった。
90年代初頭、物語の途中で唐突に歌い始める登場人物は、アニメーションのキャラクターばかりになっていた。近年屈指の成功を収めた新時代のミュージカル・ムーヴメント、楽曲をベースにしたアニメーションの大ヒット作を仕掛けたのはディズニーである。
『リトル・マーメイド』、『美女と野獣』、『アラジン』そして『ライオンキング』といったディズニー映画は、殆ど間を置かずに立て続けに公開され、あっという間に幅広く強大な支持層を築いた。観る者を惹き込む物語、ヒネリの利いたキャラクター、そしてプロットに巧みに織り込まれた歌の数々。『リトル・マーメイド』にフィーチュアされた「Under The Sea」の振り付けは、バズビー・バークリー式エクストラヴァガンザ(狂想曲)へのオマージュをも感じさせる。この映画はアカデミー賞2部門を獲得し、総興行収入は2億ドルを超えている。
この時代のディズニーの輝かしきミュージカル全作品の中でも、 恐らく『ライオンキング』を超える魅力を持ったミュージカルはないだろう。友人である作詞家のティム・ライスから手を貸してくれないかと頼まれたエルトン・ジョンがサウンドトラックの曲作りに参加。
エルトン・ジョンはこの映画の仕事に携わり、「Hakuna Matata」「The Circle Of Life」 そしてオスカーの主題歌賞を受賞した 「Can You Feel The Love Tonight」を書いたことについて、「僕のキャリアと人生のコースを一変させてしまう経験だった」と語っている。
エルトン・ジョンは更に、ランディ・ニューマンやプリンス、レノン&マッカートニー、ブルース・スプリングスティーン、アニー・レノックスといった錚々たる顔ぶれのアカデミー賞音楽部門の受賞者による人気ミュージシャン選抜バンドにも加えられた。
ディズニーの強さは圧倒的だったが、実写版ミュージカル映画も絶滅したわけではない。アーネ・グリムシャーの『マンボ・キングス/わが心のマリア』はラテン・アメリカの音楽を讃え、ウーピー・ゴールドバーグ主演の『天使にラブソングを』はボックス・オフィスでヒットを記録した。恐らくこの年代で最も記憶に残るミュージカル映画と言えば、アラン・パーカーが1976年の舞台版と、アンドリュー・ロイド・ウェバーとティム・ライスによるオリジナルのコンセプト・アルバムを翻案した『エビータ』(1996)だろう。
ジミー・キャグニーのギャング映画『ダウンタウン物語』を、子供ばかりのキャストによりチャーミングなミュージカルに仕立て直した実績や、ピンク・フロイドの『ピンク・フロイド ザ・ウォール』を手掛けたことでも知られるアラン・パーカーは、『エビータ』映画化のために6,000万ドルの予算を得た。主役を演じたマドンナはパフォーマンスに身も心も捧げ尽くし、映画は最終的に「You Must Love Me」で最優秀オリジナル楽曲賞を受賞した。
映画から舞台へ
『エビータ』でもみられる通り、ハリウッドにおけるミュージカルは歴史的に、舞台のミュージカルを映画に翻案するというパターンが大部分だった。だが近年は、例えば『シュレック』のように、大きめの予算が組まれたミュージカル映画が舞台に翻案されるというトレンドが続いている。
しかしながら、映画から舞台へと変換した成功例の原型は何と言っても『ライオンキング』だ。映画版で人気を博したお馴染みの曲をすべて使いながら、パペット的な仕掛けやアフリカ風の仮面を採り入れることにより、舞台版は独自のクリエイティヴな境地を切り拓いている。2017現在の時点で、『ライオンキング』の舞台版ミュージカルは20年間連続、20か国以上の国で上演されており、1億ドル以上の興行収益を上げているのだ。
映画版から舞台版に翻案されたプロダクションでも、もっとくだけた例を挙げるなら、『スクール・オブ・ロック』、『沈黙』(『羊たちの沈黙』のパロディ) 、それにモンティ・パイソンの『スパマロット』(『モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル』にインスパイアされた)あたりになるだろうか。
Universal Movies社は子会社としてUniversal Pictures Stage Productionsを抱えているが、その役割は主としてスタジオの 知的財産(映画作品)をブロードウェイの作品に仕立て直すことにある。既に翻案済みの作品は『クライ・ベイビー』、『リトル・ダンサー』(こちらにもエルトン・ジョンの楽曲がフィーチュアされている)、そして最も有名なのは『オズの魔法使 (オリジナルの原作本ではなく映画の方の)』の変成版で世界的なヒット作となった『ウィキッド』である。
映画のサウンドトラック
もうひとつ、約1世紀にわたって連綿と受け継がれているのはこれはミュージカルのみならず、通常のドラマも同様だが、サウンドトラックの質の高さである。映画音楽はクラシック・ミュージックに端を発しており、この2つは家族のように強い結びつきを持っている。初期の映画音楽の世界で大きな影響力を誇っていたひとりがエーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルドだった。
彼は1938年の映画『ロビンフッドの冒険』のスコアを手掛けた作曲家である。かのグスタフ・マーラーをして「音楽的天才」といわしめたエーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルドは、ヨーロッパの中でもウィーンのようなクラシックの偉大なる聖地で純粋培養された多くの音楽家のひとりであり、これらの作曲家たちが豊かなシンフォニーの遺産をハリウッドへと持ち込んだのである。
クラシックは『ジョーズ』『未知との遭遇』『スター・ウォーズ』のテーマ曲のような世界的に有名なナンバーから、『遥かなる大地へ』のように過小評価に終わったが気の利いた小品まで、数え切れないほどの映画音楽を手掛けたジョン・ウィリアムスをはじめ、現代のシーンで活躍する多くの素晴らしい映画音楽作家たちの作品に影響を与えてきた。
ジョン・ウィリアムスは『プライベート・ライアン』でも音楽を担当しているが、スティーヴン・スピルバーグが彼に『シンドラーのリスト』の映像を見せた時、彼はこう言った。「この映画には私よりもっと腕のいい作曲家が必要だよ」。スティーヴン・スピルバーグは応えて言った、「分かってる。でもそういう人はもうみんな死んじゃってるからね」。
この他、ハリウッドにおける主なフィルムスコア・コンポーザーと言えば、アレクサンドル・デスプラ、ラロ・シフリン(『ダーティハリー』シリーズ)、エン二オ・モリコーネ(スパゲッティ・ウェスタン映画のサントラで名を挙げた)、それにジョン・バリー (『愛と哀しみの果て』や、モンティ・ノーマンによる「James Bond Theme」の演奏がよく知られる一連の007映画のサントラ)といったところか。
御年 60歳のハンス・ジマーは、2017年のコラボレーション作品『ブレードランナー2049』や007の最新作『ノー・タイム・トゥ・ダイ』で、卓越したセンスの健在ぶりを見せつけてくれている。このドイツ人コンポーザーの驚異的なバック・カタログには、『ライオンキング』のスコアや『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ、『グラディエーター』なども含まれている。
加えて、現役ポピュラー・ミュージシャンたちの中にも、映画関連で自らの商業作品に殆ど引けを取らない高評価を得る作品を出している面々が存在する(ライ・クーダーなどはその好例だ)。時に映画のサウンドトラックは、一般のリスナーの間ではあまり認知度の高くないカントリー系やフォーク系のアーティストたちにとっては願ってもない露出の機会を与えてくれるものだ。
このカテゴリーに入れられるであろうミュージシャンはさしづめ、ジュリー・ファウリス(『メリダとおそろしの森』で 「Into the Open Air」を歌った)やフィンバー・フューレイ(『ギャング・オブ・ニューヨーク 』のサントラに「New York Girls」で参加)、あるいは『オー・ブラザー!』の中の「I Am Weary (Let Me Rest)」が出世作となったザ・コックス・ファミリーあたりだ。
だがこの3組は何千という中の代表に過ぎない。また、シー・ロー・グリーンが『カンフー・パンダ』で披露した「Kung Fu Fighting」のように、サントラには既にビッグネームのパフォーマーがお馴染みの曲に再解釈を加え、スペシャルなナンバーを聴かせてくれることもある。
21世のミュージカル映画
では、21世紀のミュージカル映画の立ち位置はどこだろう? 実写版ミュージカルは一時期、西部劇並みに映画界の絶滅危惧種になりそうな情勢に見えたこともあったが、現在も優れた作品が作られ続けている。『ムーラン・ルージュ』(2001)と『シカゴ』(2002) はどちらも先頃、全米映画協会選定による“最も素晴らしいミュージカル映画”25選に入った。一方忘れるなかれ、リチャード・リンクレイターの2003年のコメディ『スクール・オブ・ロック』は、2015年に『ピッチ・パーフェクト2』に取って代わられるまで、コメディ・ミュージカル部門では映画史上最高の興行成績を収めていたのである。
この他にも『レント』(2005)、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 』(2007)そして 『レ・ミゼラブル』(2012)――主演のヒュー・ジャックマン含め、殆どの出演俳優たちがそのまま配役の歌を担当した―― にみられる通り、近年のミュージカル映画の成功は、デジタル世代のオーディエンスの間にも、魅力的なミュージカルに対する貪欲な需要がまだまだ存在することを示している。例えば『マンマ・ミーア!』は公開当時、レヴューでは賛否両論だったものの、2008年のボックス・オフィスでは6億ドルを超える興行収益を上げているのだ。
ミュージカル映画はアメリカで産声を上げたアート・フォームではあるが、現在はすっかり一人前の表現形態として独り歩きし、世界中で認知されている、たとえそれがスターリン政権下のソビエト連邦におけるプロパガンダ・ミュージカルであったとしてもだ。ミュージカル映画のひとつのハブはボリウッドで――何しろインドで作られる映画の90%近くはミュージカルなのだ――実はこれもアメリカにおけるミュージカル映画復権には一役買った部分があった。
映画監督のバズ・ラーマンは、『ムーラン・ルージュ』がインド映画から直接的な影響を受けていることを認めている。バズ・ラーマンいわく「僕は30年代や40年代の映画が好きなんだ、オーディエンスとのお約束があるようなやつね。それと、僕はボリウッド映画、あるいはヒンディー映画というのかな、それにも凄く影響を受けてる。映画館で観客が映画に参加してしまうみたいなさ。彼らは本当に昔から、四六時中映画を見てるんだよ」。
1930年代、その10年間で 100本のミュージカル映画が作られていた。2016年、アメリカで封切られた実写版ミュージカル映画は僅か4本である。その中で一際目立った作品と言えば、言わずと知れたデイミアン・チャゼル監督の『ラ・ラ・ランド』だ。
1985生まれのデイミアン・チャゼルは、『トップ・ハット』でフレッド・アステアとジンジャー・ロジャースが頬と頬を合わせて踊るさまを観て閃いたのだそうだ。いわく、「それが最初だったんだよ、僕は目が覚める思いで口走ったんだ、『ナンてこったい、僕は宝の山の上で眠りコケてたんだ』ってね」。
『ラ・ラ・ランド 』はゴールデン・グローブ賞7部門とアカデミー賞6部門で賞を浚い、興行収入は4億4500万ドルに達した。 恐らくはここからまた新たなミュージカル映画リヴァイヴァルの火の手が上がるに違いない。『ラ・ラ・ランド』で歌詞を担当したベンジ・パセックは、今の若い世代は「ディズニー・アニメーション復権の時代に育ってきたからね……ミュージカルのコンテンツを受け容れる下地があるんだよ」と語っている。
さて、果たして2020年代には何が来るのだろうか? アル・ジョルスンの『ジャズ・シンガー』での台詞を借りるなら、きっと我々にはまだ耳にしたことのない音楽が沢山あるはずなのだ。
Written By Martin Chilton
映画『ウエスト・サイド・ストーリー』
2021年12月10日公開
スティーブン・スピルバーグ監督が、世界的名作ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」を実写映画化。混沌とした時代の中、偏見と闘いながら、夢を追いかける、“今”を生きた若者たちのラブストーリーを描く、ミュージカル・エンターテインメント
- 映画音楽作曲家とサントラの歴史
- ジュディ・ガーランドはなぜゲイの人々から支持されたのか?
- 長谷川町蔵インタビュー:映画サントラの過去、現在、未来(前編)
- ジョン・ウィリアムズの映画音楽半生:フォースが彼と共にあらんことを
- LGBTQに愛された15人のパイオニア
- ハリウッド史上最高の映画挿入歌50選
- レディー・ガガ主演の映画『アリー/スター誕生』予告編公開
- メロディ・ガルドー初のフルライヴ盤『Live In Europe』